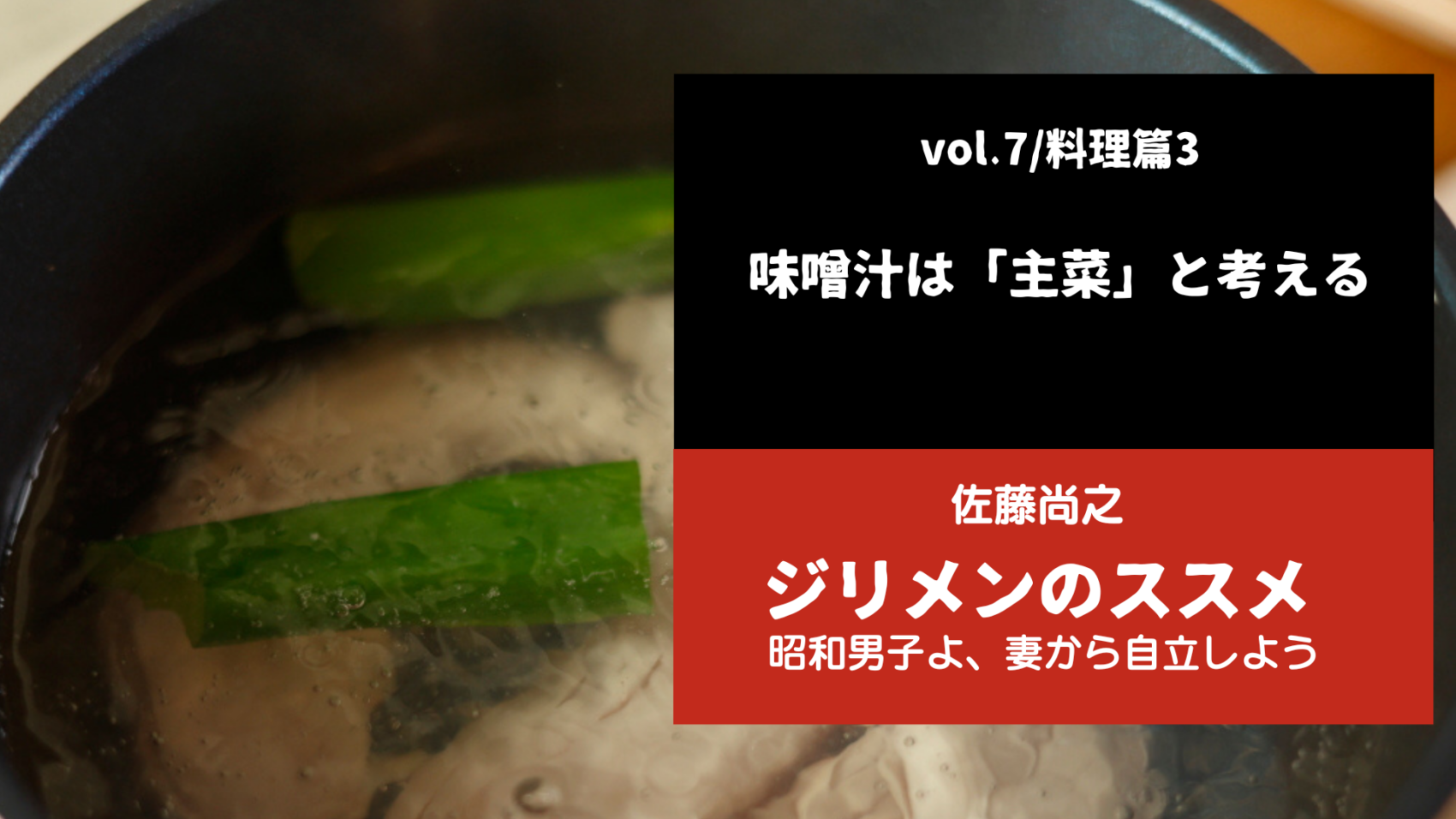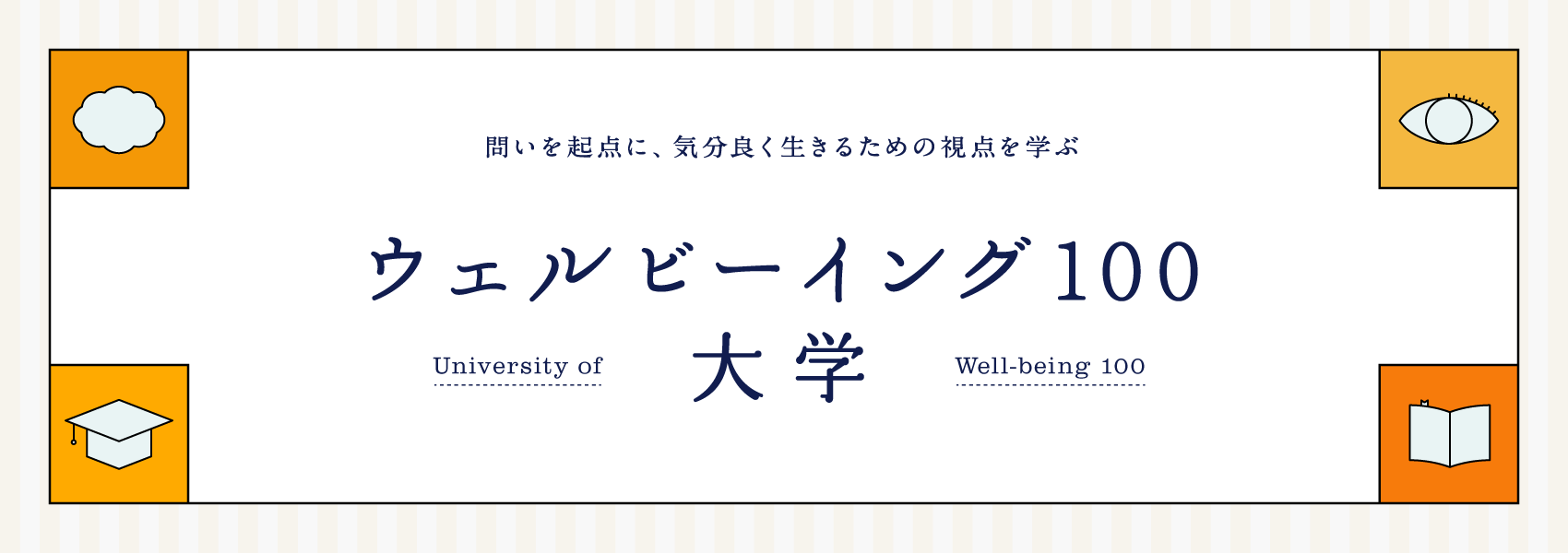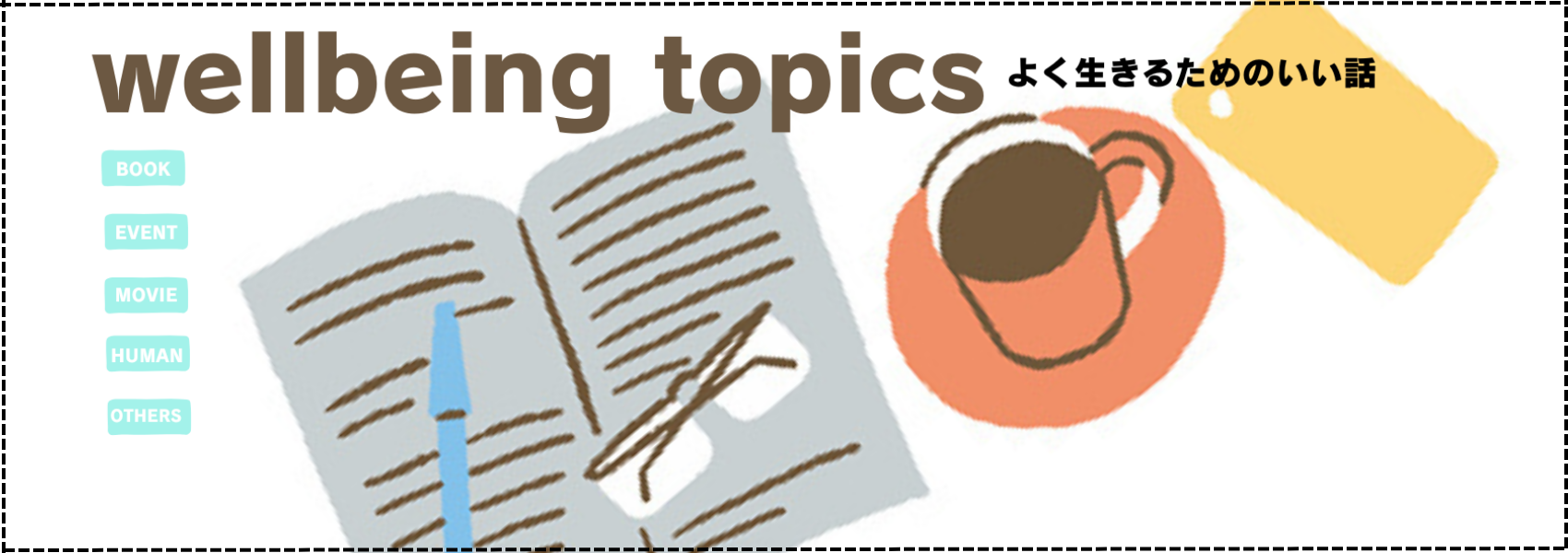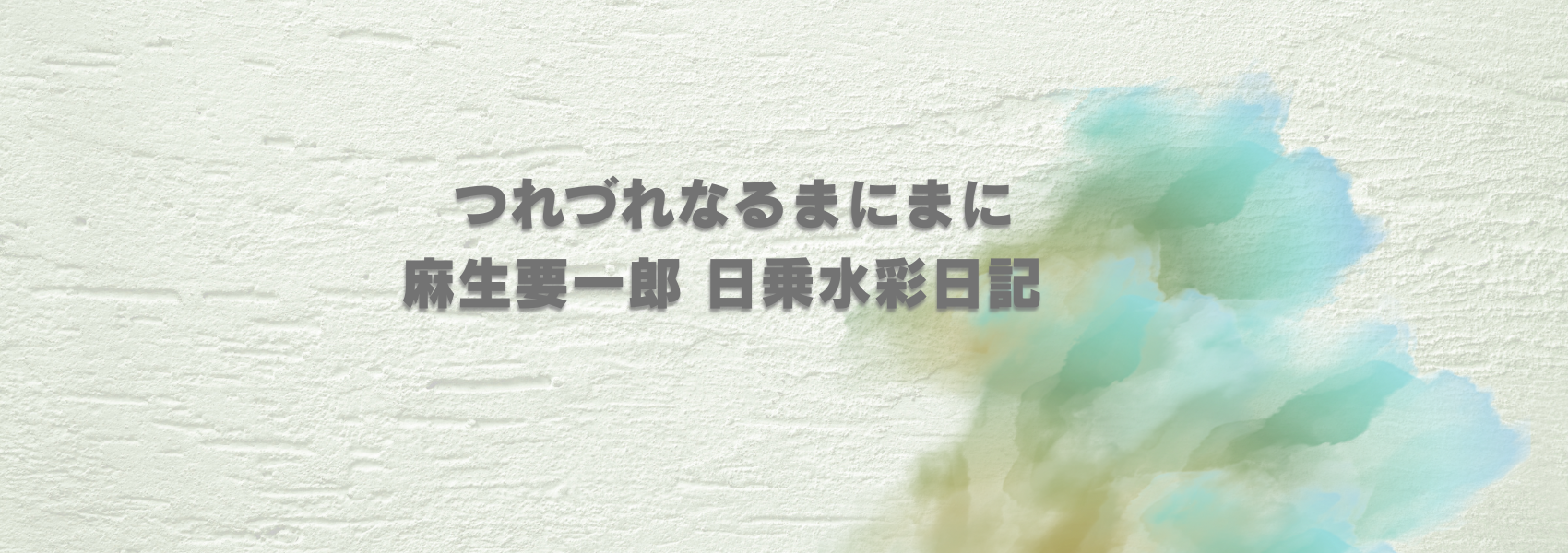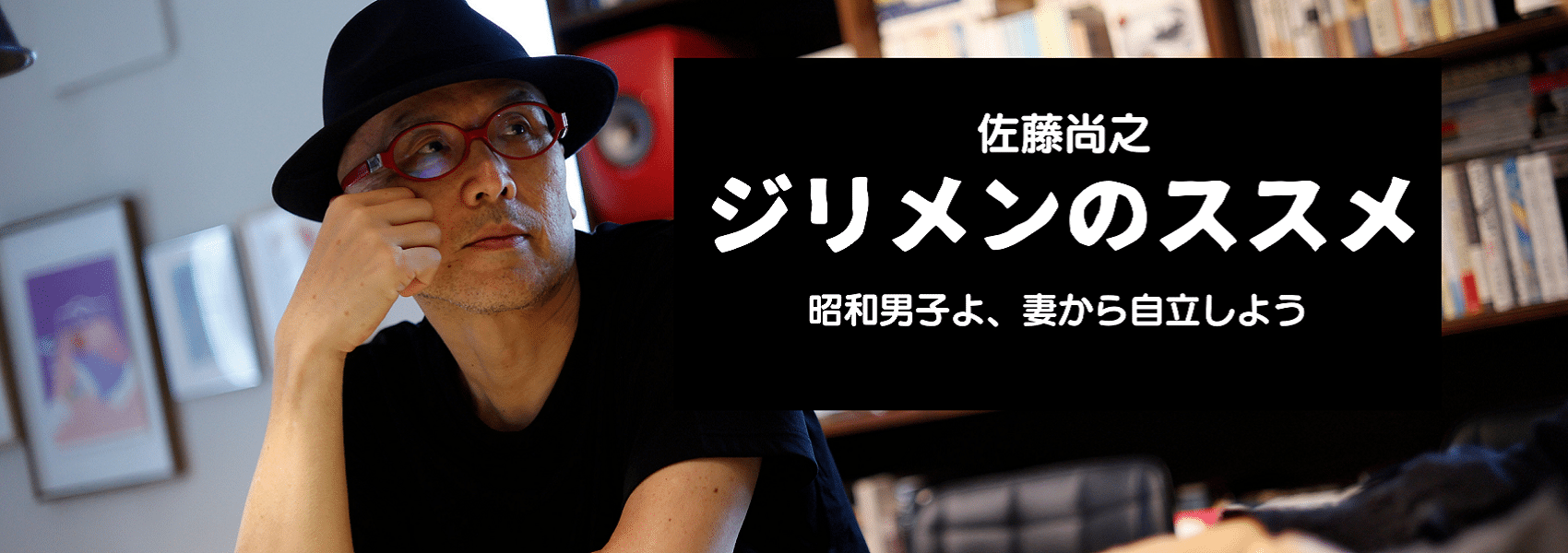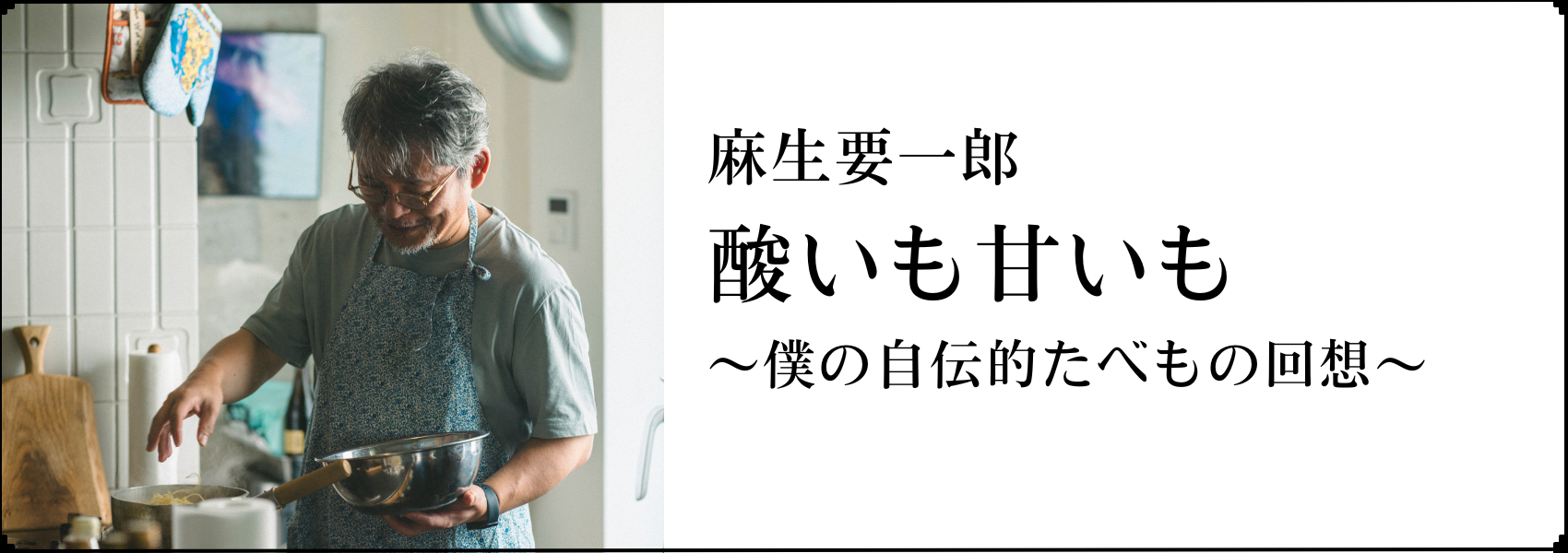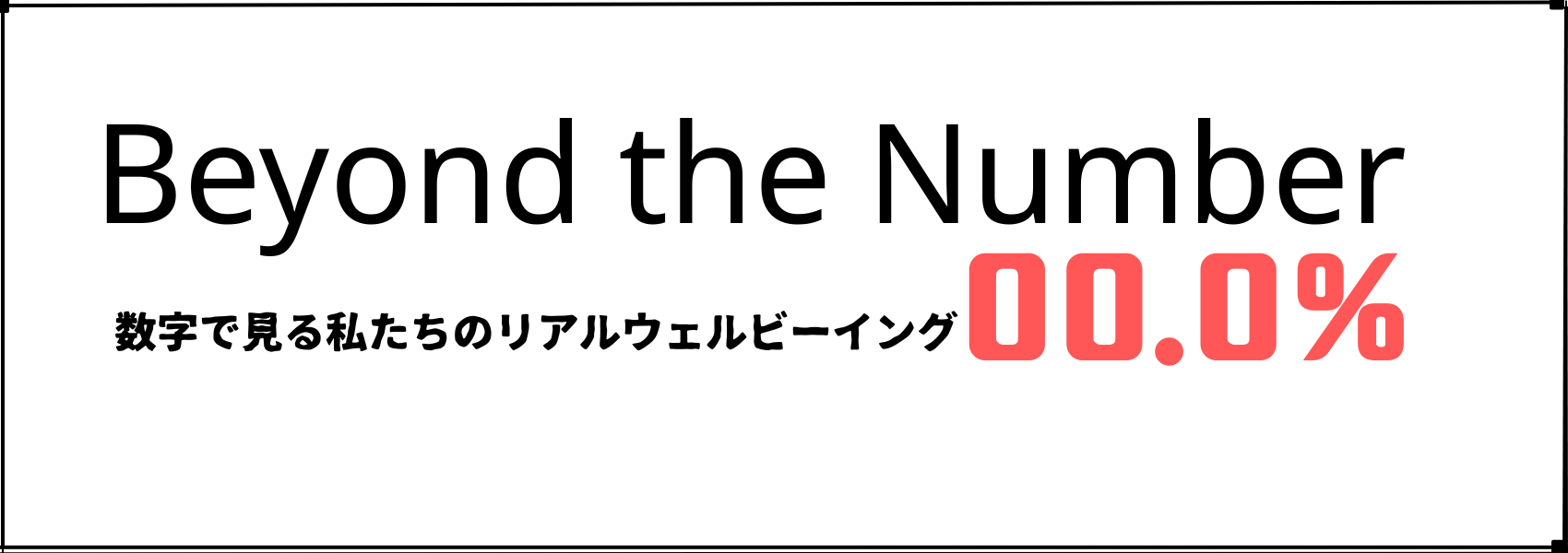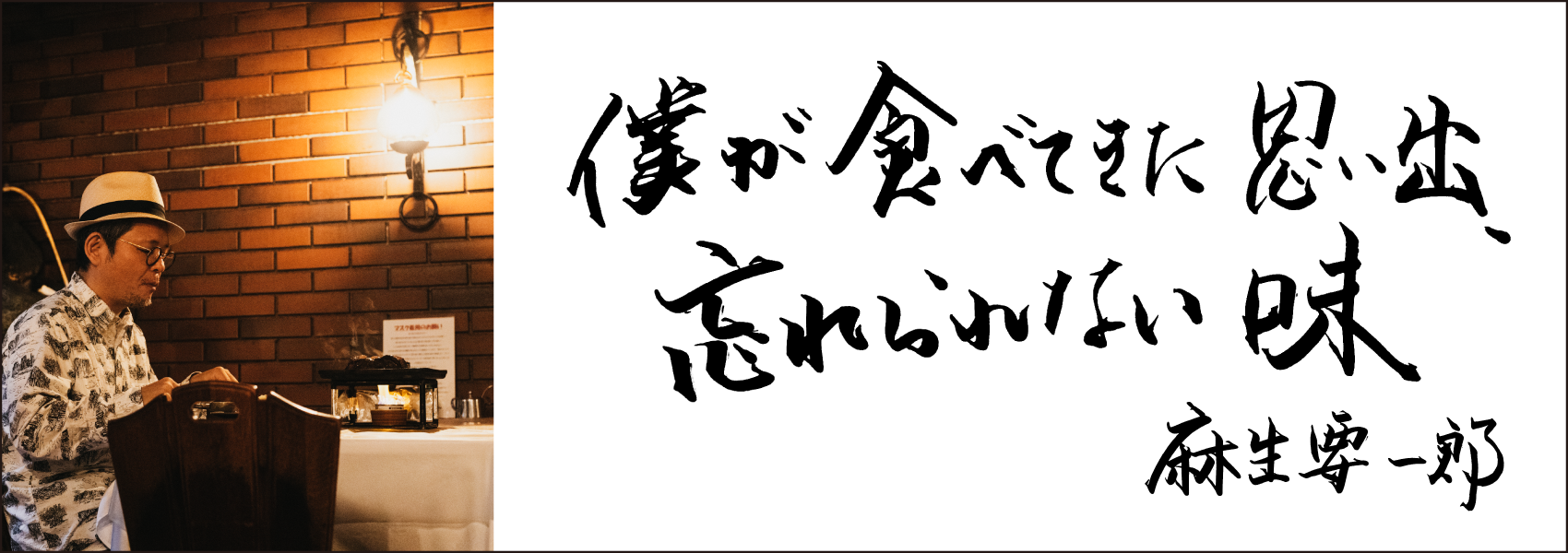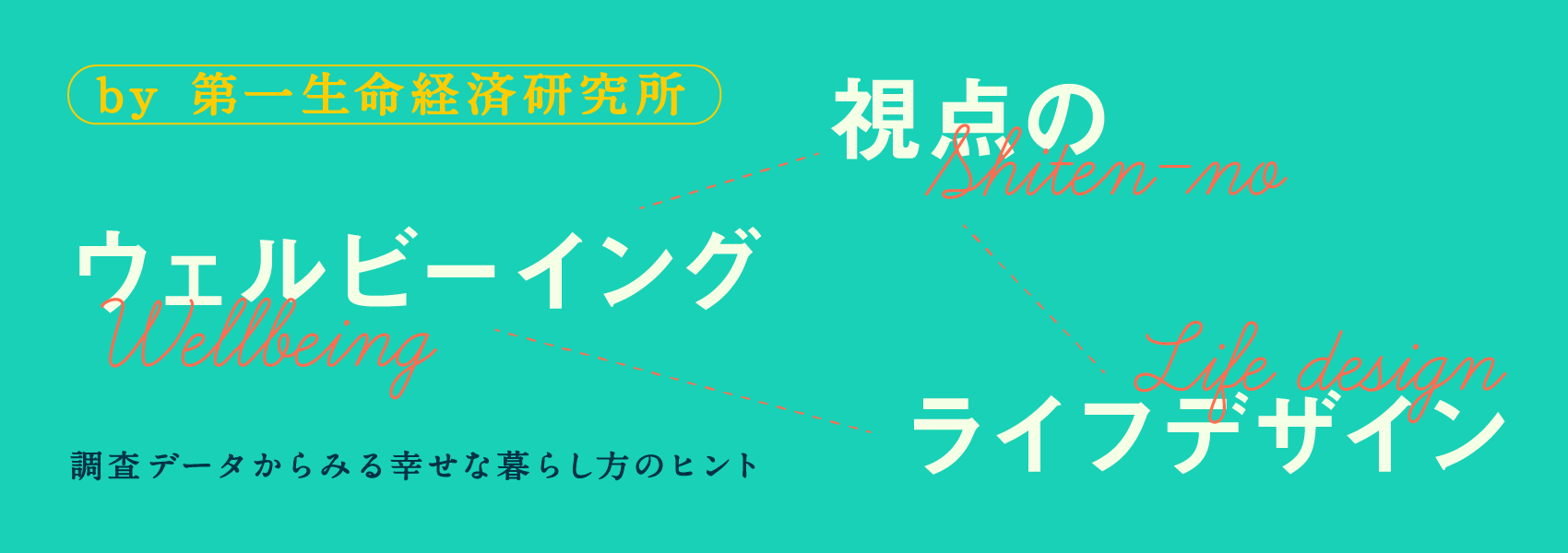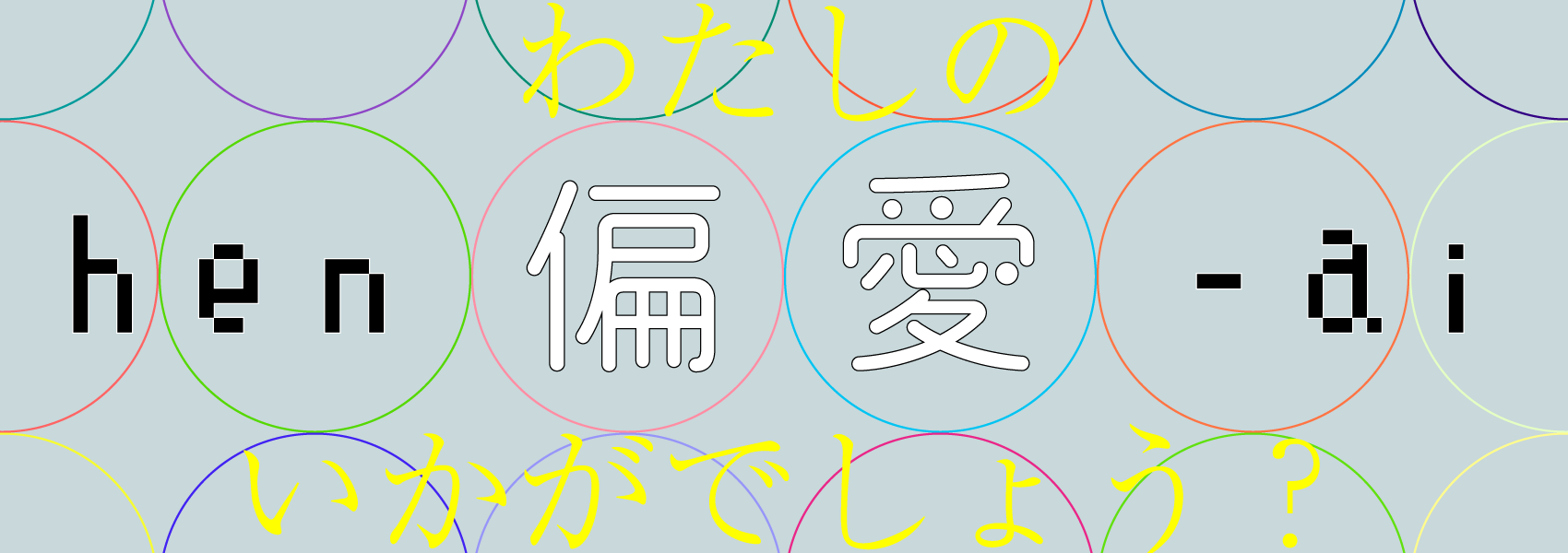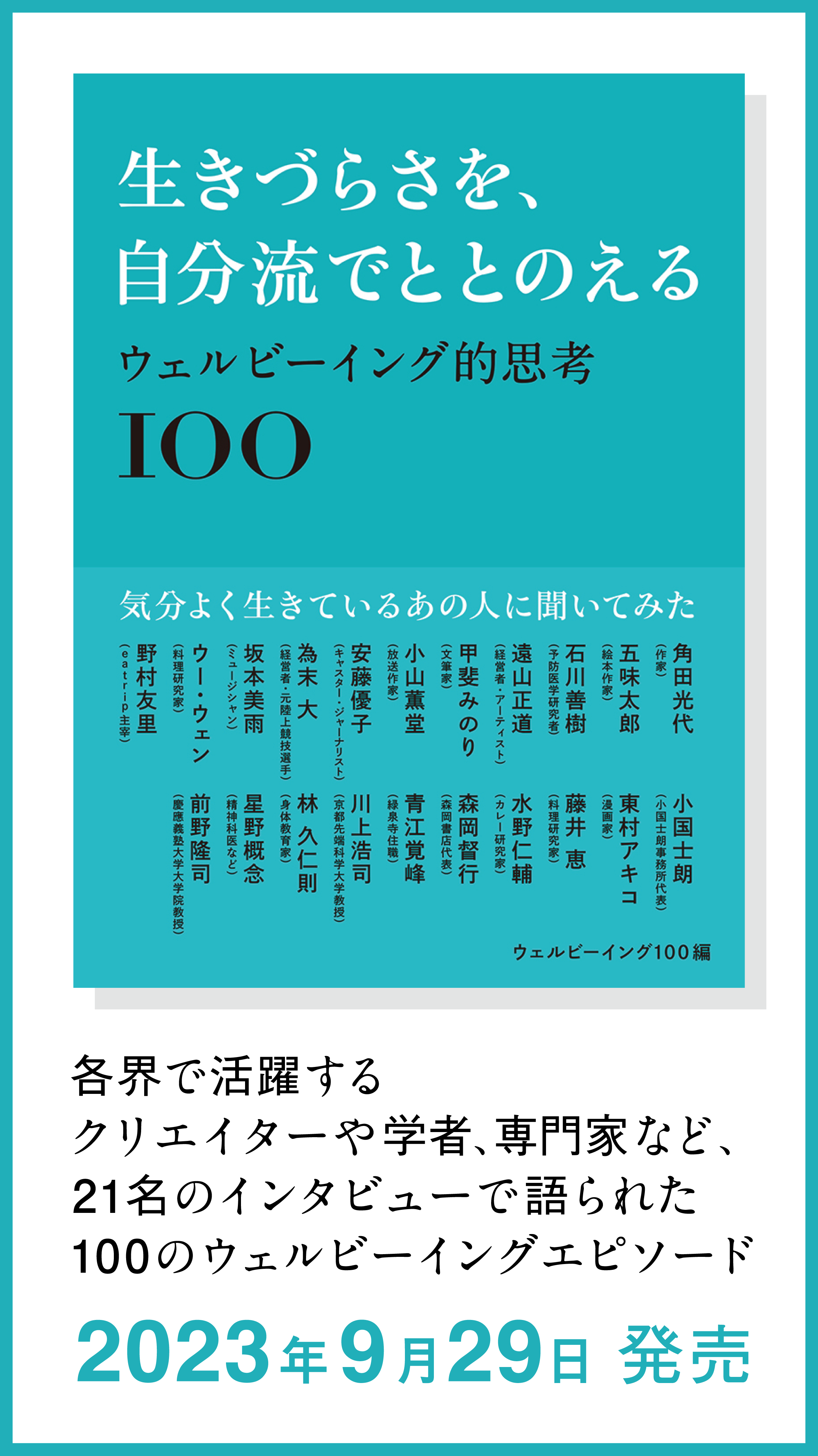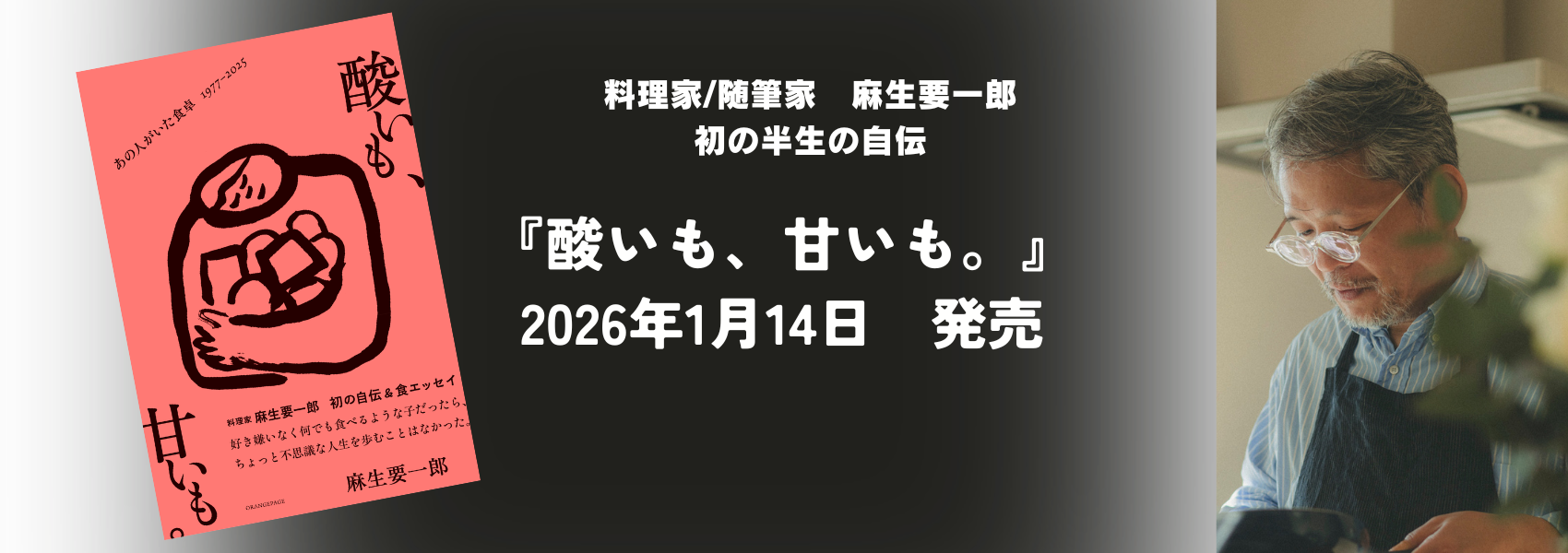「生活面で自立した男とは?」と問われて「えっ!?」と戸惑う男性も女性もまだまだ多いはず。コミュニケーションディレクターの佐藤尚之さんが提案する「ジリメンのススメ」はその初回から大きな反響がありました。そして前回から開始されたのが自炊料理家・山口祐加さんに教わる「継続できる自立の料理」の具体的なノウハウの授業です。この、あるようでなかった料理の基本レッスンの二回目は「加熱」に入ります。「習慣化」のために大切な意識の転換とは何か、示唆に満ちたさとなおさんの文章によるコーチングをぜひ体験してください。料理に慣れた女性にとっても、ハッとする部分が多いはず。キーワードは「継続」であり、「おいしさ」ではないのです。
●前回の【vol.6 最低限ギリギリの料理スキルとは何か?】はこちらから
●今回初めてこの連載を読んでくださっている皆さん! ぜひ、vol.1の「宣言編」をご一読ください。
【vol.1 もしかしてオレ、自立してなかった⁉】
佐藤尚之(さとう なおゆき)さん
コミュニケーション・ディレクター。
1961年東京生まれ。著書に「ファンベース」(ちくま新書)、「明日の広告」(アスキー新書)など。また“さとなお”の名前で「うまひゃひゃさぬきうどん」(光文社文庫)、「沖縄やぎ地獄」(角川文庫)、「沖縄上手な旅ごはん」(文藝春秋)、「極楽おいしい二泊三日」(文藝春秋)などがある。
2018年にアニサキスアレルギーになって外食や旅に行けなくなり生活がガラリと変わる。一汁一菜を毎日作ってインスタグラムにアップもしている。
facebook:http://www.facebook.com/satonao
instagram:https://www.instagram.com/satonao310/
一汁一菜instagram:https://www.instagram.com/enjoy_ichiju_issai
note:https://note.com/satonao310/
撮影/原 幹和(佐藤さん/山口さん)
おかずを「主菜」にすると継続しない
さて、「継続すること」を前提とした一汁一菜の「料理スキル編」第2回目である(全体では第7回目)。
自立のために、歯磨きの領域まで習慣化できる料理とは何か。
この連載では「一汁一菜」を圧倒的にオススメしているのだが、前回はそのスキルとして必須な「野菜を切る」であった。改めての基礎のキである。包丁をほとんど持ったことないヒトでも切れるように「構え方」から習ってみた。
で、今回は「一菜」を作ってみよう、という回である。
ここで大切なのは「主菜概念の変換」だとボクは思っている。
日本で長く普及してきた「一汁三菜」とは、「ごはん(白米)と味噌汁、そして主菜一品、副菜二品」のこと。
主菜・副菜。つまり、おかずの中に「主役と脇役」という役割分担があったので、どうしても「主役」が必要となる。ステーキとか焼き魚とかハンバーグとか青椒肉絲とか。そういう「食事には『主役』が必要だ」という意識が昭和以降の毎日の食事で身に染みついてしまっていると思われる。
だって、あなただって、たとえば「ご飯と味噌汁と納豆」という夜ご飯を出されたら「なんだこのみすぼらしい食事は!」ってなりますよね?
なるんです。
だって「納豆が主役?」って感じちゃうから。「主菜がないじゃん!」って感じになっちゃうから。そのくらいは身に染みついている。
でも、一汁一菜だと「ご飯と味噌汁と納豆」でもとても満足度の高いいい夜ご飯となる。
なぜなら一汁一菜においては「味噌汁が主菜」だから。
主役が丼でドンッと居座っているので、おかずがパックから出しただけの納豆だけでも全然みすぼらしくないのである。

「継続」を目的とする場合、いままでの「おかずに主役が必要」という概念は変えた方がいいと思う。いや、はっきり言おう。変えないと続かない。だって大変手間がかかるから。その手間が「継続」を難しくするから。
そう、もう「おかずが主役」という時代は終わらせよう。
おかずは脇役、つまり「副菜」だ。主役は「具だくさん味噌汁」。味噌汁が主菜で、副菜であるおかずで「足りない栄養を補う」という考え方である。
上の写真の場合は「主菜は栄養たっぷりだけど、たんぱく質が足りないので、副菜をたんぱく質にする」と考えた、というわけだ。
もうおかずに主菜はいらない。おかず(一菜)は一汁という主菜を助ける脇役。そう、一汁一菜における主菜は味噌汁で、一菜は副菜なのである。
味噌汁はブラックホール
あの土井善晴先生も本『一汁一菜でよいという提案』(新潮文庫)の中でこうおっしゃっている。
これなら、どんなに忙しくても作れるでしょう。ご飯を炊いて、菜(おかず)も兼ねるような具だくさんの味噌汁を作ればよいのです。
毎日三食、ずっと食べ続けたとしても、元気で健康でいられる伝統的な和食の型が一汁一菜です。毎日、毎食、一汁一菜でやろうと決めて下さい。考えることはいらないのです。
土井先生も書かれているように、栄養面でも充分に足りている。
不安な方は今後の連載を読んでいただきたい。順天堂大学医学部教授の小林弘幸先生との対談回において「一汁一菜は健康のための食事として最強に近い」というお墨付きをいただいている。
そして、味噌汁の懐の深さが尋常ではないのも有り難い。
とにかく「具材に何を入れてもすべてまとめてくれる」のだ。野菜はもちろん、魚や貝、肉類、加工食品など、ほぼすべてを受け入れ、美味しくしてくれるのである。
そう、味噌汁はブラックホールだ。
何もかも吸い込んで、すべてを「味噌汁」にしてしまう、世界でも希有な汁物なのである。
そう、何でもいい。何でも受け入れて美味しくしてくれる。
でも、そうなると逆に何をいれればいいか迷うよね?
ご参考までに、ボクは以下の具を毎回味噌汁に入れている。
野菜を「根・葉・実」と分けて、それぞれ2種類ずつ入れることにしている。
こうすると「根は2種入れたな。葉も小松菜と玉ねぎを入れた。あ、実がなすしか入れてないや。スナップえんどうでも入れよう」とか、頭の整理がしやすくなる。
そして、海藻(海の物)ときのこ(山の物)を入れる。
そうすると全部で8種類になり、もう「栄養の玉手箱」みたいになる。味がさっぱりしすぎるなと思ったら、薄揚げを入れるのもオススメだ。
野菜8種の具沢山味噌汁:
根(2種):にんじん、だいこん、かぶ、ごぼう、れんこん、たけのこ、じゃがいも、さつまいも、さといも、生姜、etc
葉(2種):小松菜、ほうれん草、春菊、菜花、水菜、玉ねぎ、ねぎ、白菜、キャベツ、セロリ、ブロッコリー、チコリ、クレソン、アスパラガス、モロヘイヤ、空心菜、あしたば、etc
実(2種):トマト、なす、ピーマン、パプリカ、かぼちゃ、おくら、ズッキーニ、ゴーヤー、とうもろこし、スナップえんどう、いんげん、etc
海(1種):わかめ、ひじき、こんぶ、生のり、あおさ、もずく、etc
山(1種):えのき、まいたけ、なめこ、しいたけ、ぶなしめじ、きくらげ、山菜、 etc
どの野菜を入れても味がまとまる。その野菜も旬ごとに移り変わっていく。そしてもちろん味噌もいろいろ変えていく。
だから飽きない。味のバリエーションがとんでもないから飽きる暇がない。
そして栄養面でも優れているのは説明するまでもない。
人生でこんなに野菜をとった時期はないかも、というくらい手軽にたっぷり野菜を取れるようになる。ダイエットにも効果抜群だ(ボクは1年で8キロ痩せた)。
ちなみに、もちろん魚や貝、肉類を入れてもいい。
ボクは連載初回でも書いたようにアニサキスアレルギーなので魚や貝は入れられないが、お好みで入れるのは栄養的にもとてもよい。
肉類も味を豊かにするだろう。たとえばベーコンを入れると味に変化が出る。あ、卵を落とすのもオススメだ。
ちなみのちなみに、三食これにしてもいいのだが、そうなると栄養的には必須脂肪酸のオメガ3や不飽和脂肪酸のオメガ9も入れておきたいので、ボクはこの味噌汁にオリーブオイルとアマニオイル、ついでにMCTオイルをたらりと垂らす。
味噌汁にオリーブオイル!? とか思う方もいるかもだけど、具だくさんすぎていろんな味が混ざるので全然気にならない。いやむしろ美味しい。
また、この「根・葉・実・海・山」の分類は買物のときもチカラを発揮する。
買い忘れが圧倒的に減るのだ。
スーパーの棚の前で冷蔵庫を思い出しつつ、「ええと、冷蔵庫に葉は3種あって実もたしか2種はあるよな。あ、根が足りないかも」とか思い出しやすいのである。
あ、書き忘れるところだったが、「味噌」ですね。
味噌は奥深いので、また連載の終盤に取り上げるかもしれないけど、ひとつ言えるのは、「天然醸造のいい味噌」を使ってください、ということ。
前回書いたように、ダシはとらなくても大丈夫(土井先生お墨付きだ)なのだが、その場合「天然醸造の味噌」がオススメだ。ダシをとらなくても充分おいしくなるので、いつもよりちょっと高めの天然醸造の味噌を買ってみてほしい。
副菜としての「一菜」を、最低限ギリギリの料理スキルで作ってみよう
さて。
味噌汁が主菜、一菜が副菜、というご理解をいただけた(と思う)ところで、今日のレッスンに移っていきたいと思う。
副菜としての「一菜」をさらっと作ってみる、というレッスンだ。
具体的には「炒め」「茹で」「焼き」の3つについて「最低限ギリギリ」を教えていただく。
ちなみにボクは「炒め」「茹で」「焼き」と、もうひとつ、「開け」も推奨したい。
「パックの納豆」や「パックの豆腐」を「開け」る。
「魚や肉の缶詰」を「開け」る。
これも立派な料理なのである。
炒めたり茹でたり焼いたりするのが面倒で一汁一菜を作らないくらいなら、パックの納豆を開ける、というくらいでも全然いいと思っている(パックをそのままお皿として使うのもあり)。
「具だくさん味噌汁が栄養豊富」であるのも大きい。
あとはたんぱく質を補えばいいくらいだと思うので、納豆や豆腐でも充分だ。
そう、「パックを開ける」のも立派な料理なのだ。
ただ、ちょっとだけ次の段階に進んで、料理の楽しみを知るといきなり世界が広がるのも確か。それを今回、山口祐加さんに習っていきたいと思っている。山口祐加さんが教えてくれる「炒め」「茹で」「焼き」は、ちょっとビックリするくらい簡単なので、まずは見てみてください。
ということで、山口さん、すいません、超初心者が毎日の料理を「継続」できるギリギリ最低限の焼く・炒めるスキルを教えてください!

山口祐加(やまぐちゆか)さん
自炊料理家®︎
1992年生まれ。東京都出身。出版社、食のPR会社を経て独立。共働きで多忙な母に代わって、7歳の頃から料理に親しむ。現在は料理初心者に向けた料理教室「自炊レッスン」やレシピ・エッセイの執筆、音声プラットフォームVoicyにて「山口祐加の旅と暮らしとごはん」を配信中。著書に『自分のために料理を作る 自炊からはじまる「ケア」の話』(晶文社/紀伊國屋じんぶん大賞2024入賞)、『自炊の壁 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法 』(ダイヤモンド社)など多数。
2024年、世界の自炊をレポートする旅をスタート。
note「山口祐加の海外自炊通信」
https://note.com/yucca88/m/mb0a92b36ef45/hashtag/34956
山口祐加 オフィシャルサイト
https://yukayamaguchi-cook.
はい、みなさん、こんにちは。
自炊料理家の山口祐加です。
では、今日は一汁一菜用の、本当に本当に簡単な「一菜」を3つお教えしたいと思います。
レパートリーは当分この3つでいいと思います。
レパートリーというのが憚られるくらい簡単ですが(笑)。あとはさとなおさんが言っていたような「納豆パック」「豆腐パック」「ゆで卵」あたりも含めて、半年くらいはこの6つくらいで回していくといいかと思います。
佐藤「そうですよね。最初はいろいろ覚えず、応用が利くものをほんの少し覚えれば充分かと」
そう思います。
では、ここからは、
・炒め・・・トマト卵炒め
・茹で・・・茹でささみ
・焼き・・・鶏もも肉の塩焼き
の3品を作って行きますね。
(おまけで魚の缶詰も入れましたが)
●トマト卵炒め
トマトはへたを切って4等分に。
へたを切り落とすとき、指に気をつけてくださいね。写真のように指とは逆の方向に切ります。男性は握力が強いので、4等分にしてから指でグニュって取ってしまっても大丈夫です。


で、フライパンにごま油を引いて、すぐトマトを投入。
フライパンを熱くしなくて大丈夫。
そのとき重要なのは「基本は放置」ということです。
動かさなくていいです。「炒める」となるとフライパンを前後にさっさっと動かしたくなったり、菜箸やヘラでトマトをジャージャーと動かしたくなったりしますよね。
その「炒める」というイメージを変えて下さい。
あおらなくてよし。かき混ぜなくてよし。
強火でなくともよし。時々混ぜる程度でよし。
基本は放置です。

油が飛ぶのが怖かったら蓋をしてもいいです。

そして、卵は直接フライパンに割って落とします。
どうせかき混ぜるので、黄身が崩れてもOKです。お椀やボウルに割らないでそのまま落とせばいいんです。お椀を洗 う手間が省けます。
ただ、卵がうまく割れない人は、フライパンに殻が入っちゃうことがあるので、一度ボウルとかに割り入れてみてください。数回練習すればすぐ上手に割れるようになると思います。
で、かき混ぜる。


卵が半熟状に固まったなぁと思ったら、塩を一つまみ。入れてもいいし入れなくてもいいです。味は自分で確かめて、「あぁ塩がちょっと欲しいかも」と思ったら食べる直前に入れてもいいです。
トマトと卵で味は充分と思ったら、そのままでも大丈夫。
はい、完成です。
ものの3分くらいでしょうか。

この要領で、ネギなどでも出来ます。
ネギも動かさないでくださいね。炒めるというより焼く感じ。時々さっと混ぜるくらいで充分です

このくらい焼き色がついたらOK。


卵炒めのポイント
・卵炒めは青菜や薄切り肉などいろいろ試してみて
・火加減は中火。強火であおるイメージは捨てる
・卵は直接フライパンに割り入れてOK
・卵の加熱加減は、回数重ねると自分の好みがわかる
●茹でささみ
次は「茹で」の最低限ギリギリをやりましょう。
鶏肉を茹でてみますね。
鶏のささみを買ってきましょう。
ささみとは胸肉に近い部位で、カタチが笹の葉に似ているコトから「ささみ」と呼ばれています。どうですか? 似て います?

脂肪が少なくて淡泊。栄養豊富だし美味しいですよ。
1パック3~4本くらい。スジナシの方が食べやすいですが、ちょっと値段も上がるので気にならなさそうな人はスジがある方を買ってもOKです。
まず、フライパン(写真では深めのフライパンにしていますが、浅いフライパンでも小鍋などでもOKです)に水、日本酒(臭みをとる効果)と塩少々、ネギの青いところを入れて沸かします。
極端に言ったら、日本酒もネギもなくても大丈夫。塩は少々入れた方がいいですね。
で、沸騰してこのくらいの泡が立ってきたらささみを入れます。

ささみを入れて、再度お湯が沸いてきたら火を止めます。
そう、もう火を止めていいんです。

で、蓋をして10分くらい放置します。
余熱で火が通ります。そんだけ。
つまり、フライパン(or鍋)の底がふつふつしてきたらささみ投入。
沸騰したら火を止めて10分放置。
これだけです。簡単ですよね。


茹でささみは淡泊なのでどんな調味料でも合います。
一口大に切って、柚子胡椒を添えてみるなど、好みでアレンジしてみてください。
茹で汁は立派なスープになっているので、そのまま飲んでもいいですし、ネギなどを入れたり、ごま油を垂らしたりするとより本格的になります。
ポイント:
* ふつふつと沸いたお湯にささみを入れ、沸騰したら火を止めて10分放置
* 6分という説もあるが、安全のため10分推奨
* 水はささみが完全に浸かる量でOK
* レンジより茹でる方が柔らかく仕上がる
* 筋を取る必要はない(無駄な手間)
●鶏もも肉の塩焼き
さて、「炒め」「茹で」と来て、次は「焼き」です。
鶏もも肉を買ってきてください。
さっと焼きましょう。

皮を下にしてフライパンに入れます。
皮から脂が出るので。油を引く必要はありません。

表面に塩とコショウを全体に。
最初は塩もコショウもなしで作ってみて、「やっぱり塩が欲しいな」「コショウがあった方が美味しいな」と思ったら入れてみる、でもOKです。
レシピとして「塩コショウ」とか覚えると継続のハードルが上がるので、とにかく省力化してまずは作ってみて、少しずつ塩コショウを覚えましょう。

そのうち皮から出た脂がジュージューいってくるので、音がし出したら蓋をして5~6分待ちます。
蓋は基本的に開けません。フライパンを振ることも必要ありません。動かさないでください。

表面が白くなったらひっくり返しましょう。
ここまでのポイント
* 弱めの中火で(中火と弱火の間程度)
* 皮目を下にして焼き始め、蓋をする。
* 片面5分程度ずつ焼く
* 全体で約10分の加熱が基本
* ひっくり返しは1回だけが理想的
* 途中で何度も蓋を開けない

「鳥の皮はパリパリじゃないと!」という思い込みやイメージは捨ててください。そういうレベルの料理は「継続」できたあと、ゆっくり腕を磨いていってください。大丈夫です。
普通に焼けるようになったらだんだん感覚でわかってきますから。

ひっくり返したら蓋をして5~6分待ちます。
トングで押してみて跳ね返る感じがあればOKです。

火加減と火通りの確認ポイント
* 焦げてきたと感じたら火を弱める
* 火通りは触って確認(弾力があれば OK)
* 肉に触って跳ね返りがあれば中まで火が通っている
大事なところですが、中まで火が通っているか不安な場合は切って確認してください。
火の通りが甘いと、細菌リスクがあります。誰に出すわけでもなくご自分が食べる料理なので、盛り付けとか不格好でOKです。切って確認してください。

熱いときはトングで押えながら切るといいです。
この時、前回やったように包丁をスライドさせることを忘れないように。押し切りしないことです。
皮目は上にしても下にしてもやりやすいほうで大丈夫。

ポイント
* パリパリ食感を求めすぎない
* 切るときは皮目が上か下かは好みで
* 肉汁は捨てずに味噌汁などにうまみだしとして活用してもOK
* 焼いた後はしばらく置いて肉汁を落ち着かせる。

フライパンに出た肉汁を盛り付けた後にかけると美味しいですよ。

完成です!
ここで、ついでに後片付けを。
油で焼いたり炒めたりしたあとは後片付けが必要になります。
馴れたら簡単なので、さらっと出来るようになっておきましょう。


ポイント
* フッ素樹脂加工のフライパンは冷めてから洗う
* 油はキッチンペーパーで拭き取ってから洗う
* 熱いフライパンに直接水をかけない
* 早めに片付けないと汚れが落ちにくくなる
これらの基本を押さえることで、家庭でも美味しい肉料理を作ることができます。過度に完璧を求めすぎず、基本を大切に、あまり難しいことを考えずに続けてみてください。
●おまけ:魚の缶詰
さて、「炒め」「茹で」「焼き」とやってきました。
あれ? 魚はないの?と思われた方もいらっしゃると思います。
今回は「焼き魚」はやりませんでしたが、まずは「鶏もも」を焼けるようになることがオススメです。
焼き魚はグリルで焼くのが一般的で、洗い物が出てしまうのと、まずはフライパンを使えるようになることを目指していただきたいと思います。ちなみにフライパンで魚を焼くことも出来ますが、まずは「鶏もも」を焼けるようになってから、トライしてみてください。
ということで、おまけで魚料理も一品。
私は魚の缶詰の利用をオススメしたいです。
もう「開けて盛り付けるだけ」ですが、立派な「継続の料理」です。




鯖缶、鮭缶、鰯缶などの缶を開け、中身をそのまま器に盛るだけです。
シソの葉を好みの量、千切って載せてもいいですが、なくても大丈夫です。味が足りなかったら、醤油などをかけてもOKです。
ということで、今回は「炒め」「茹で」「焼き」をやってみました。
この3つでほとんどの料理は作れます。
最近は「蒸し」も流行していますし簡単でおいしいですが、まずはこの3つを覚えることをオススメします。
+++++++++
山口祐加さん、ありがとうございました!
上でも書いたけど、この3つに「パックを開けるだけ」の料理を2種類くらいレパートリーでもっていれば、5つのバリエで一週間とか充分回せます。
ぜひ試してみてください!
次回は山口祐加さんとの対談をお届けします!
→次回に続く【「おいしさ」を求めるとジリメン料理は続かない!】
●「ジリメンのススメ vol.1 もしかしてオレ、自立してなかった⁉」
「ジリメンのススメ」記事一覧
【宣言篇】Vol.1「もしかしてオレ、「自立」していなかった!?
【社会問題篇1】vol.2浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(前編)
【社会問題篇2】vol.3浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(後編)
【料理篇4】vol.8 自炊料理家/山口祐加×佐藤尚之対談「おいしさ」を求めるとジリメン料理は続かない!