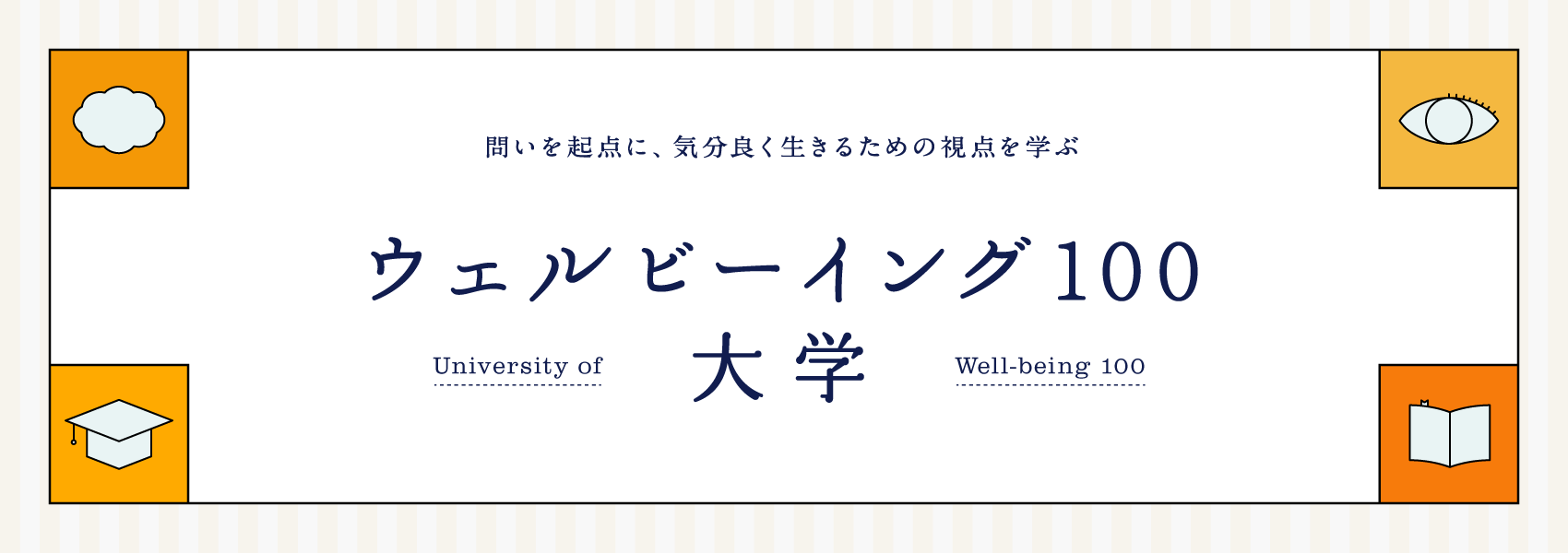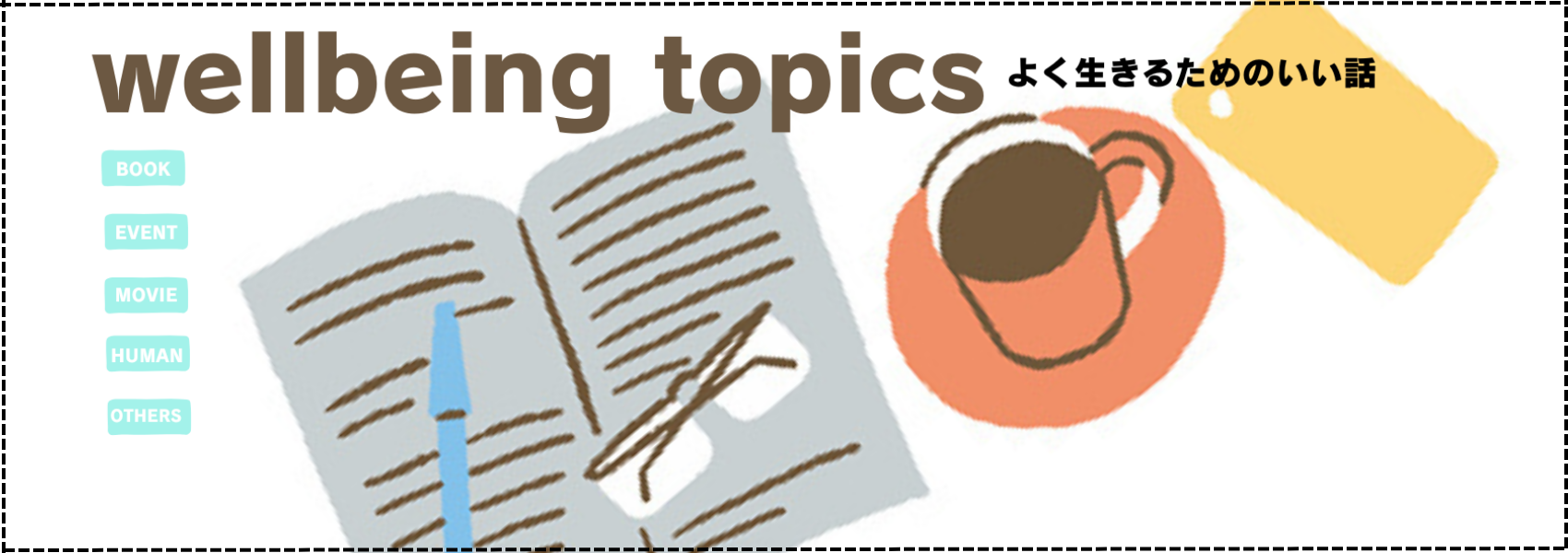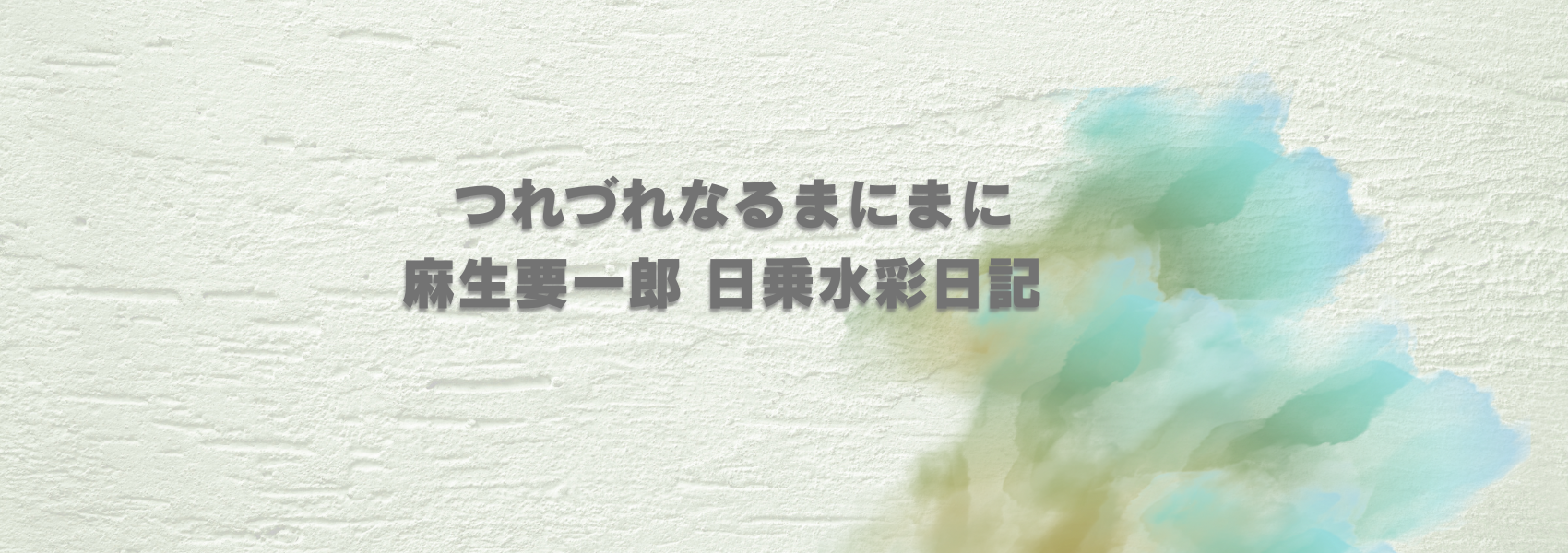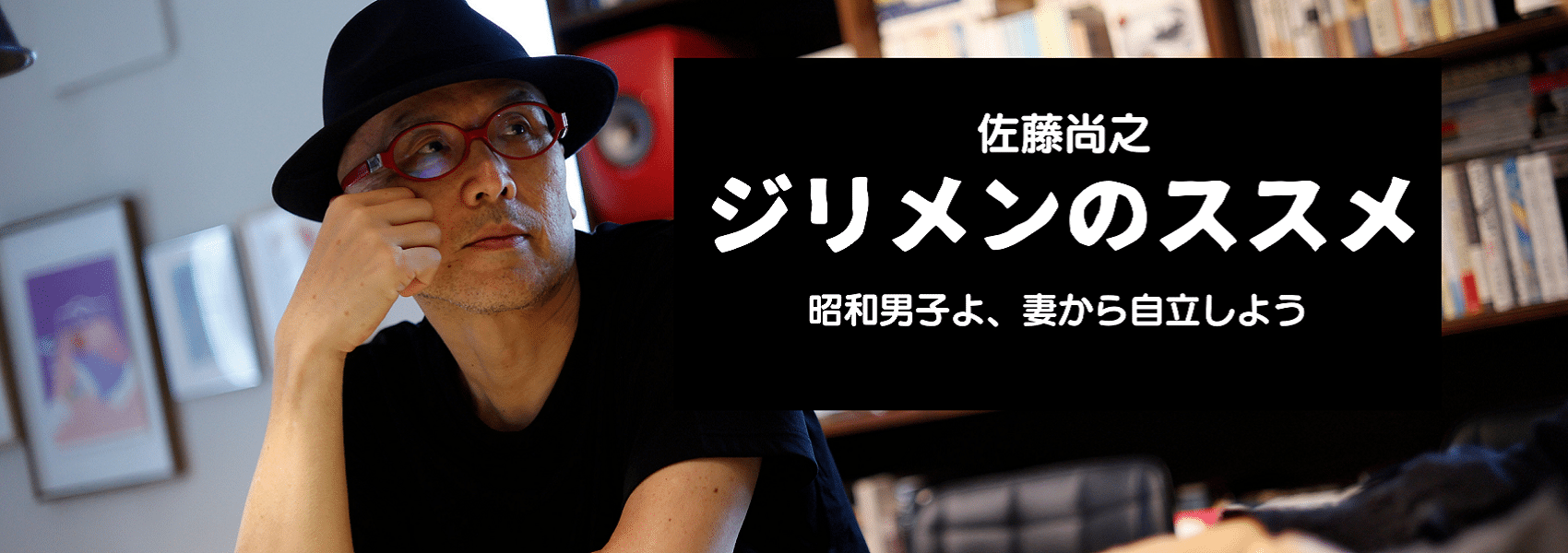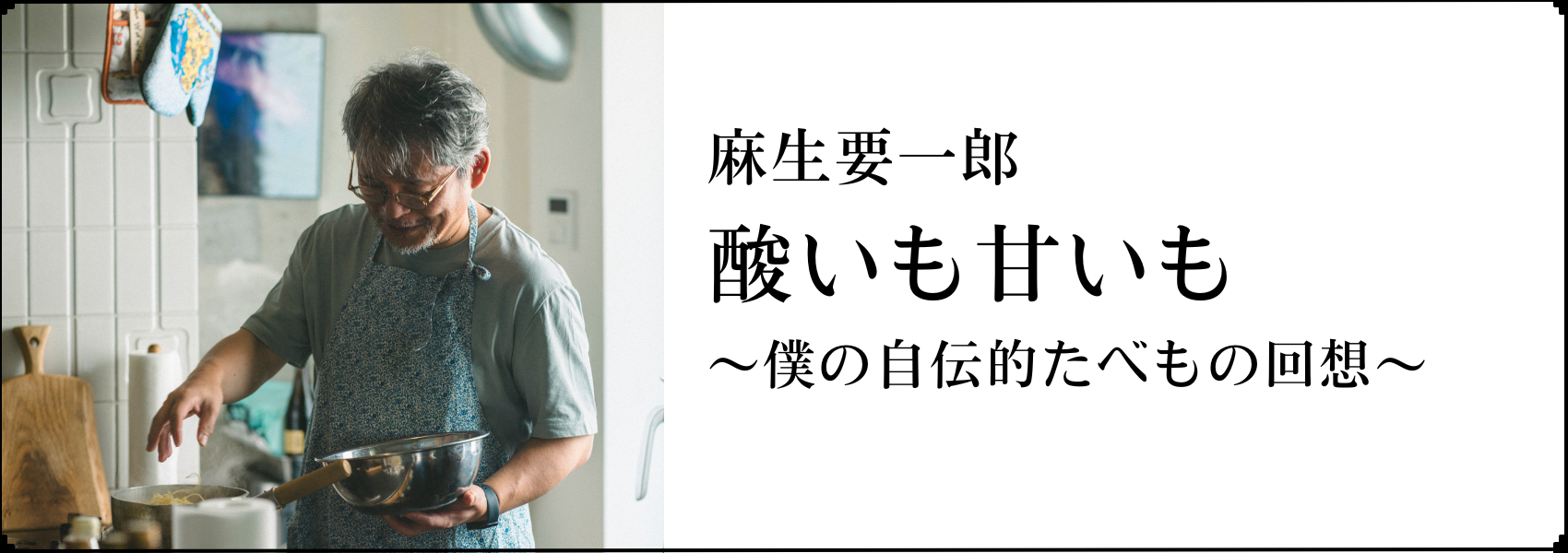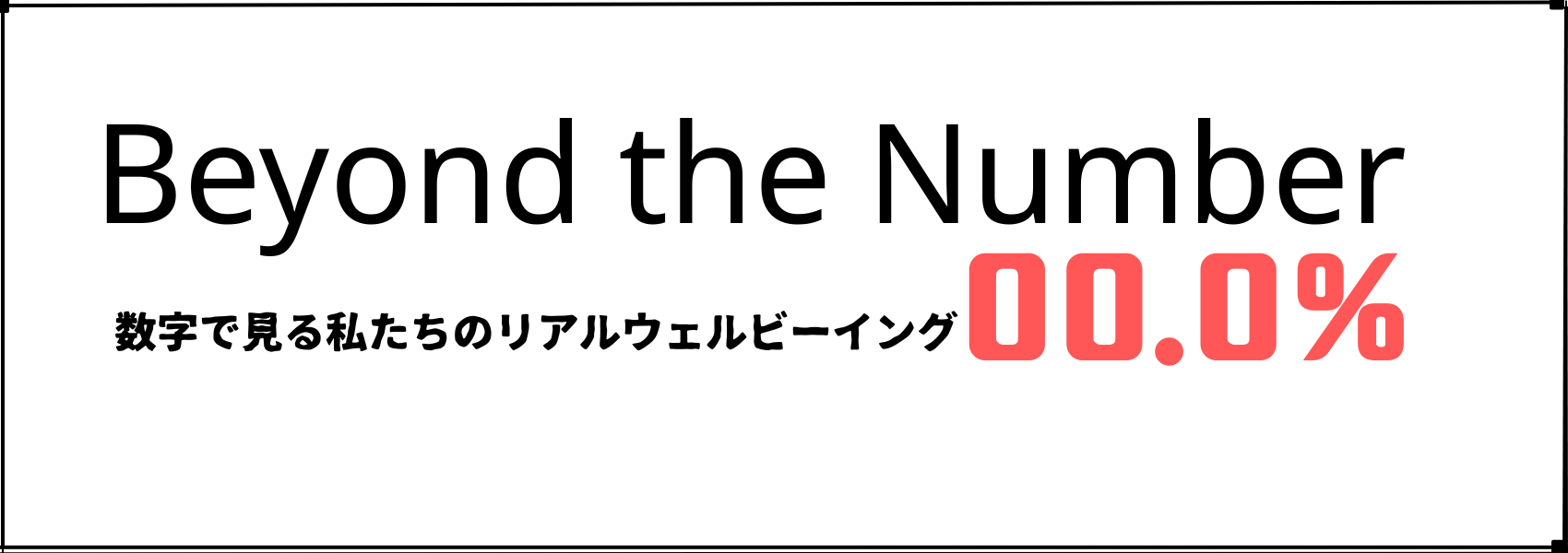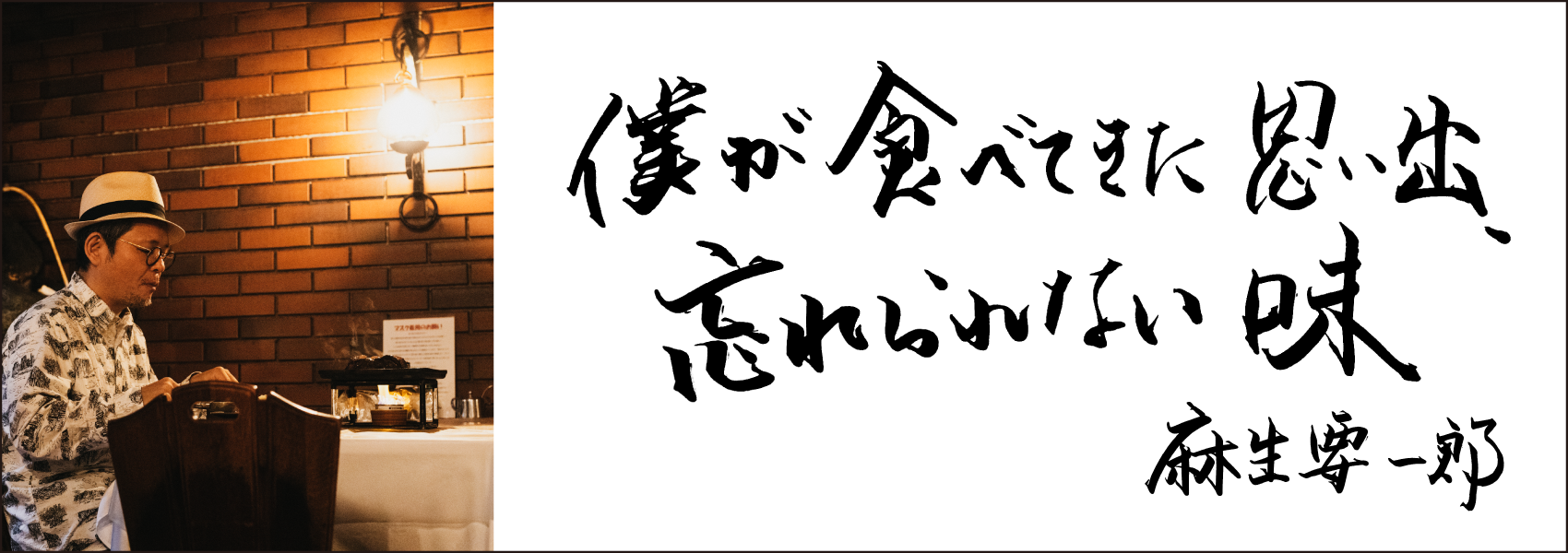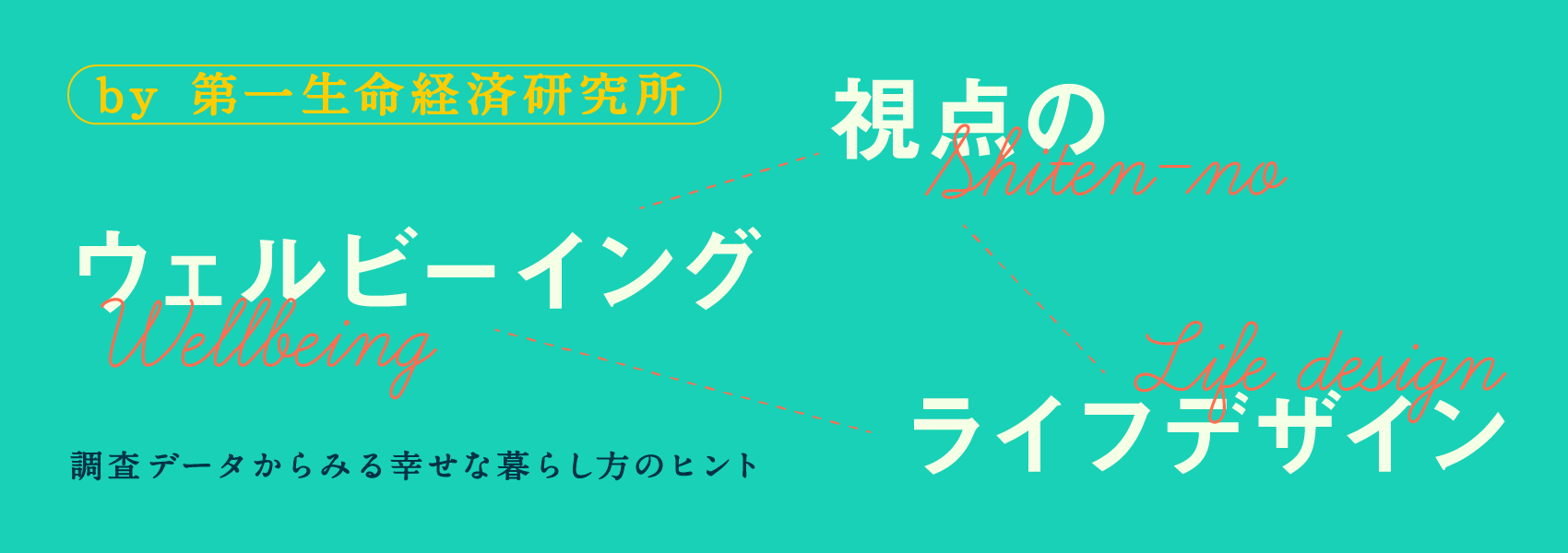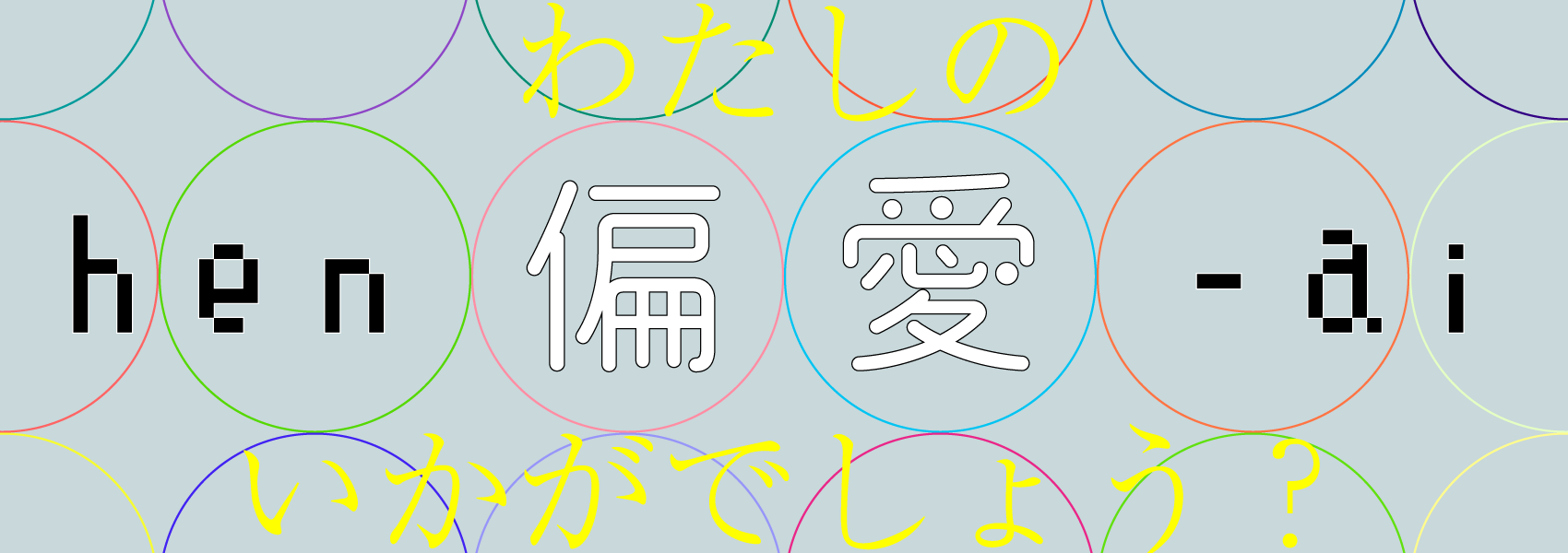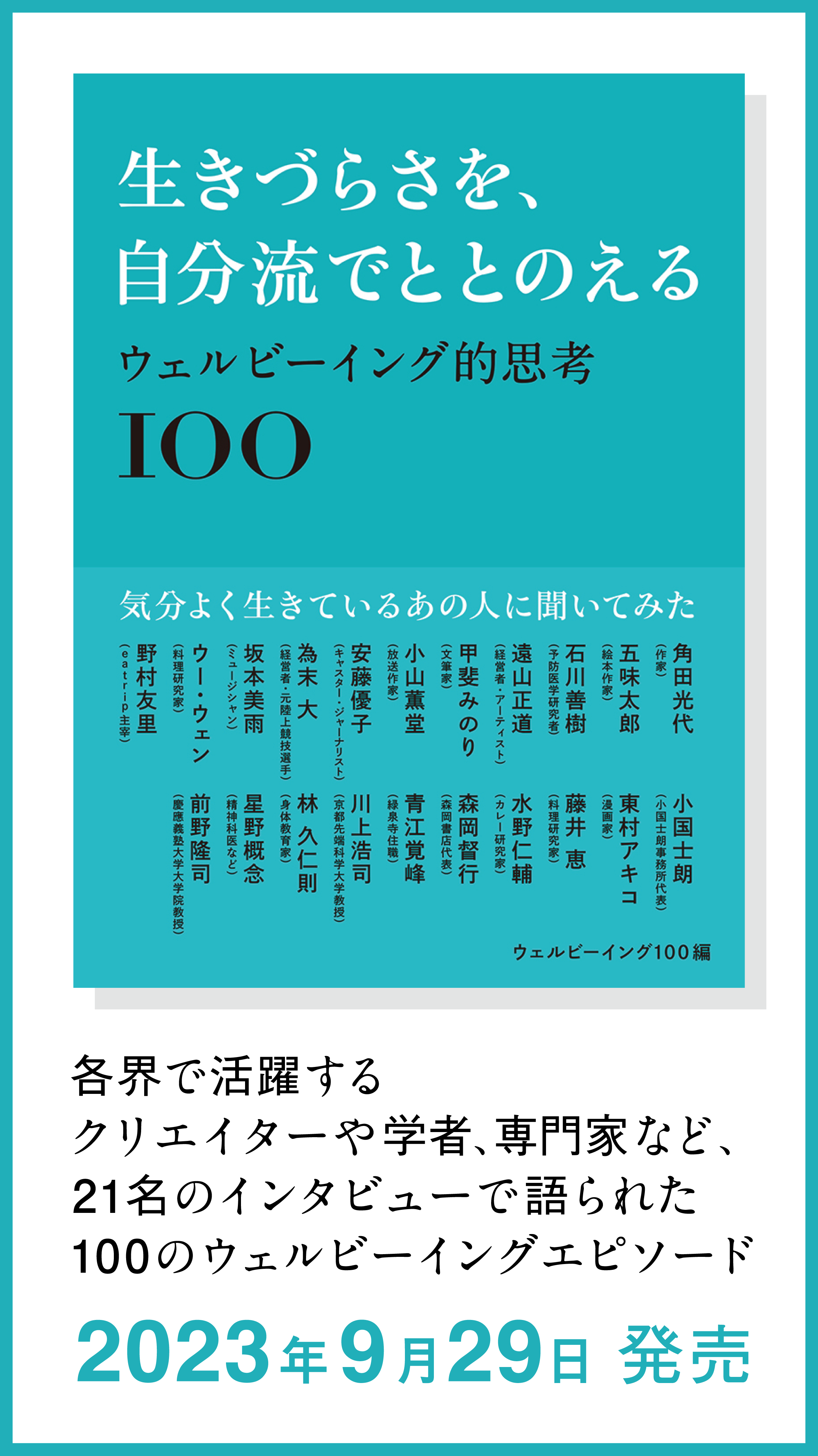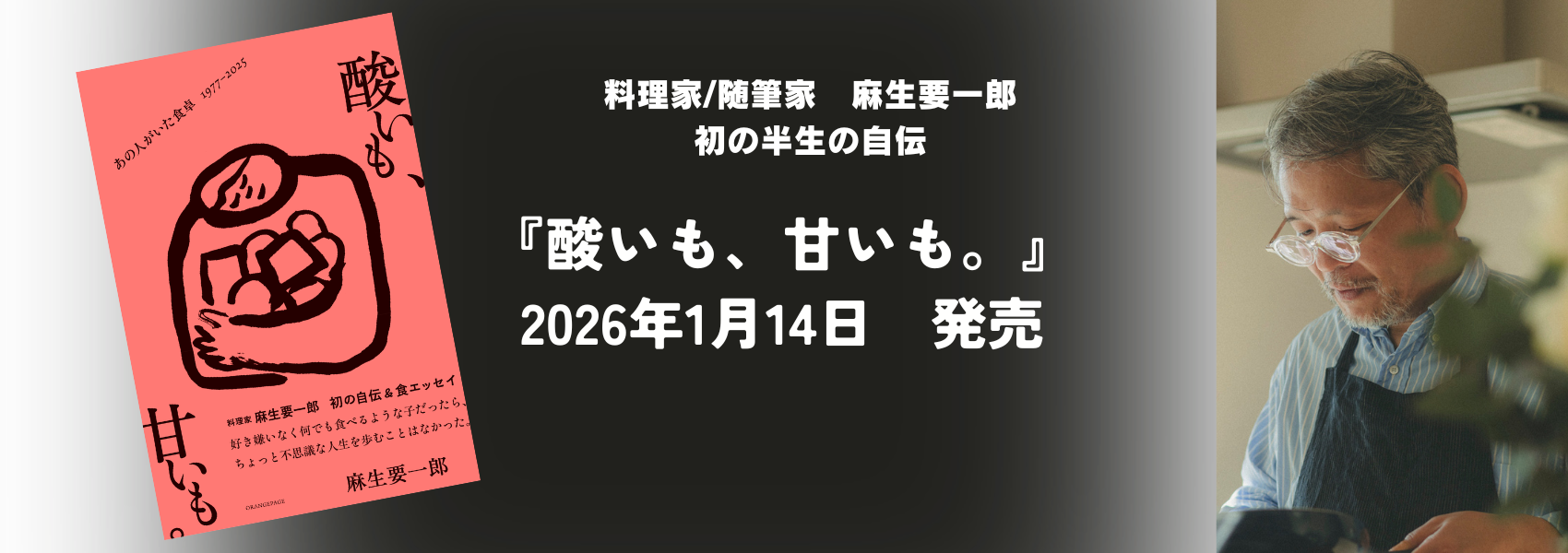昭和男子たちの生活面での自立を提案する「ジリメンのススメ」、前回は「生活面で自立する“ジリメン”の料理は男の趣味の料理とは違う」と、「継続」をキーワードとして皆さんにお伝えしました。そして、いよいよ今回から「継続できる自立の料理」編に入ります。「自分の食べるものを自分で作ること」は、大げさに言えば生殺与奪の権の奪還とも言えます。そして、生きるために継続する料理は最低限でいい、そう、さとなおさんは自らの試行錯誤の果てに断言してくれます。さて、その「最低限」とは……?
●前回の【vol.5 その料理、毎日毎食、作れますか?】はこちらから。
●今回初めてこの連載を読んでくださっている皆さん! ぜひ、vol.1の「宣言編」をご一読ください。
【vol.1 もしかしてオレ、自立してなかった⁉】
佐藤尚之(さとう なおゆき)さん
コミュニケーション・ディレクター。
1961年東京生まれ。著書に「ファンベース」(ちくま新書)、「明日の広告」(アスキー新書)など。また“さとなお”の名前で「うまひゃひゃさぬきうどん」(光文社文庫)、「沖縄やぎ地獄」(角川文庫)、「沖縄上手な旅ごはん」(文藝春秋)、「極楽おいしい二泊三日」(文藝春秋)などがある。
2018年にアニサキスアレルギーになって外食や旅に行けなくなり生活がガラリと変わる。一汁一菜を毎日作ってインスタグラムにアップもしている。
facebook
http://www.facebook.com/satonao
instagram
https://www.instagram.com/satonao310/
一汁一菜instagram
https://www.instagram.com/enjoy_ichiju_issai
note
https://note.com/satonao310/
撮影/原 幹和(佐藤さん/山口さん)
料理本のほとんどはボクたちにとってTOO MUCH!
前回(連載第5回目)、自立のための料理とは「継続」や「習慣化」が一番大切だと書いた。
カレーや唐揚げ、パスタなどの「趣味の料理」はいったん封印して、料理を毎日の習慣、つまり「歯磨きの領域」に持っていこう。そう書いた。
歯磨きの領域。
つまり、毎日無意識にできるレベル。
どんなにやる気がなくても毎日続けられる習慣。
そう、「やる気」があるうちはいい。容易に続く。始めた頃は特にそうだろう。
問題は「やる気レス」のときだ。
やる気がまったくないときにでもなんとか続くこと。それが「歯磨きの領域に近づいた自立の料理」なのである。
改めて妻や母の毎日毎食の仕事ぶりをよく観察してみてほしい。
どんなに疲れているときでも、どんなに落ち込んでいるときでも、どんなにやる気がないときでも、キッチンに立って作ってくれている。
これはすごいことであり偉業だと思う(だって男性の会社仕事は土日休みだけど、もし妻が専業主婦なら家の仕事は土日もない。共働きなら言わずもがな)。最大限感謝すべきことなのだが、これをボクたちも出来るようになることが重要だ。そうならないと「自立」とは言えないだろう。
では、「やる気レス」でも出来る料理とは何か。
その代表格&決定版として「一汁一菜」を前回提案させていただいた。そして今回ご紹介するのは「極限まで簡略化した一汁一菜」である。
「いや、お気に入りの料理家さんがいるから、どうせ毎日作るならその料理本のレシピを作ってみたい」
「どうせ毎日やると決めるなら、料理がうまくなりたいからじっくり初心者用の料理本に取り組んでみたい」
うん、わかる。
わかりすぎるほどわかる。
だってボクも通ってきた道だから。
でもね、さっき妻や母を観察したでしょ。
あれ、生半可じゃないです。まず続かない。一週間で面倒になってくる。いやホント、保証する。
百歩譲って「いま現在すでに料理が好き」という人ならそれでも続くかもしれない。でも、もしあなたが「いままで料理をほとんどやってこなかった人」だと、そういうレシピ本を追っても確実に挫折するだろう。
なぜならボクたち「継続を目指すジリメン」にはTOO MUCHなのだ。
たとえその本が初心者用にカスタマイズされていても、下拵えして、計量して、合わせ調味料作って、炒めて、味を調えて、小鉢も作って、とか、そんなことやっていたらまず続かない。「歯磨きの領域」には程遠い。
極限まで簡略化した一汁一菜。
マジでこれをオススメする。悪いことは言わない。まずはここを入口に、続けてみてほしい。
大切な前提:自分のためだけに作ること
ひとつだけ、大切な前提を設けたい。
それは「自分のためだけに作ること」。つまり、家族に食べてもらうとか、しないことだ。
誰かのために作る。それこそが料理であり喜びの根源。そんなことを書いてある本もたくさんある。でもね、ジリメン第一歩目にそれを意識しちゃうと続かない(断言)。
たとえば「せっかくなら妻にも食べてもらおう」って考えるよね。自然なことだ。
妻も「どうせ作るなら私の分も作って。ご飯作るのさぼれてちょうどいいわ」ってなると思う。これまた当然の成り行き。
でも、「誰かに作る」という要素が入ってくると「おいしく作らないと」とか「下拵えもちゃんとしよう」とか「前回とは味を変えよう」とか、余計な要素や思考が増えてしまう。これが継続のハードルになる。継続のためにはとにかく要素を減らすことが大切だ。
妻は妻で、「ねぇ、このさやいんげん、筋とってないでしょ!」とか「にんじんは皮を剥いてほしい!」とか「煮立てすぎ!味が飛んじゃう!」とか、ついいろいろと口を出したくなってしまう。
これも仕方がない。だって会社で言ったら経験豊富な上司みたいなものだ。右も左もわからない新入社員の仕事ぶりを指導したくなるのと一緒。仕方がない。でもこの「善意のおせっかい」や「ガミガミ」が料理を続かなくする。
とにかく、せめて最初の100食(毎日一食作るなら約3ヶ月)くらいは「妻にも子どもにも食べさせず、自分のためだけに作る」と決めて、一人分だけを作ってほしい。妻も最初の3ヶ月だけ口出すのを我慢してほしい。
とにかく「自分のためだけに」作る。
そうすると少々おいしくなくてもあんまりがっかりしない。致命的な間違い(全然煮えてなくて根菜が噛み切れないくらい堅いとか)を犯しても「ま、いいか」と諦められる。
そう、おいしいおいしくないは、継続のずっと後。
習慣化のかなり先に考えるべきことなのである。
一汁一菜に必要な道具:小鍋、包丁、まな板
ということで、極限まで簡略化した一汁一菜を始めよう。
まずは道具だ。
くり返すが「自分のためだけ」に作る。道具もできれば自分用を確保しよう。なかなか良いですよ、自分の道具を持つのって。妻は妻で「自分の愛用道具」を初心者である夫に使われるのを嫌がる人もいるだろう。
だから自分用の道具を持とう。
道具から入るのは特にガジェット好きな男性には向いている。
とはいえ申し上げたい。
計量カップも大さじ小さじもキッチンばさみもピーラーもいらない。あった方が後々便利とか思って買いたくなるだろうけど、まずは我慢。せっかく揃えたのに使っていない、って意外と苦になる。最小限の道具で始めるのも継続のコツのひとつなのだ。
小鍋と包丁とまな板。
この3つでいい。これで一汁一菜は作れる。
正確に言うと、他に「炊飯器、丼ひとつ。お椀ふたつ、お箸、スプーン(orお玉)」は必要だ。まぁ炊飯器はあるだろう(うちはずっと鍋で炊いていたので炊飯器は買ったけど)。あとのものもわざわざ買い揃えなくても家にあるものだ。
とにかく最小限から始めよう。必要になったらひとつひとつ増やして行こう。自分で必要性を理解して買うのって快感だし楽しいですよ。楽しみはあとに取っておこう。
ではざっと「料理の段取り」をご説明する。
段取り、というほどのことはない。極限まで簡略化した一汁一菜だ。簡単だ。
ボクはこの作り方で1年4ヶ月毎日作って約1000食継続している。
料理が続いたためしがないボクが続いたやり方、最初だけでも、ぜひ、マネしてみてください。
(1)炊飯器で米を炊く
「どうせなら土鍋で炊きたいな」とか欲を出すなかれ。3年早い。まずは「継続」がメインテーマだ。
米の洗い方・炊き方はトリセツか検索で調べてほしい。超簡単だ。洗米はいい加減でいい。どうせあなたしか食べないのだ。少しくらいぬか臭くても大丈夫。
最近の米は精米技術の進歩で軽く洗うくらいでよくなっている。無洗米だって売っている。ボクの場合は玄米なので、落とす”ぬか”がない。洗米と言っても軽くギュッギュとするくらい。簡単だ。
その炊飯器に「一合炊き」があったら一合炊き。そうでない場合は三合くらい炊いてラップで包んで冷凍しよう。ラップの仕方、冷凍の仕方も検索すればすぐ出てくる。ラップは少し面倒だ、という方は100円ショップなどで「ごはん冷凍容器」も売っている。
(2)では具沢山味噌汁を作ろう。まず丼に一杯分の水を入れる
さて味噌汁だ。ざっくり10分〜15分で出来上がる。
初期の一汁一菜において主に作るのは味噌汁だけだ。慣れてきたら「一菜」としておかずを作ってもいいが、初期は納豆パックとか豆腐パックをあけるだけでいい。その方が続くし栄養も充分だ(具沢山味噌汁が栄養たっぷりだし、たんぱく質的にもかなり優秀な組み合わせである)。
味噌汁はお椀ではなく丼がオススメ。男性でも丼に具沢山(ぐだくさん)の味噌汁ならお腹いっぱいになる。
計量カップとか使わずに、飲む量の水を丼に入れる。それが今日の味噌汁の分量だ。それで良い。シンプルだ。

(3)丼の水を小鍋に移す
この小鍋は雪平鍋でもミルクパンでもなんでもいい。「一人前の味噌汁」なので、中鍋より小鍋がいいと思う。大は小を兼ねない。家にあったらそれを使おう。なかったらスーパーで2000円とかから売っているので充分だ。ボクも初期は安い雪平鍋を使っていたが、1年くらい経ったあたりで使い勝手を考えて柳宗理のミルクパンに買い替えた(下の方の写真に写っている独特の形をした鍋)。
(4)あいた丼に今度は野菜を切って入れる
水を移した丼に具材を切って入れる。野菜や肉、魚類、なんでもよい。
大丈夫、味噌汁はブラックホールだ。何でも受け入れ、何でもおいしくしてくれる。
そして「自分しか食べない」という前提がここで大切になってくる。どうせ自分しか食べないのだから、多少の味の乱れや個性は許容範囲なのだ。
ちなみにボクは野菜の皮は剥かない。筋も取らない。全部そのままぶち込む。
え? 残留農薬? うん、それについては専門書も買って読んでみた。毎日毎日相当の量をカラダに入れない限り健康に影響ないと知った。だからさっと洗うくらいでもう気にしていない。子どもは気にしたほうがいいかもしれないが、ジリメンを目指す45歳以上の男性など、ほぼ気にしなくていいと思う(これは個人的な意見なので、それぞれ考えてやってみてください。でも、皮を剥く手間は「継続」を確実に難しくするので、初期は剥かないで進めた方がいいと思う)。
あと、下の写真を見て欲しいのだけど、丼からはみ出るくらいたくさん入れている。茹でると嵩(かさ)が減るので、このくらい多めに切って大丈夫。

いつもはもっとぐじゃぐじゃに放り込んでいる。丼容量より多くても茹でると嵩が減るので大丈夫。
(5)丼の野菜を小鍋にぶち込み、中火にかける
本当は「根菜を先に」とか「葉物は最後に」とかあるのだが、そういうのは馴れてからでいい。初期は「とにかくぶち込む」でいいと思う。すべては「継続」と「習慣化」のための簡略化だ。全部ぶち込もう。
(6)ひと煮立ちしたら火を止め、味噌を溶き入れる
ひと煮立ちとは「鍋の中の汁や煮汁がふつふつとしっかり沸騰すること」だ。「沸騰してひと呼吸」くらいなニュアンス。グラグラ煮込むのとは違って、まぁ沸騰してから十秒待つくらいな感じかなぁ。これもそのうち塩梅(あんばい)がだんだんとわかってくるだろう。何事も慣れが大事。
味噌は火を止めてから最後に入れるのだが、お玉かスプーンで適当に入れればいい。敢えて計量するなら一人分で大さじ一杯強くらいだが、そんなの面倒くさいので大スプーン一杯とかで良い。飲んでみて濃かったら少なく、薄かったら多く、と数回試行錯誤するとだんだんわかってくる。それで充分。
で、入れたお玉かスプーンでかき混ぜればだいたい溶ける。もしくは食事に使うお箸でお玉の上で溶かしてもよい。菜箸? 洗い物が増えるだけ。自分のお箸で混ぜればよい。自分しか食べないんだし。

※鍋が扁平なのはそういうデザインの鍋だからなので気にしないでください。
これでほぼ味噌汁完成だ!
馴れてくると10分かからない。
え? だし?
かつおだしとか使いたい方は使ってもいいけど、男性は「かつお節削り器」とか買ったりしてすぐ凝ってしまう。そういうの絶対続かないので、だしの素みたいなもので充分だと思う。
ただ、「いい味噌」さえ使えば充分にコクが出るので、だしは特にいらないということはお伝えしておきたい。
土井善晴さんも著書『お味噌知る』の中でこう書いている。
「味噌汁を作るのに、だし汁(鰹と昆布)は不要です。水で具材を煮て味噌を溶く、それだけで充分と心得てください」と。
実際作って行くと、野菜やきのこからいいだしが出る。それだけで充分おいしくなる。どうしてもだしを取りたくなると思うけど、「継続」「習慣化」まではなしでやってみることをオススメするなぁ。
ということで、これで具沢山味噌汁の出来上がり!
炊飯器のお米をよそい、一菜は冷蔵庫にある豆腐パックか納豆パックで充分。
それで下の写真のようなお膳が完成する。

切り方を自己流にするのは危ない。プロにちゃんと習っておこう!
ざっくりした段取りは以上なのだが、いままでちゃんと料理を習ってこなかった人も多いと思う。なのでここからは「プロ」に習ってみたい。
料理のプロというより「自炊のプロ」のほうがふさわしいと思ったので、ボクも個人的に習いに通ったことがある「自炊料理家」の山口祐加さんをお招きして、「基本のキ」、「基礎のキ」を習ってみたい。
山口さんは、あえて「自炊料理家」を名乗っている。
つまり、自炊の伝道者であり、自炊が生活を、そして社会を変えることを心の底からわかっている人だ。ボクたちにピッタリすぎる先生なのである。

山口祐加(やまぐちゆか)さん
自炊料理家®︎
1992年生まれ。東京都出身。出版社、食のPR会社を経て独立。共働きで多忙な母に代わって、7歳の頃から料理に親しむ。現在は料理初心者に向けた料理教室「自炊レッスン」やレシピ・エッセイの執筆、音声プラットフォームVoicyにて「山口祐加の旅と暮らしとごはん」を配信中。著書に『自分のために料理を作る 自炊からはじまる「ケア」の話』(晶文社/紀伊國屋じんぶん大賞2024入賞)、『自炊の壁 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法 』(ダイヤモンド社)など多数。
note「山口祐加の海外自炊通信」
https://note.com/yucca88/m/mb0a92b36ef45/hashtag/34956
山口祐加 オフィシャルサイト
https://yukayamaguchi-cook.com
ということで、山口さん、すいません、超初心者が毎日の料理を「継続」できるギリギリ最低限のスキルを教えてください!
はい、みなさん、こんにちは。
自炊料理家の山口祐加です。
ここから数回に渡って、さとなおさんといろいろ話しながら、「料理の基本のキ」をお伝えしていきたいと思います。
佐藤「ありがとうございます。今日はまず『切り方』について、料理を一度も作ってこなかった中高年の男性にもわかるように教えていただけますか?」
山口「はい。では、包丁の話からしましょうか。
まず自分専用の包丁を買うことをオススメしたいです。
いろいろな種類の包丁をそろえる必要はまったくありません。
家庭用の「三徳包丁」が一本あれば十分。値段は5000円以上、1万円くらいまでのものがおすすめです。それより高価な包丁は趣味の世界です。なかなか研ぐこともないと思うのでそのくらいの値段の品質のものを買えば、研がなくても長く持ちます」
佐藤「小さいペティナイフとかより三徳包丁がいいんですね?」
山口「包丁は重さも大切なんです。軽すぎると切りづらいんですよ。
刃渡りは大体18cmくらいが扱いやすいですが、これも好みで。握ってみていい感じのものを買うといいと思います。
値段は1000円くらいの安いのもたくさん売ってますが、すぐに切れなくなってしまいます。包丁はそんなにすぐ捨てないものだから長持ちするものがいいですね。
あと、研ぎたくなったら、「研ぎ」のサービスをしているところがあるのでそこで。私は近所の床屋さんがやってくれるのでそこに出しています。シャープナーも売っていますが、個人的にはあまり切れるようになった感じがしないですね。金物屋さんとか『研ぎ』のサービスのあるところに頼んだほうが切れ味のレベルが上がりますし、テンションも上がります」

包丁は上から押し切りしないことが大切!
佐藤「持ち方、構え方も意外とわからないんですよね。。。」
山口「はい。包丁の持ち手は人が握りやすいサイズにできているので、自分が扱いやすい位置で持つのがいいですね。指で刃を握らないようにだけは注意してください。
私は人差し指の第一関節を「包丁の刃の背の部分」にくっつけています。この第一関節で切る方向性と、切る厚みなどをコントロールする感覚です」


佐藤「切るときの体勢というか、立ち方を教えてください」
山口「はい。特に初心者はまな板の真正面に向かって立つ人が多いんですが、それだと右手が動かせないんです。
使う手と同じ側の脚を少し後ろに引くのが重要です(約一歩分)。右利きなら右脚、左利きなら左脚。そうすると体全体が少し引くので手と肘が動く隙間ができるんです。
テニスやゴルフでもボールを打つ方向に対して正対して立ちませんよね。それと同じと思ってください」

佐藤「なるほどー。よくわかります。で、切るわけですが・・・」
山口「なんでしょう、初心者の方はみなさん下に向かって押して切るんですよね。包丁は上から下に押しても切れません。そこだけ覚えておいてください」


佐藤「まな板に押しつけて切るイメージがありますよね」
山口「そうなんです。でもそれだと切れないんですよ。
時代劇で侍が人を切るときに斜めにスライドさせていますよね。あれと同じ。刃物は斜めにスライドした瞬間にモノを切り始めるんです。上から下に「押す」のではなく刃物をずらしながら動かすのが重要です。
奥に押しても手前に引いてもいいです。とにかく斜めにスライドさせるんです!」


佐藤「あぁ、斜めにスライドさせていくとスムーズに切れますね。
なんか、母親がトントントンと切っているイメージがあって、上から下に押しがちですが、トントントンというよりニュッニュッニュッと斜めに入れていくイメージですね」
山口「そうなんです」
利き手じゃないほうは猫の手??
佐藤「右手で切る場合、左手はどうすればいいですか?」
山口「ちょっとにんじんを切ってみましょうか。
お味噌汁に入れることが前提なら、私ならまずは半分に切ってしまいます」


山口「で、丸いままだと転がりそうなので、安定させて作業するために、下のほうを薄く切る。そうすると安定してまな板におけるようになります。
ちょうどこんな感じで(下の写真参照)、下を薄くスライスするんです」

もちろん薄くスライスしたものも味噌汁に入れましょう。

佐藤「なるほどー。丸いまま上から押さえて切っていました」
山口「それでもいいんですが、安定が悪いのでケガの危険があります。なので私は下を切って安定させますね」
佐藤「マネさせていただきます」
山口「で、こういうとき、包丁を持っていないほうの手はよく『猫の手』っていうけれど、実際はちょっと怖いので、私のオススメは『幽霊の手』ですね」
佐藤「幽霊の手?」

山口「はい(笑)まぁ猫手に似てはいますが、指は伸ばしています。
で、人差し指の第一関節を包丁の腹にくっつけます」

山口「第一関節をずらすことによって厚さを変えてるって感じですね。ちょっと爪切りそうですが、指を曲げてる限りは切れないんで。この関節を前に出すか、後ろに引くかで厚さが変わる感じです」
佐藤「おお、急に難しくなってきた気がしますが、この上の写真(↑)をよく見て、切り方を覚えるといいですね」


山口「そうですね。これはリアルで会ってお教えしないとなかなか伝わりにくいかもしれませんが、人参みたいな堅い根菜で一度練習してみてください。たぶん感覚はわかっていただけると思います」
佐藤「慣れてくると、トントントンと切れますかね」
山口「あのですね、料理を始める男の人は、たいてい母親の『トントントン』というリズミカルなイメージに憧れるんですが、そのイメージは捨ててください(笑)
『トントントン』ではなくて『トン・・・トン・・・トン・・・』でいいんです。早さよりも確実にケガせず切ることを意識してください」
佐藤「なるほど、そりゃそうですよね。こちとら超初心者なわけですし」
山口「そうなんですよ。だって私は7歳の時から包丁を持っているからトントン切れるんです。皆さんが会社で一所懸命働いている時間、ずっと料理してきたわけですから。
専業主婦が多かった時代のお母さんもいっしょです。トントントンは忘れて、トン・・・トン・・・トン・・・でゆっくり切って下さい。それでもお味噌汁が出来るのに1分くらいしか余計にかかりません。ぜひゆっくり切って習慣にしてくださいね」
※次回、「炒め」「茹で」「焼き」を習っていきます!
Check It Out!
→次回に続く【vol.7 味噌汁は「主菜」と考える】
●「ジリメンのススメ」【 vol.1 もしかしてオレ、自立してなかった⁉】
「ジリメンのススメ」記事一覧
【宣言篇】Vol.1「もしかしてオレ、「自立」していなかった!?
【社会問題篇1】vol.2浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(前編)
【社会問題篇2】vol.3浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(後編)
【料理篇4】vol.8 自炊料理家/山口祐加×佐藤尚之対談「おいしさ」を求めるとジリメン料理は続かない!