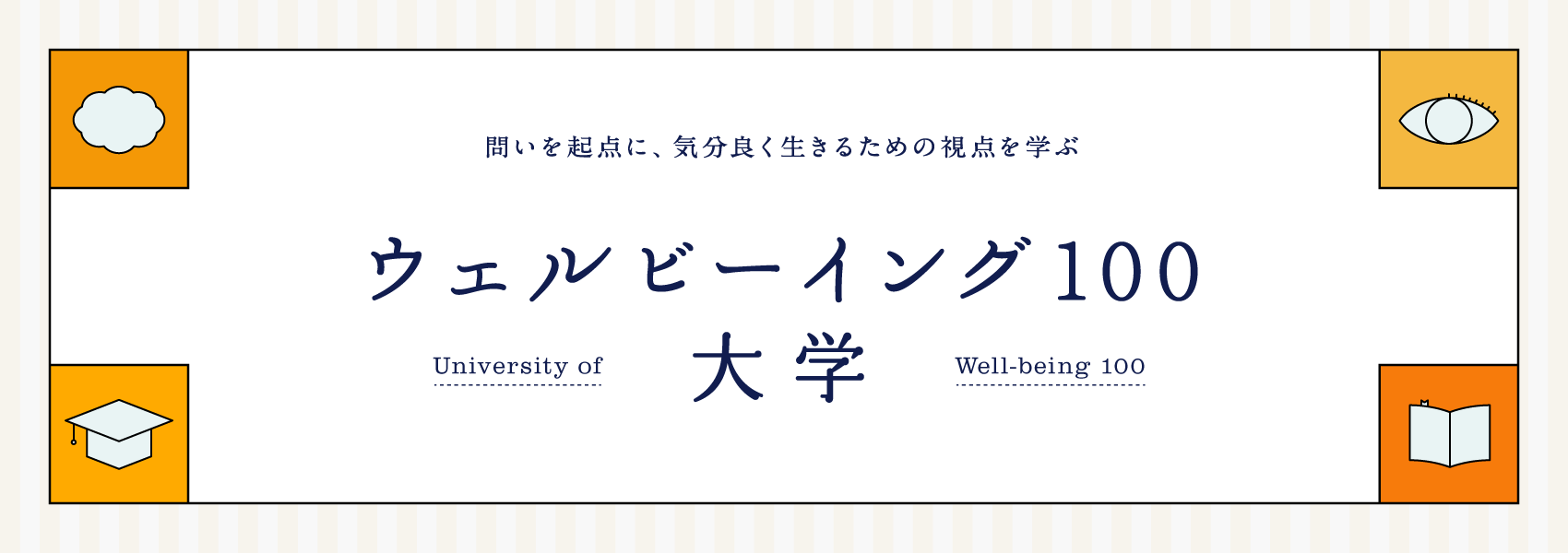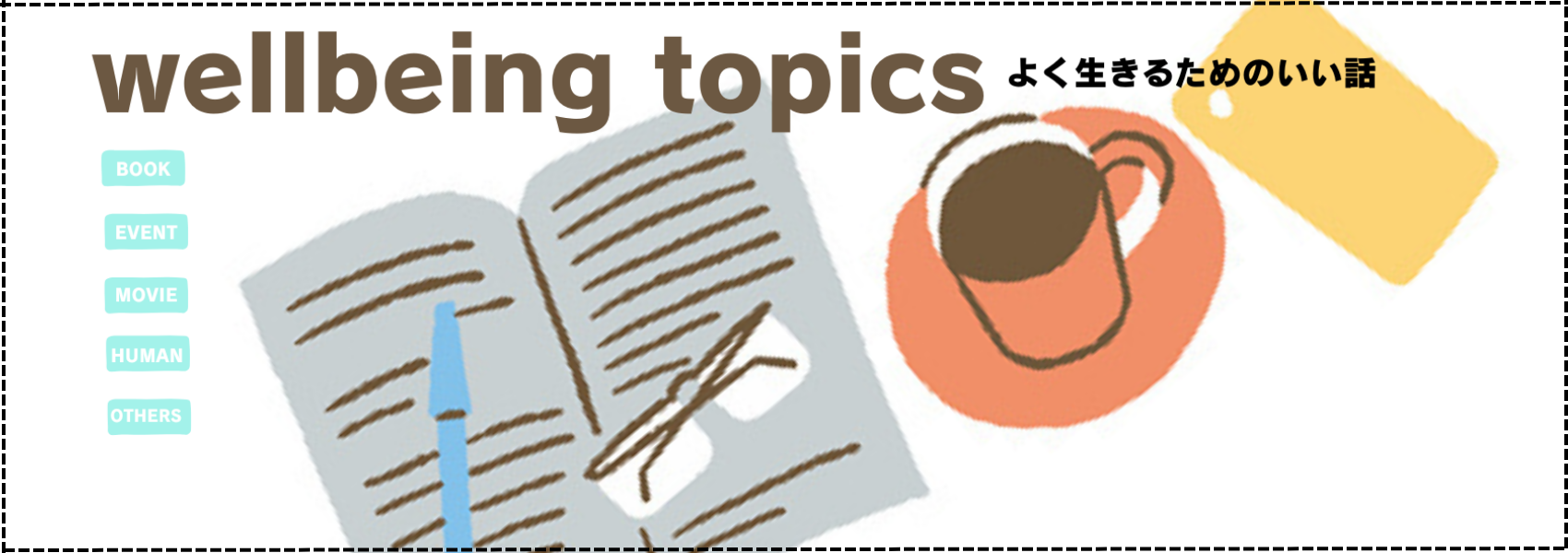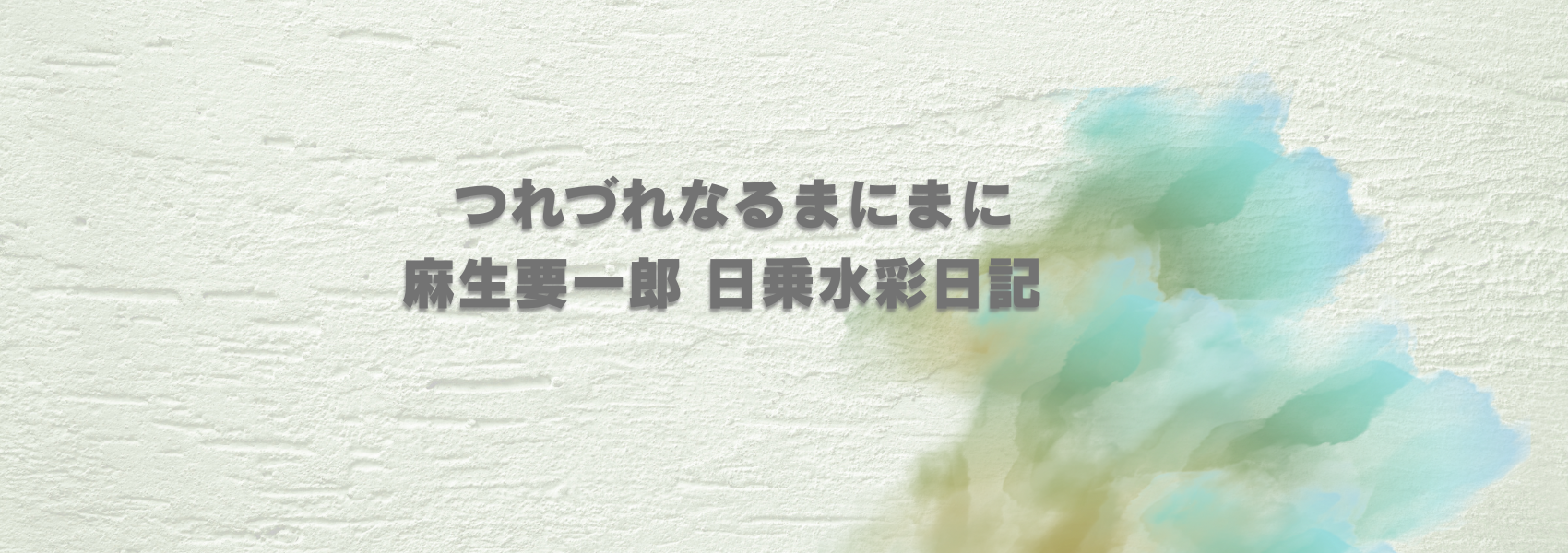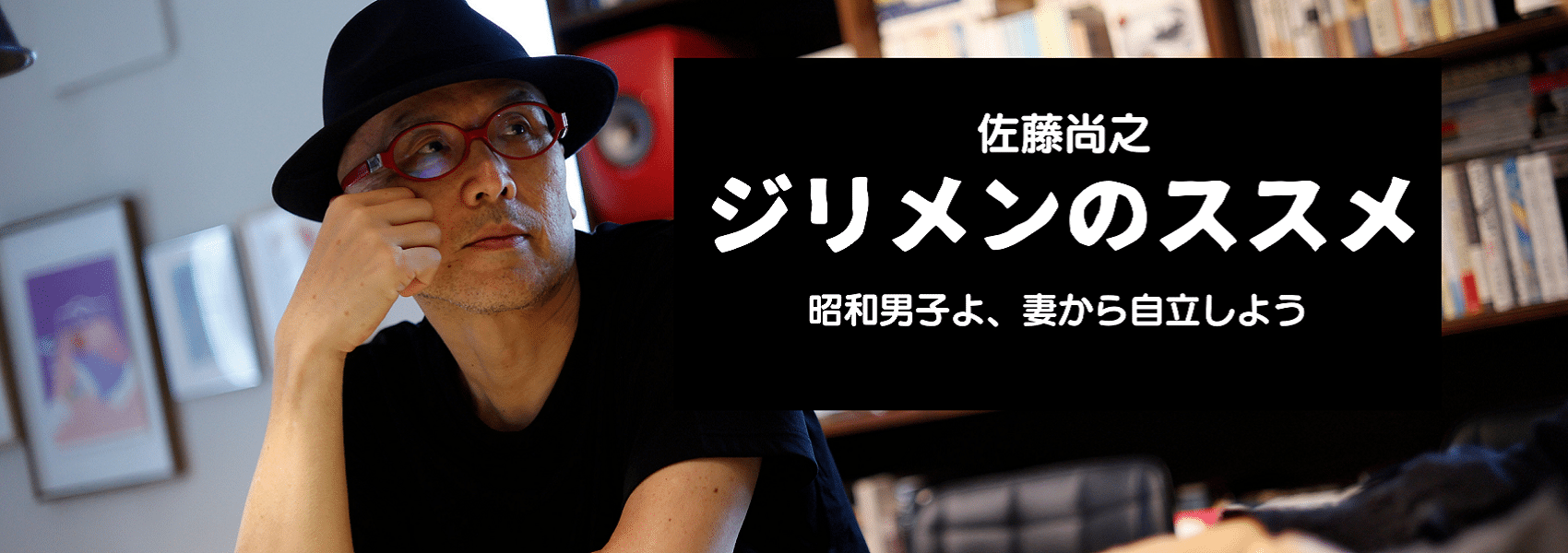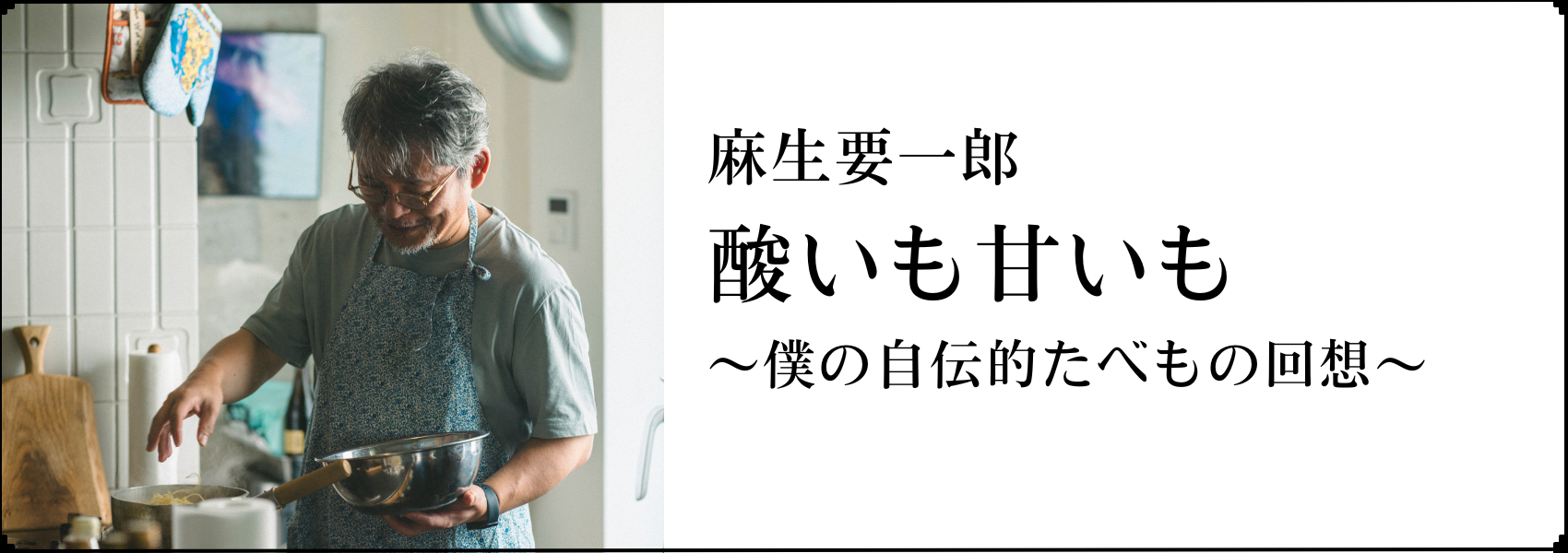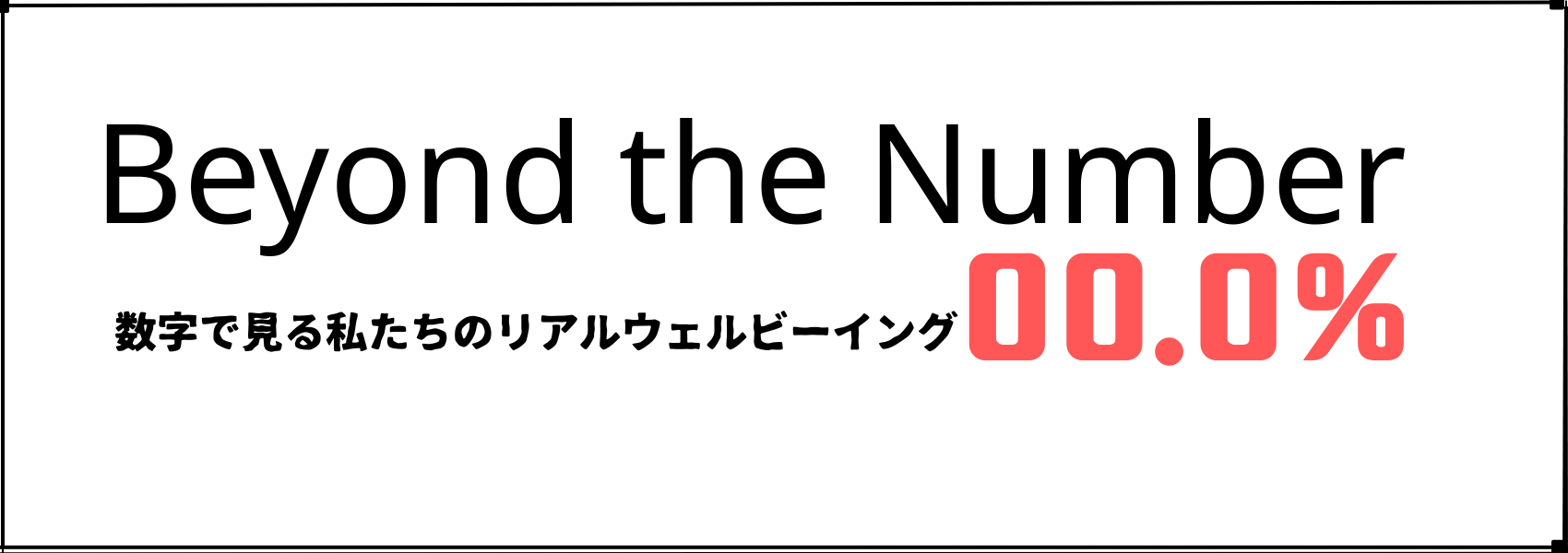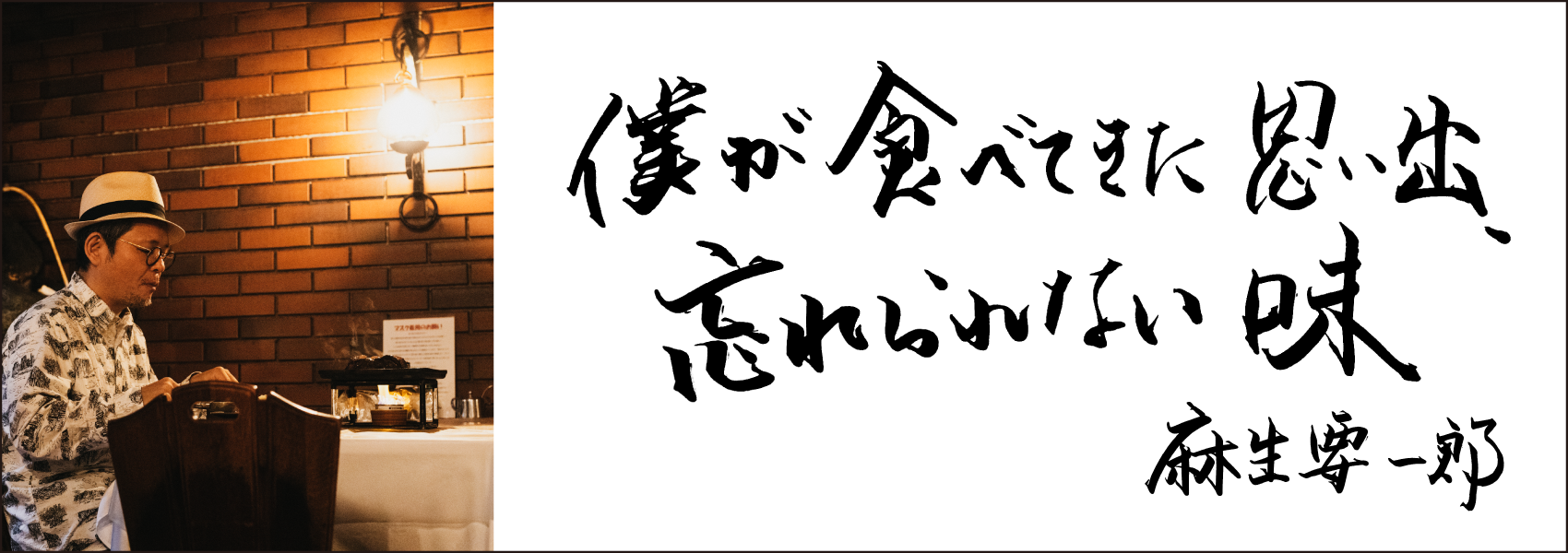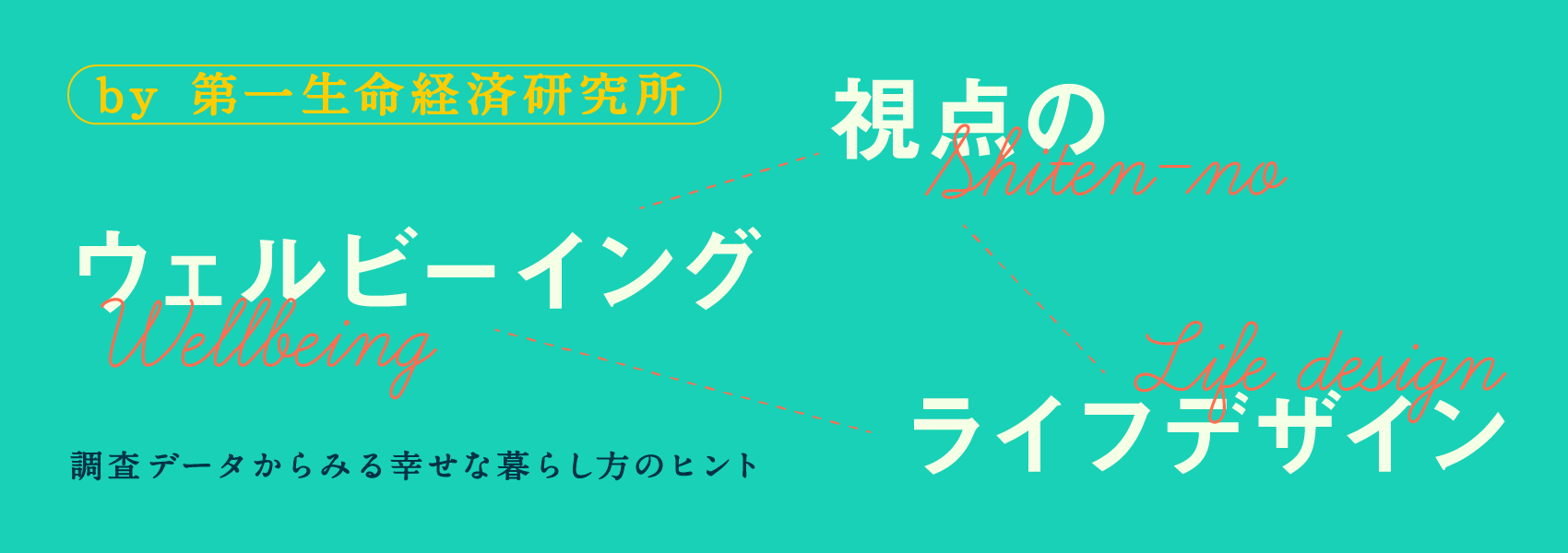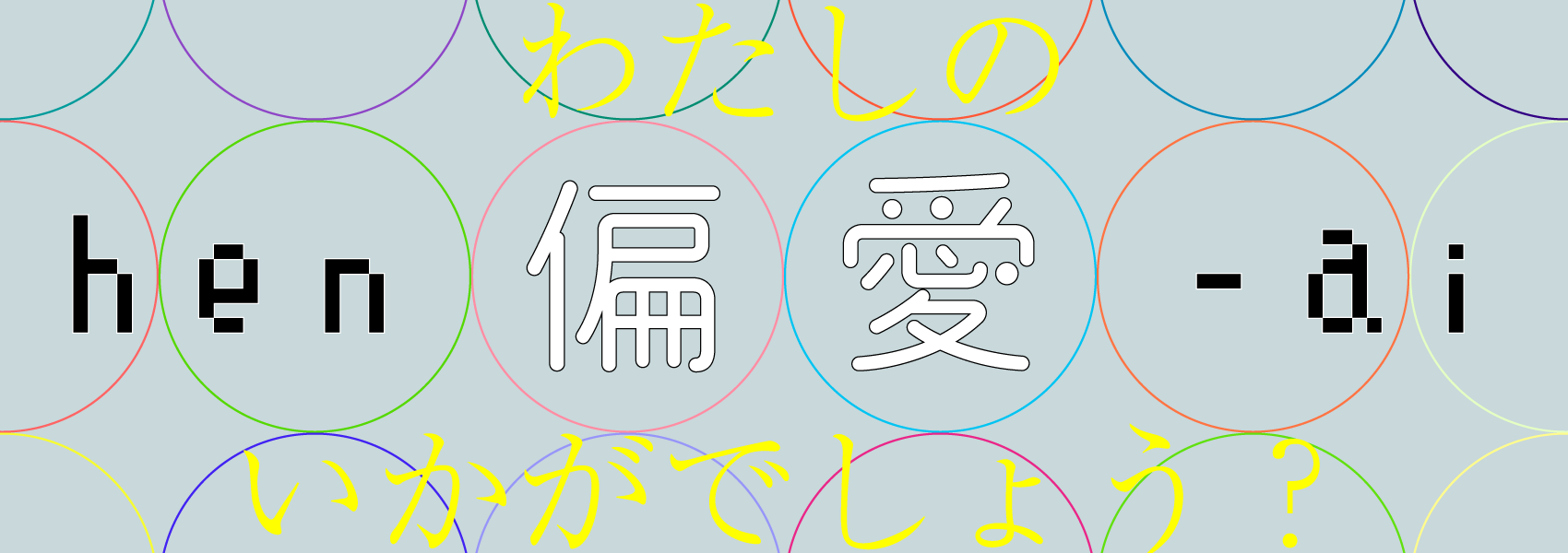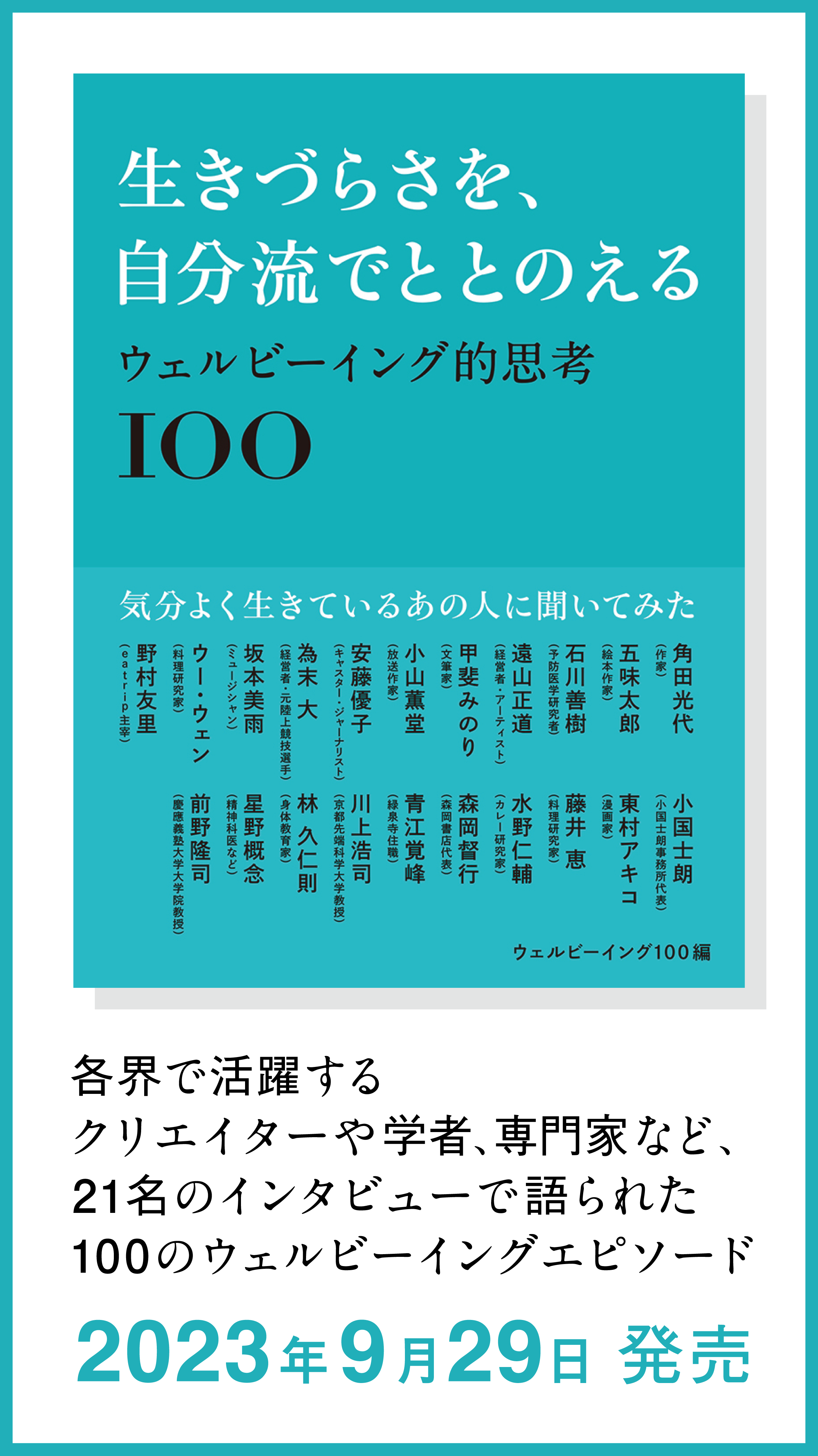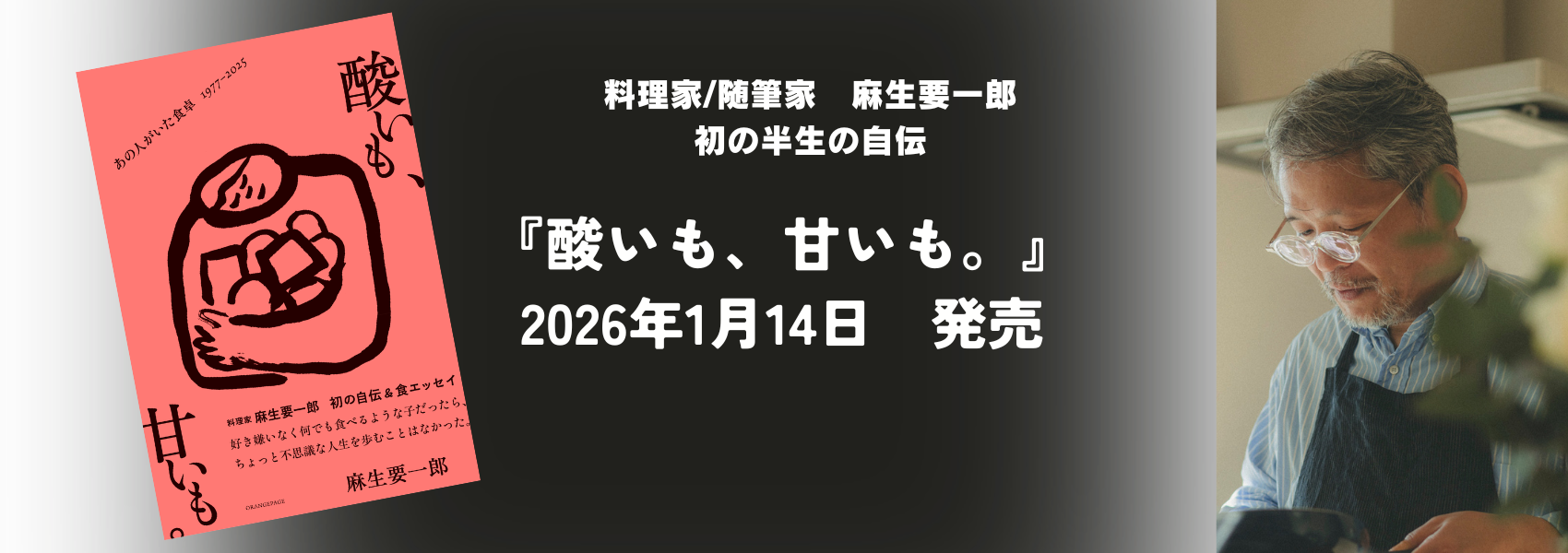麻生要一郎さんが小学生だった頃の話です。いやいや参加した剣道の合宿でごはんがまずくて食べられなかった麻生少年の姿がまざまざと目に浮かびます。幼いころには自分が親に似ているなどとあまり思わないものかもしれませんが、大人になって振り返ると「ああ、やはり自分は親に似ているな」と感じることも多いのでは。「嫌なものは嫌」として頑として受け付けない、麻生さんの芯にあるダイヤモンドのように硬くて尊いものが感じられます。
著者紹介
麻生要一郎(あそう よういちろう)
料理家、文筆家。家庭的な味わいのお弁当やケータリングが、他にはないおいしさと評判になり、日々の食事を記録したインスタグラムでも多くのフォロワーを獲得。料理家として活躍しながら自らの経験を綴った、エッセイとレシピの「僕の献立 本日もお疲れ様でした」、「僕のいたわり飯」(光文社)の2冊の著書を刊行。現在は雑誌やウェブサイトで連載も多数。2024年は3冊目の書籍「僕のたべもの日記 365」(光文社)を刊行。また、最新刊は当サイトの連載をまとめ、吉本ばななさんとの対談を掲載した「僕が食べてきた思い出、忘れられない味 私的名店案内22」(オレンジページ)。
麻生要一郎さんのこちらの記事もご一読を!
●「ウェルビーイング100大学インタビュー」麻生要一郎さん
●「料理とわたしのいい関係」麻生要一郎さん
●麻生要一郎「酸いも甘いも ~僕の自伝的たべもの回想~」記事一覧
麻生さんの連載が本になりました。大好評発売中です!
●麻生要一郎「僕が食べてきた思い出、忘れられない味 私的名店案内22」
撮影/小島沙緒理
僕が小学校3年生の時に剣道を始めたのは、息子に武道をやらせたい父の意向だった。「剣道か柔道どっちが良い?」と言われて、どちらもやりたくないとは言えなかった僕は、剣道を選んだ。柔道は肉体のぶつかり合いという感じが苦手だったし、剣術にはやりたいかどうかは別として興味があった。小さい頃、時間を一緒に過ごす事が多かった、母方の祖父母が時代劇をよく観ていた影響があったのかも知れない。

小学3年生から父親の決めた道場へ通い始めた、稽古は毎週火曜と金曜日の夜だった。武道をやらせたいという父親は毎夜午前様、見に来るわけでもなかった。嫌々通う小学生と、嫌々通っているのを承知の上で送り迎えをする母。稽古が終わると、家の近所にあるお菓子屋さんに寄り道して、アイスを食べさせてくれたのは、母なりの労いだったのだと思う。

いざ始めてみると、防具をつけているとは言っても、誰かを棒で叩くことは苦手だった。動いている相手の小手を叩こうと思っても、変なところを叩いてしまいそうで気が引ける。おまけに防具は独特の匂いがするし、奇妙な声を出さなければならない。「3秒間、やーーーっ!とのばしてから、面とか小手。」と、決めてくれたらありがたいのにと何度も思った。今でこそ、何でも恥じらいなく出来るが、当時は一人っ子の引っ込み思案、先輩を見習って自由に大きな声を出してと言われたところで、もう憂鬱過ぎて家に帰りたくなってしまう。しかし、不思議なもので強い人はこういう面でもぬかりがない。キエエーーーッ!などと、オリジナリティ溢れる声を張り上げられる人は遠慮なく打ち込んで来てやっぱり強いのだ。そういう声を浴びせられるたび、僕は心の中で勘弁してくれよと思いながら、お返事のような声をあげて、なるべく早く退散することを考える。



チョビが島暮らしでまだ外へ出かけていた頃、意地悪そうな他の猫に「シャーーーッ!!」と、激しく威嚇されるとチョビが、可愛い大きな声で「マーーーッ!!」と返事をしていた。喧嘩に関しては痩せている猫達が多かったから、身体の大きなチョビが一歩前に出ると、迫力があるのか大体チョビが勝つことが多かった。やっぱり、僕とチョビはちょっと似ている。あの時も、チョビは仕方なしに声を上げていたのだろうと思う。



幸か不幸か通っていた道場は名門で(誰でも入れるのですが)、全国大会を主催していた。主催している割には劣勢が続いたため、僕が5年生のころに合宿が行われることになった。何チームかが結成されて、大会に臨む。末端のチームであったが、僕は大将に選ばれた。合宿なんて絶対嫌だなあと、仮病を使いどうにかさぼりたいと考えていたが、さすがに大将に選ばれてしまっては、参加せざるを得ない。



合宿の場所は、市内から離れた畑の真ん中にある農業系の学校で2泊3日。何十人かが一緒に布団を敷いて畳の部屋に寝泊まり、僕は一番隅っこを素早く陣取った。真ん中では、絶対に眠れる気がしなかった。練習を一日何時間やったかという細かい記憶は全くないが、ご飯が口に合わなかったことだけは、鮮明に記憶している。母の慣習で朝食はパンと決まっていたので、好きかどうかは別にしても朝から白飯と納豆に味噌汁が並んでは調子が狂う。これは未だに続いていて、例え旅館の美味しい和朝食であっても同じ気持ちになる。今のような米が高い現代においては、一日3度の白飯はありがたく贅沢なことだけれど、人にはそれぞれペースというものがある。おかずは、業務用冷凍食品の揚げ物、味のしない味噌汁。母が僕の好き嫌いに合わせていつも食事の用意をしてくれていた、過保護な要一郎少年は食べる気がしない。白飯は生命線と決めて食べていたが、他は一口食べてはそれでお終い。付き添いのお母さん方や先生方からは、その態度が本当に不評だった。最初のうちは優しく「お腹空いちゃうよ」と言ってくれていたのが「食べなさい!」と言われても、食べない。今も昔も、自分の決定は覆さない主義である。終わりの頃には「要一郎君は、普段いいもの食べているから」と嫌味を言われて、我関せずという感じだった。こちらも、嫌味を言われているのは分かるから、愛想笑いもしなくなるから、益々評判は悪くなる。

我が家も外から見たら会社を経営している家とはいえ、質素倹約の創業者の祖父のもと、贅沢な生活をしていたわけではない。最終日に何も知らずに迎えに来た母は、当番のお母さん方や先生からきっと嫌味を言われ、しつけがなっていないとか、我儘だと言われたかも知れない。母の姿が見えた時に僕は「もう帰れる!」と一目散に車に乗った。母は咎めたり、怒ったりしなかった。車に乗ると、僕が好きだったアーモンドが入ったチョコレートを渡してくれたのは、恐らくご飯が合わなかったと予想してのこと。普段はたくさん食べないように促されたが、全部食べてしまっても母は何も言わず、ただ静かにハンドルを握っていた。



帰り道、行きつけの洋食屋さんで早めの夕食。いつも頼むのは、カニクリームコロッケ。テーブルに運ばれてくると、まるで3日分の空腹を埋めるように、喋らずに夢中で食べた。今、改めて考えると、僕の性格は母にそっくり。夢中で食べている様子を、ぼんやり眺めていた母の表情を今も覚えている。きっと自分の性格を受け継いでしまっているなあと、思い悩んでいたのかも知れない。でも、自分の基準を崩さない感じ、好き嫌いがはっきりとしているお陰で、僕は今のちょっと不思議な人生を歩んでいるのだと思う。人生の分岐点で必ず、そういう事が試されてきて、今がある。例え、どんなリスクを負うとしても、嫌なものは嫌だと選択をしてきた。もし、好き嫌いに関わらずなんでも食べるような子だったら、今の状況は生まれていない。まだ家業の建設会社にいただろう。自分に子供はいないけれど、もし子供がいたとしたら、自分の褒められないような部分が際立って目につくのかも知れない。そして母のように思い悩むのだろう。益々複雑化する時代の中、そういう事で悩んでいる、親御さんも多くいらっしゃることだと思う。しかし、誰かの長所は裏返せば短所であって、短所もまた裏返せば長所になる、全ては捉え方次第だ。時間はかかるかも知れないけれど、きっとそれはその子の変え難い個性になるのだと、信じてあげて欲しい。

僕にとってカニクリームコロッケは、幸せな記憶の象徴。作るのには、ちょっと手間もかかるけれど、是非少し気持ちの余裕がある時に作ってみて欲しいと思います。

【 カニクリームコロッケ 】
材料(2人分)
・コロッケ
かに(缶詰・約100g入り) 1缶
玉ねぎ 1/2個
白ワイン 大さじ1
小麦粉 50g
牛乳 200cc
塩、こしょう 各適宜
バター(有塩) 25g
・ころも
小麦粉 50g
卵 2個
パン粉 50g
揚げ油 適宜
作り方
1 かには軟骨を取って粗くほぐす(缶汁はとっておく)。玉ねぎはみじん切りにし、弱火で熱したフライパンにバターを溶かして、しんなりするまで炒める。かにの身、白ワインを加えて炒め合わせる。小麦粉を入れて、弱火で炒める。
2 牛乳を少しずつ加えて、最後にかに缶の汁も加え、全体がまとまってきたら、塩、こしょうで味を整え、バットに移す。ラップで覆い、冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。
3 好きな大きさに成形し、小麦粉、卵、パン粉の順に衣をつける。揚げ油を180度に熱してコロッケを加え、こんがり揚げ色がついたら完成です。
→次回に続く【朝のパンとコーヒー】
●麻生要一郎「酸いも甘いも ~僕の自伝的たべもの回想~」記事一覧
麻生さんの連載が本になりました。大好評発売中です!
●麻生要一郎「僕が食べてきた思い出、忘れられない味 私的名店案内22」