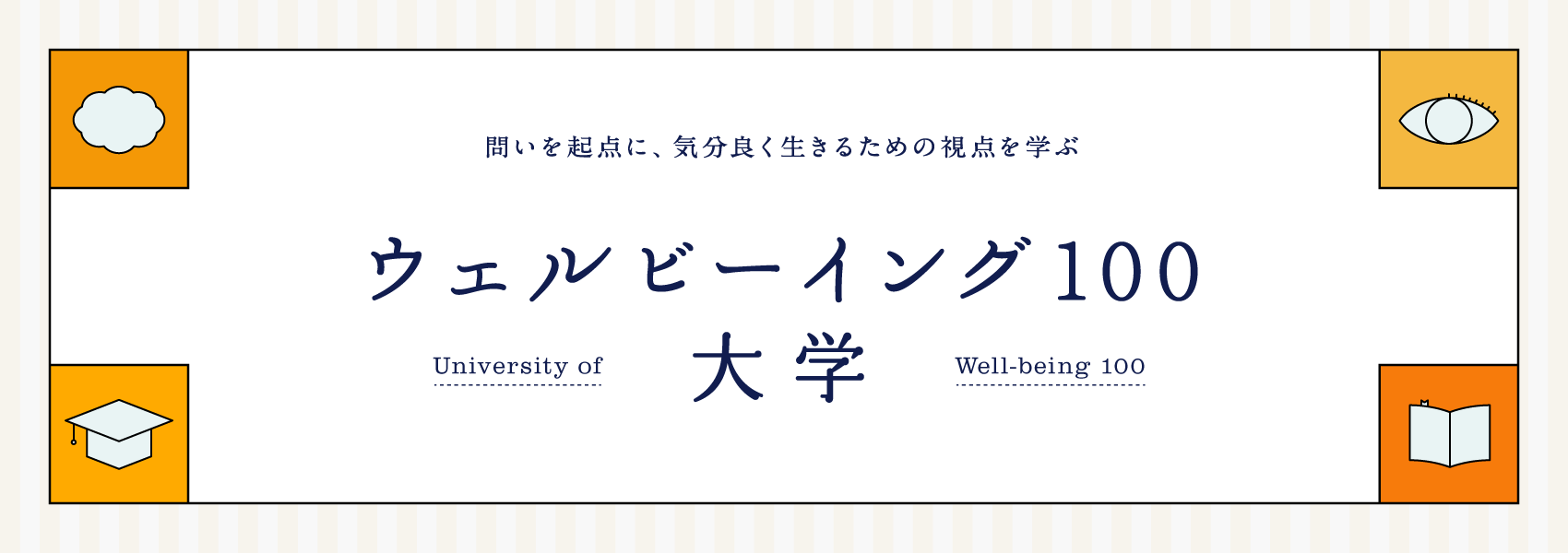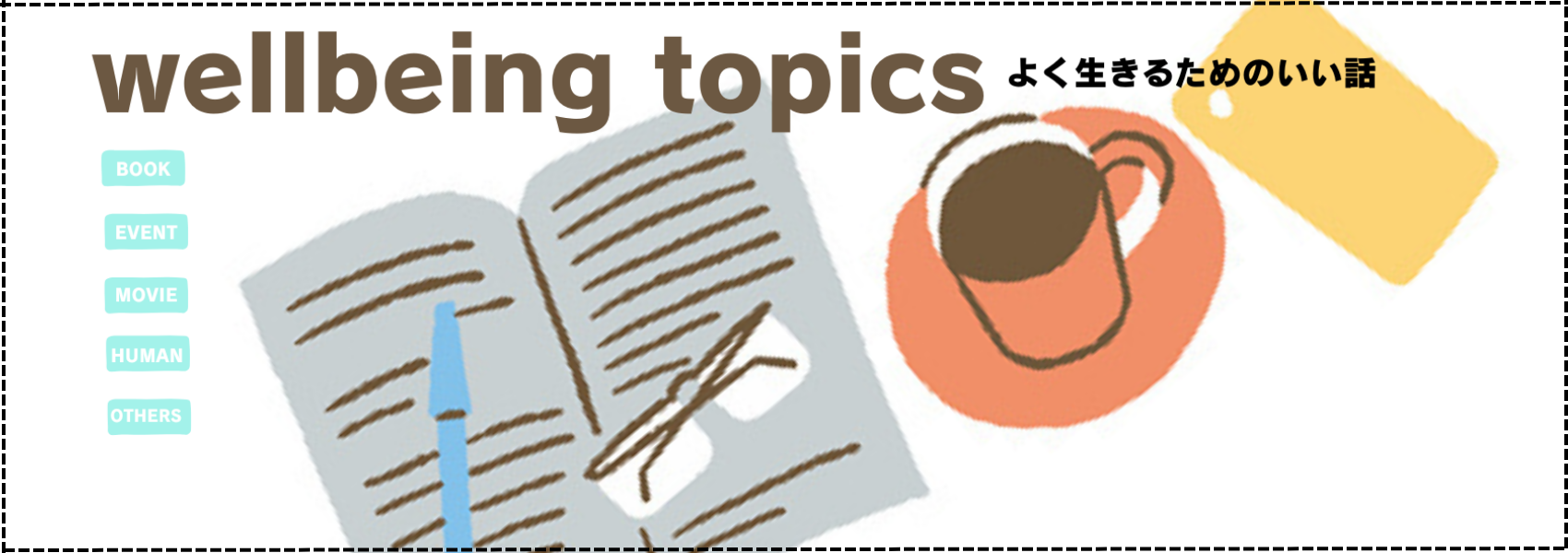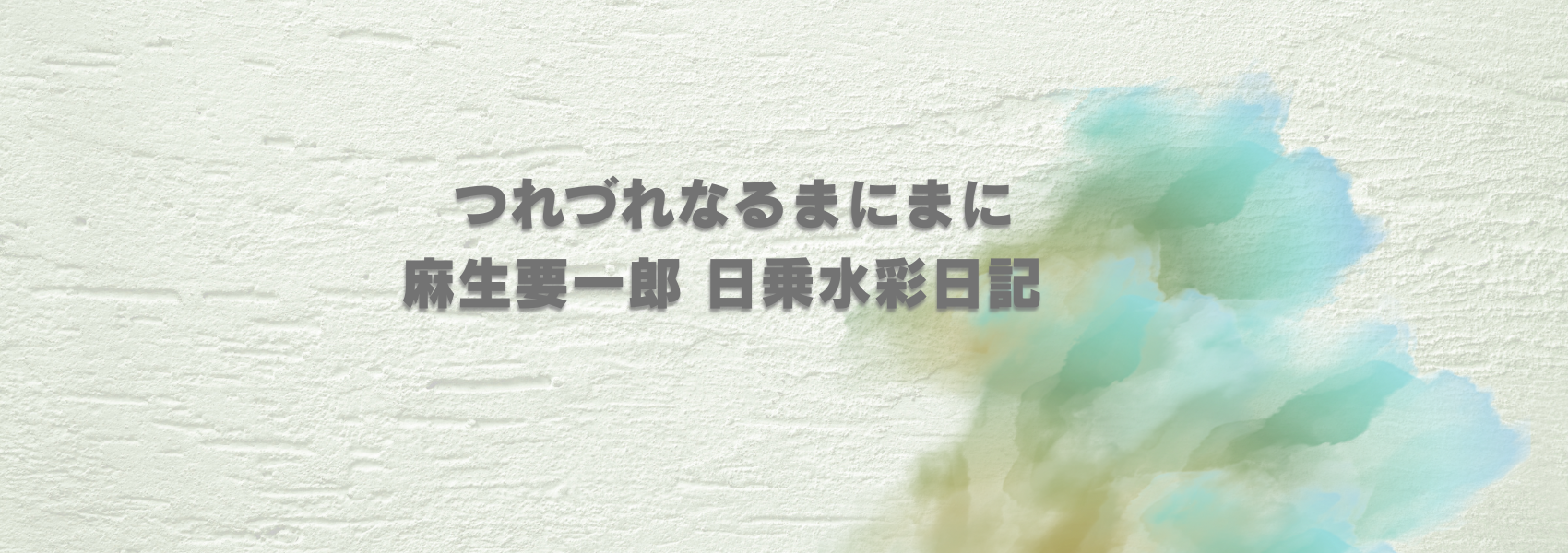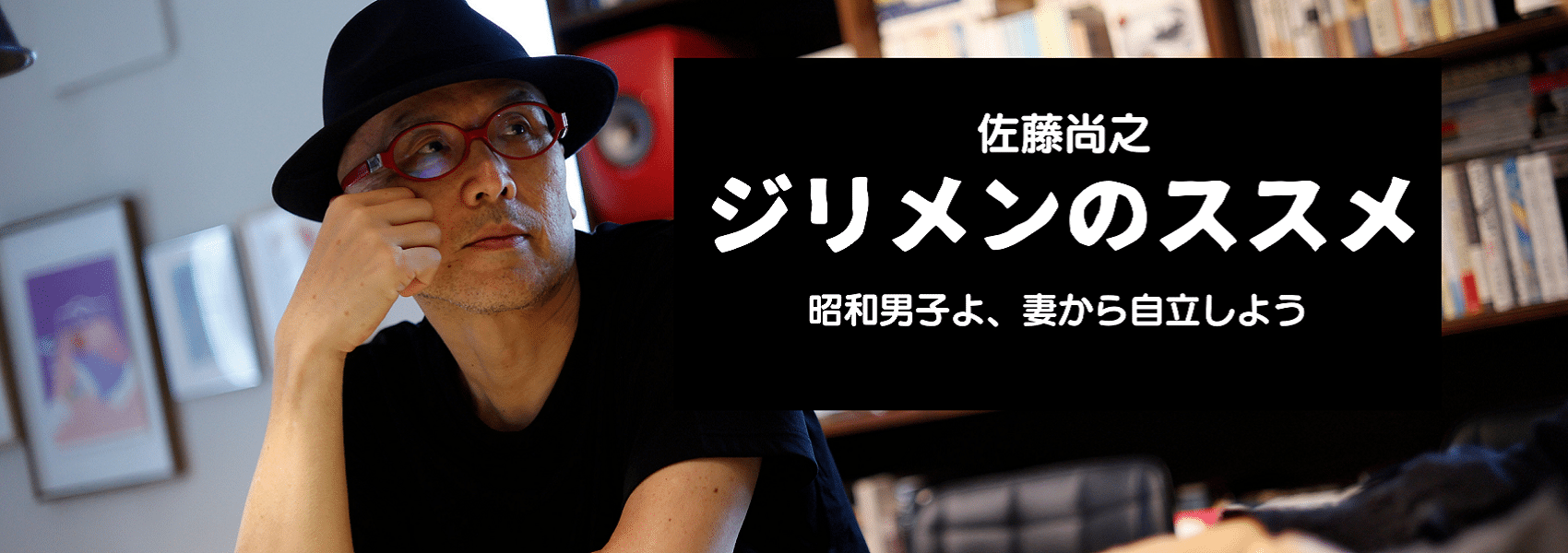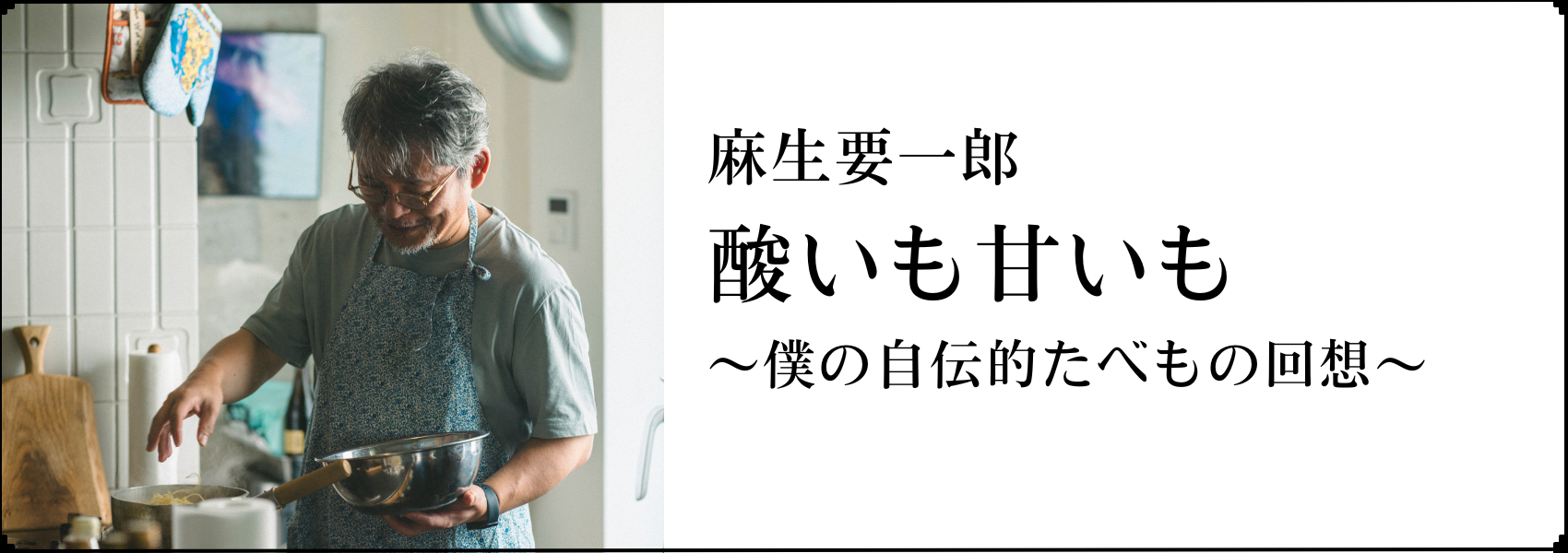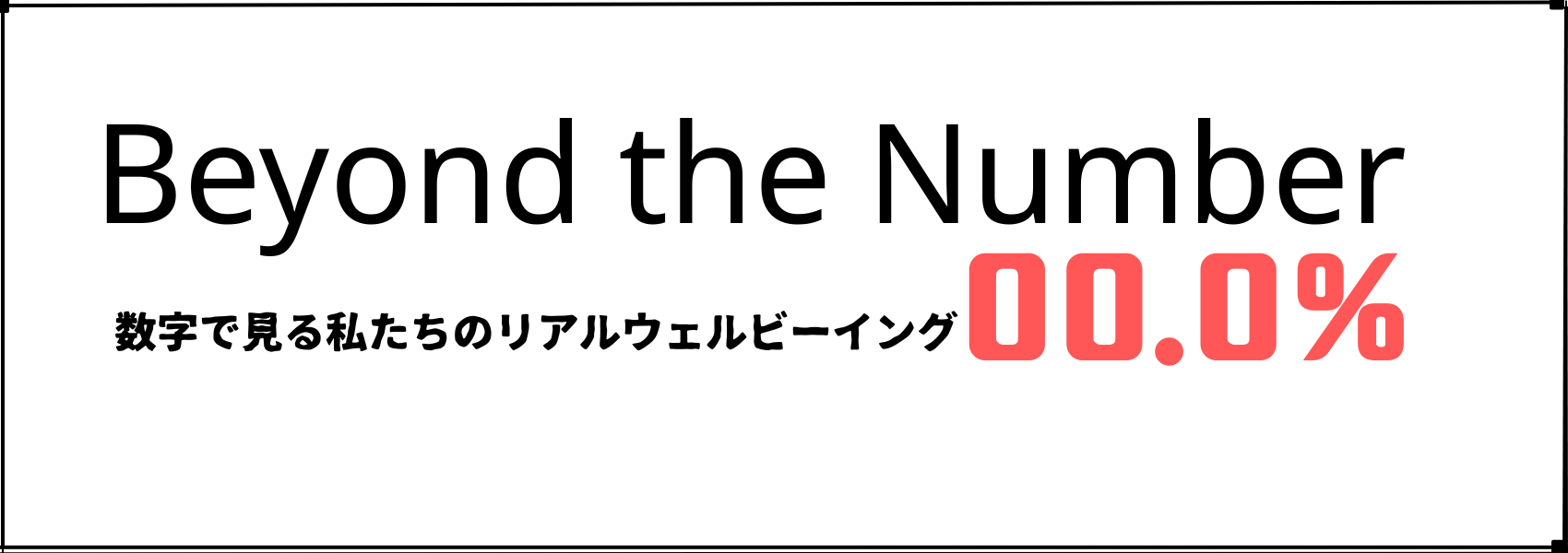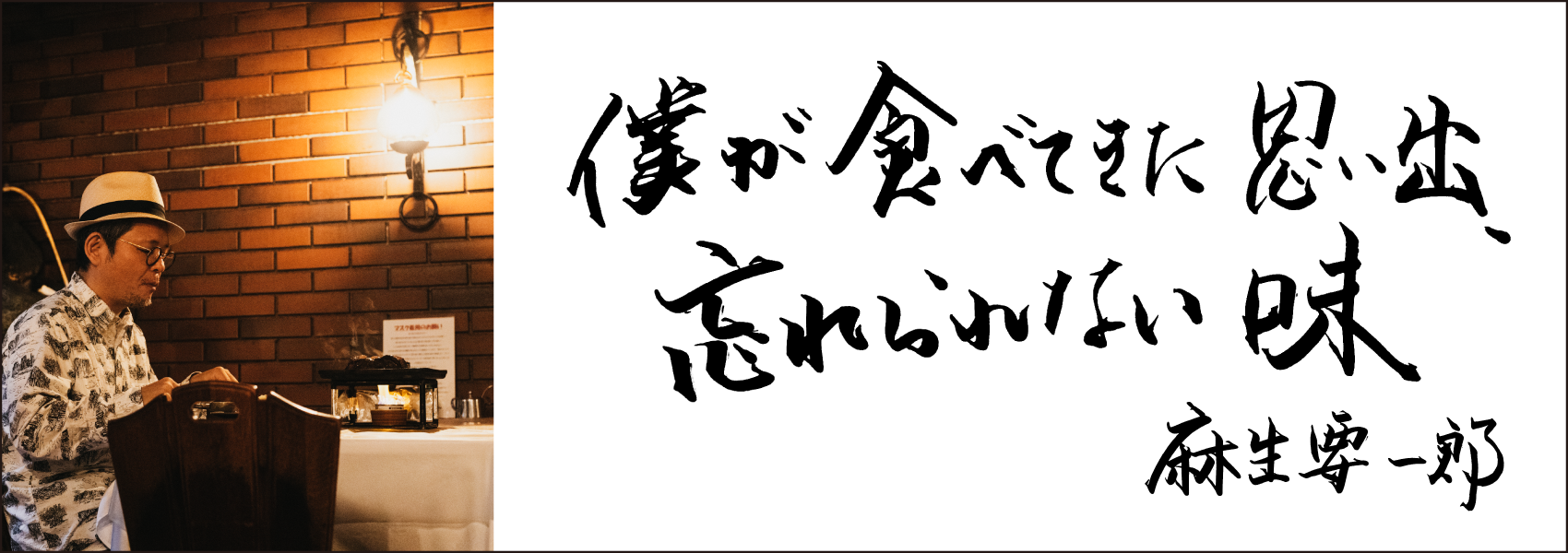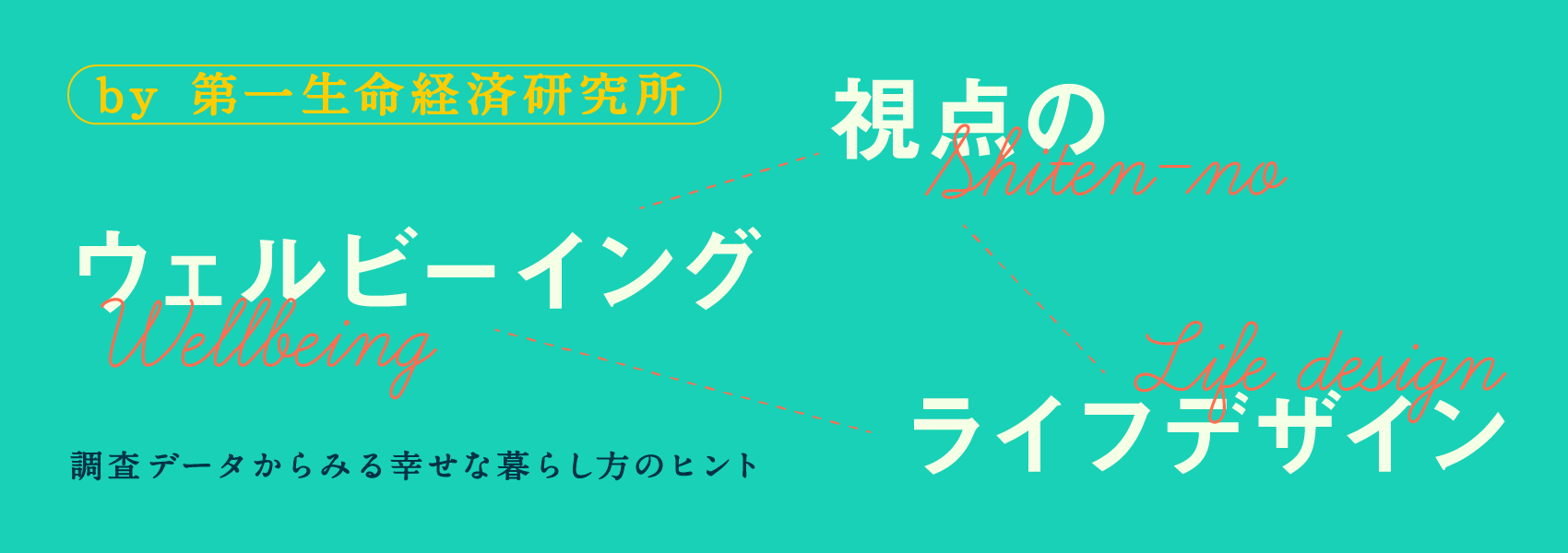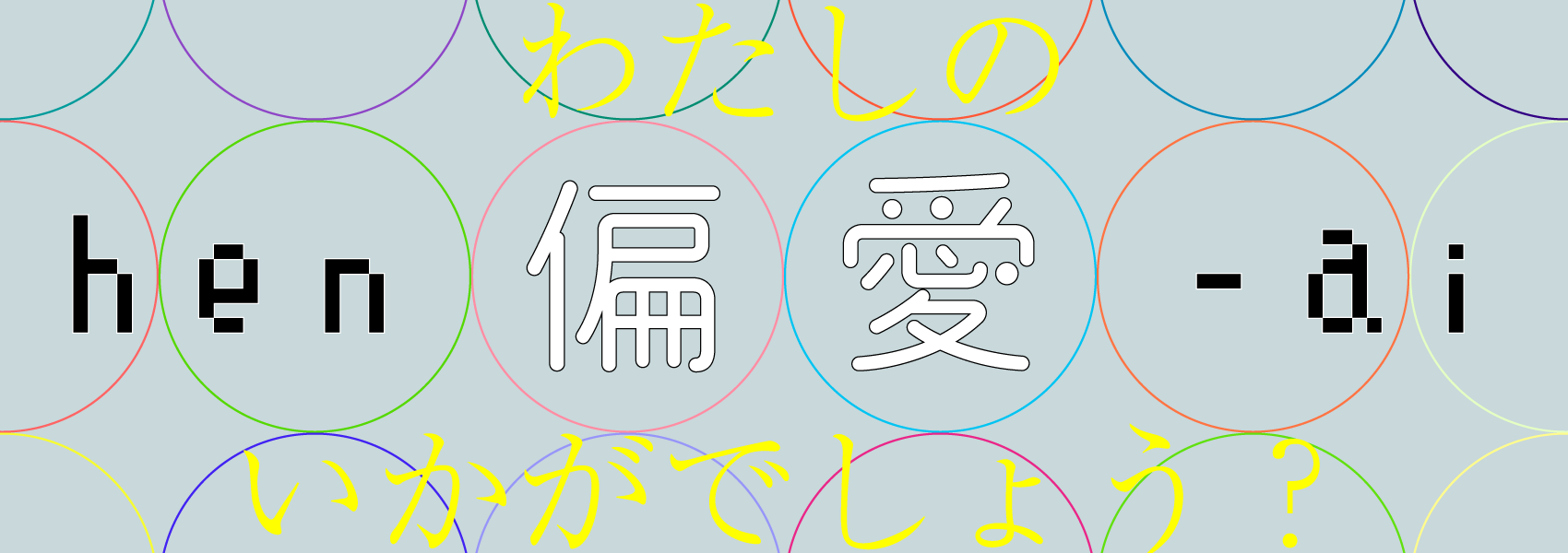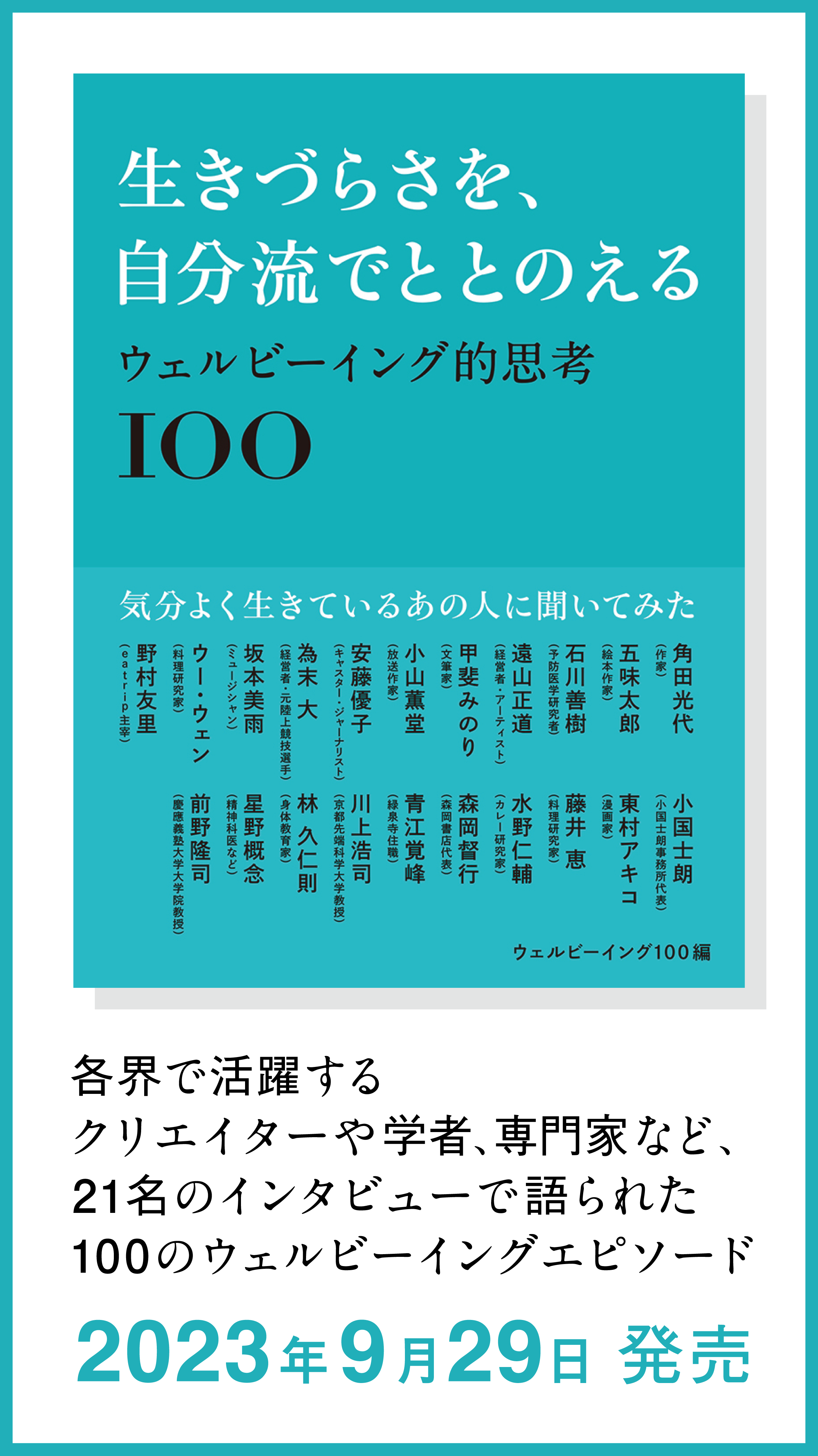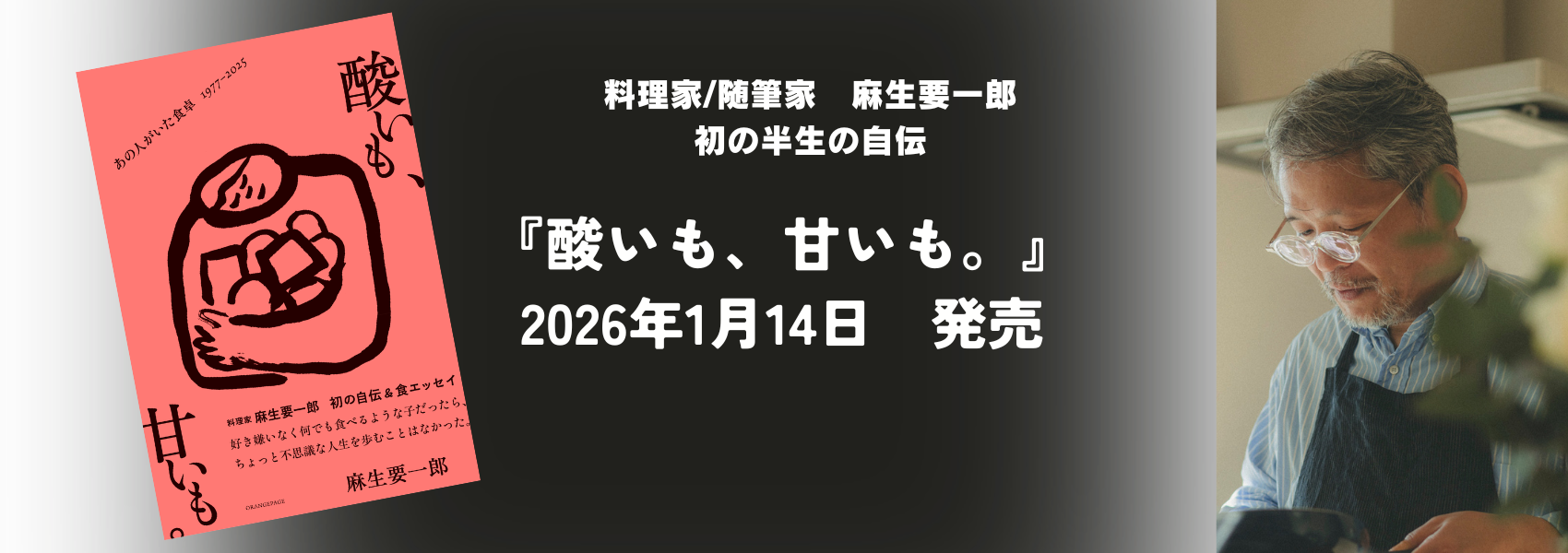横浜流星がCMでその世界観を伝える「LIVIO」、日鉄興和不動産のマンション事業です。広さとか、機能とか住み心地ではなく、「内面の変化」をさりげなくアピールする内容で印象に残ります。
幸せの形が一様ではなくってから、住まいに求めるものも常に変化しています。入居して終わりではなく、そこから先も住人と地域へのケアの姿勢を失わないデベロッパーが、今街にも人にも求められているのではないでしょうか。
住む人の体と心、そのウェルビーイングを包み込む住まいづくり、それを実践する日鉄興和不動産のインタビューは、今、住まいづくりにおいて優先すべきものは何かを考えさせてくれます。
お話をうかがった人/日鉄興和不動産株式会社 常務執行役員 住宅事業本部長 奈良 敦さん
聞き手/ウェルビーイング100 byオレンジページ編集長:前田洋子 アンティーファクトリー:中川直樹
撮影/原 幹和
文/中村 円

━━━今日はお時間をいただき、ありがとうございます。御社の展開されている事業や取り組みを調べたり、ホームページを拝見していると、「ほかとはちょっと違う不動産会社」、いわゆる、マンションや建物を作って売るだけの不動産業とは違うのかな? という印象があります。衣・食・住の中でも「住」は、衣や食の営みを包み込む時間と空間の基盤です。御社がどのような志と具体的施策で「住」を再定義し、生活者のウェルビーイングに貢献しようとしているのか、その根幹にあるコンセプトをぜひ伺いたいと考えています。また、社員の方がとてもウェルビーイングな状態で働くことができる土壌がある、という印象もあります。そのあたりも含め、どうぞよろしくお願いいたします。
奈良敦さん(以下:奈良) よろしくお願いいたします。
個性あるマンションLIVIO(リビオ)の持ち味は、徹底的な顧客理解と地域への対応力にあり
━━━数値的、統計的なデータ分析などが重んじられる一方で、それぞれの事象や人の背景にあるナラティブ(語り、物語)な側面も意思決定において大切にされているように思います。企業も一人の「人」と考えたときに、どんな物語があるのか、そのあたりについてお伺いしたいと思います。まずは御社の「LIVIO(リビオ)」という住宅づくり、LIVIOの特徴や提供価値についてお伺いできますか? LIVIOは横浜流星さんのCMでも認知されていますね。
奈良:LIVIOというマンションブランドは、二十数年前にスタートして以来、私たちが大切にしています。私は今年の4月に住宅事業本部に着任したのですが、それまでは同じ社内でも、外から見ている立場でした。中に入ってみると、見えてくる景色が違ってくるんですが、進化してきたブランドだ、しかもまだ進化を続けているブランドだと感じています。二十数年間進化してきたLIVIOがあって、その現在地を見ているところです。
━━━変化しているんですね。
奈良:LIVIOは「人生を豊かにデザインする」というコンセプトで皆さんにお届けするブランドです。マンションは「衣・食・住」の住、人間の運営動作のひとつじゃないですか。住まい方とか、暮らし方とか経済状況が強く反映されてくるんです。
━━━たとえばどんなふうに今は進化しているのでしょう?
奈良:ブランドスタート当時は、デフレの時代だったんです。今は皆さん忘れてしまわれていますが、デフレの時代のキーワードって「品質はそれなりに、価格は安く」だったのです。でも価格だけを軸にはできません。当時のLIVIOの商品構成も基本機能や基本性能をしっかりつくっていました。たとえば銀座にサロンがあった+ONE LIFE LAB(プラスワンライフラボ)は1LDKの間取りを徹底的に研究していて、どうやったら効率的に住まえるか、収納をどうするのか、そういったことに価値をおいていました。
━━━そうでしたね。デフレでしたね……。
奈良:それがインフレの時代―インフレになってきたのは最近ですけど、機能はもちろんのこと、機能の上に「人生の豊かさ」を表現しよう、内面的な部分にも踏み込もうとしています。横浜流星さんにイメージキャラクターにもなっていただいて、機能や価格の上に、「住まうようになってからの価値観の変化」をお伝えできればと思っています。
━━━単に暮らすだけではない、プラスアルファの豊かさですね。
奈良:私ども日鉄講和不動産にはLIVIOとは別に1950年代から展開しているHOMAT(ホーマット)シリーズというラグジュアリー路線の住宅事業がありまして、当時はアメリカ進駐軍の幹部の方たちが住まう家が日本にはない、ということでわれわれが提供していました。そのラグジュアリーブランドのコンセプトとノウハウが、脈々と続いているんですね。ラグジュアリーのDNA。デフレ時代のLIVIOと、ラグジュアリーのDNAが重なり合って、今のLIVIOがあります。インフレの時代になって、富裕層の方が求める豊かな住まいと、われわれのLIVIOがちょうどマッチしてきている。大きなトレンドの中で、変化と進化をしてきているLIVIOがうまく流れに合ってきている。着任してからの半年間で、そんなふうに感じています。

リビオタワー品川(外観完成予想CG)港区港南 2026年5月上旬竣工予定

入居者に住み心地をヒアリングする「入居者調査」で次代のニーズを掘り起こす
━━━変化はどのようにしてキャッチしていくのですか?
奈良:これが結構地道で、課長クラスまでは年に一度「入居者調査」といって、マンションを購入してくださった方のお宅を訪問して直接お話を伺うという活動をしています。現場の社員には、お客様がどういうふうに暮らされているか、われわれの商品がどのように使われているか、を見せていただくんです。データを読む、アンケートを取る、情報の取り方はいろいろありますが、入居者調査では生で感じることができるわけです。そんな活動が、また商品づくりに生かされていくんです。
━━━結構地道な取り組みですね。
奈良:大きなトレンドの話と、現場の地道なモノづくり。家を購入されてから何年も経ってから見せていただくこともあって、われわれが「価値がある」と思っていたことが合っているのか、そして、その価値は時を経て変化しているかもしれない。そういうお声をみんなでつかみ取ってきて、次のモノづくりに生かす。そんな活動を行っています。今のLIVIOでは「人生の豊かさ」を謳っていて、入居者調査という取り組みを内部に盛り込んでいっています。
━━━時代のトレンドや消費者のニーズをとらえるというソフトの部分を、土木、建築というハードの部分にどう生かすのか、自分たちが感じていることをマンションとか住宅づくりに反映できるのか、ということにすごく興味があります。おもしろいですね。事業部ではいろいろな人が携わっていらっしゃるようですね。
奈良:この会社は大学生までのキャリアに多様性があって、経済学部とか、文学部とか、いわゆる文系学部の人が半分くらいいて、残りの半分くらいは建築学科とか理系学科の出身です。職種では文系、理系が渾然一体となっていて、仕事を分けないんです。経済学部出身でも図面を見て、モノづくりをやっていますし、建築、設計の人たちもきちんとお金の計算までするし、営業もするという感じで、みな同じ活動の中にいます。得手不得手はあるんでしょうけど。
━━━そのあたりが他社と違うんでしょうね。
奈良:お客様調査の現場に出ている人間は、設計の図面は引かないですけど、頭の中にあるイメージを設計の人に伝える。現場に出ている人たちの頭の中にあるものが大事なんですね。説得力のある基盤になる。
━━━「この会社に入ればいろいろな仕事ができる!」というだけでもワクワクしますね。多彩な人材が携わっているというのが御社の魅力ですが、もうひとつ、「三方よし」という視点があるともお聞きしています。これはどういったものですか?

「この土地に100年後まで栄える建物はどういうものか」それを考えて「三方よし」の街をつくる
奈良:「三方」は、もともと土地を持っていらっしゃる方と私ども、そして、建てたものに入居される将来のお客さまですね。その三方が皆、よしとなる着地点を目指しています。たとえば私たちが現在いるこの本社ビルも、もとはといえば60人くらいの個人の地権者の方がいらして、住んでいたり、事業をされていたりしたんです。その土地と、私たちの土地を合わせてひとつの土地にして、このビルが建ちましてね。ビルもマンションも、そうやって、再開発しているものがたくさんあるんです。大事なポイントは、地元とわれわれとの関わり合いかた、もともとその土地で住まわれていた方たちとのコミュニケーションです。このビルをつくるのにも十数年かかっていて、長い時には30年くらいかけて話し合いを重ねていきます。権利者さんたちがつくっている組合と、われわれの話し合いの議事録を見ると、「第三百何十何回」なんていうものが普通にあります。
━━━へえ、すごい!
奈良:地元に住まわれている方がどうして一緒に再開発されるかというと、家が古くなった、道幅が狭い、耐震性に問題があるなどです。一人の力では解決できないときに、私たちが持っている資金力、構成力といったものがお役に立ってくるわけで、ビルを建てれば100年使えますから、「この土地に100年後まで栄える建物はどういうものか」というのを考えていくのが私どもの仕事です。その思いを伝える。そういうものをつくっていく過程の中で、皆さんが個々に抱えている問題を解決していく、そのプロセスで10年程度要します。
━━━非常に大切ですがなかなかできない作業だと感じます。
奈良:皆さんが納得されて、「じゃあ、やりましょう」となる。それで、建物ができあがると新しい入居者さまや購入者さまがいらっしゃる。もともとの権利者の方と、新しい方たちと街をつくるわけです。マンションなら、家を手放した権利者の方たちにご入居いただくわけで、LIVIOのブランドに新しい価値を感じていただける。長い年月がかかることを、昭和の時代からやっています。
━━━こうやってお話をお聞きすると、文系、理系とさまざまな人材が必要ということがよくわかりますね。
奈良:土地や場所に「根ざす」ということですよね。時間を相当かけますし、対話を徹底的にやる。根ざして未来を語り合う。
━━━まさに今必要とされる対話や、ナラティブなモデル、「ひとりひとりへの共感を」ということを昭和時代から自然にされていたんですね。今後の課題としては何を感じていらっしゃいますか?

精神的な充足や安らぎは、資産によって重層的に得られるマンションを資産として育てる、見守る
奈良:マンション事業では、時代がかなり急速に変わってきているように感じています。先ほどもお話ししましたが、近年はインフレに振れてきて、モノの値段がかなり上がってきていますよね。私たちの商材、土地と建物も価格が上がってきていています。今まで5000万円の価値として売ってきたものが8000万円、1億円となっていて、提供するものの価値だけでなく、サービス内容も上げていかないと満足に繋がらない。インフレの時代ならではの課題を感じています。値上がりしたなりの満足感をお客さまに差し上げるためには、前と同じことをやっていては満足感に届かない。「その次」を考えていかないと…というのが、私たちが直面している課題です。物件を売る、ものづくりをしているメンバーだけでなく、お客さまに接しているメンバーがどのように接するかということですね。
━━━今までのようなプロダクトアウト、とにかく建物をつくればいい、という発想から、つくるだけでは終わらない、人が何を求めているのか、人生の質を高めるウェルビーイング的な視点が求められるのだと思います。そのニーズが、「日鉄コミュニティのマンション管理」や、スマホの「myLIVIO」、「新生活コンシェルジュ」「ご入居後の様々なイベント」※といったリビオのお客様へのサービス、ライフサポート体制で受け止められるようになっていて、「内面的な人生もサポートします」というメッセージになっているように感じます。LIVIOに関しては、本当に「つくって終わり」ではないですね。既存樹木の再利用を推進し自然との共生を図る「緑の循環プロジェクト」に取り組んでいらしたり、ブックライブラリーがあったり、ガスの洗濯乾燥機「乾太くん」を全戸に装備してあったり、物件によってそれぞれ特徴がありますね。
※「日鉄コミュニティ」は、マンション管理事業を主とする日鉄興和不動産のグループ会社。「myLIVIO」、「新生活コンシェルジュ」は入居者専用サービス。
奈良:そうなんです。住宅に住まわれてから、お客さまの人生がどんどん変化するので、ずっと満足していただけるサービスを提供できるのか、われわれも相当先を考えて読み込んでいかないといけないです。LIVIOで共通で入れるものと、その土地土地で異なるテーマがあって。「乾太くん」は浦安のLIVIO(リビオ浦安ザ・プレイス)で全戸実装しましたが、これはその前の浦安の物件(リビオ浦安北栄ブライト)で、一部に乾太くんを取り入れたところ、すごく評判がよくて。それで浦安の担当が、その次のLIVIOに全戸採用することにしました。うちのいいところは、そういう決裁を担当者ができること。僕が知ったのは、パンフレットを見てからですから(笑)。
━━━ええ? そうなんですか!?
奈良:そうなんです。そういうのを決めるのは現場の担当者で、「このマンションでは何を提供すべきか」を自分で決めていきます。実際にお客さまにお会いしているのは僕ではなくて、彼らですから。お客さまに会っている若手に、かなりの権限が移っています。それが現場の活力にもつながり、商品のブラッシュアップにもつながる。身内の話をすると、じつはそういう特徴があります。
━━━なかなかないことですよね。「乾太くんが入ってる」って聞いたらご入居される方は多いですよね(笑)。ほかにもコンポストと連携した取組があったり、最初のうちは「何をやっているんだろう」と不思議に映るものも実を結んで。現場の担当者への権限移譲が「だからリビオがいいんだ」と思われることに繋がっているのですね。
奈良:認知度が確実に上がっていて、様々な施策が実を結んでいると思います。
━━━奈良さんはさまざまな事業を手がけられてきたと思いますが、特に印象に残っているプロジェクトはありますか?
奈良:商品も大切なんですけど、「みんなでつくりあげた」と思えるものが自分の中では心に残っていて。2010年に自分でプレゼンテーションをした事業がありまして、約15年の歳月をかけて今年の5月にようやく着工した仕事ですね。その地鎮祭で住宅事業本部長として壇上であいさつしたときに、地域の方が集まってきてくださって。こういうシーンが一番うれしいですね。
━━━17年間、ずっと心血を注いできて、住民の方にも「一緒にやってきた」という思いがあるんでしょうね。
奈良:「久しぶり」「偉くなったね~」なんて冷やかされながら、皆さんもとても喜んでくださっていて。あと3年くらいすると建物が建ち上がって、その方々がご入居される。新しい住人の方もいらして、そこが街になる。そのプロセスを見るのが好きですね。「ようやくここまできたね」というのが楽しいし、この仕事をやっていてよかったなと思いますね。開発の醍醐味ですね。もうひとつあるのは、入居したお客さまがどう暮らしていくのかを感じることですね。私は生のお声を聞いた経験はあまりないのですが。
━━━入居して時間がたっていく……マンションは住まいであり「資産」ですから、その資産価値を保ってリフォームしたり、売る場合も含めて、ずっとケアしていかないといけないですね。
奈良:リフォームはお部屋の中も大事ですけど、外壁とか、エントランスとか、植栽とか、ここがしっかり管理されているかが大きいんじゃないですかね。それで、共用部分をグループ会社の日鉄コミュニティが管理するわけです。皆様の財産である共用部分を、美しく経年していけるように管理する。モノですから当然古びるんですが、しっかりメンテナンスしたものの古び方ってきれいじゃないですか。風格が出てくるというか。そういう管理をしていくことが、じつは財産全体を守っていくことにつながっていると思います。
━━━マンションにおいて外観、エントランス、植栽は大事ですよね。
奈良:大事なんですよ。お宅を訪問したときには、部屋に入る前にその3ポイントで印象が決まってしまうじゃないですか。
━━━何だかんだといって、将来への安心と人の幸せを支えるものは資産であることが大きいです。「このマンションはいくらで売れるから将来は大丈夫」と思えるように、管理をしっかりしてもらえるのはありがたいですね。
奈良:資産であり、居住するものでもあるのがマンションですから、ライフスタイルが変わったら売って、また別の場所に住まう。そのときに高く売れる商品であり続けてほしいと思います。それが買われた方の安心にもつながるし、資産形成にもなりますから。今は価値観も変わって、マンションは住み替えるものになっている。以前、デフレの時代はマンションを、正に「使いきって」いましたよね。30年のローンを組んで、ずっと住んで、働いている間に返しきる。まさに「使いきり」の商品でした。
━━━そうでした。ずっと住む感じでした。
奈良:ところが最近はそうではなくて、80歳くらいまでローンを組む。それはどういうことかというと、資産形成なんです。劣化しない資産。だから長いローンを組んでも大丈夫だぞと金融機関も考えているんでしょうね。「マンション」というものの資産性や、社会からの目が随分変わったと思います。

━━━建物の耐震性や建築技術も高まって50年以上、100年もつ構造になってきて、リノベーションや再開発を含めた「街づくり」への意識も変わってきているように感じます。
奈良:そうですね。マンションは「一生の買い物」ではなくて、ライフステージの変化に合わせて買い替えるものになってきています。うちの社員でもすでに不動産を持っている若者がいっぱいいて、住まい方を変えていく、マンションを買い替えていくことが当たり前になってきています。住居というものの価値観が変わりました。使い方も随分変わってきていますね。
━━━長期にわたって自分のものを持つというより、一時期だけ、一部分を持つという考え方になってきて、(途中で手放すことを前提に)ちょっと高くても、その時に自分に合ったものをチョイスする形になってきていますね。
奈良:家は一生物の買い物として、手狭でも「子どもが巣立ったらまた狭くてもよくなるから」ってがまんしたものでしたが、彼らのように途中で手放したりしながら住み替えていくほうが豊かな暮らし方なのかもしれませんね。変ながまんをしないで、もっと自由に家をとらえていっていいのかもしれないですね。
━━━買い替えが進む中では、マンションの建て替えや町の再開発も進んでいくかと思いますが、そういった視点で御社が留意している点はありますか?
奈良:都市の再生は最近ではなくて、2000年代の初めの小泉政権から始まっています。規制緩和が進んで、大きなビルを建てるような開発が進みました。今はこうした開発は一段落していて、これから先は多分、選ばれた地域をどう残していくのか、という視点に変わっていくと思います。うちの会社はこの赤坂というエリアに10くらい、オフィスビルを持っているわけですけど、これからは選ばれた「守るべき地域」をどう発展させていくか。働くだけの街では魅力がないので、住んで、遊んで、働けてという街を守り育てていく。そういう時代に街づくりが動いていくんだろうなと思います。デベロッパーの役割としては、街の人と共にないといけない。いいデベロッパーがいる街のほうが、時代の求めるよい発展をしていくんじゃないかと。共に歩んでいける街を、みなで大切にしていく、そんな時代が来るんじゃないかと思います。
━━━お考えを伺え、とても学ぶことが多かったです。ありがとうございます。