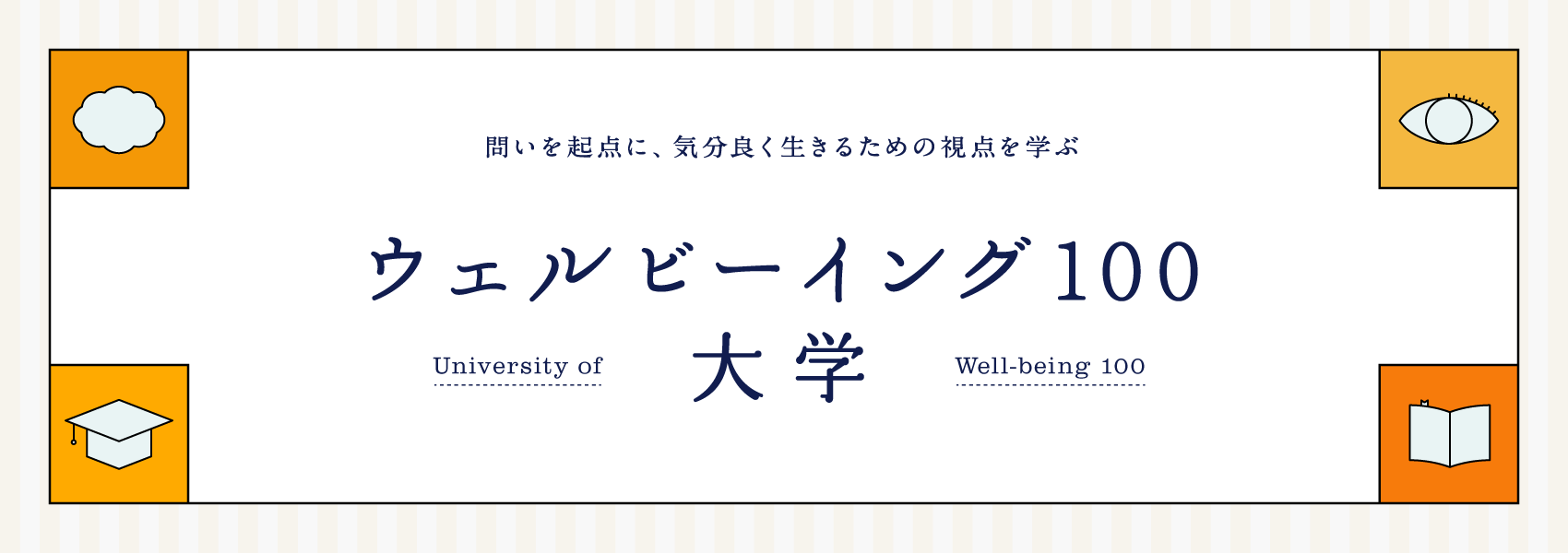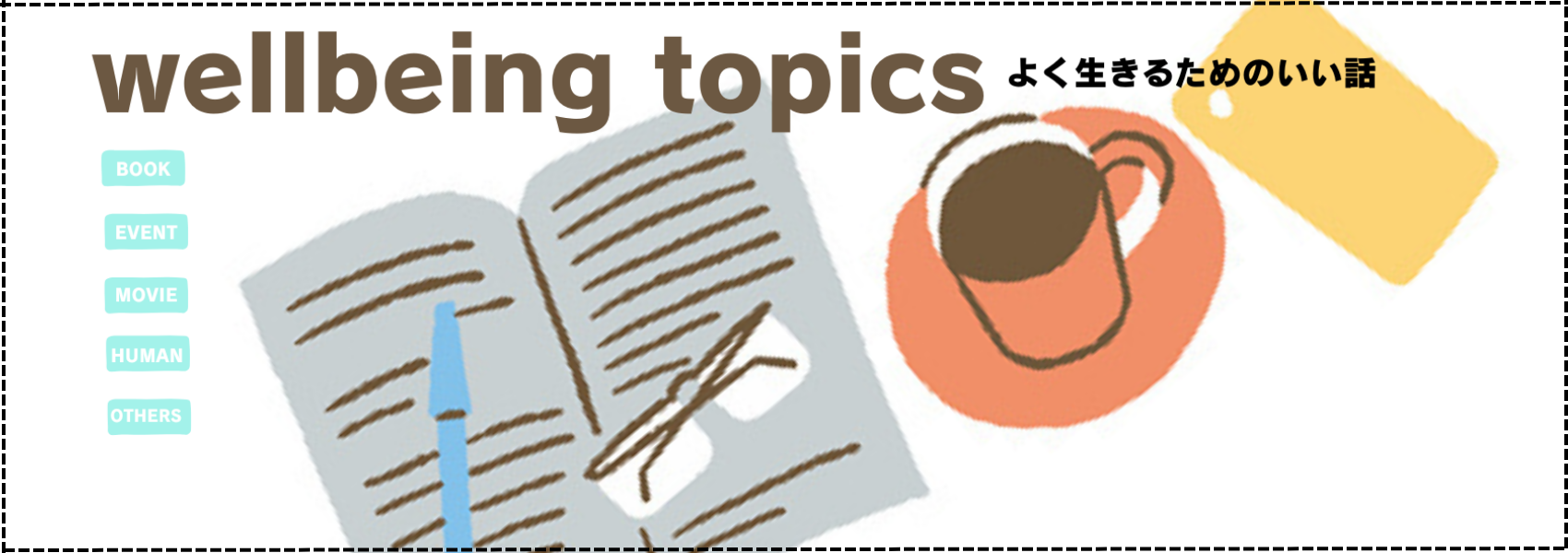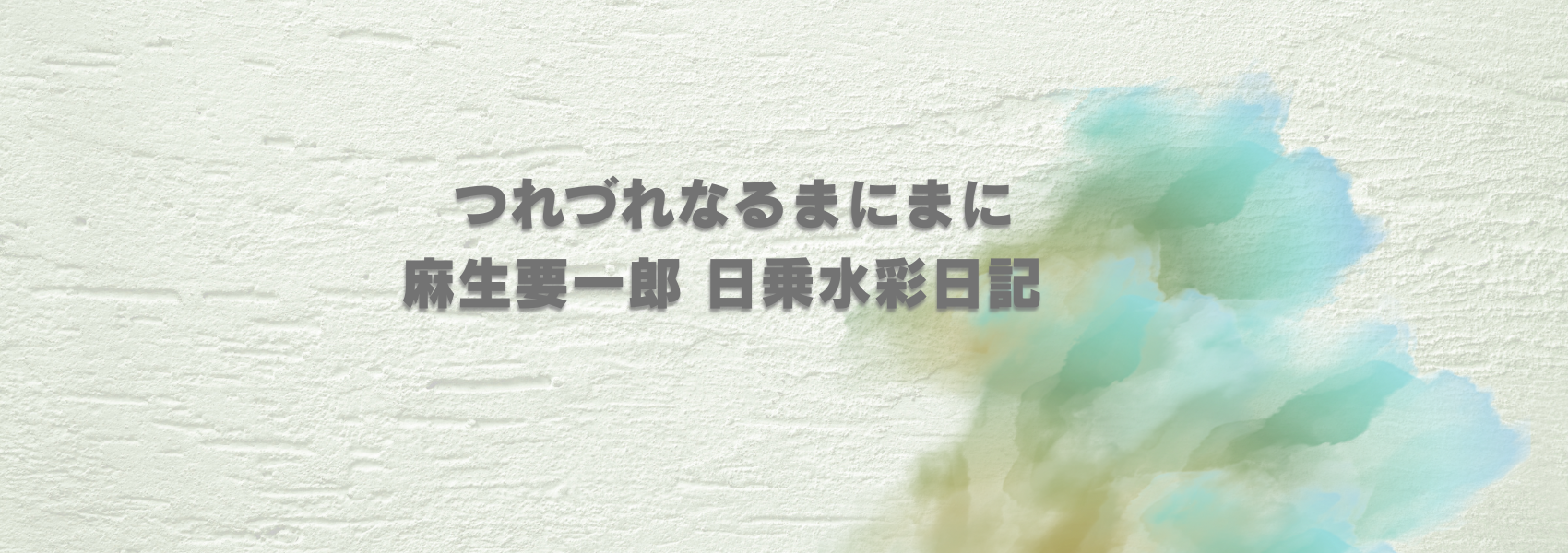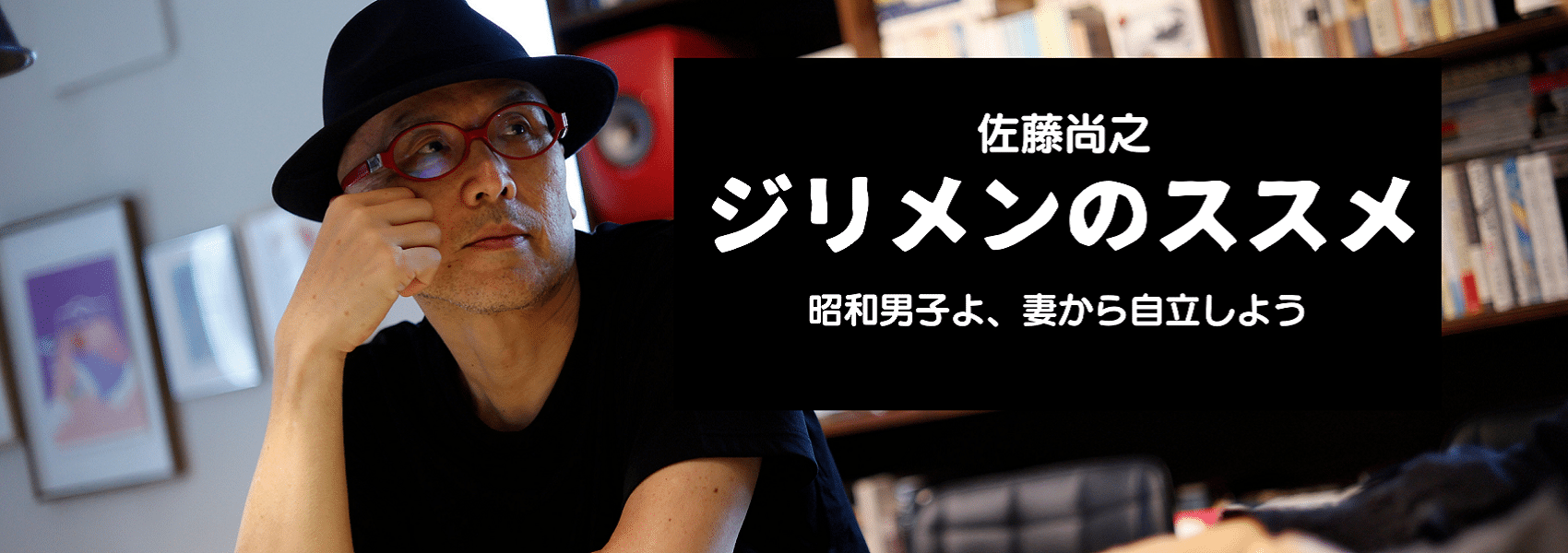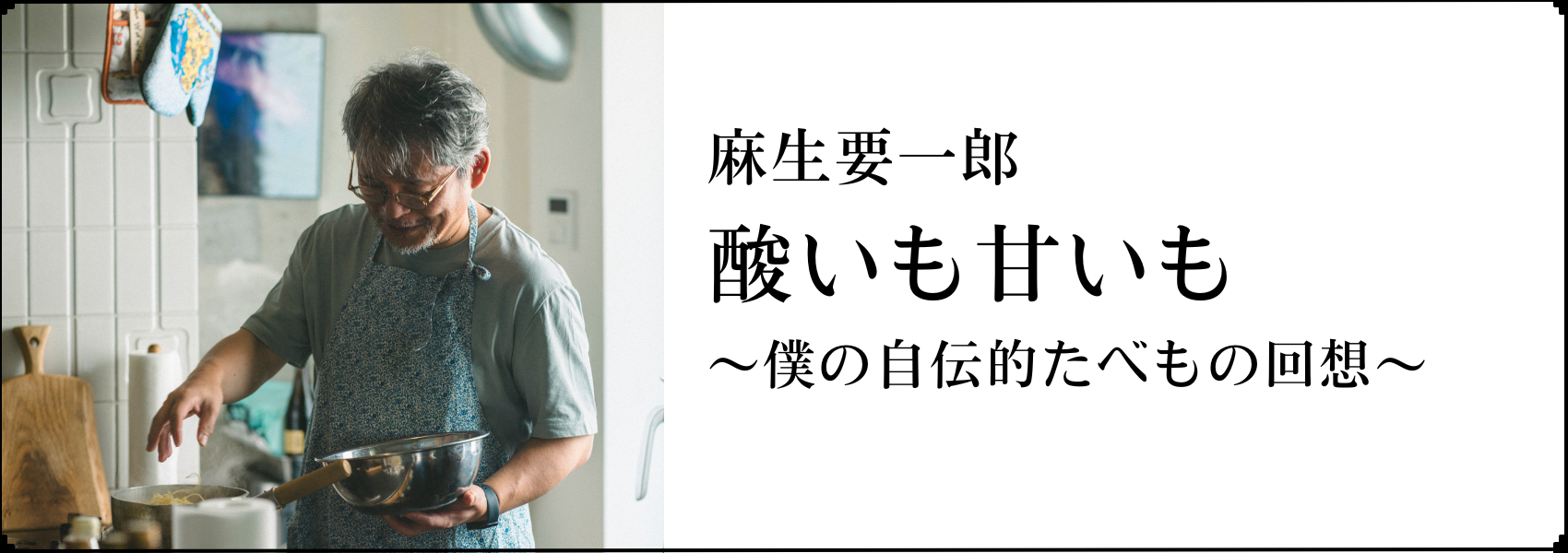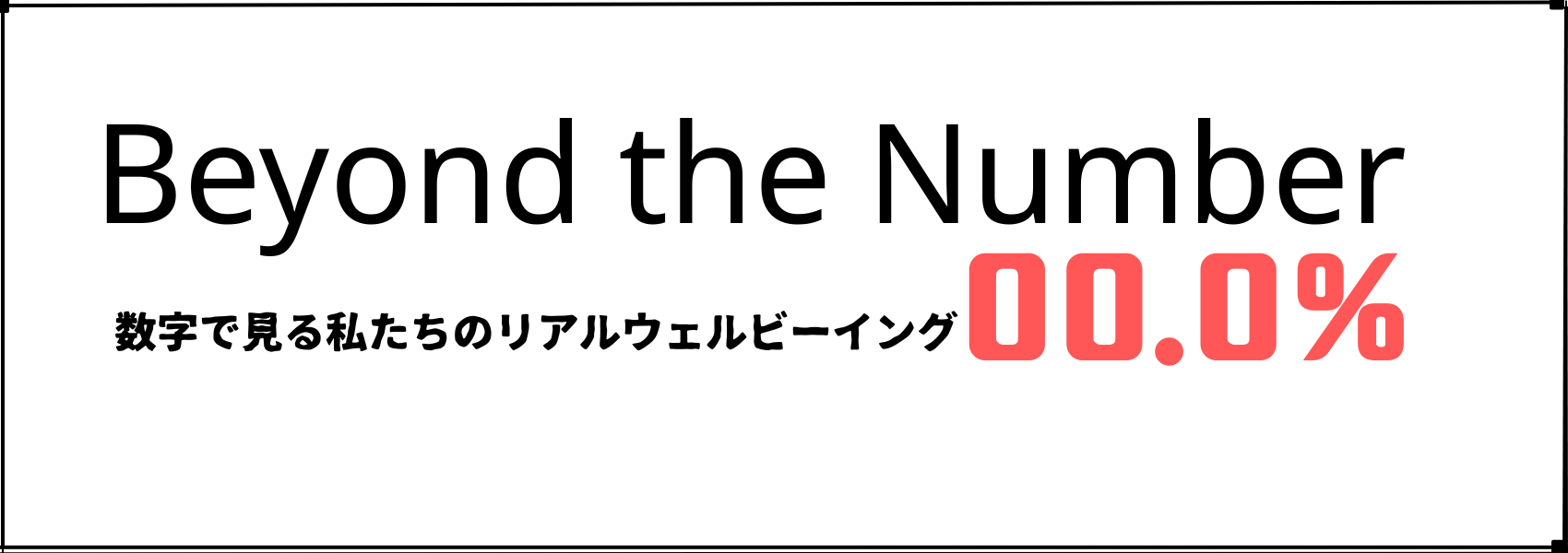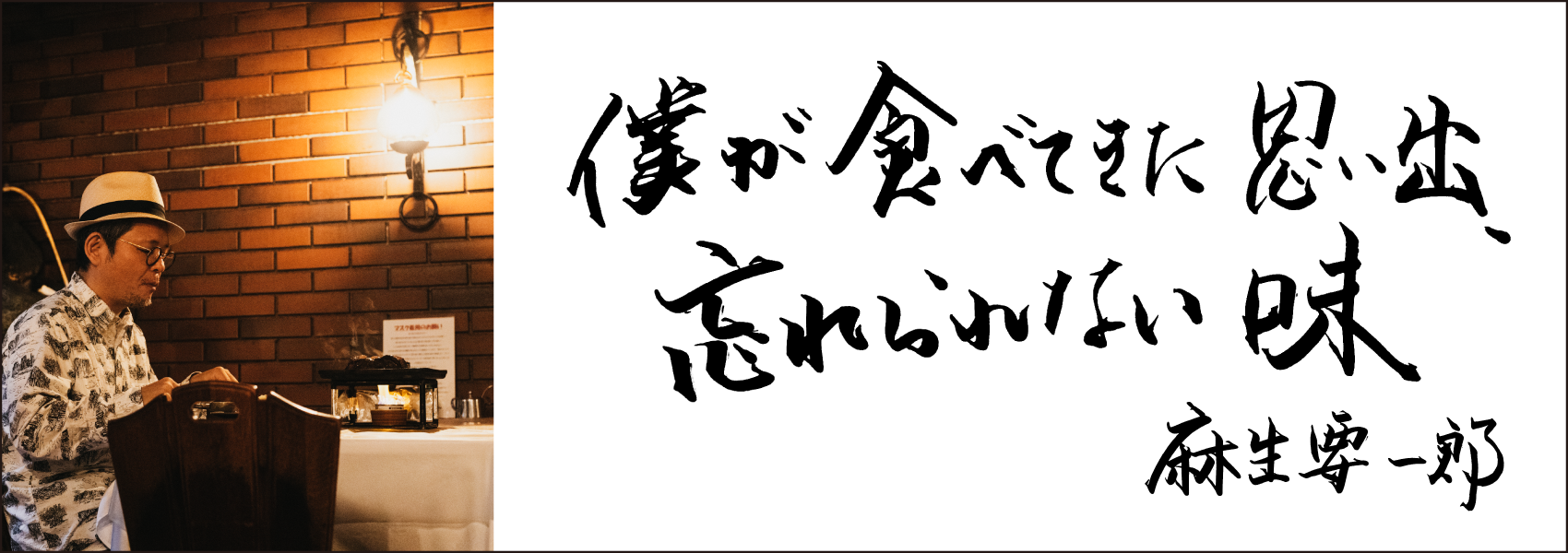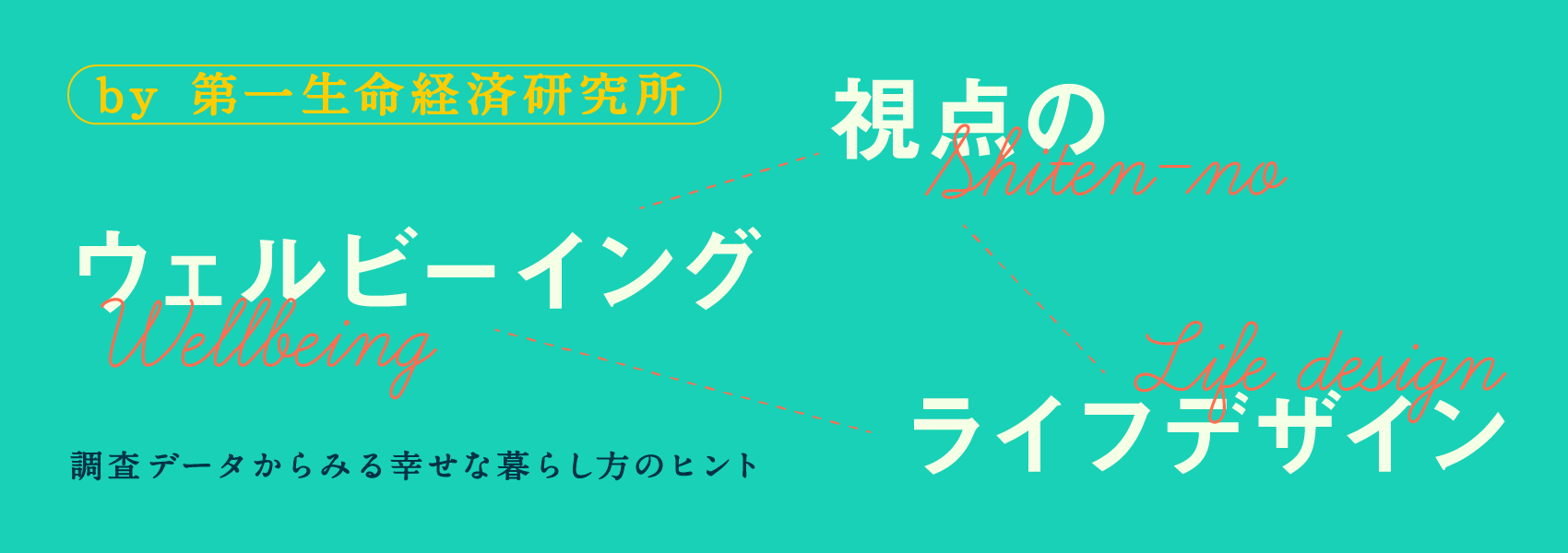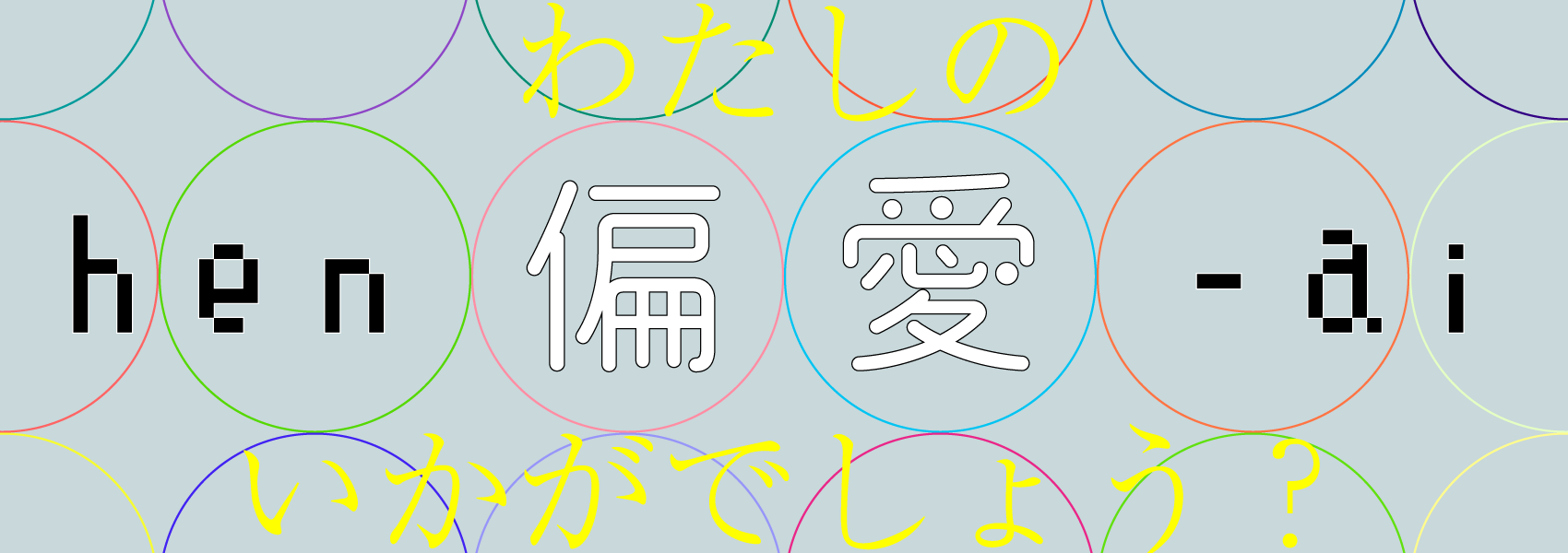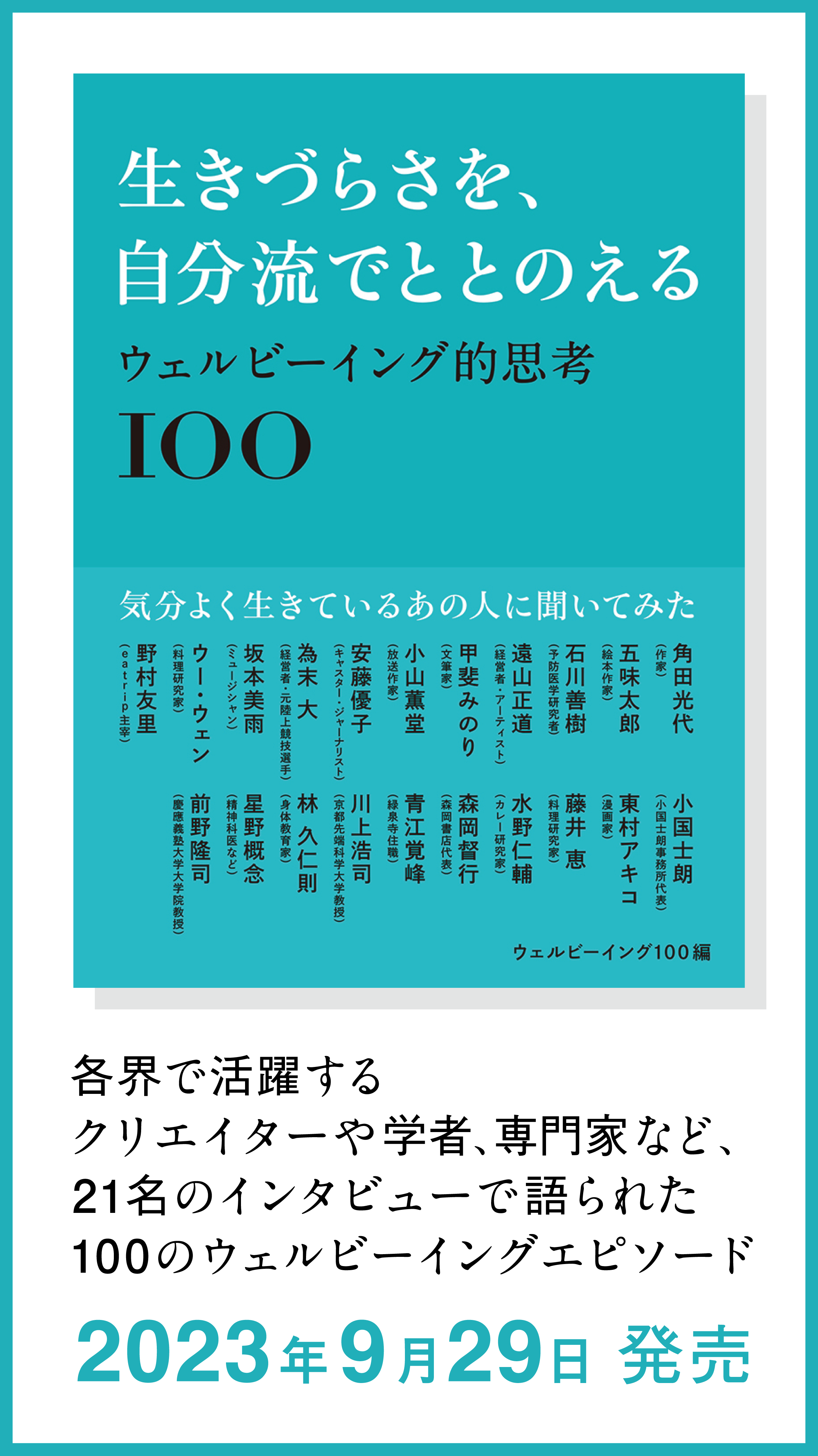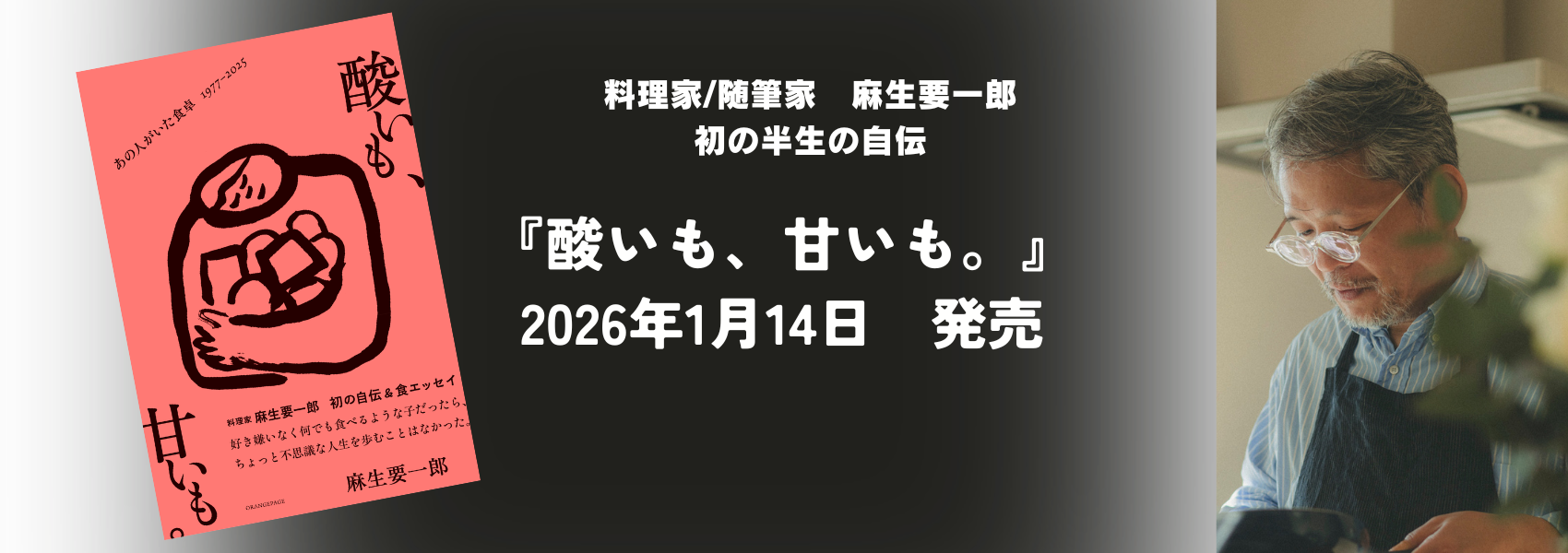第一生命、という名を知らない人はほとんどいないでしょう。
明治35年に創業された業界の老舗は「お客さま第一主義」を掲げて時代に合わせた変革を随時成し遂げてきました。
早くから従業員のウェルビーイングにも注目してきた第一生命グループ。
健康経営の代表格として有名な企業が、
人々の価値観が多様化してきた2025年の今、さらなる大改革をしようとしています。
どこを目指して、何をどう変えていこうとしているのか。
従業員のウェルビーイングをどう位置づけ、どんな施策を打ち出しているのか。
グループの人事制度の改革に取り組む執行役員の沼田陽太郎さんに、その思いとこれからの展望をお伺いしました。
お話を伺った人/第一生命ホールディングス(株)執行役員 人事担当 Group Chief Human Resources Officer 沼田陽太郎さん
聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100 byオレンジページ編集長:前田洋子
撮影/原 幹和
文/小林みどり

「会社や社会への貢献を実感でき、自分自身の成長も実感できる会社にしていきたい。それが我々の掲げる“多様性”です」
━━━第一生命といえば日本の生命保険の老舗ですが、株式上場をするなどここ十数年の変革には目を見張るものがあります。
「ありがとうございます。生命保険を祖業としてもう120数年やってきましたが、急速に事業の多様化をすすめているところです。
2007年に初めて海外で生命保険事業を開始して以来、今では日本を含め9か国で事業を展開していますし、ペット保険や福利厚生サービスの会社を買収するなどして、非保険事業も含む「保険サービス業」を目指しています。
私は2年前に人事担当になりました。現在はグループ事業の多様化をさらに推し進めようと、人財戦略のキーワードを「多様性」にしました。多様で多彩な人財が個性と可能性を最大限に発揮して、会社の変革に挑戦していく、そういう人財を育てたいという思いです」
━━━人財戦略としての多様性。具体的にはどのような施策を?
「人事は強烈なメッセージ性を持ちますので、我々は変革するんだ、多様性の方向でやっていくんだという意思を示そうとしており、例えば、現在では持株会社の役員の4割以上を、外部からの人間で構成しています。
新卒で入って30年同じ人間関係の中でやってきた人ばかりだと、どうしても発想が固まってしまいますし、上の言うことに右に倣えとなりやすい。でも、持株会社の役員には外国籍の人も複数名いて、これまでの日本的な慣例にとらわれずに自由なスタイルで会議にも参加して、CEOに対して厳しい意見が出ることもあります。
実は私自身、これまでずっと資産運用と海外事業をやってきて、初めての人事担当なんです。この人事は、「初めてだからこそ、従来の慣例にとらわれずに、既存のものを壊すことに抵抗がないだろう」という、トップの経営判断だと思っています」
━━━役員人事は公開されるので、外部の私たちにも、第一生命グループが変革・多様性に向かっていると分かりやすいですね。従業員の方々についてはどうですか?
「2024年度は、内勤の新卒採用とキャリア採用の数がほぼ半々でした。もちろん途中で出ていく人もいるわけですが、異なるキャリアを目指したり、異なる価値観で他社で活躍したいという人が出てくることも、弊社に多様性の土壌が育ってきた証かなと、むしろポジティブに捉えています。
やはりコロナ禍以降、従業員のもつ価値観が多様になりました。必ずしもいわゆる「出世」を目指さない人が一定数いますし、同じ社員でも個人の生活が変化するライフイベントによって目指す方向が変わる人もいます。
これまでの弊社の人事制度は、新卒で入って誰もが上を目指すことを前提に考えられたものでした。入社してから定年まで、どの部署で何の仕事をするかほぼ会社側が決めていたのが実態。会社が主体で、社員がそれに合わせる制度設計となっていました。
でも今の時代、それは違うよねと。多様な価値観をもつ従業員ひとりひとりが安心して働ける企業風土にしたい。そして会社や社会への貢献を実感でき、自分自身も成長している実感を持てるような会社にしていきたい。それが我々の掲げる人財の「多様性」であり、そこを目指して「変革と挑戦」をしているところです」

「ウェルビーイングを人財戦略の一つと捉え、みんな同じでなくていいよね、というスタンスから様々な人事制度が生まれています」
━━━人財育成の制度設計から変えているということですか?
「そうです。“主体的にキャリアをひらく人財”ということで、自分がどうしていきたいのか、そのために何をすればいいのか自分で考えてもらい、会社はそれを最大限サポートするスタンスになっています。
たとえば、将来の経営幹部候補となりうる人財には集中的に資本投下して、6~7人の女性社員が社長と徹底的に議論する「女性社長塾」であったり、かなりハードな英語の特訓コースを受けてもらうなどしています。自らポストに応募してもらう「Myキャリア制度」も導入し、年々応募者が増えてきています。
また、弊社には年々積み上がっていく資格がありまして、育休などで間があいてしまうと資格が途切れ、管理職になるのが難しかったのですが、今は、そのような運営は行っていません。
これにより、ブランクがあっても安心して復帰できるので、3年間の休業を認める「Myキャリア準備休職制度」の利用も活発になってきました。妊活に集中したいという人もいますし、若い社員が見聞を広めたいとワーキングホリデーで外国に行った例もあります」
━━━人事制度をガラリと変えた大改革ですが、ウェルビーイングはその中でどんな位置づけでしょうか。
「弊社にとってウェルビーイングは、人財戦略の中のひとつのパーツと捉えています。なのでキーワードは「多様性」であり、みんな同じじゃなくていいよね、というスタンスです。
結婚する人、しない人、子供を持つ人、持たない人、家族との時間を大切にしたい人、仕事を最優先にしたい人。いろんな価値観を持つ多様な社員に対して画一的なアプローチをするのではなく、できるだけ細かく、丁寧に対応していきたい。
小手先でやるのではなく、まずは大きな体制づくりから。先ほど申し上げた個々の社員の生き方をサポートする様々な制度も、従業員の働く幸せという意味ではウェルビーイングのひとつだと思っています。

「“健康経営戦略マップ”で従業員のヘルスケアを体系的に支え、底上げする具体策を打ち出しています」
また、ウェルビーイングの柱となるヘルスケアについては、「健康経営戦略マップ」を作って体系的に取り組んでいます。アブセンティーズム(病欠や健康理由の休職)やプレゼンティーズム(体調不良での出勤)の改善をしていこうという強い意思のもと、さまざまなニーズをもつ社員ひとりひとりのウェルビーイング実現に向けて、かなり細かな具体策を打ち出しています。
健康経営戦略マップに書き切れていないことも多々ありますが、具体的には、グループ会社が行っている健康増進アプリ「QOLism」を導入して生活習慣の改善を目指したり、そのアプリを使ってウォーキングイベントを開いたりですね。事業会社の第一生命には女性が多いので、乳がん検診の巡回バスを走らせて検診を受けやすい環境づくりにも力を入れています」
━━━社員の多様化を推し進めると、一方でこういったウェルビーイングの施策がなかなか浸透しづらいこともありそうですね。
「難しいところではありますね。ウォーキングイベントひとつとっても、ケガしないでよと心配になるくらい頑張る人もいれば、まったく無関心な人もいる。個人や組織によって、取り組みに温度差はあります。
でも、それも多様性のひとつであり、強制することはできません。目的は社員みんなが健康に仕事をすることであって、ウォーキングイベントの参加率を上げることではないんです。だから、多様なニーズに応じられるような柔軟性を持ってやっていこうと考えています。
そのポイントは、ハードルの低さかなと。たとえば、全員ジムに行って体重10キロ落としましょうと言ったって誰もやらない。でも、アプリで知らないうちに歩数計測されていて、気づいたら1日1万歩いっていたとなると、ハードルがかなり下がる。ゲーミフィケーション(ゲーム感覚を応用した手法)もそのひとつでしょうし、やりたいと思う仕組みをいかに作るかが重要だと思っています。
組織で「2・6・2」といって、協力的な人が2割、そうでない人が2割、その間が6割と表現しますが、これが「2・7・1」くらいになるとうれしいですね。100%をあきらめているわけではありませんが、100%を目指すものでもないと思っています」
━━━時間がかかることだと思いますが、かなり迅速に進んでいる印象です。
「ありがとうございます。健康経営戦略マップに書かれていることは、それこそ何十年も前から取り組んできたことではありますが、重要だけど最重要ではないという、さじ加減の難しさはありますね。
人財育成にしても、多様な従業員が自分の価値観を大切に、誇りを持ってこの会社で働けるようにと、この2年間でさまざまな制度を作ってきました。でもそれが社員のマインドを変え、企業文化の変革として現れるのは、おそらく何年もかかると思っています。
実は2026年4月に、グループ名称を変えるんです。第一生命グループから、第一ライフグループへ。弊社は第一生命保険という1902年にできた会社が祖業ですが、それをコアとしつつ、保険サービス業へと変革していきたいというのが経営の意思。それを、社内外に打ち出していきます。
「変革と挑戦」はまだ初期段階。これからの弊社の姿を、期待して見ていてほしいです」