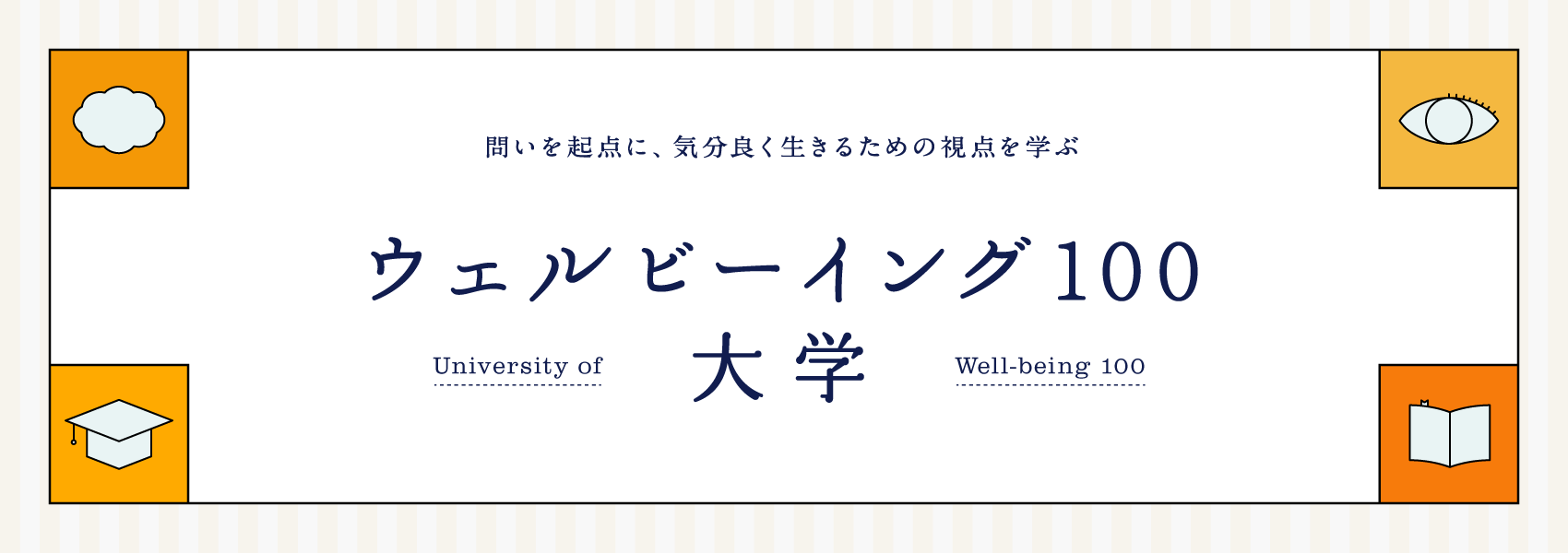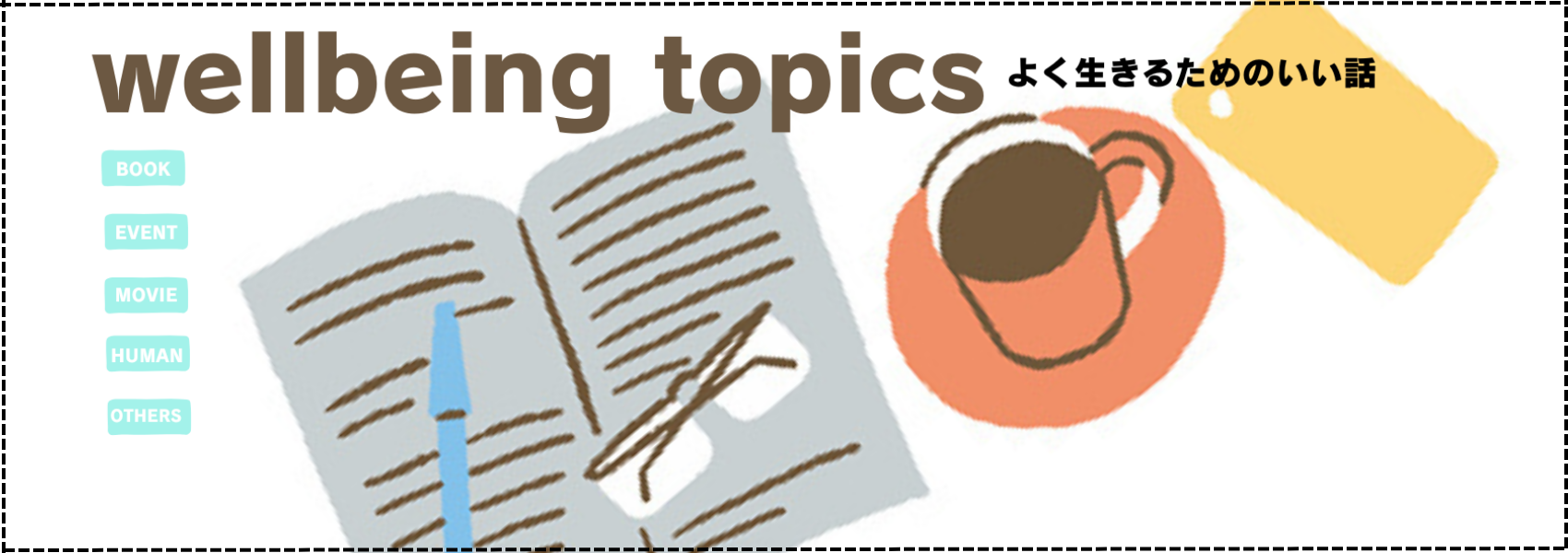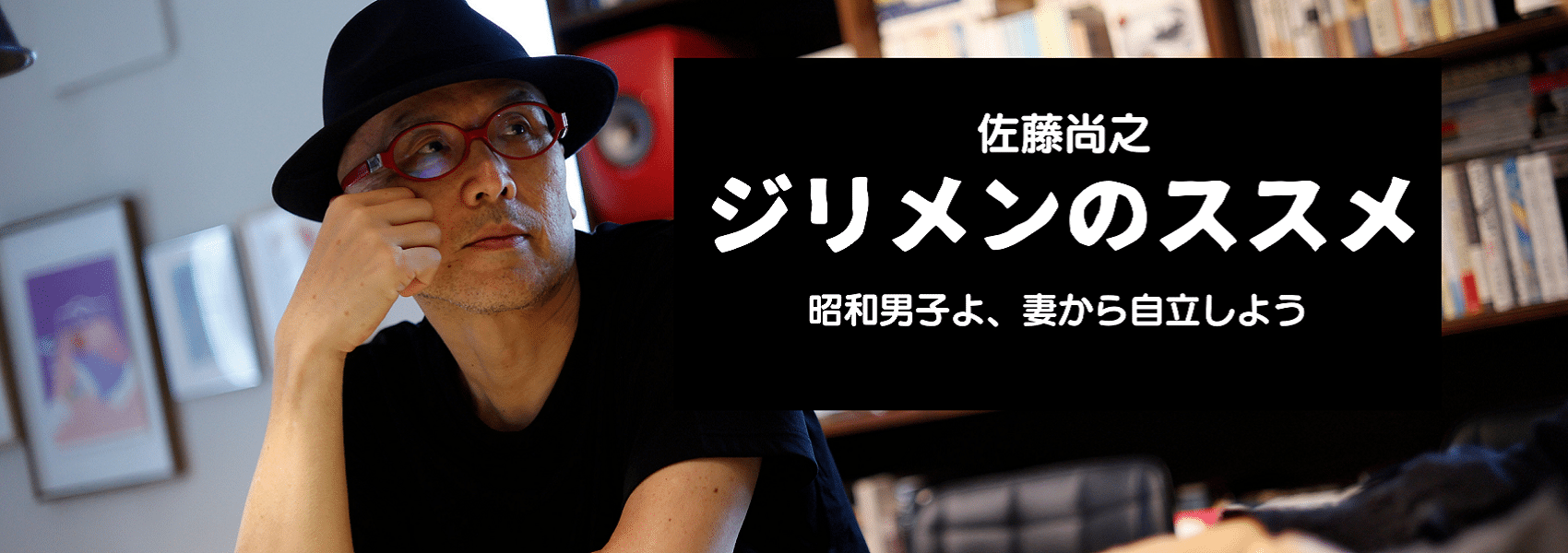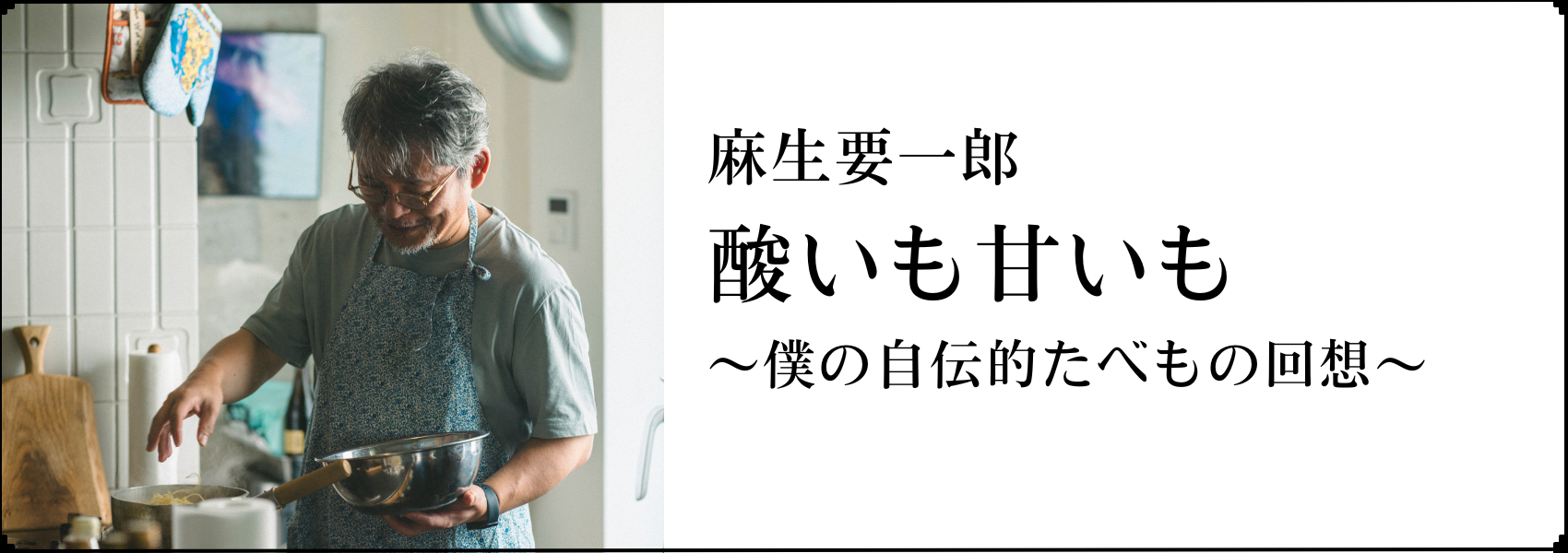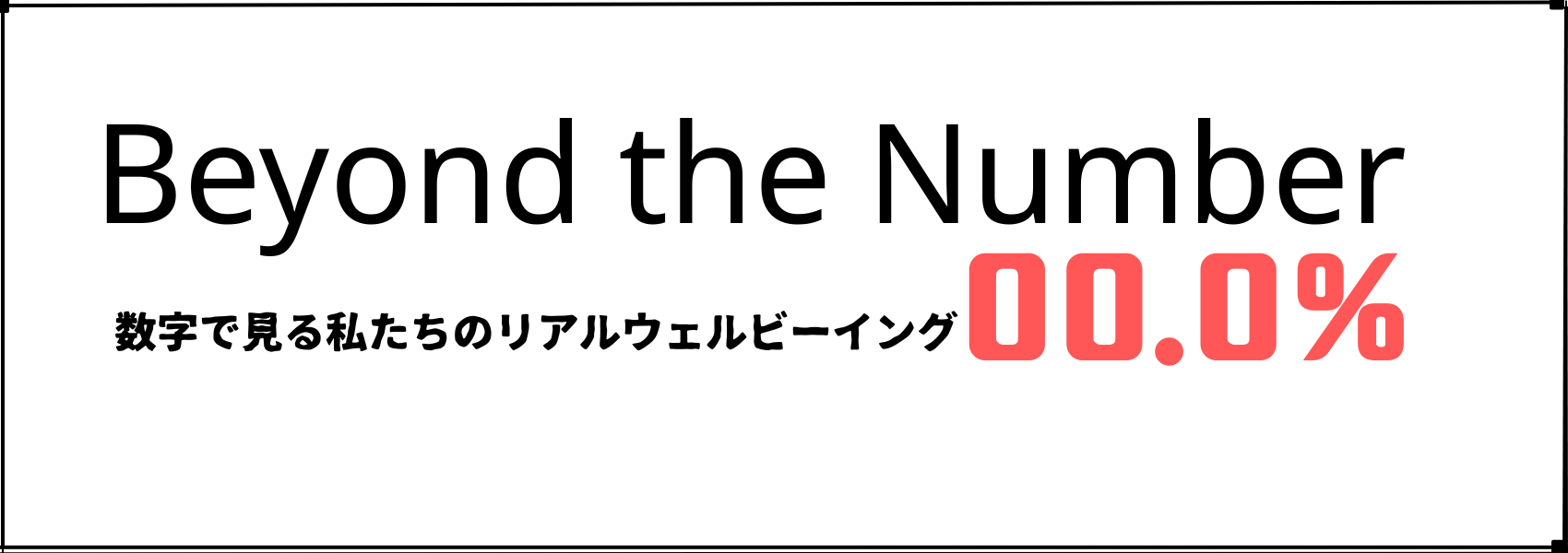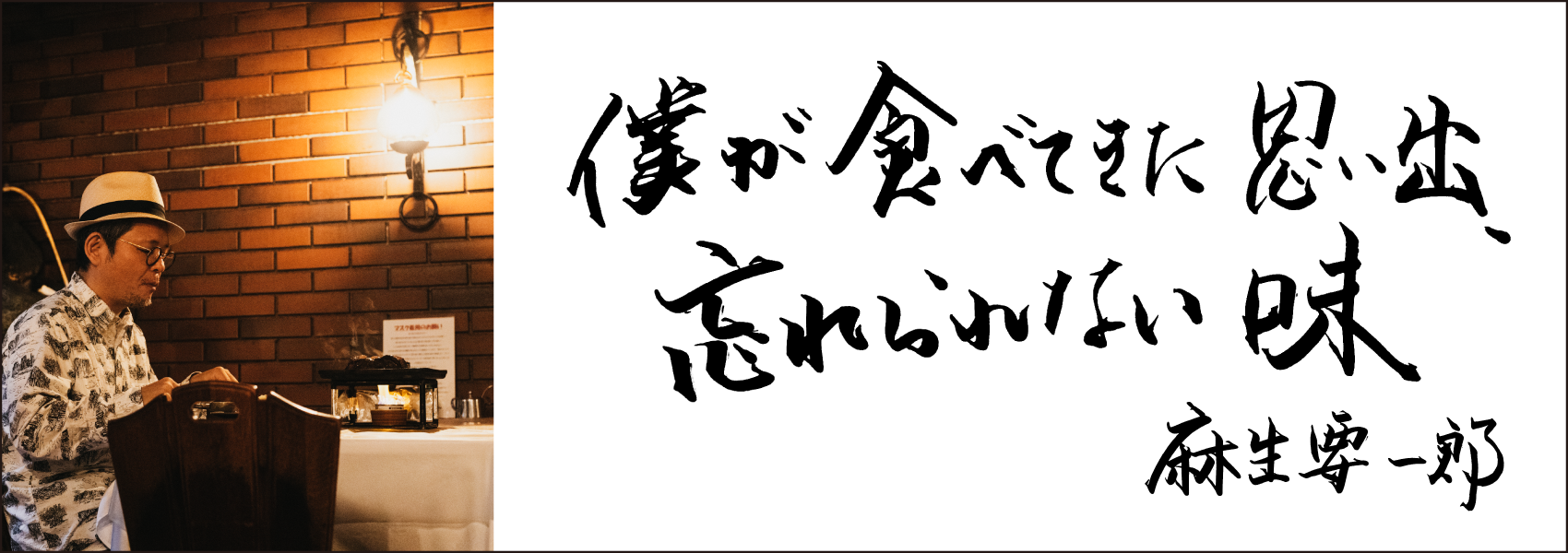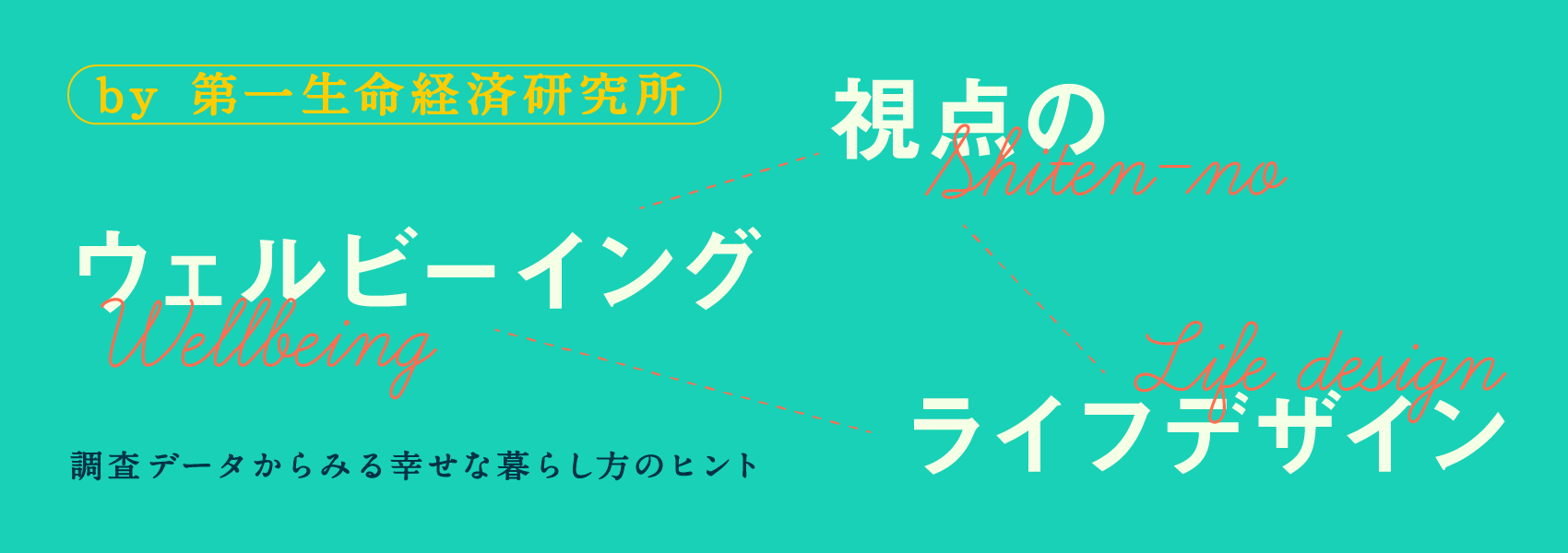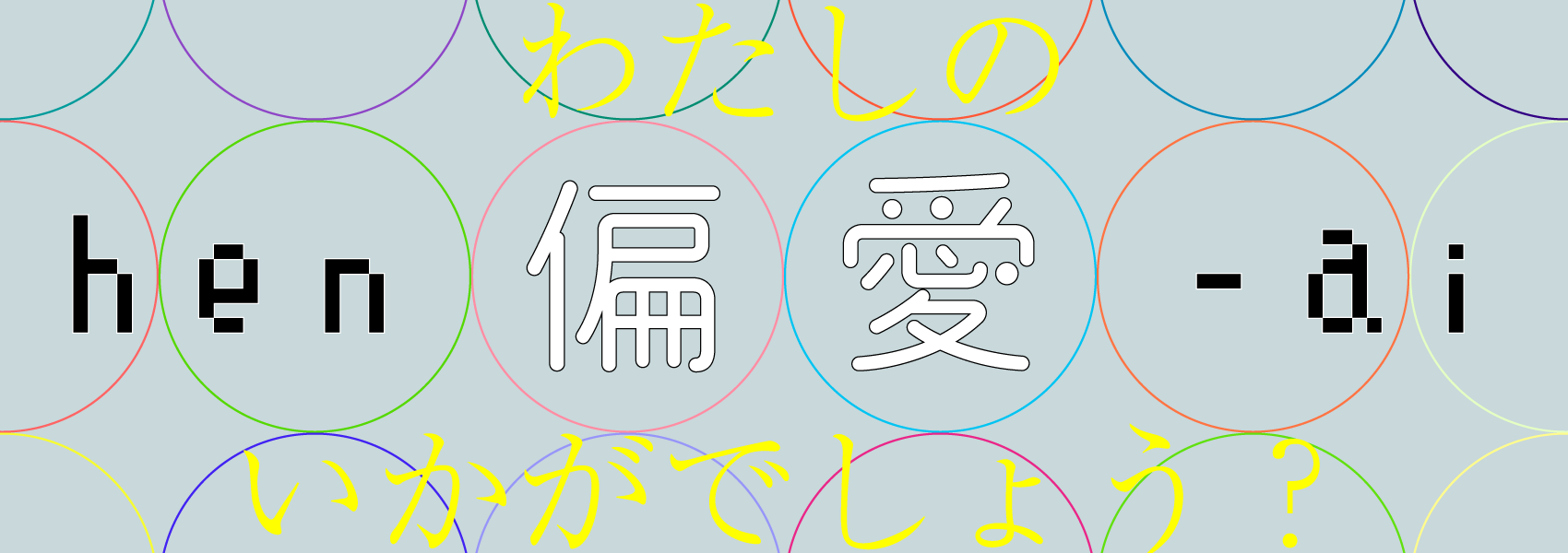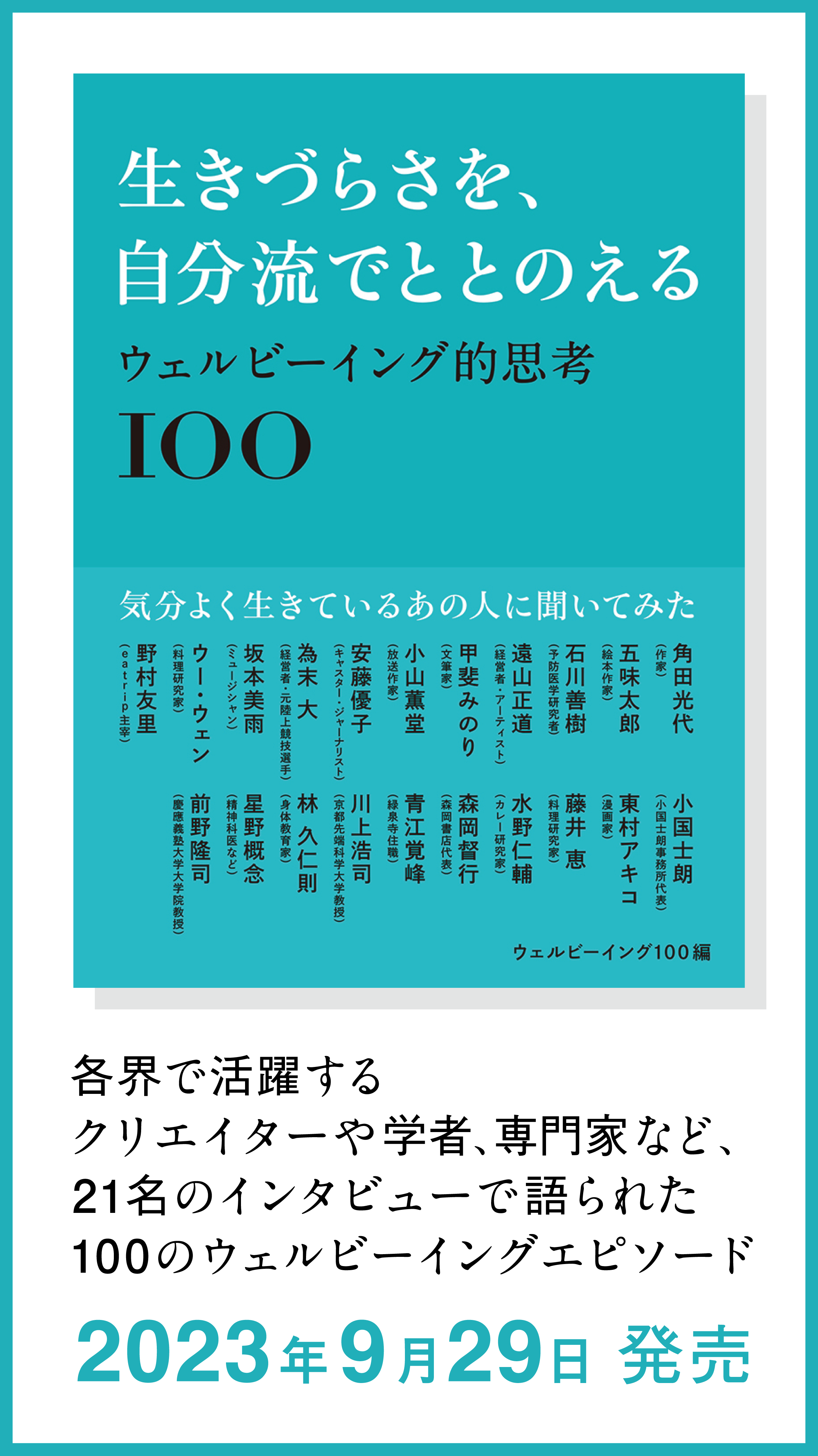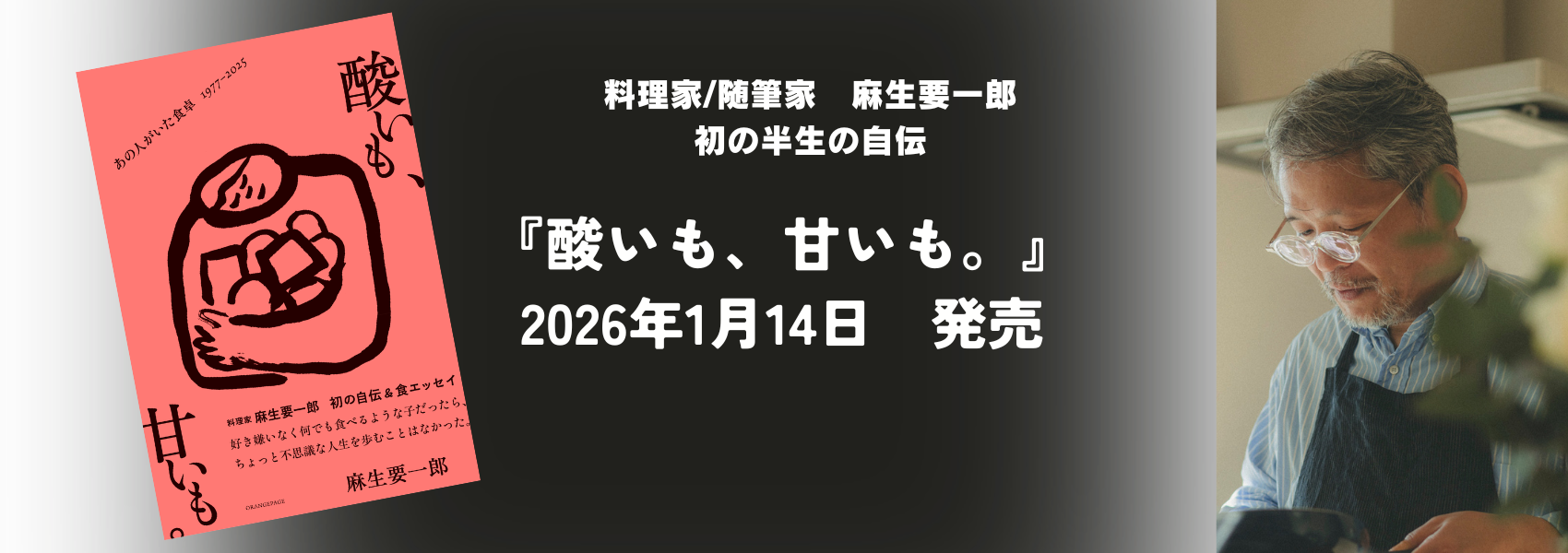これまでになかった新たな視点や気づきのヒントを学ぶ『ウェルビーイング100大学』。今回は初めて参加者を募り、リアルで「ウェルビーイング100トークセッション」として、武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスのコワーキングスペース「ma」で開催しました。『ソトコト』編集長であり、関係人口や二拠点生活の実践者でもある指出さんと、予防医学の観点から人の生き方を探究している石川さん。テーマは「“移動”は人を幸せにするのか?」。
人は、現実でも、脳内だけでも、大きくも小さくも”移動”します。
「ここではないどこか」「今ではないいつか」に行き、思いを馳せることがどれだけ人を豊かにするか。お二人の話に触発され、会場は好奇心と熱気で湧きました。
さあ、あなたも一緒に旅に出ましょう。
聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基
ウェルビーイング100byオレンジページ編集長:前田洋子
文/中川和子
撮影/原 幹和
指出一正(さしで・かずまさ)さん
『ソトコト』編集長
1969年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。『Outdoor』編集部などを経て2011年より『ソトコト』の編集長に。定住でも観光でもなく、地域の人たちと関わる『関係人口』の提唱者のひとりで、全国各地の自治体のアドバイザーや官公庁の委員などを多数務める。2024年に著書『オン・ザ・ロード 二拠点思考』(ソトコト・ネットワーク)を上梓。
石川善樹(いしかわ・よしき)さん
予防医学研究者、博士(医学)
1981年、広島県生まれ。東京大学医学部健康科学科卒業、ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で博士(医学)取得。公益財団法人Wellbeing for Planet Earth代表理事。「人がよく生きる(Good Life)とは何か」をテーマに、企業や大学と学際的研究を行う。専門分野は、予防医学、行動科学、計算創造学、概念進化論など。近著は、『フルライフ』(NewsPicks Publishing)、『考え続ける力』(ちくま新書)など。

昭和元年の一大移動キャンペーン
石川 今年は昭和元年から100年目ということですが、昭和元年に鉄道省が『日本八景』を選ぼうとしたのをご存知ですか?
前田 いえ、初めて聞きました。
石川 「日本三景はもう古い、昭和という新しい時代の風景を8つ選ぼう」と、新聞社と協力して全国から募集したのです。八景というのは、川部門、谷部門とか1部門ひとつで八景。当時の日本の人口が6,000万人を超えたぐらい。その人口をはるかに超えるハガキが全国から集まったそうです。それで8つだけではもったいないということで、日本百景が生まれた。鉄道省としては、汽車に乗っていろいろな所に行ってくださいということですね。
酒井 その頃からもう、日本をあげて移動を推進するキャンペーンが実施されていたのですね。
石川 さかのぼると古くは戦国時代からですね。全国のいい場所、行きたい場所というのはだいたい神社やお寺があって、そういう場所は本来、修行者が行く所だったのです。そもそも『御成敗式目』の第一条に「神社を大事にしよう」と書かれているんですよ。それなのに戦国時代になると、武士たちは神社仏閣からいろいろ奪っていったりしています。修行者も来なくなって、困った神社仏閣はターゲットを修行者から一般の人に変えたのです。全国の神社仏閣の人たち、たとえば山形の人が「出羽三山いいよ~」とか香川の人が「金比羅さんいいよ~」とか広範囲に宣伝して歩き回ったんですね。
その覇者になったのが伊勢神宮です。そこに向かうために整備されたのが東海道ですよ。人が移動する近代観光は、困窮した神社仏閣が庶民をターゲットにしたというところに始まり、その次が昭和元年の鉄道省のキャンペーンなんです。
指出 おもしろいですね。
酒井 石川さんご自身もよく旅をされるんですか?
石川 はい。以前は海外が多かったのですが、コロナ禍をきっかけに国内を移動するようになりました。日本の歴史を振り返ると、開国と鎖国を繰り返しているなと改めて思いました。過去1,200年でみると、鎖国を600年しているんです。1度目は菅原道真が遣唐使を中止したときで、2度目は江戸時代。では今はどちらのフェーズなんだろうと考えると、たぶん日本だけではなく、いろいろな国が鎖国フェーズに向かっているような気がします。こういう時期には自分の国の中を移動したほうがおもしろいと思って、国内を移動するようになりました。
指出 僕が仕事でもプライベートでもよく行っているのが、山形と新潟の県境にある小国町というところ。ここに大宮子易(おおみやこやす)両神社というお社があって、日本でもいち早く女子旅を受け入れていた場所なんです。飾られている絵に女性が描かれていて、“講”として新潟あたりからここに来る人もたくさんいました。そのときだけは血縁関係などすべて忘れて、女子だけで楽しむ、みたいなことが許されていたようです。
石川 女子旅の元祖ですね。たぶんダーゲットをそこにしたんでしょうね。
指出 そうそう。それで「子易」と書くように、安産の神様でもあるので、飾られるものも枕だったり。
石川 おもしろいですよね。移動していると、不思議と何度も行く場所というのができて。そうなると「二拠点目はここにしたいな」という気になりますよね。

移動が「健全な多重人格」を生む
指出 僕は昨年、『オン・ザ・ロード 二拠点思考』という本を出し、今、神戸と東京の二拠点生活をしています。ただ、積極的に神戸に住もうと考えたわけじゃないんです。息子が神戸の中学校に通うことになったので、妻と僕と息子の家庭としての拠点は神戸に。仕事は東京を拠点にして、僕は往き来すればいいということで4年前に始めたんです。でも、最初は胸躍る新天地・神戸という感じでもなく、不安だらけでした。その時、僕が「ここだったら生きていけるかも」と思ったのは住吉川という直線の都市型の川があったから。実はこの川は生活排水が一切流れてこないので透明で、天然のアユが遡り、1995年の阪神・淡路大震災の際は、ここが生活用水の要になったのです。町に暮らす人たちが、川に背を向けて暮らしていない。
僕はそういう町が大好きなんです。奈良県吉野郡の下北山村といい、長良川水系といい、中山間地域に行くと川とともに歴史がある。そういう川に背を向けていない町はすごくいいなと感じていたので、住吉川があることで、背中を押されたようなところがありました。
石川 以前、楽天さんと協力して、コロナ禍の緊急事態宣言があけて人が移動するときに、その移動を利用してGPSでデータを取りながら、移動とウェルビーイングの関係の大規模調査を行ったんです。そこで2つおもしろいことがわかりました。ひとつは移動距離。移動距離が長い方が人はウェルビーイングだったということ。もうひとつは移動の多様性です。たとえば、同じ距離でも、いろいろなところに行っている人のほうがウェルビーイング。距離も大事だし、移動の多様性も大事なんだという結果が出ました。それで僕は移動は大事なんだということを改めて考えたのです。
指出 僕がウェルビーイングの話を教えていただいたおひとり、福井県立大学の高野翔先生に、今、石川さんがおっしゃったいろいろな移動をしている人のほうがウェルビーイング度が高いというお話を聴きました。
石川 なぜかと言うと、さまざまなメカニズムがあって、そのうちのひとつが「いろいろな関係性ができる」ということなんです。同じ所に何度も行くようになると、そこで関係性が生まれる。濃い関係もそうだけれど、薄い関係でもいいんです。薄い関係でも自分が素になれる場があるということが大事で。ウェルビーイングの重要な概念に「健全な多重人格」というのがあるんです。ひとつの人格だけで生きていこうとすると、どこかでつらくなる。
指出 よくわかります。
石川 何者かである自分と、何者でもない自分、このグラデーションが大事だと最近よくいわれるようになってきています。それを専門的に言うと「健全な多重人格」ということになります。法政大学の田中優子先生が「連と号」という話をされていますが「連」とは何かのグループ、「号」はペンネームですね。江戸時代はまさに健全な多重人格が実現されていて、お祭りの連とかお酒を飲む連とか、いろいろな連に人は接続する。
人格は首尾一貫しているというよりも、他者との関係性の中でそれぞれににじみ出て、複数の人格が出てくると思うんですよ。どれだけ自分が明るいと思っていても、明石家さんまさんの前に出ると「意外とそうでもないな」となる。明るさとかそういうものも、結果、関係性の中で人格ができるというので、江戸時代はいろいろな連に入って、いろいろな号があったんだという話です。それはすごく良かったんだろうなと思います。
指出 僕の個人的な経験でいうと、東京にいるときはソトコトの編集長とかサスティナビリティとか、関係人口の、みたいな肩書きがつくのですが、神戸で3〜4年暮らしていると、しだいに○○くんのパパの指出さんとか、沢田研二の歌ばかりカラオケで歌っている指出さんとか(笑)、そういわれる毎日です。それは自分の中では星新一の世界みたいだなと。同じ時間の中で、東京にいたら違う自分を求められるのだけれど、神戸にいるときは自分に求められている役割が違う。これが石川さんのおっしゃる「多重人格」みたいなことなのかなと思います。

石川 移動すると、自分が相対化されると言いますか。東京にいるときに自己紹介するとたぶん、仕事の紹介などすると思うのですが、東京から離れれば離れるほど「東京から来ました」で済んでしまう。何の仕事をしているかとか、肩書きみたいなものがはずれて、ちょっと素の自分になれたりするというんでしょうか。
指出 僕は観光以上移住未満、第三の人たち、つまり関係人口のみなさんが中山間地域に行くことを設計する仕事も多くしているのですが、地域に関わることが楽しいという人たちが、どうして楽しいのかと聞くと、やっぱり匿名性みたいなものなんですね。今、東京にいる自分とは違うかたちで認識されるのがとても楽しいとか、「バーベキューの火を起こすのがとても上手ですね」と言われると、自分はそういう役割ができるんだというのがおもしろいとか。
石川 「いる・なる・する」ということがすごく大事な考え方だと僕は思うようになってきました。人は、他者との関係性をつくるときに、子どもの頃はお互いがただ「いる」ことを認め合うところから関係性が始まって、だんだん仲良く「なる」、そして一緒に部活をするとか、旅行するとか「する」関係になるんです。
「いる・なる・する」の順番で関係性をつくるから、大人になって一緒にすることがなくなっても一緒にいられるし、出会った時と同じ感覚でいられるんですよ。それが、大人になるとだいたい最初は「何をされている方ですか?」の「する」から始まる。そうなると仲間になれるかどうかは能力で決まってしまうんです。ましてやそこで公私を超えて一緒に「いる」ということはなかなかありません。仕事をしなければもう関係性が終わってしまう。都会にいると、何を「する」人なのかと求められるけれど、地方に行けば行くほど「いる」が大事になってきます。
地方に行って「よ~し、創生するぞ!」とか言うと、そこではじかれますよ。とにかく「いる」こと、そして待つことが大事。ある村に移り住んだ人は、1年間ひとことも喋らずにずっと村の人の話を聴いていたと。で、1年後にようやく「きみはどう思う?」と聞かれて初めて意見を述べる、みたいな。だから都会から鼻息荒く「よーし、ここを変えてやるぞ!」と言って地方に行く人は、その時点で何もできないし、向いていないですね。
指出 そう、向いてないですね。たぶん「ビーイング」だと思うんですけれど、そこに「いる」ということが認知されることからプロセスが始まるので、何かをなすとか、巻き込むぞ!みたいなことを言っている人を、僕はいつも制するんですけれど。そもそもその人の夢の実現のために、その地域がお供を買って出ることはまずないから、自分がほんとうに自然物と同じくらいに自然にそこにある、みたいになるための時間のほうが大事だという話をしますね。
僕も3年目くらいになってやっと「指出さん、普通にこっちにいる人なんだな」と思われるようになってきて、逆にその地域の人から「一緒に何かやりませんか」みたいな話になる。先に仕事ありきのチームビルディングではなく、そこにいる人たち同士で何かやろうという中に入れてもらってプロジェクトが始まるのは、とても嬉しいですね。
石川 岐阜の郡上によく行くんです。頻繁に通うようになって地元の人たちと飲み会をしているときに「郡上↘」って言っていたら、「石川さん、違う。郡上↗だ」と。「郡上↘って言っているとよそ者だと思われるよ」と言われたんです。ということは僕も地元側の人間だということなんだなと。すごく嬉しかったです(笑)。
指出 物理的な移動だけではなく、自分がその土地に入っていけているか、その中にいることが不自然でなくなりつつあるなというのも、たぶん、移動のひとつだと思うんです。そういう意味で、移動というのは、自分が生きている中でコミュニティに属するとか、そこに含まれていく中のプロセスみたいなものを含めて、人は常に移動をくり返してきたのではないかと思います。

「時間の移動」もウェルビーイングに
石川 空間の移動ではなく、時間の移動について、最近、すごい気づきがあったんです。日本語で「雲孫」という言葉があるのです。雲の孫と書いて「雲孫」。
酒井 知らないですね。
石川 自分の子、孫、曾孫(そうそん)と続いて、玄孫(げんそん)、来孫(らいそん)、昆孫(こんそん)、仍孫(じょうそん)、そして九代目が雲孫。その次になると、また雲孫の子、雲孫の孫になっていくんです。九代目に雲孫という言葉があるということは、何か意味があるんだろうと、ここ数年、考えていたんです。僕はアメリカに留学するまで、日本とは何かということをあまり考えたことがなかった。天皇制もあまり意識していなかったんです。でも、天皇制は、よく考えたら神武天皇から2,600年で126代続いているんですよ。一代でだいたい20年くらいで。
前田 改めて考えるとすごいですよね。
石川 もし仮に、自分が127代の天皇になれと言われたら、何をするんだろうと思ったんです。過去の126代を勉強しているうちに一生終わってしまう。それで天皇陛下の即位の儀を調べてみました。すると、おもしろいことがわかった。さすがに126代全部は無理だから、初代の神武天皇と過去4代を勉強したり、祈ったり、思いを馳せるというんです。
指出 自分は5代目であるという認識なんですか。
石川 そうです。そして、5代目の自分の振るまいが後ろの4代まで参照されるということなんですよ。つまり九代、ですよね。それが区切りなんだ! と。自分がいる時代を軸にして、前後100年くらい、過去100年に対して敬意を払う、そして次の100年に対して責任を持つ。これが天皇陛下の即位の儀なんだと思って。
「今を生きる」という「今」って、伸び縮みする概念。今日も今だし、今月も今だし、今年も今、今世紀も今なんですよ。たぶん9世代くらいで考えるのがちょうどいい今なんじゃないかと思って、それで言うと、おじいちゃんおばあちゃんのさらにおじいちゃんおばあちゃんくらいまではちゃんと理解しておいたほうがいい。その歴史のつながりの中で自分がいるんだなあと。その時間の移動をする中で、たぶん人って、幸せを感じられるのではないかと思うんですね。
前田 なるほど。じゃあ自己紹介するときも、自分よりも大分前の先祖から紹介したほうがいいとか。
石川 昔はそうしてたと思うんです。「やあやあ、我こそは○○の子孫なるぞ」みたいに。
指出 そのお話で、先ほどの奈良県の下北山村を思い出しました。僕が30年以上通っている場所で、奈良県から熊野のほうに流れる北山川の源流域みたいなところなんです。下北村山には前鬼(ぜんき)という地域があって、前の鬼と書く。この前鬼には道路ができる前から集落があって、前鬼、後鬼(ごき)という鬼の夫婦がその場所にいたと伝わっています。もともと役行者(えんのぎょうじゃ)に仕えた二人で、役行者が「おまえたちは徳を積んだから、そろそろ人間になって、その土地で子孫繁栄をしたほうがいい」という話。まだ鬼の子孫も住んでいるんです。その人は五鬼助(ごきじょ)さんといって61 代目なので、その61代までの家系図が出てくるんです。
石川 それ、YouTubeで見たことあります。
指出 そこに若い人を連れて行って家系図を見せるんですけれど、その家系図にはいつからいつまでご存命かも書いてあるのですが、初代は195歳まで生きたと書いてあるんですよ。2代目が147歳、3代目が131歳で、4代目でようやく115歳くらいになって人間に近づいてきた。行くと見せてもらえますから、ぜひ行って見てみてください。それを見ると、61代のどこまで史実に基づいているかがわからないですけれど、実際に鬼の子孫といわれる人がそこで宿坊を開いているというのを関係人口のみんなに見てもらうと、やっぱりそこでちょっと違う移動が起きるんですね。
そういう移動を混ぜ込むことで、日本地図だけの物理的な移動じゃないものにまで思いを馳せてくれるのであれば、移動というダブルミーニングがやっぱり必要だと思いますね。
石川 余談ですけど、日本の古事記とか日本書紀という歴史書は、神話の話と伝説的な話と人間の話がうまく連続している、世界的にみても珍しいそうなんです。これが地方に行けば行くほど、そういう伝説や神の話になってくる。
指出 それこそ遠野物語の世界みたいなところ、デンデラ野※に行ったら、ほんとうにそういうことが起きているのかなというふうに感じたりするし。移動は人を幸せにするというか、刺激を与えてくれるのかなと思います。
※デンデラ野:岩手県遠野市山口地域に広がる野原。「姥捨」「死者の霊が行くところ」を意味する。
石川 都会にいると、自然の中で生かされているという感覚もわからないですけれど、地方の自然豊かな所にいると感じられる。今、ふと思い出したんですけれど、海にホヤっているじゃないですか。ホヤは移動しているときは脳があるんですけれど、「もうここでいいや」と定住したら、自分の脳を食べてしまうんです。だから移動しない人は脳はいらないんだと(笑)。
最近、睡眠研究でブレイクスルーが出て「人はなぜ寝るのか」という問いがずっと昔からあるんですけれど、実は寝ているほうがデフォルトで、逆なのではないかと。「人はなぜ寝るのか」ではなく「人はなぜ起きるのか」のほうが問いとしては科学的に適切なのではないかというのです。
指出 それはおもしろい!
石川 確かに寝ているほうがデフォルトの可能性が高くて、なぜ起きるのかというと、それは移動するためだということなんです。

以下、みなさんの質問に指出さんと石川さんがお答えします。
Q:ことわざでも「犬も歩けば棒に当たる」と言うように、移動するから何かに当たるということで、それはすでにウェルビーイングではないかと思っていました。ただ、冒頭に日本百景のお話があったのですが、移動を促さないといけないという環境は必ず生まれているようです。移動が大切だといわれているのに、そうやって促さないといけない環境が生まれるのはどうしてなのか、ぜひお聞かせください。
石川 移動っていうのは人類の本能だと思っています。人類発祥の地と言われるアフリカから飛び出した人※が地球全域に移動していった。それを別の言い方をすると、移動しなかった人たちは滅びていったわけです。結局、その移動した人たちが今も生き残っているわけなので、移動が今の人類の本能になっていると思うんですね。
移動の最終地点として都市をつくったのは人類の大発明で、人類の5割以上が都市に住んでいるという中で、でも移動が本能だから、そこにもう理由はないんだと思います。でも、もし移動しない人たちがいて、数万年経ってくると、移動しないことが本能になってしまうかもしれませんね。
指出 僕は魚が好きなので、人の生き方と魚を意識的に合わせて考えることが多いので、その話を。サクラマスという魚に僕は魅了されていて、年に1、2度は東北に行って、サクラマスを釣るために頑張って釣り竿を振ります。サクラマスはヤマメが海におりて大きくなって戻ってくる魚なんです。なぜ海におりるかというと川で負けたからなんです。
渓流や細い川の流れの中で、もっと強い同じヤマメの仲間がいて、強い仲間に追い出されて、仕方ないから下って下って海に行く。海でイカとか食べて、大きな体になってまた自分の川に戻ってくることを考えると、移動は必ずしも強い者(人)たちがやっているわけでもない。何かしらのマイナス要因、ネガティブな要因で移動することで結果的にはポジティブなかたちになって戻ってくることもあるんだと思います。
山形県ではサクラマスプロジェクトというのを実施していて、一度東京に出てきて、仕事を経験したり、人間関係を学んだ後に、サクラマスのように山形に戻って、何かしらのかたちで地元に関与して欲しいというプロジェクトです。県魚もサクラマスなんですよ。僕はそういう意味で、人間とすごく似ていると思います。
※アフリカから飛び出した人:人類の大移動のこと。約20万年前にアフリカで誕生したホモ・サピエンスが、約6万~5万年前にアフリカを出てユーラシア大陸の広範囲に拡散し、最終的には地球全域に広がっていった過程を指します。この移動は主に徒歩で行われ、氷河期には陸橋が形成されたことで北アメリカやオセアニアへの移動も可能になった。
Q:ウェルビーイングってひとことで言うと何なんでしょう?
石川 そうですね、こういう風に考えたらいいんじゃないでしょうか。
そもそも、新しい言葉が出てくるときはどういうときか、ということなんです。今は、ウェルビーイングであったり、ちょっと前だったらSDGsとか、何か新しい言葉でわざわざ表現する状況が出てくる時があるんですよ。
僕は時代が本質を見失っているときに新しい言葉が誕生すると思っています。別に言葉なんかいらないんです。でも、よくわけのわからない言葉が出てくることで「いったい何?」と思うじゃないですか。それを理解しようとする過程で、必ず見失っていた本質にタッチするんですね。だから、ウェルビーイングという言葉が出てきたということは、素朴にどう生きていったらいいだろうかとか、どう生きていきたいのかという、その本質を時代が見失っているからだと思うのです。
昔はたぶん、福祉とか言われていたんですよ。「福」も「祉」も両方ともハッピーな意味合いなんです。でも、どんどん本質から離れて、今、福祉と言われたら、特定の人たちのイメージが出ると思う。本来はみんなの福祉のはずだったのに。ウェルビーイングに限らず、新しい言葉が出てくるときは、時代が本質を見失っていて、要はどうやって生きていくのか、よく生きるとはどういうことだろうということを、時代が改めてそこに生きる人に求めているのだと思ってもらうといいのではないでしょうか。
指出 僕は雑誌を中心としてオンラインのメディアもやっていますけれど、これまでもスローライフとかロハスとか、いろいろな言葉がその時代時代に出てきました。でもそれは流行りというよりも、暮らし方が揺らいでいるときにそういう言葉が出てきて、それを「なぜ?」と考えているうちに、「なるほどね」と納得するポイントが出てくる。
新しい言葉が意味することは、昔からやっているはずのことなんだけれども、その言葉が出てきて引っ張ることで自分たちがやってきたことを再度確認し、未来に進むみたいなことが起きやすいんじゃないかという気がします。
石川 だから言葉にそんなに惑わされなくていいんですよ。