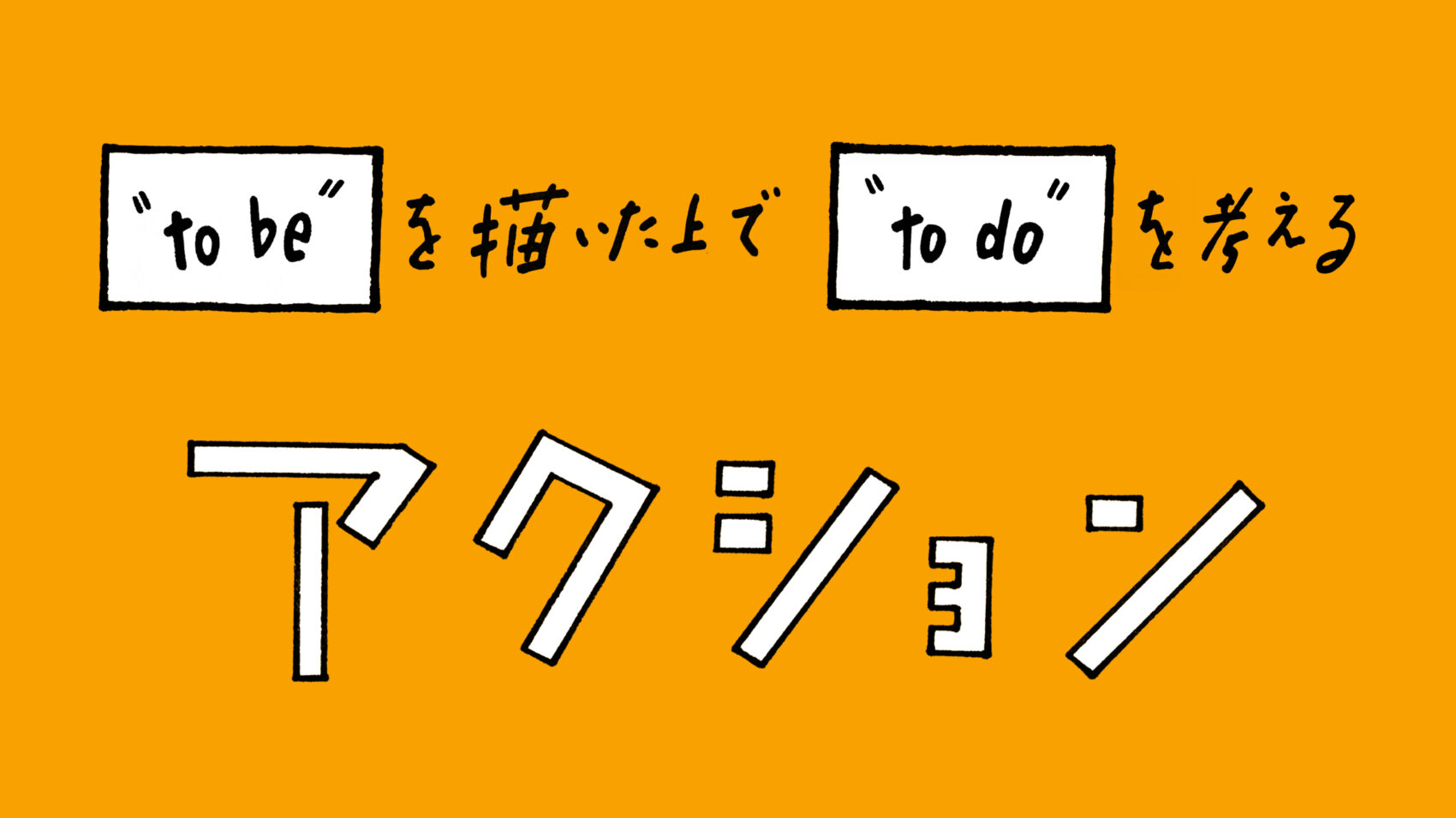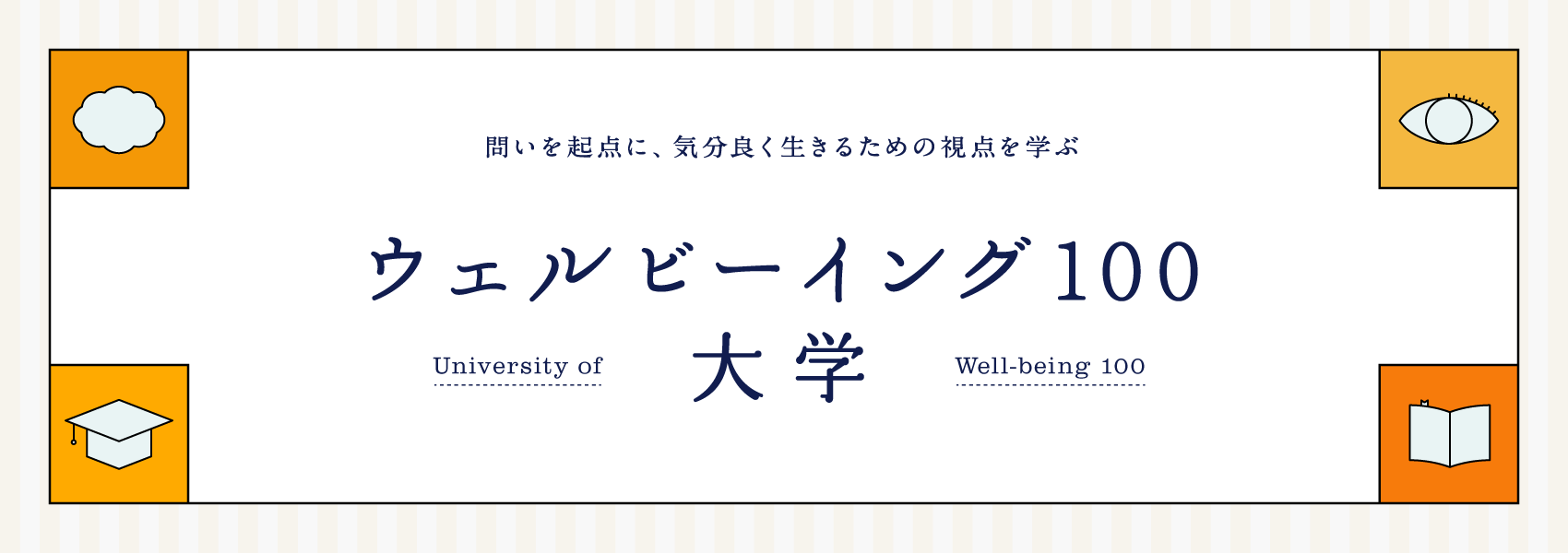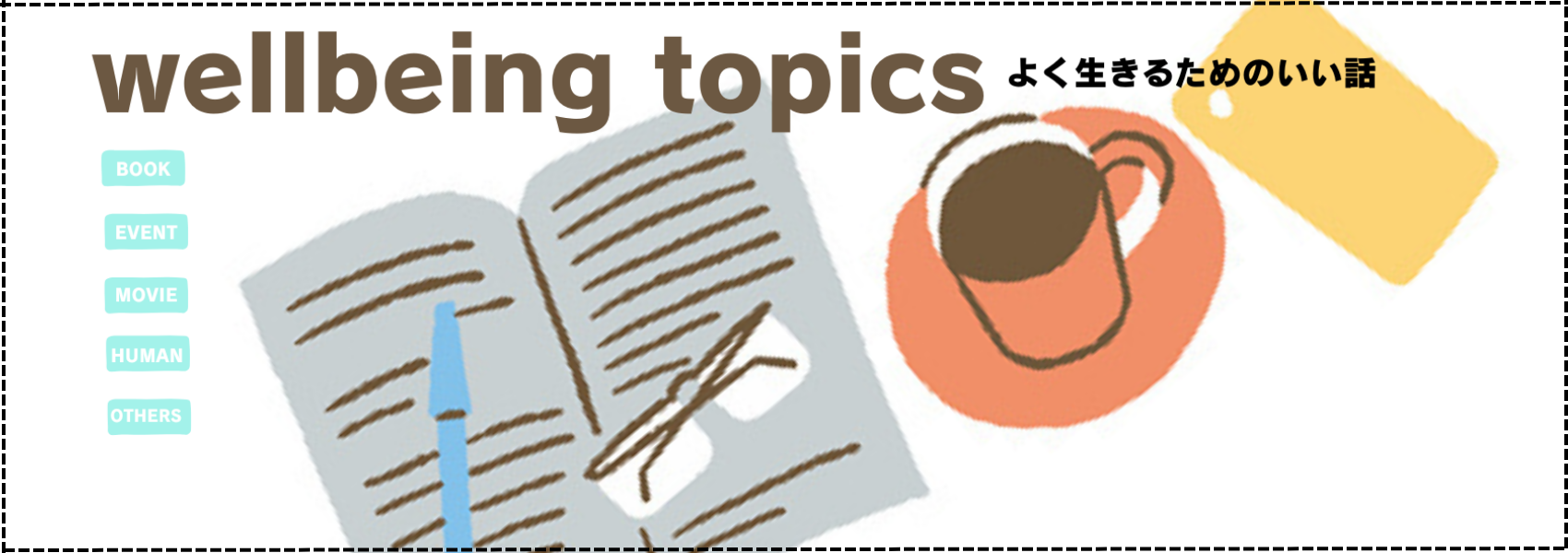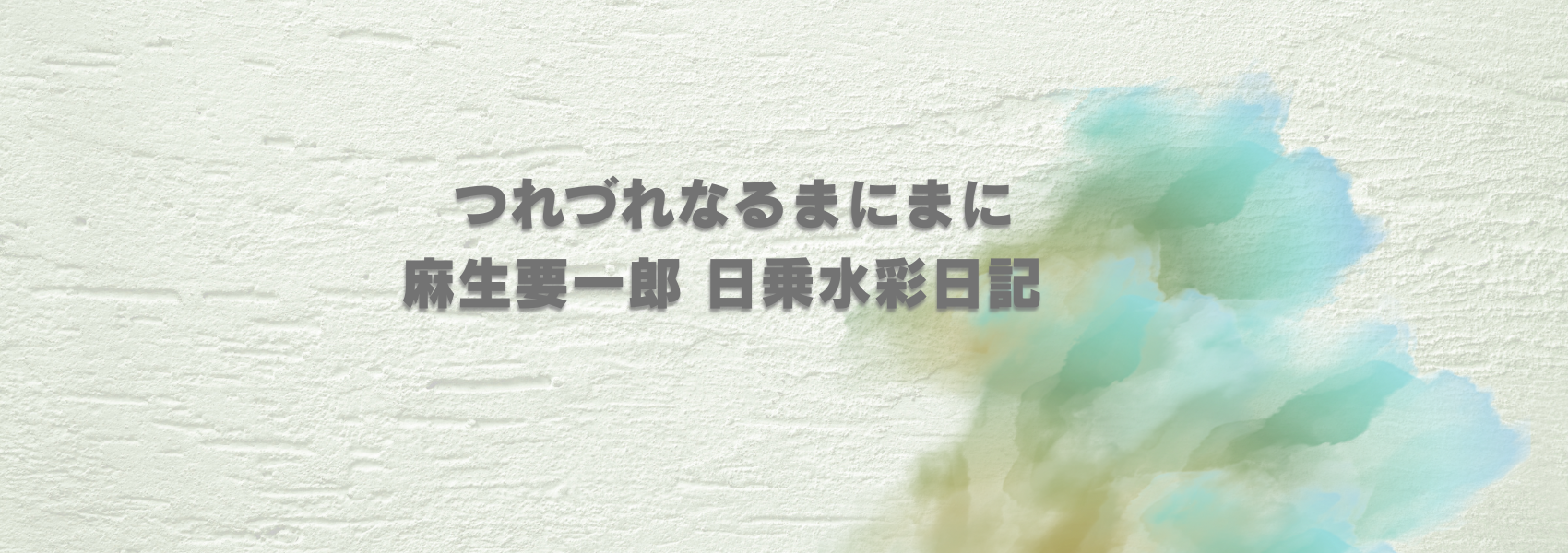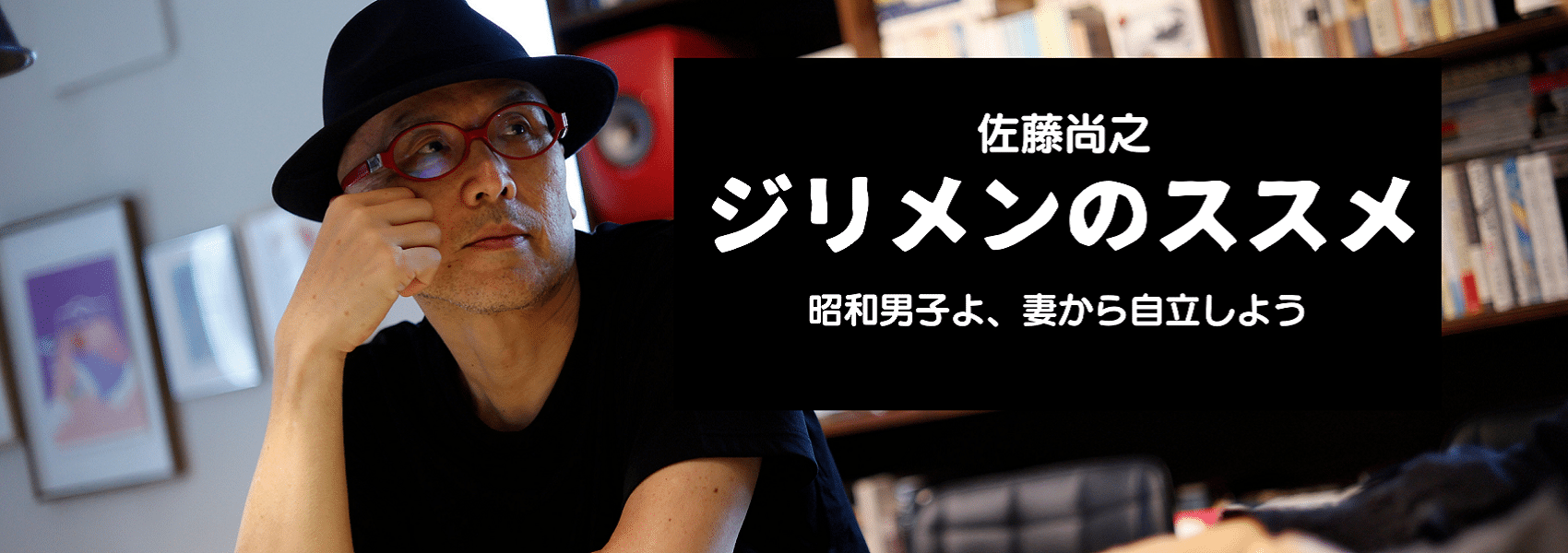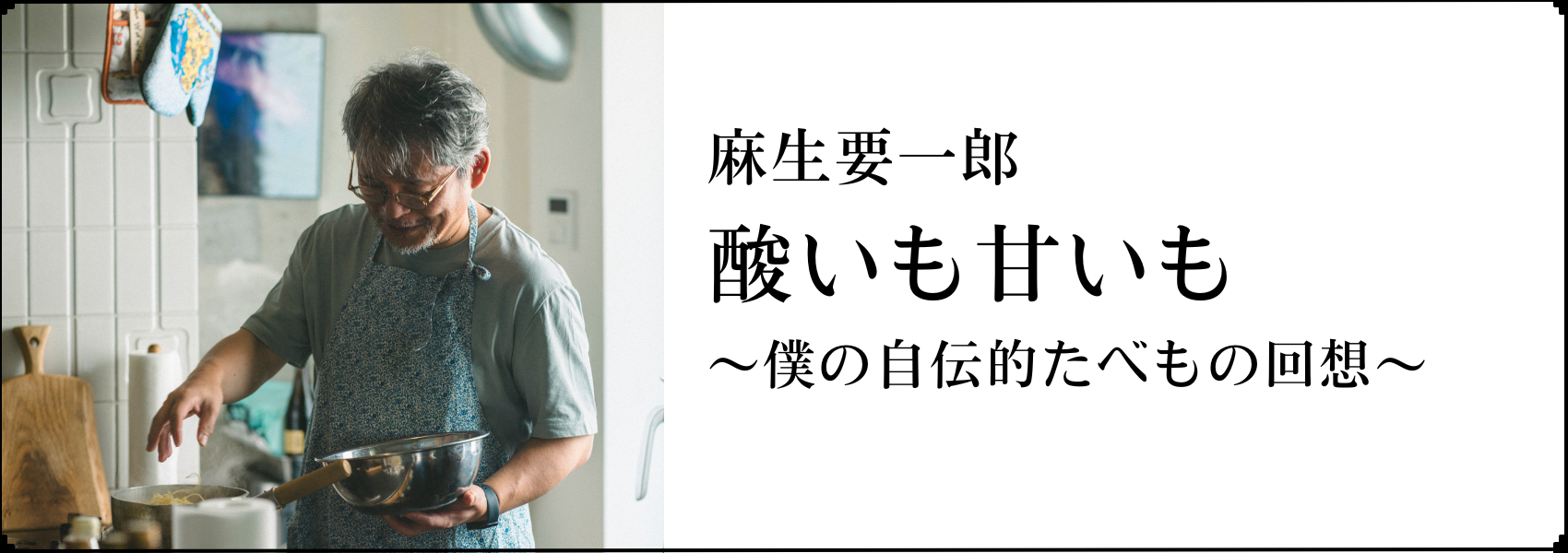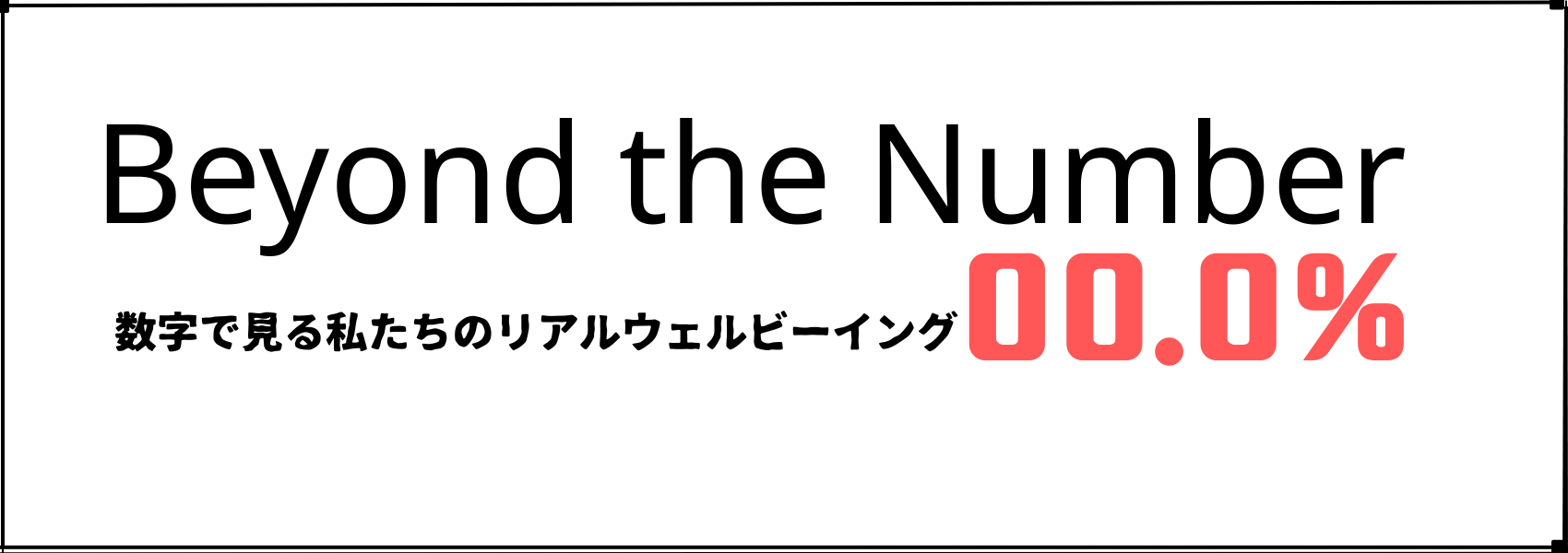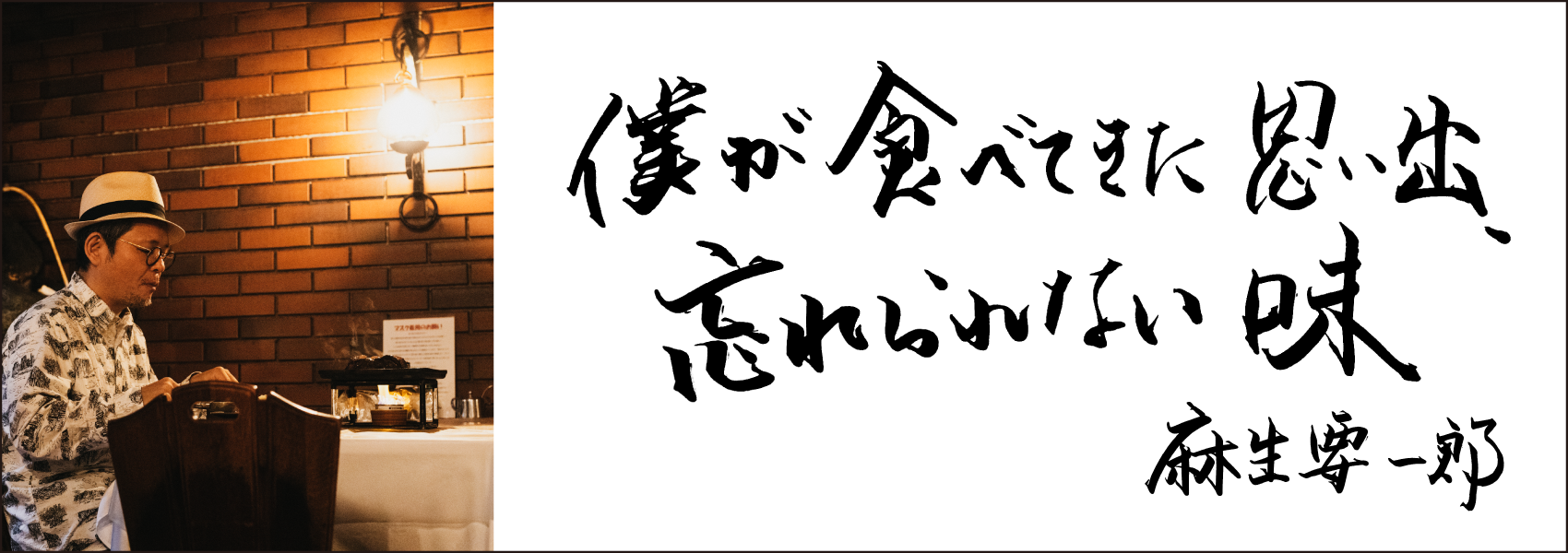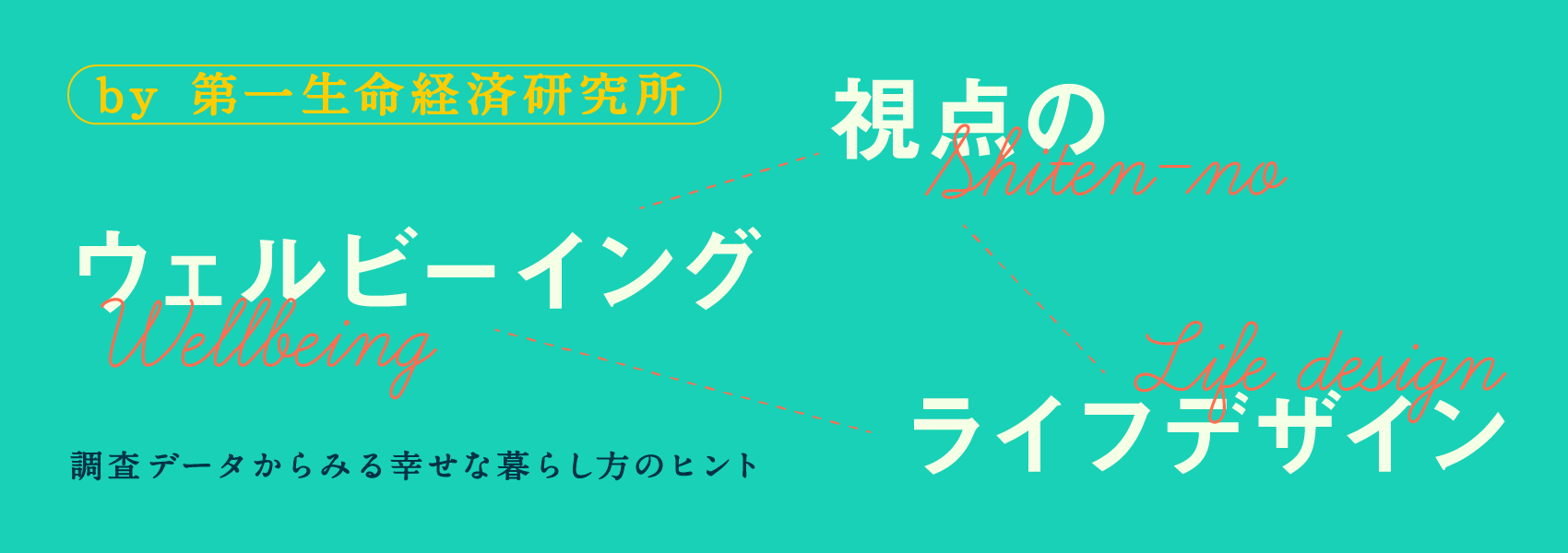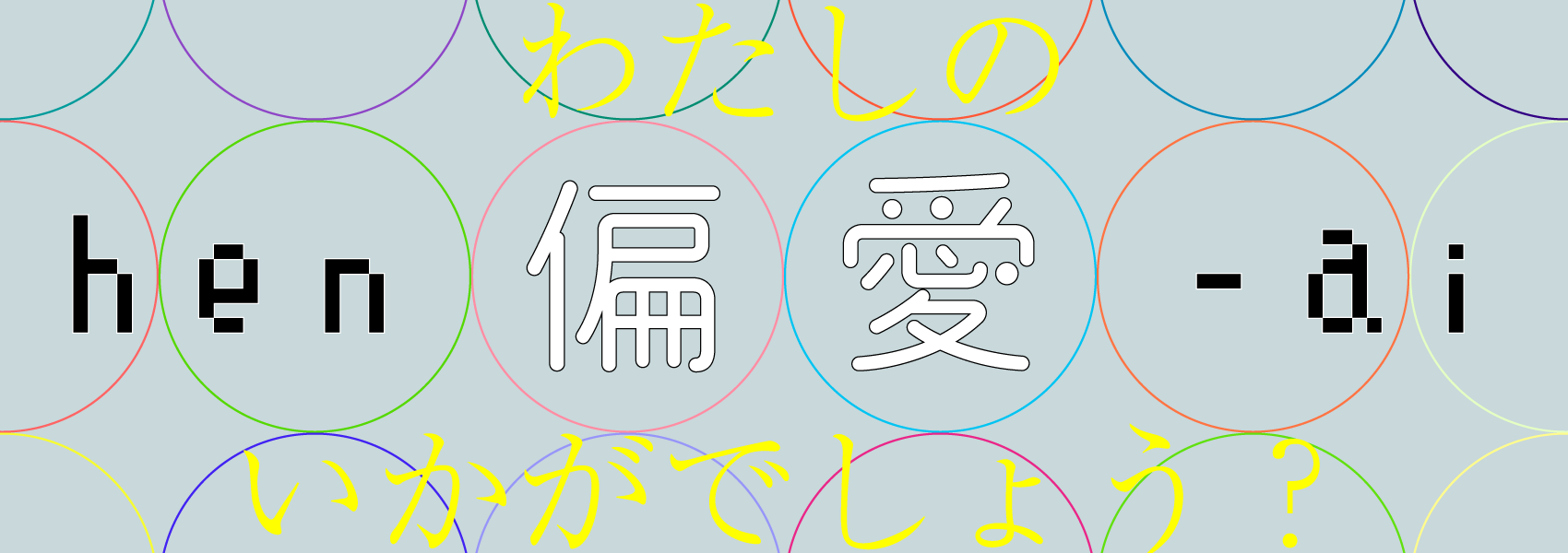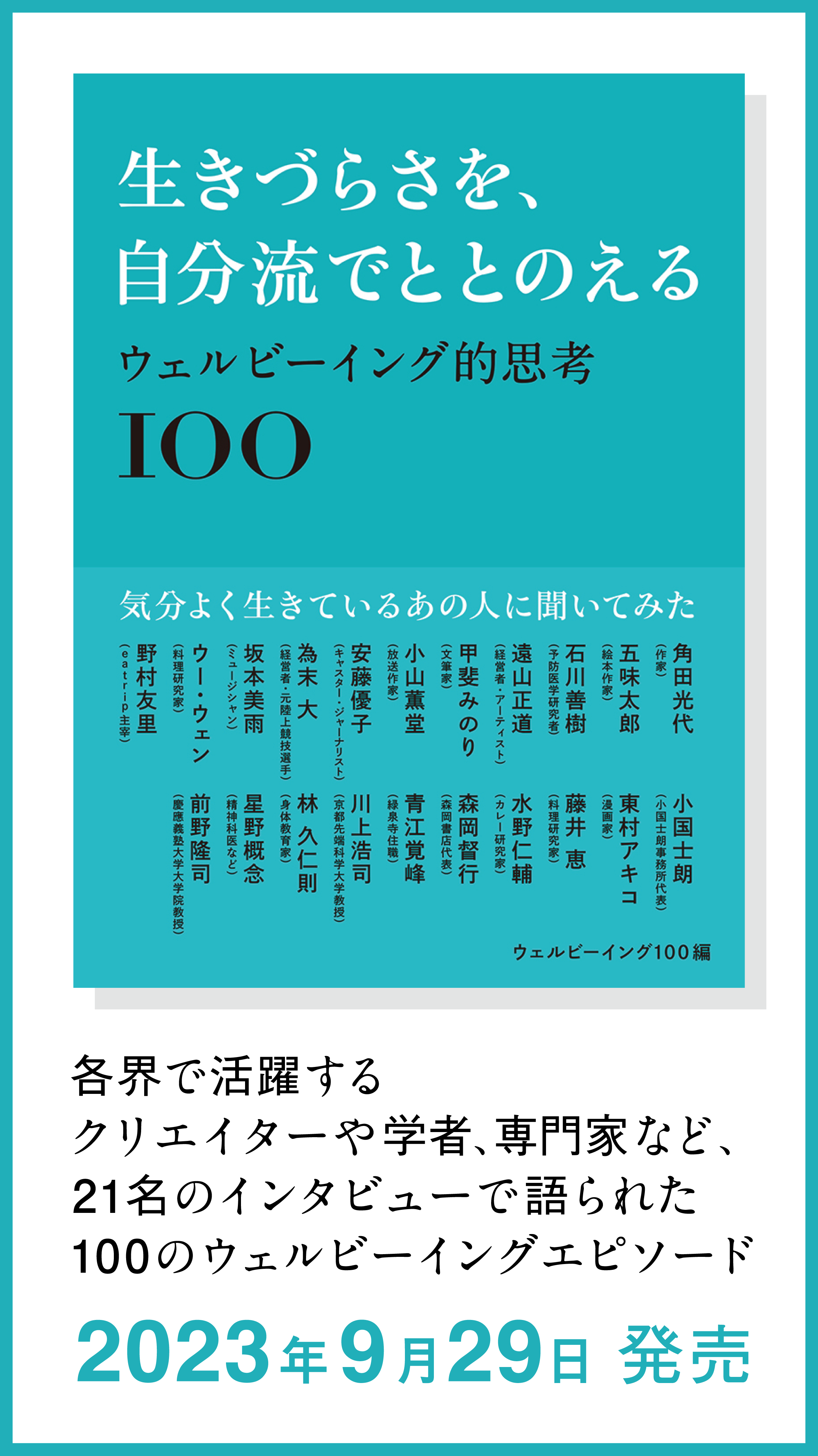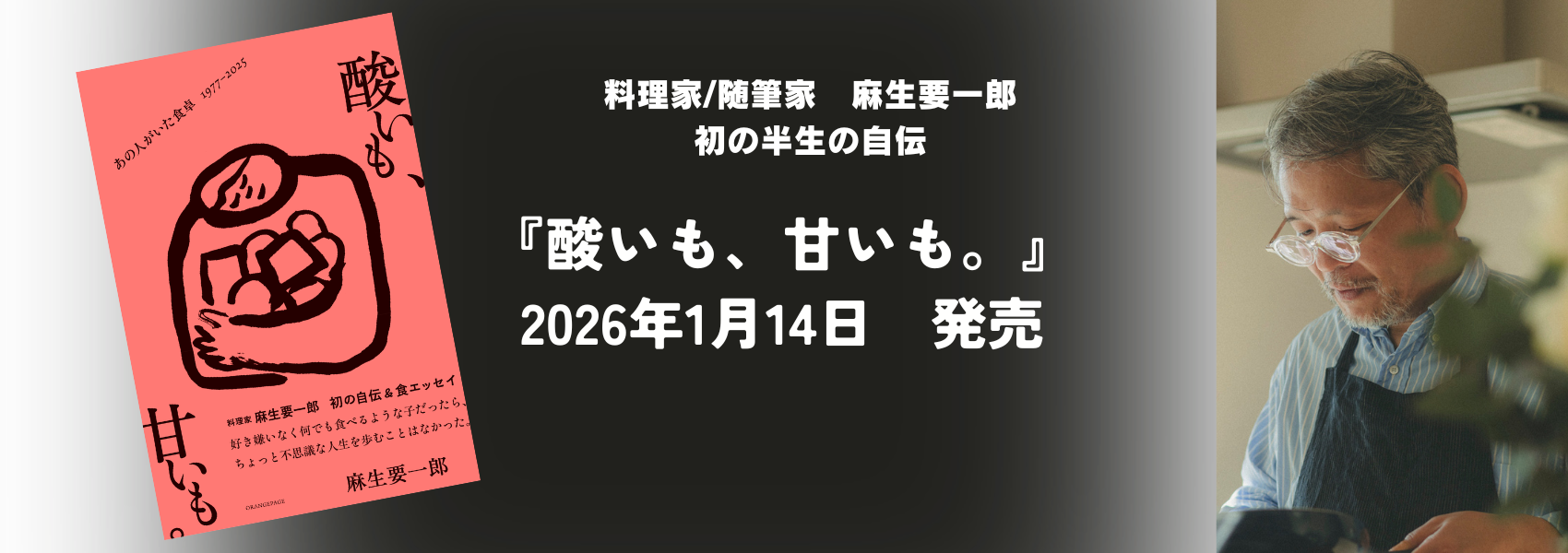文/宮木由貴子
第一生命経済研究所常務取締役 ライフデザイン研究部長兼主席研究員
専門分野はウェルビーイング、消費者意識、コミュニケーション、モビリティ
イラスト/ながお ひろすけ
30年前から、「幸せなライフデザインを考える」チャレンジ
この「ウェルビーイング視点のライフデザイン」のコーナーは、2022年2月に当社が定期的に発行している「ライフデザイン白書」をもとに連載を開始し、当社研究員が各自の専門領域における様々なテーマで発信してきました。筆者が「なぜ今、幸せ視点が求められるのか」という第1号の原稿を書いてから3年。今号で最終回を迎えることとなりました。
ライフデザイン白書の初号を刊行した1995年から、私たちは「生活満足度」という言葉で幸せを語っていました。そして、言葉は違えど、「ライフデザインと幸せには関連がある」ということを、この30年間発信し続けてきました。ウェルビーイング視点のライフデザインを提唱したのは2019年出版のライフデザイン白書「人生100年時代の幸せ戦略」(東洋経済新報社)になりますが、当初、書籍のタイトルに「幸せ」とつけることに社内では不安の声もありました。「ハッピー」「ハピネス」という表現に抵抗はなくても、「幸せ」という言葉で正面から暮らしや生き方を語ることが読者に受け入れられるかどうか懸念があったからです。
今、世の中が「ウェルビーイング」という言葉で幸せを真正面から考え始めたのは、私たちの長年の活動と発信が生活者に必要とされていたことの証左であり、とても意義深いことだと考えています。
なぜ今、「ライフデザイン3.0」なのか
当研究所では、ライフデザインのモデルを、昭和=1.0時代、平成=2.0時代、令和=3.0時代と区分して考察しています。
高度成長期のライフデザイン1.0時代は、人々の価値観の「多様性の低さ」から、皆で同じ幸せモデルを追求することで日本を急成長させることに成功しました。1.0時代は、第一次ベビーブーム世代を中心に、三種の神器(電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビ)やマイホームの取得などを成功モデルとして共有し、皆が同じ方向を向いて頑張った時代で、個人が幸せについて考えるうえで「どうあるべきか(=to be)」を改まって考える必要はありませんでした。
平成のライフデザイン2.0時代は、バブル崩壊に始まる長い不況が続きました。団塊ジュニア世代が大学を卒業するタイミングで就職氷河期に突入した一方、人生100年時代といわれる長寿社会となり、これまでの1.0モデルでは立ち行かない事態に多々見舞われました。また、女性の大学進学率が上昇し、結婚・出産は個人の選択によるという考え方も広がるなど、ライフデザインの多様性が一気に高まりました。人々は人生のカスタマイズの自由を手に入れた一方で、自らの選択により自己責任を負うという意識も併せもつ必要がありました。こうした中、1.0時代には考える必要がなかった「どうありたいか(=to be)」がないまま、がむしゃらに「何をすべきか」という“to do”だけを考えて迷走した人が少なくありませんでした。
令和の3.0時代に求められるのは、まず一人ひとりが「どうありたいか(to be)」を考えることです。1.0時代のように共有された基準がない時代、幸せの形は人それぞれとなっています。ありたい姿(to be)を描くことなく何をしたらよいのか(to do)を考えても、自分に必要なアクションは見えてこないでしょう。
そこで重要となるのが、「ライフデザイン」という、ありたい姿(to be)とすべきこと(to do)を考えるアクションなのです。

「ココロ」を考える時代
では、ありたい姿(to be)はどのように描くのでしょうか。
近年、「人間中心の社会」という言葉をよく聞きます。筆者はこの言葉に少々違和感をもっています。SDGsや環境のサステナビリティ(持続性)などをグローバルに訴える一方で、人間を中心に据えることに対する矛盾を感じるからかもしれません。
しかし、これを「ココロ中心」と考えてみるとどうでしょうか。最近よく耳にする主観的幸福感や、ファイナンシャルウェルビーイング、つながりの価値なども、すべて「その人がどう感じるか」というココロ(主観)に基づくものです。「その人がどう感じるか」を価値基準として物事をとらえようとすると、それはダイバーシティ&インクルージョン(多様性の受容)にもつながります。
私たちは、しばしば目的と手段を混同します。健康でいること、お金をたくさんもつこと、つながりをもつこと自体を目的として、そのためにすべきこと(to do)を考えてしまう傾向があります。しかし、健康・お金・つながりは、私たちのココロの充足のための手段に過ぎません。
まずは、自分のココロが何を求めていて何をどう感じるのか、そのうえで周りの人たちのココロも大切にしつつ折り合いをつけるために、自分は何をしていけばよいのか。周囲が自分に求めるものばかりを気にするのもまた、自分の“to be”を見失う一因です。自分と周囲のココロにバランスよく耳を傾けることが、自分の“to be”を形成し、それによって“to do”の道が可視化され、ウェルビーイングにつながっていくのではないでしょうか。
「これから」をどうデザインするか
第一生命経済研究所の前身である「ライフデザイン研究所」が1988年に設立された際、所長であり筆者の恩師でもある故加藤寛先生(元慶應義塾大学名誉教授、元政府税制調査会長)は「5K」をコンセプトとして掲げました。5Kとは、「家族、教育、経済、健康、心」の頭文字です。
心(ココロ)は「生きがい」と言い換えられていましたが、主観的なものであるがゆえに難しい研究テーマでもありました。しかし35年の時を経て、“ココロを考える”ことはまさにウェルビーイングの研究であり、今さらながら加藤先生の先見性に感服する次第です。先行き不透明で変化が激しい社会において、私たち一人ひとりが、どうありたいか・どうあるべきかという“to be”をしっかりもつことが大事なのではないでしょうか。
当連載は今回で終了しますが、私たちがこれまで36回にわたって執筆してきたのは、書籍「ウェルビーイング視点のライフデザイン」にもとづく各論であり、具体的なアクションのご提案やヒントです。どうか、ご興味のあるテーマだけでも、もう一度皆様にお読みいただき、何かを感じていただけたら、これほど嬉しいことはありません。
最後に、これまで長年にわたって連載を支えてくださったオレンジページの読者のみなさまと、関係者のみなさまに心より感謝を申し上げて、最終回の筆を下ろしたいと思います。
ご愛読いただき、誠にありがとうございました