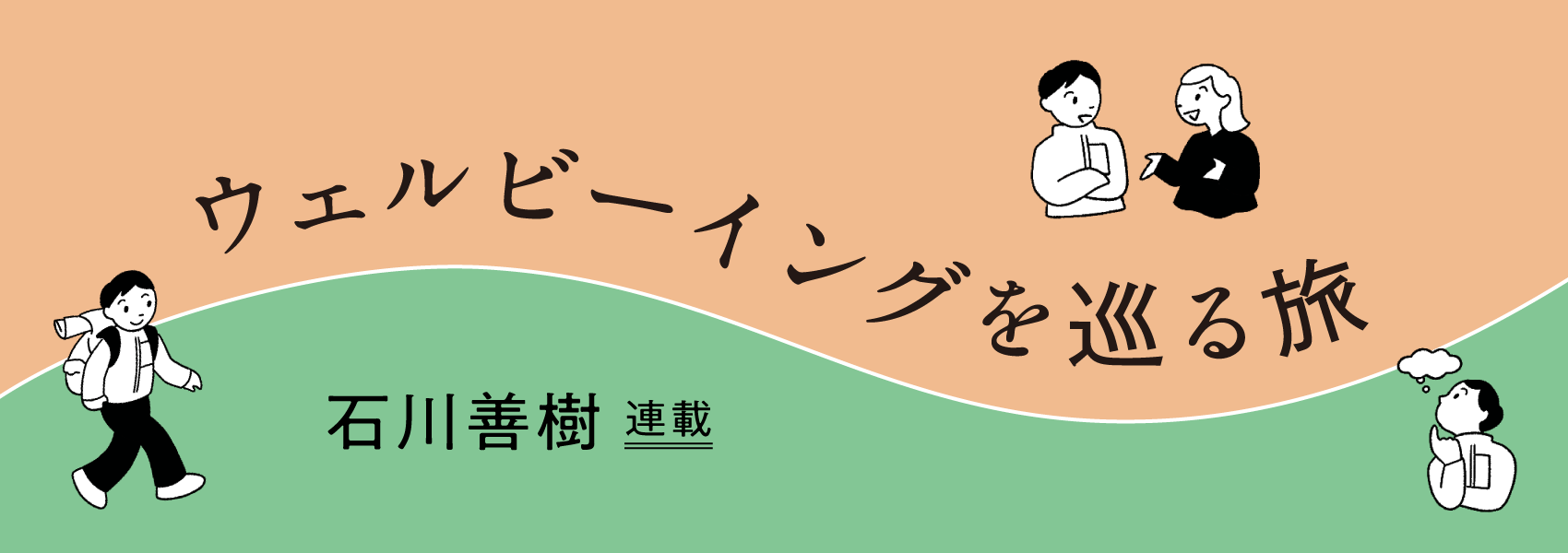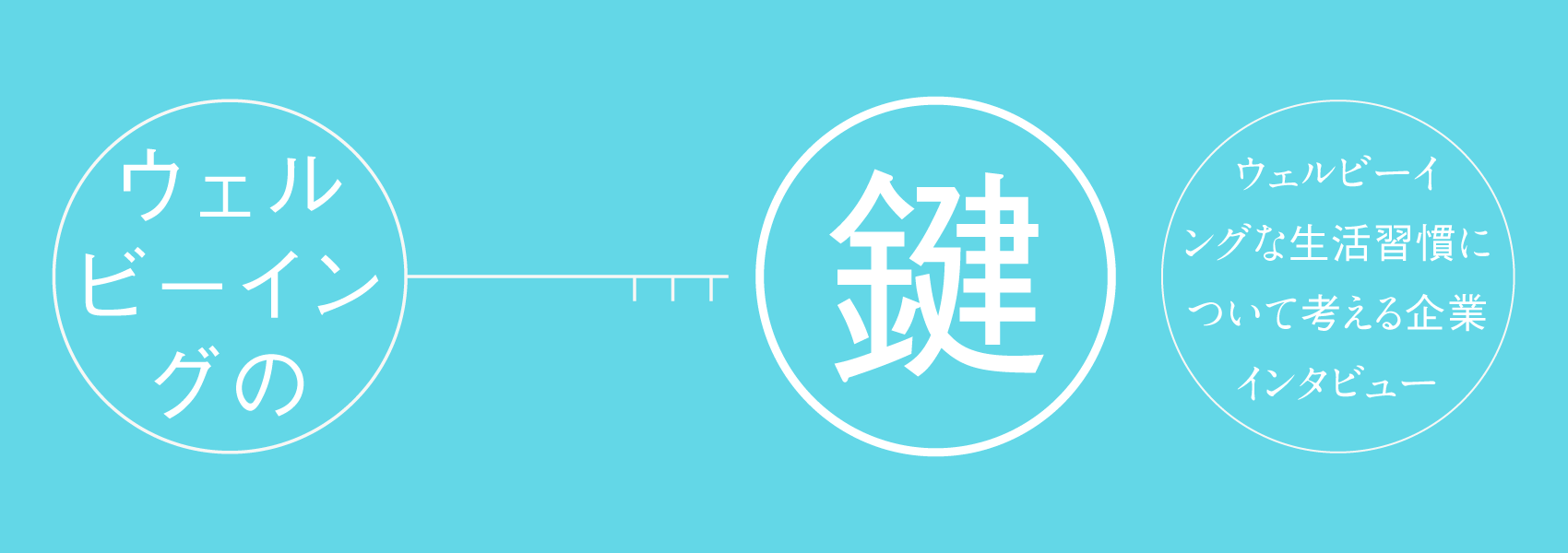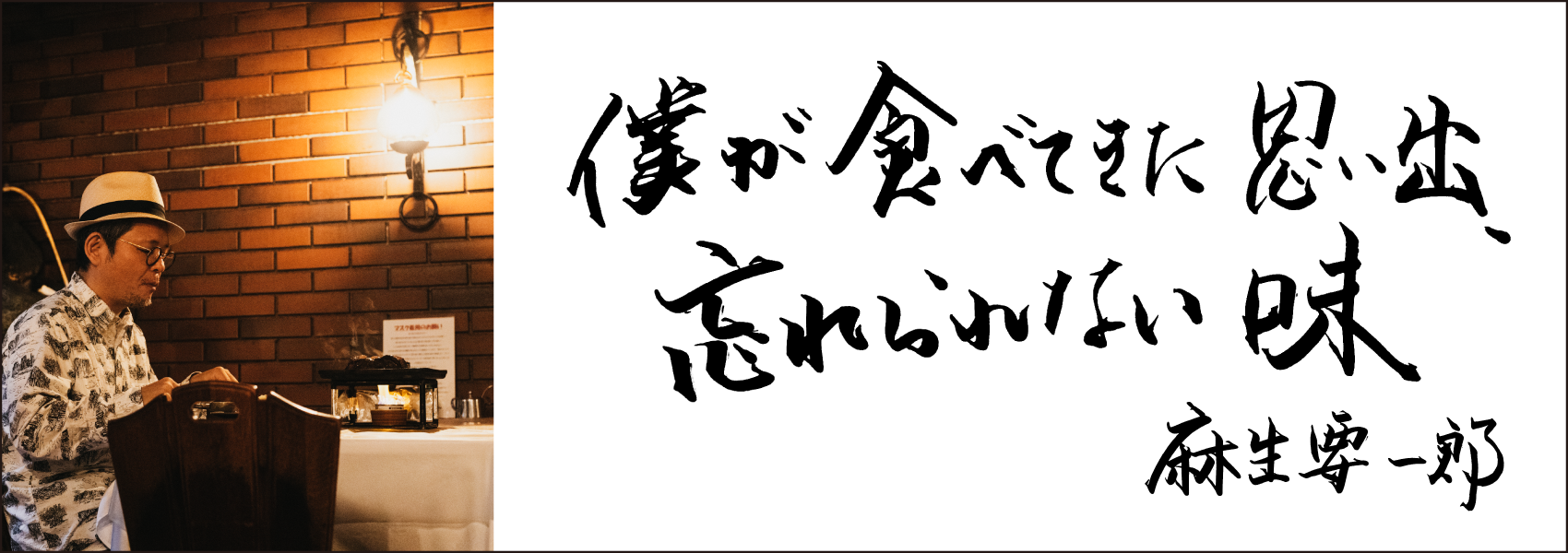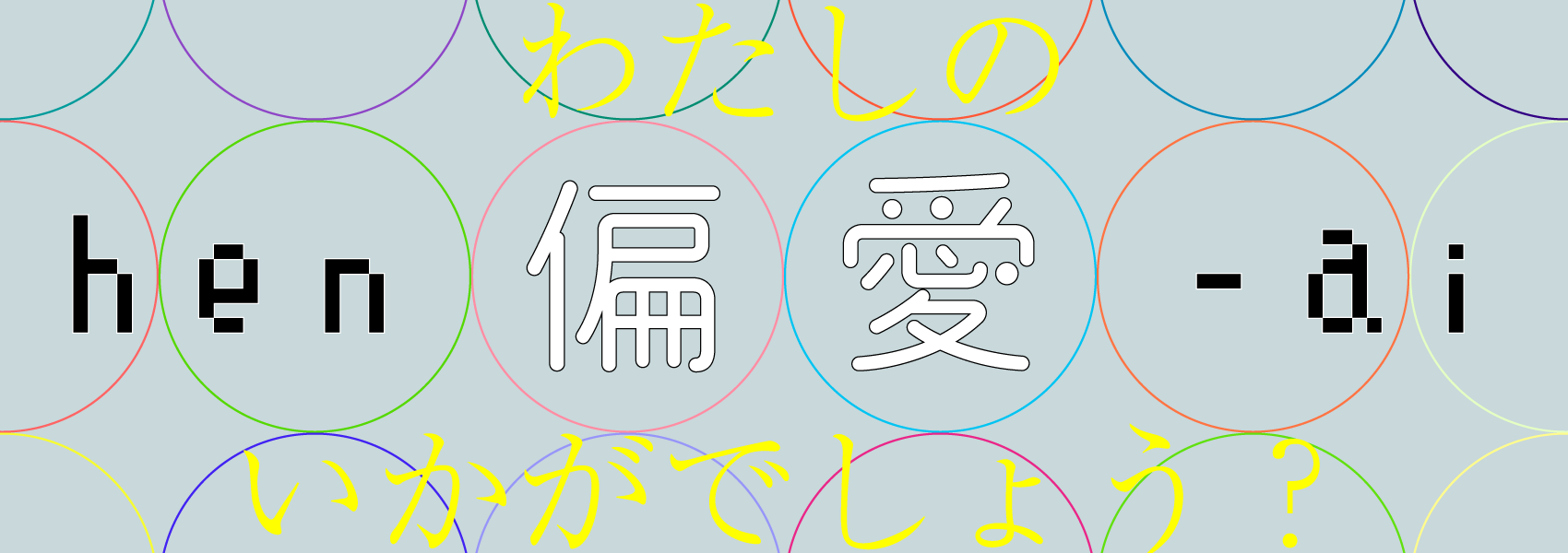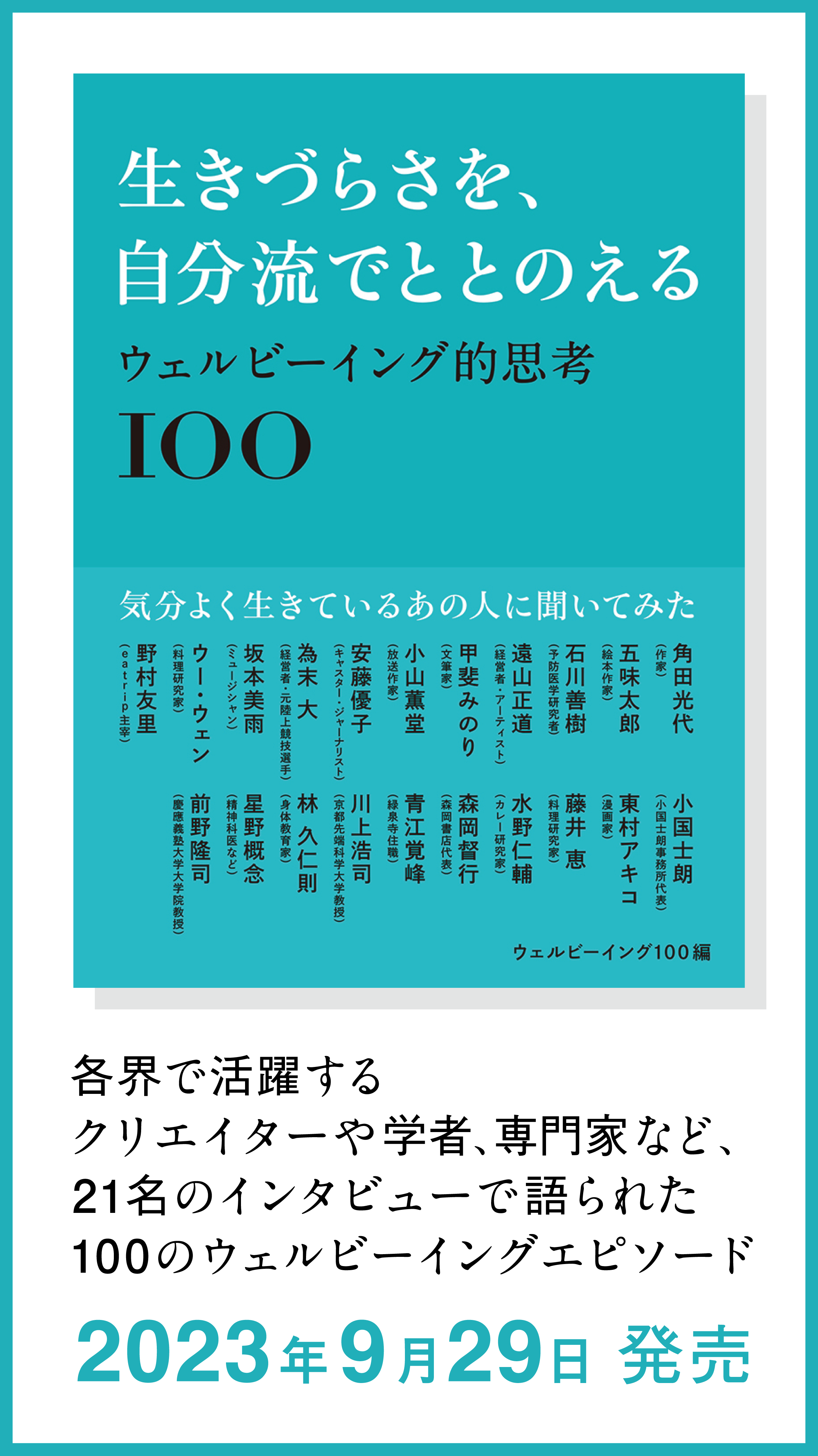文/麻生要一郎
撮影/小島沙織理
「鰻は前川よねえ」
養親の姉が、たばこを燻らせながら言ったのを覚えている。
彼女の父親、文芸評論家の大井廣介も、この「前川」へよく出かけたそうだ。

都心に戦火が迫った頃、我が家には大きな防空壕があって、その中には洋酒がたくさん隠し置かれていた。いよいよ東京を離れるかという前日、盛大にカクテルパーティーをしたとか。随分、呑気な話だけれど、小学生の姉が、御使いに浅草まで出かけて行った。その時に眺めた、戦前の浅草寺周辺の街並みが、今でも鮮明に記憶に残っているという。浅草を車で走っていると、ふとした瞬間、この辺りはこうだったとか、エノケンがね、なんて話をしてくれた事もある。そんな戦前の浅草界隈の様子を語る時、彼女の目にはうっすら涙が浮かんでいるようだった。

その姉が、自宅で転倒して大腿骨を骨折、救急車で運ばれ入院しいていた病院から、暑い夏の日に電話がかかってきた。病棟の看護師さんが「麻生さん、食欲がないようでして、ただ鰻なら食べられるっておっしゃっていて…」と言う。切り出しがあまりに真剣だったので、ドキッとしたが、病院のごはんが口に合わないから、好きなものを持って来いということ。何だか妙にホッとして、思わず笑ってしまった。

我が家は千駄ヶ谷、病院は池袋、もちろん近所にも鰻屋はたくさんある。近くでと思うが、「鰻は前川よねえ」という、姉の言葉を思い出し、前川へ電話をする。車で30分かけて、鰻を受け取り、家を通り過ぎるようにして病院を目指した。面会が叶わぬ時期だったので、看護師さんに袋を託し、その後にかかってきた電話が入院生活の中で一番機嫌が良かった。「わざわざ、前川まで行ってくれたの、あなたも食べた? 良いお店だったでしょ? やっぱり良いお店に行くのは気持ちが良いのよ。」と、何度も同じ話を繰り返していた。もし、近場の店で済ませようなら、電話もかかって来ないし、かかってきても嫌味を言われるのだから、やはり良いお店に行くのが気持ち良いのである。しかし、考えてみれば戦火の中、買い物に出かけた経験からすれば、容易い事かも知れない。


僕が生まれ育ったのは、茨城県の水戸市で、鰻屋が多い街だった。東京に出てきてからも、帰省すると友人達と食べるのは決まって鰻。年に何度か帰るので、鰻欲は満たされており、東京で鰻を食べる機会があまりなかったのである。前川へ何度か通いながら、病院に届けてばかりでは、勿体無い。暖簾をくぐると、いつも丁寧に迎えて下さって、老舗の佇まいが、どこか憧れを抱かせる。そこで思い立って、自分達が食べるためだけに、家人と訪問した。目の前を流れる、隅田川、アサヒビールのフィリップ・スタルクのあまりに有名なオブジェ、その奥にスカイツリーも見える。なんと気持ちの良い眺めであろうか。創業は江戸時代、景観はすっかり変わっているに違いないが、隅田川の流れだけは当時のまま。悠々としたその流れに、しばし目を奪われた。

今回は、二枚目の七代目に、様々なお話を伺う事がかなった。蒲焼き、うざくと、食べる事ばかりが頭に浮かんでいたが、鰻の未来を見据えた話に心が動かされた。養殖も成功しているとはいえ、その生態についての謎はまだまだ多くある。そもそも、僕らが子供の頃は、夏場に30度を超えることが稀であったが、今では夏場に30度を下回る事が稀となった。これだけ気候が変化している事からも、その生態にも当然影響があるだろう。漁獲量が減り、高騰しているなんて話もよく耳にする。鰻屋は、“鰻”がなくては話にならない。こだわりと信頼関係で最も良質な、天然ものに近い品質の養殖鰻を安定的に作る努力をするという。様々な飲食店がある中で、これほど一つの食材と対峙しなければならないのは鰻屋くらいではないだろうか。代々続いた店の歴史と、その未来を語る時、七代目はこの店だけではなく、鰻の未来を背負っている、そんな印象を受けた。先の震災の時、向かいのビルの上階にいた先代が、店の方へ向かって大きな声で「たれを守れ」と、言ったそうである。素材は鰻と伝統のたれ、鰻屋の在り方とは、もはや日本の伝統文化だと言える。


待望の鰻重とうざくが、目の前に運ばれてきた。

お話を色々伺ったあとに、重箱の蓋を開けて、鰻と対面した時の喜びはひとしお。箸を入れた時のふっくら加減が絶妙で、一口頬張れば、うーんと唸り、何とも言えぬ幸せな気持ちになる。そうか、これを入院先の病室で食べたら、機嫌が良くなるに決まっていると、改めて感じた。




うざくは、大人になって、その美味しさが理解できたメニュー。子供の頃には、せっかくの鰻を酢の物にしてしまう事が、何だか勿体なく感じたものである。人生経験を積むことで、味わう事の出来る一皿。隅田川を眺めながら、食べるのはまた風情があって良い。大きな窓から見える景色も、この店のもてなしの一つ。隅田川の花火大会は、店の前で打ち上げられるとか。当然ながら、例年予約で埋まっている。しかし、いつかここから見てみたいもの。皆さん、食事を先に済ませてから鑑賞すると伺ったけれど、僕ならば、花火を眺めながらうざくをひと口、そんな贅沢を味わいたい。


ゆっくり味わって食べようと思っていたのに、撮影をしてもらいながら、あっという間に食べてしまった。しっかり時間をかけたつもりだったが、美味しさのあまり一口が大きくなっていたようだ。気がつけばもう最後の一口が重箱の隅っこで待っている、名残惜しいが、うなぎ坂東太郎(養殖ブランド鰻の名称)との再会を重箱に向かって誓い、完食した。


池波正太郎先生の「むかしの味」に、若き日の池波先生が、吉野さんという方に連れられて、「前川」に来ると、鰻が焼き上がるまで酒を飲みつつ、何か一品頼もうとすると、鰻が来るまでは何も食べてはいけないと厳しく言われたそうだ。僕も、肝焼など頼んでしまうのだが、今回は一口目に鰻重を食べたので、吉野さんの教えの意味が分かったような気がした。この一口のためにという喜びを感じることができた、もちろんその一口のあとには、解禁、何を食べても構わない。

美味しさの余韻に浸って、お茶を飲みながら、隅田川に目をやる。いつまでも、この景色、この味が変わらないことを願った。入院などしたくはないけれど、もしその時には、誰か僕の病室まで前川の鰻を届けて欲しいとここに記しておく。

暑い夏を乗り切る為にも、ぜひ前川へお出かけ下さい。
駒形 前川 浅草本店


創業は江戸文化・文政期、川魚問屋を営んでいた初代勇右衛門が、鰻料理屋を開業、当時は大川と呼ばれた現在の隅田川河畔に位置するこの店は、水上交通が盛んだった江戸時代、舟で水神参りをする客でにぎわい、大繁盛した。
現当主は七代目の大橋一仁さん。「前川」には、代々当主が自ら包丁を握ってうなぎを捌かねば「前川」の蒲焼にならぬという信念と誇りがあり、大橋さんも大学卒業後に調理専門学校に通い、38歳で跡を継いだ。
たれは代々引き継がれており、長い歴史で度重なる戦争や災害の時も、必ずたれを持ち出し、難を逃れた。このたれには蒸したうなぎの味がうつるので、そのうなぎの品質には最もこだわる。「味を守ることも大事だが”うなぎ”という食材の品質を上げ、保ち、持続可能な生産体制を養殖業者とつくりあげることが、この業界全体にとっても大事なことなのです」と大橋さんは語る。
ふんわりと柔らかいのはもちろん、うなぎそのもののうま味が濃く、凝縮した味わいは老舗ならではのたれともあいまって、思わず笑みがこぼれるおいしさ。川の流れを窓外に眺めながら、江戸の人の暮らしぶりを思うのも楽しい。
https://www.unagi-maekawa.com/history/
うな重 御吸い物、御新香、甘味付き *+400円で御吸い物を肝吸いへ変更できます
・特選国産養殖うなぎ 5,900円/上:7,200円/特上:8,500円
・うなぎ坂東太郎 7,300円/上:8,600円/特上:10,600円
昼会席 全8品 11,000円
住所:東京都台東区駒形2-1-29
電話:03-3841-6314
営業時間:11:30-21:00(ラストオーダー20:30)
定休日:なし
予約はこちらからも受け付けます
https://www.tablecheck.com/shops/unagi-maekawa-asakusa/reserve
麻生要一郎(あそう よういちろう)
料理家、文筆家。家庭的な味わいのお弁当やケータリングが、他にはないおいしさと評判になり、日々の食事を記録したインスタグラムでも多くのフォロワーを獲得。料理家として活躍しながら自らの経験を綴ったエッセイとレシピの「僕の献立 本日もお疲れ様でした」、「僕のいたわり飯」(光文社)の2冊の著書を刊行。現在は雑誌やウェブサイトで連載も多数。今年新たな書籍も刊行予定。
麻生要一郎さんの、こちらの記事もぜひご覧ください!
↓「料理とわたしのいい関係」麻生要一郎さん
https://www.wellbeing100.jp/posts/478