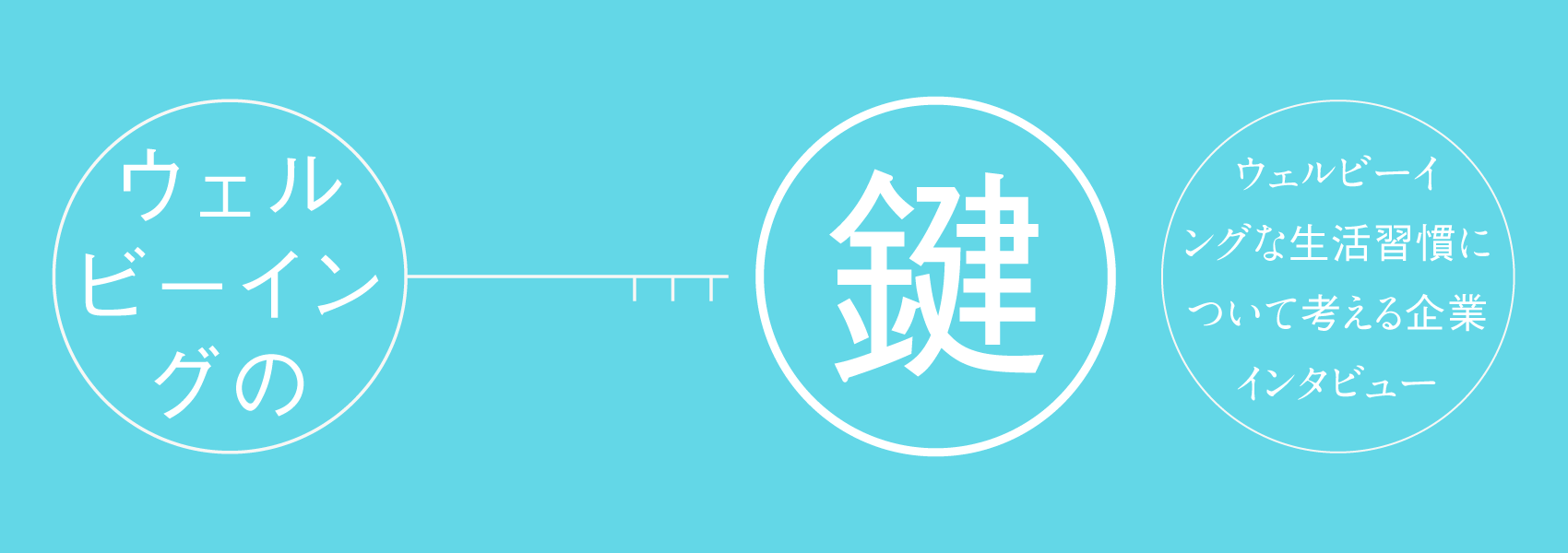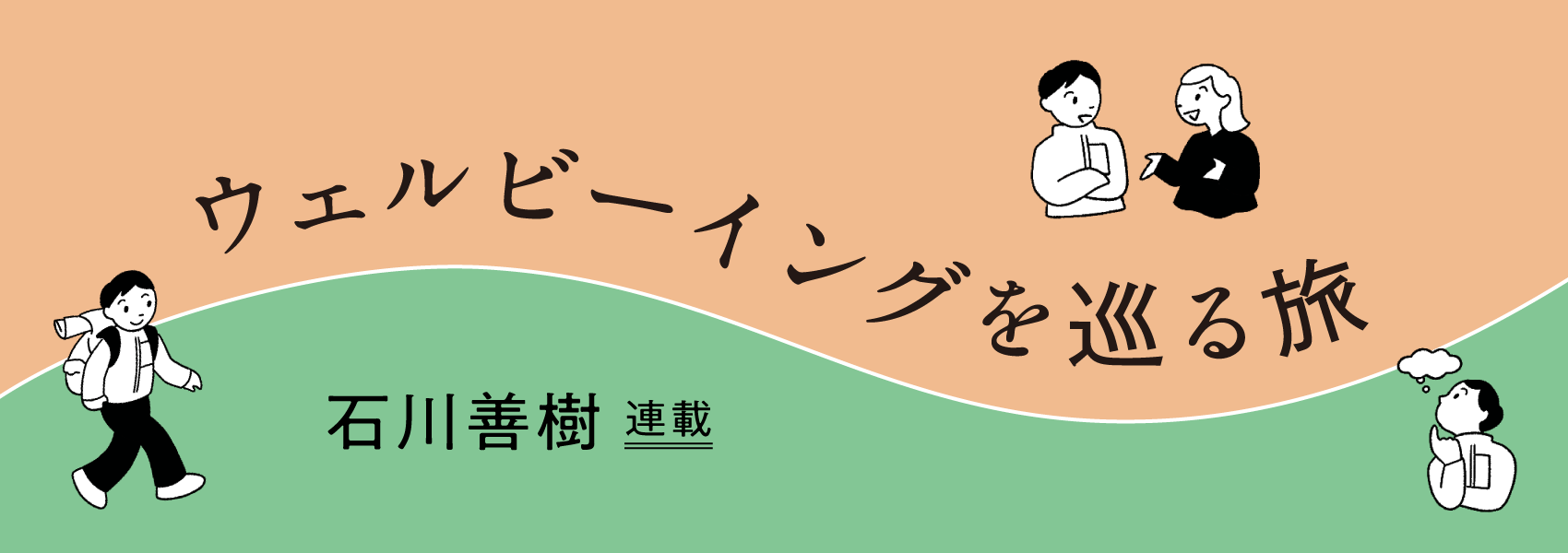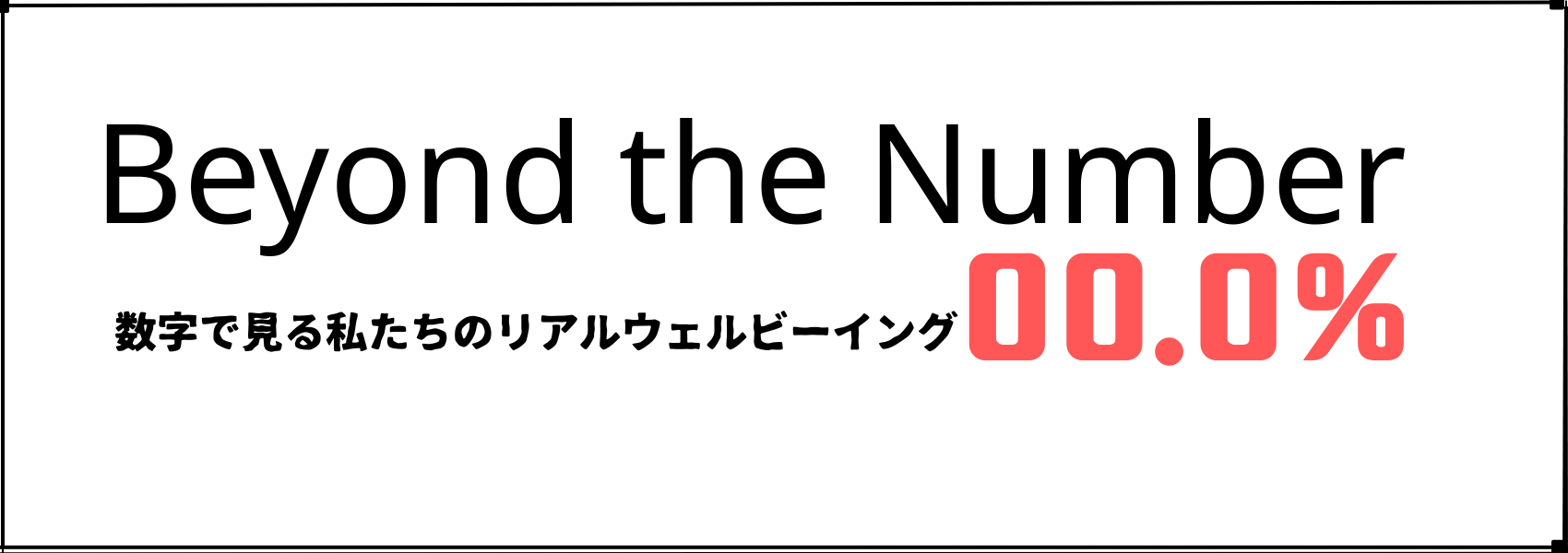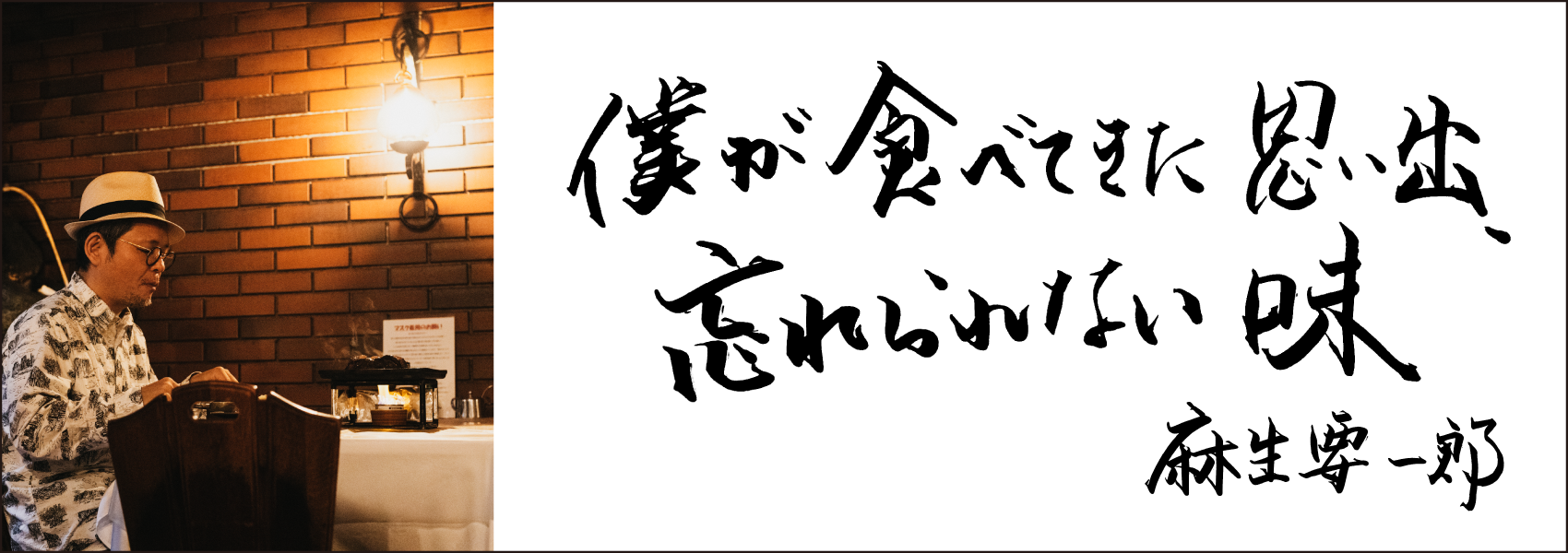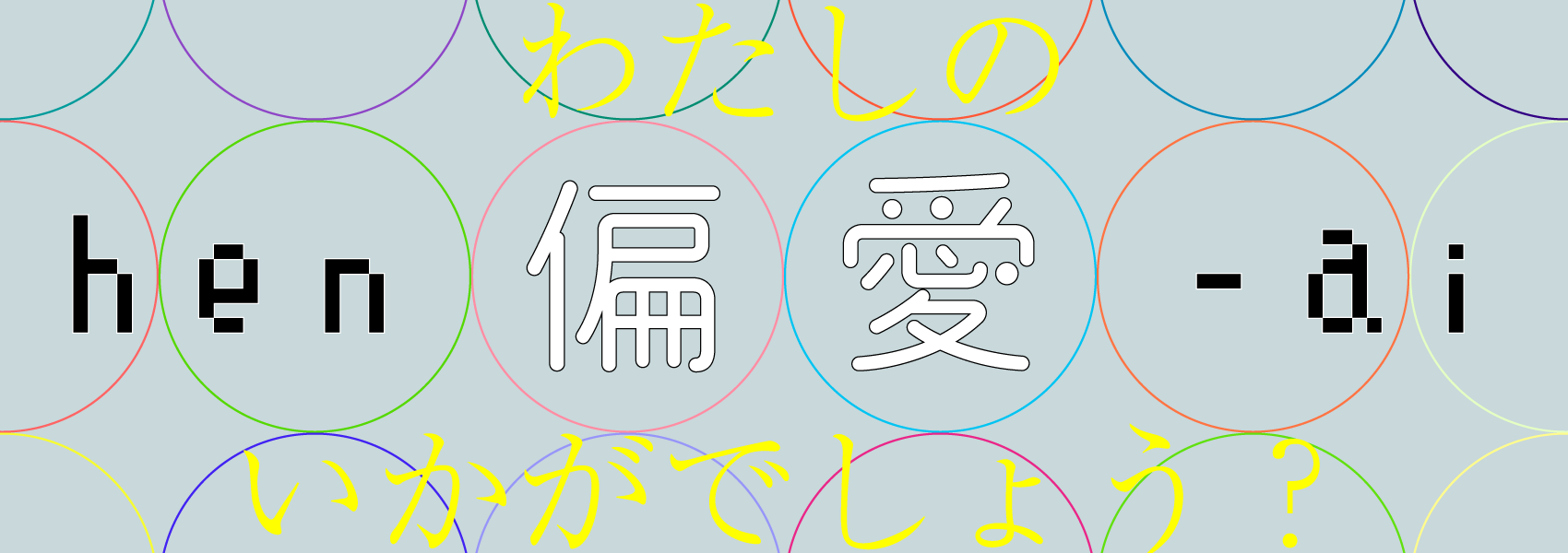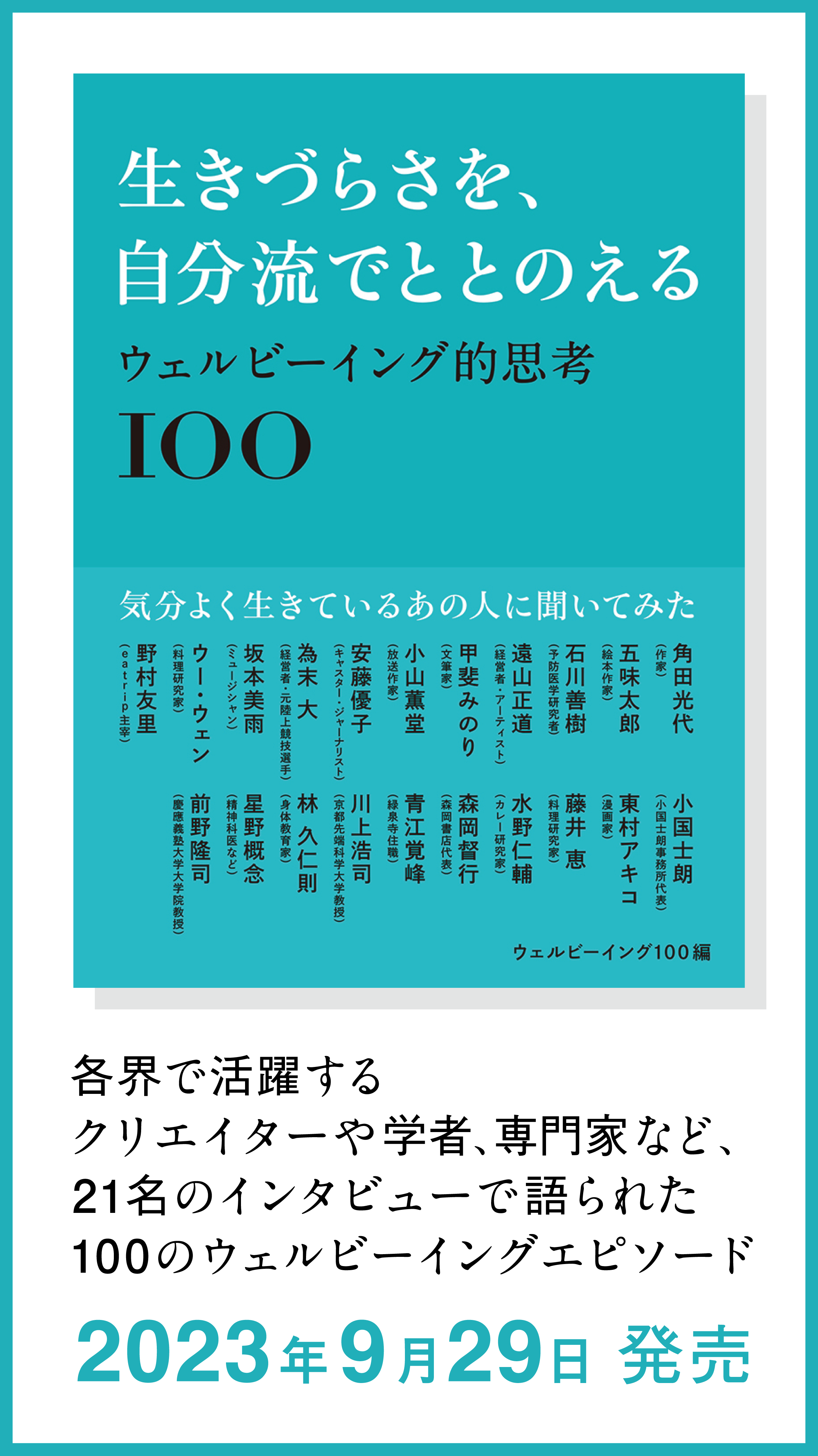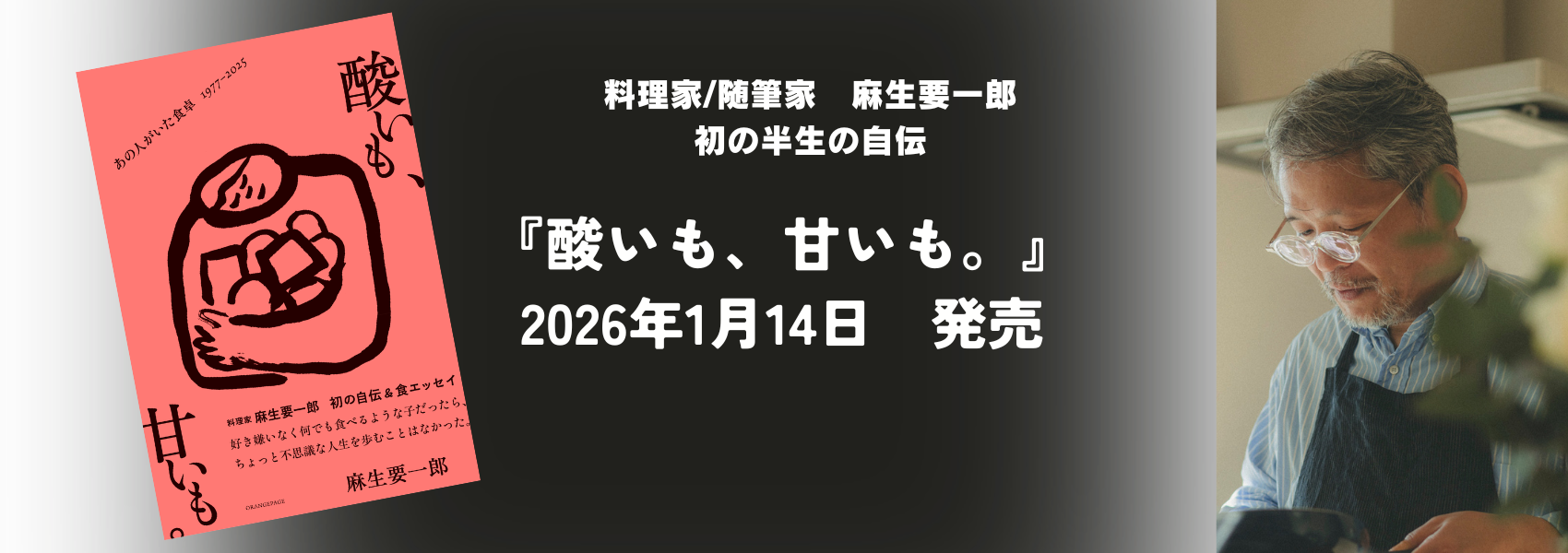これまでになかった視点や気づきを学ぶ『ウェルビーイング100大学 公開インタビュー』。第13回はeatrip主宰の野村友里さんです。フードディレクターとして活躍し、東京・原宿
のレストラン「restaurant eatrip」、食材店「eatrip soil」では、料理人として、また生産者と消費者をつなぐ立場で、食材の持つ野生や旬を大切にし、食のもつ力や豊かさを深く広く伝えています。野村さんの言葉から導かれる“食とウェルビーイング”を考えるヒントとは?
聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100 byオレンジページ編集長:前田洋子
撮影/原 幹和 JOHN LEE(本)
文/中川和子

少しだけ人より得意で、居場所を見つけられたのが料理でした
酒井:野村さんはお母様の影響で料理人になられたということですけれど、影響を受けた、または印象に残っていることはありますか?
野村:母のポリシーが「お腹空かせている人はほっておけない、お腹いっぱい満たしてあげたい!」っていうものだったんです。
酒井:それは食に対して、とてもていねいに向き合ってくださったという……。
野村:母には「食べさせたい」という気持ちがとても強くて。
前田:その温かさはたまらないですね。
野村:でも「おなかいっぱい」って言っても、さらに料理が出てきちゃう。とにかく「食べて、食べて」と(笑)。
前田:おもてなし教室をされてたんですよね。
野村:そうです。祖母もお茶の先生をしていたこともあるので、私がレストランという、お客様を迎えて、おもてなしをする場を作ったのは、そういう空間が好きだからなのかなあとも思いますけど。
酒井:小さい頃から料理のお手伝いをされてたんですか?
野村:母は料理しながら一緒におしゃべりをしたいので、スタートは「一緒に作ろう」なんですけれど、結果から言うと、母がタタタ!と作って「できた!」となる。だから私自身は母がいないときに、自分の作りたいものをゆっくり作るようにしていた記憶がありますね。
酒井:お母様から受け継いだものや、考え方とかありますか?
野村:「受け継ぎたい」とか「受け継ごう」と意識したことはなくて、職業としても料理に携わる人生になるとは全然、思ってもいませんでした。こうやってお話をさせていただいたりする中で、最近、ようやく見えてくるものがあって。「受け継ぐ」って目に見えないものなんですけど、私も料理をするということが全然苦ではないので、そのあたりはすごく似ているのかもしれないなあと思います。
酒井:“食”に対して明確に「好きだな」「これを仕事にしようかな」という気持ちが芽生えたのは何かきっかけがあったんですか?
野村:料理することは当然だと思ってたんですよ。だから、料理を仕事とも思っていなくて。どちらかというと私は音楽とか写真とか絵とか、そういったアートのほうが好きではあったんです。でも、最終的には少しだけ人より得意で、そこに居場所を見つけられたのが料理だったという感じです。

「いきいき」とした食材を「いきいき」食べる楽しさ
酒井:野村友里さんといえば、僕は映画『eatrip』*を劇場で観て、これはどういう人がどういう想いでつくったんだろうとすごく衝撃を受けました。
※映画『eatrip』……野村友里さんが監督を務めたドキュメンタリー映画。さまざまな分野で活躍するアーティストたちや、築地市場の仲買人といった食に携わるプロを通じて「食」を見つめ直した作品。2009年制作。
野村:あれは私が料理を生業にしはじめて10年ぐらい経った頃ですね。有難いことに「本を作りましょう」と言われたり、ラジオ番組とかテレビ番組に出させていただくようになったんですけど、その頃、みんな“ロハス”*ってタイトルがつくんですよ。ちょうど地球環境を考えるライフスタイルのはしりの頃だったので。で、すごくざっくりしたそのロハスが、自分の中でまだしっくりきていなかったんです。たとえば、古い車は好きだけど、ガソリンをたくさん使ってしまうとか。本を作るといっても、まだ10年ぐらいしかやっていなくて、その後の自分も変化するだろうし、それを文字として残していいのかと。食べるという行為と料理が、日常の中にちゃんと溶け込んで生活をしている、そういう方たちから影響を受けたことが多くて、そういう方たちの生き方のほうが、世の中でいうロハスっていう言葉に近いんじゃないかと思っていて、そういう話をしていたら、「じゃあ映画にしましょう」ってことで、トントンと話が進んでいったんです。
※ロハス……LOHAS= Lifestyles of Health and Sustainability の頭文字をとった略語。健康で持続可能な生活スタイルのこと。
酒井:“食育”とか“食の安全性”とかいう言葉が認知されはじめた時期ですよね。それと同じように、このメディアの “ウェルビーイング”という言葉を聞くと、みなさん、すんなりとは腑に落ちないとおっしゃるんですが。野村さんはどういう印象がありますか?
野村:私もよくわかりません(笑)。
一同:笑
野村:その人が満足していればいいのかなあとは思うんですけど。でも、より良く、と思うことが、生きている限り続いていくことが生きるってことなのかもなとも思うし、その気持ちに終わりはないと思うんです。映画には、農家の方とか役者さんとか、お茶の師匠とか、いろんな方に出ていただいてるんですけど、その中に、池上本願寺の山主さまがいらしたのです。
前田:山主さまですか。
野村:そう。その方が「いきいき生きる」っておっしゃったんですね。「生きているからには娑婆*がいいんだ」と。みんないつかは死ぬんだけれど、生きているからこそ「いきいき」ですよね。だから「野菜もいきいきがいい。全部いきいき、それが生きるっていうことなんだ」っていうお話をされたんです。それが言葉だけじゃなくて、そうおっしゃる声や目の輝き、すべてから、内側から生きているのが楽しいと滲み出ている。で、「何が楽しいって、やっぱり食べることなんだよ。夏は氷を削るシャシャッという音に涼しさを感じたり、冷たい飲み物を喉でゴクっと飲む愉しみがある」と。ほんとうに人それぞれ、人と比べることじゃないんですけれど、毎日のごはんがそういうふうにいただけたら最高だろうって。それは男女の別や年齢に関係なく、みんなができることだなと思ったシーンだったんです。
※娑婆(しゃば)……仏教語。煩悩や苦しみが多い現世。釈迦が衆生(しゅじょう)、すなわち人を救い、導くこの世。

酒井:生きることと食べることの深い関わり……“ウェルビーイング”って言葉を理解していくときに、「食べる」から考えはじめてもいいんじゃないかと思います。
野村:そうですね。その山主さまが、「誰もあっち(死後)がどんな世界かわからないけど、生まれたからには間違いなく全員あっちへ行く。食べることは今の瞬間を“生きている”と実感できる行為、だから誰かと時間をシェアして同じ食べ物を体に入れる、胃袋を分かち合うっていうことはこれ以上ない“共有”だから、五感を使っていきいき食べられる」っていうようなことをおっしゃったんですよね。
酒井:「五感を使っていきいき」って聞くと、改めて体と心って分離できないんだなと思います。
野村:仕事をしていたりすると、体と心がいつの間にか離れて、遠くなってくると感じるときがあるんですが、それでもたぶん、いちいち言葉にしない体感、感覚ってたくさんある。風の心地良さとか、寒いときに温かい湯気にほっとする感じとか。「いきいき」ってそういった小さいことを楽しめるようになるということでもあるのではないかと。
酒井:言葉にできることって限られている中で、食事の時間の五感を、たとえ短い時間でも共有できると、人ってすごく距離が縮まるような気がしますね。
野村:そうだと思います。食事を共にしたことって、のちのち時間が経つと、記憶としてよみがえるときが多くないですか? 「あのときの料理はグツグツしてたな」とか、「冷え切ってたなあ」とか。「味も何もしなかったな」っていう心境で食べたことなども。記憶として残ることはすごくある気がしますね。
「おいしさとは何だろう」という思考の先にあるのは食材そのもの
前田:野村さんがおいしい野菜を食べて「これはなぜおいしいんだろう?」って思うところからはじまって、食材を作った人とご自身の関連について考えるようになったのはどんなきっかけがあったんですか?
野村:私は母の手作りの料理が、とてもありがたいことでおいしかったと、のちのち気づいたんですが、いつも食べていた時にはわからなかった。何でもちょっと距離をおかないと見えにくいことっていっぱいあるなと思うんです。成長して外のごはんを食べたり、人の家で食べたり、ちょっと留学したりして、母と物理的、時間的な距離ができて初めて、手作りには時間をかけた愛情があって、それがいちばんなんだと思いました。それは料理だけでなく食材も同じで、愛情をかけて育てられた食材はやはり美味しい。自分が料理の道に入るようになって「おいしいって何だろう?」と考えたとき、料理の組み合わせとか、お皿との相性とか切り方とか、そうしたものに惹かれた時期もありましたけど、突き詰めて考えると、やっぱりどんどん食材にたどり着くんですよね。ほんとうにおいしい食材にあたると、何もする必要がないと思うくらい。いいグリーンピースなんて生でいただいたほうが「こんなにおいしかったの!?」って思うし、そら豆だって、はしりの頃のやわらかい小さいものは、生でいただくとほんとにおいしいですし。

前田:確かにそうですね。
野村:素晴らしい食材に出会ったときに「これをどうしよう。どうやっておいしく自分らしくしようか」と思うようになってから、いろいろな食材が気になりはじめて。「おいしさって何だろう?」という思考がますます“素材という原点”に近づいていく。で、それを他の人にパスする料理人、つまり媒介者になると、自分の引き出しをうまく使って、傷みかけていれば、そこは技術でおいしくパスする。どちらかといえば、出自の知れない「あなたどなたですか?」っていうようなお野菜よりは、生産者の顔が見えて、主張しまくるお野菜のほうが、エネルギーも全然違うし、安心感もあるし。「わー、あの人のエネルギーを食べられるんだ」って思えるものは同じレタスでも、きゅうりでも違うと思います。
酒井:レタスっていうと、レタスという存在でひとくくりにしちゃいそうですけど。
野村:全然違うんです。グループ分けにしたら、たぶん違う惑星産、というぐらい違うんですけれどね。。
前田:確かに、普通に食べているのは「これはレタスだ」って思って食べるからレタスの味がしてる気になってるけど、たまに意欲的な生産者の畑のレタスを食べると「レタスってこんな味だったのか!」って思いますよね。
野村:そうですね。今、「eatrip soil」という食材屋さんをやっていますが、味の違いは子どものほうがよくわかるようで。最初はお母さんに連れられて来た野菜嫌いの子どもが、食べられるものが増えたり、逆に子どもに連れられてくる親御さんも増えたりとか、みかん嫌いの子どもがみかんが好きになったり。見かけは一緒なんだけれども、それこそ、言葉にできないようなエネルギーがいい食材にはあるのかなと思います。
酒井:そういうエネルギーを人は敏感に受け取ることができる……。
野村:みんな受け取ることができると思う。おいしいときは「わっ!」と感じて、「おいしい!」って言葉にしちゃうし、エネルギーのある素材に出会うと、「はあ~~」という感動や発見があるのだと思います。
身体が元気になると思考も元気になり、思考が元気な人が増えれば社会も良くなる
酒井:ご自身が畑で野菜を育てるときって、どういうお気持ちなんですか? 先ほどお料理するときは媒介者って言葉が出てきたんですけど、生産者としての思いは?
野村:まだ、生産者って言えるほどやっていなくて。父が15年ぐらいやっている畑をタイミングをみては手伝いに行ってるだけなんです。それでもやっぱり土を触るとか、草の匂いを嗅ぐとか、大げさに言えば少しだけ自然と一体化できるような感覚で畑をやると、まずおなかがすくし、いい汗もかくし。やっぱり空腹は最高の調味料になるんですよね。畑をやることで、なんでもおいしくいただけるようになったのがいちばんの発見です。土や水などの自然環境が食材を育むように、自分の体の中も、多様な腸内細菌などの微生物がたくさんいる環境にすることがすごく大事だと思う。良い微生物がたくさんいると健康になって、元気が出て、すると思考も元気になる。そうした人が増えれば、たぶん社会も良くなる。
酒井:“元気”って大事な言葉ですよね。
野村:元気って字の通り、その人が元々持っている「気」ですよね。元気があると、思考がとてもポジティブになる。「わーっ」と騒ぐようなパワーが出るのではなく、前向きに、おおらかになるというか。
酒井:ウェルビーイング研究の第一人者の石川善樹さんが「元気」ということに言及されていて、人にもともとある「気」をどう呼び覚ますかが大事で、体が元気になると思考も良くなるという話をされていました。
野村:子どもは大きな声で喋って、笑って、走って元気っていう、いわゆるみんながイメージする元気の塊ですよね。でも、大人はどんな状態が元気なのか、なかなか難しいですよね。病気をしていなければ元気とも言えるけど、それだけでもない。本当の元気って忘れている人も多いと思う。思わず走り出したり、芝生に寝転んだりして「私、今、元気かも!」という沸いてくる感覚と、「元気ですか?」と聞かれて「元気です」と答える感覚は、ちょっと種類が違うと思う。
前田:元気じゃないときにかぎって「うん、元気」って言ったりすることも(笑)。
野村:やりたいことをやって夢中になっているとき、体全体を使って満たされたと感じるとき、おいしいものを食べてうれしいとき、元気って言えますよね。心と体はつながっているし、つながりやすくすることは大事だと思うんです。
酒井:つながりやすくする。それで思考も元気になってくると社会も良くなるというのは、飛躍じゃなく、本当に自然なことですね。
野村:元気な人たちが話し合えば、お互いの会話もシンプルになるし、とってもストレスがない。たぶん、言いたいことも言うし、「それもそうか」と受け入れもするし、体を動かすし。そうすると、ちゃんと発散もできるし。で、おなかすかせて、おいしいごはんを食べれば「じゃあ、まあいいか」って。

「3世代100年」で考える
野村:先ほど父の畑のことを言いましたが、このコロナ禍になって、“畑ミーティング”が盛況なんです。屋外だから密でもないし。いろんな人が手伝いに来てくれます。父は今80歳ですが、その父の先輩、という方がいらしたりと、様々な年代の多彩なジャンルの方が自然に集まるんです。たとえば映画監督をめざす人、役者さんやミュージシャン、そして「これからの医者は病気を治すだけじゃなく、心も健康にしなきゃいけない。病院は健康になるところだ」というお医者さん、それに共鳴する医学生。そこに今度、小さい子たちが入ってくる。普通の仕事や遊びでは絶対に成り立たない人同士の関係なんだけど、それぞれの役割をそれぞれがやっている。これってひとつの理想だなっていうカタチを畑の上で見ることができているんです。。
前田:新しい村の成り立ちみたいな。
野村:そうですね。いろんな世代が一緒になることって、なかなか自然にはないんですけど、それが畑だとできるんです。今、人生100年時代と言われますが、社会人としてがっちり稼働する年代って、30~60代の30~40年くらいじゃないですか。そのなかで、世代間のバトン引き継ぎは絶対必要ですよね。人生100年というのは、3世代で100年と捉えるべきだと思うんです。各世代が得たものを、次の世代、次の次の世代へと授けていく。3世代で初めて伝わるものって多いと感じてます。たとえば、きかん坊の小学生が、親には反抗期なのに、おじいちゃんがボソッと言ったことには素直に共感できたり。
前田:なるほど。人間の活動できる時間を合わせて、3世代100年なんですね。
野村:そうですね。今、自分の位置が3世代100年の真ん中だとすると、バトンは前世代と次世代につながっているから、私が同じ場所に両世代を引き合わせる役になるんです。それが、自然に伝わっていく瞬間が見える。
前田:いいですねえ。
野村:だから、モノでも「これ、誰かにあげたくなるかな」という視点で選びます。今は自分のところにいるけれど、次、誰かのところに行ってもらいたくなるようなモノだと無駄にならないし。料理もそうですね、食べたら残らないものだけど、受け継いで、渡す。
前田:家族の味とか。
野村:そうです。だから家族の味を世代と世代でつなぐには、親子だと関係が近すぎてなかなかうまくいかないことが多いけど、母と孫とか、ワンクッション置くとうまく継承できることも多いので。あと、肉親より他人との関係で、それがうまくできることも多いですよね。関係性や年代の距離感をうまく使いながら、伝えたいものを残していく、受け継いでいくことがとてもおもしろい、と思います。

100年後に「前の世代はいいことをした」といわれる選択を
野村:私、今ここで戦争になったらと、しょっちゅう考えるんです。70~80年前は表参道も焼け野原になった。忘れてはいけない、でも、つないでいかないと忘れてしまう。さっきの3世代の話と同じく、上の世代から下の世代へ、言葉で直につないでいくことは大切だと思いますね。
酒井:人生100年時代についてアンケートを取ったら「前向きになれない」「どうしよう」という戸惑いが多かったんですが、3世代で100年という単位で考えると、すごく気持ちが軽くなりますね。自分だけで100年を引き受けるのではなく、地球や社会から一定期間預かったものを、誰かに手渡していく。ちょっとワクワクします。
野村:これからは地球も社会も軌道修正モードに入って、100年後は「前の世代はいいことをした」って言われることを選択していけばいいんじゃないでしょうか。自分では見られないけど。
前田:「いいことした」って言われるようにしなくては。
野村:東京の明治神宮の森。あれも100年なんですよね。100年がかりで計画されて、木が植えられ、森がつくられた。同じように、今から木を植えておけば、次の世代に引き継げる。そう考えると、やれることはいっぱいあります。
酒井:あの森の環境、生態系を見ると、100年という時間の重みや可能性のすごさを感じますね
野村:コウノトリも来るし、ほんとに明治神宮の森や皇居の緑がなければ、東京の生態系って変わっていたと思います。
美しく枯れて土に還る
前田:さっき微生物のお話がありましたけど、すごく興味があります。
野村:野菜もたくさん微生物がいる土のほうが、外からちょっとお行儀の悪い菌が来ても入る余地がなかったり、撃退できるから、強い。微生物の少ない土は、負けちゃうんです。いろいろな種類の菌がたくさんいることで抵抗力がついたりするので、完全に「悪い」「善い」菌というのはたぶんなくて。それと同じで体内にもいろいろな菌が存在することが大事なのかと。
酒井:体の中に菌のダイバーシティみたいな。
野村:そうなんです。無菌なんて絶対無理だから。消毒したら、いい菌もいなくなっちゃうんで。土づくりと同じように、体の中にたくさんの種類の菌を常に蓄えておくことが大切なのかと。
前田:いい土で育ったものを食べる機会を多く持つことが重要なんですね。
野村:うちにはいっぱい野菜のミイラがいるんです(笑)。いい菌がいる野菜は、ものすごく小さくなっても、水分が抜けてミイラになるだけで絶対に腐らない。あまりにきれいなので、取っておくんです。でも、トロトロに溶けてカビてしまう野菜もある。私が野菜なら、どうせならミイラになりたいなと。一生懸命いい菌がいる野菜を食べたら、なれるかなと(笑)
前田:おばあちゃんになったときに。
野村:はい。美しく枯れていったらいいなあと思うし、土に還ってもまったく違和感ないですよね。
前田:還るところ、循環っていったらそこですね。
野村:コンクリートじゃダメなんですね。

酒井:土に触れることも大事?
野村:大事。いつかはたぶん、そこに入る。でも、いっぱい目に見えない生き物もいるから、コンクリートの上よりはほんとに気持ちいいですね。
酒井:お父様の畑にたくさんの人が集まってくるのがわかります。
野村:畑にいるときって、全員が何者にもならなくていい。今、この瞬間をどうするかということだけ考えて、ただ働いて、食べて、っていう時間なんです。
前田:先ほども酒井さんの話に出た石川善樹さんから「何かになる」ことで認められるより、「いる」というだけで認めあえる関係が気持ちいい、とうかがって、今、偶然野村さんもおっしゃったんで「なるほど」と思って。
野村:そんな瞬間があるのは、とても生きている感じがします。
前田:いきいき、できますね。
酒井:いきいき生きるって深いですね。

以下、野村さんがみなさんのご質問にお答えします。
Q:「おいしいって何だろう?」って考える機会を、どうやったら持てますか?
野村:「とりあえず」っていう食べ方を一つ我慢する、その時本当に食べたいものを食べるっていうのはありかもしれないですね。
前田:なるほど。食べたいものを食べているつもりでも、実は「とりあえずおなかが空いたからこれでも食べておくか」っていうことが多いような気がします。「とりあえず」をやめてみるのはいいヒントですね。他にも何かありますか?
野村:汁物はなかなか外食ではいただけないので、まず、温かいお味噌汁でもいいですし、なければインスタントでもいいんですけど、汁物をひと口飲んで落ち着かせると、素直な体の反応、要望が出てくるときはあるのかなって思います。
前田:お味噌汁ってすごいですよね。
野村:母も割と「家庭料理は必ず汁物」って言うんです。まず心を緩める作用があるので、私も汁物は欠かさないようにしています。
Q:料理が苦にならないとのこと、うらやましいです。私のように面倒くさがりで料理に苦手意識がある人が料理を楽しめるようになるには、どうしたらいいのかアドバイスをください。
野村:解決策のひとつは、うんとおいしい素材じゃないですか。ピーマンだって生で食べたほうがおいしいものとかあるんですよね。お豆腐もほんとに素晴らしいお豆腐があって、みんな感動する。普通のお豆腐より100円くらい高くても、いい素材を選ぶと、どう使おうかいろいろ考えたりして、料理も楽しくなる。せっかくいいお豆腐なら、いつもお醤油だったところを塩で食べてみようか、塩もちょっといいものにしようか、とか。少し、いいオリーブオイルを垂らしてみようとか、自然に愉しさが生まれると思うのです。
酒井:おいしい食材に出合うと料理はしなくていいんですか?
野村:料理しなくてもいい食材というのはいっぱいあります。たとえばオクラも、いいものは生がすごくおいしくてびっくりするはずです。調味料も、少し使うだけで十分美味しいですよ。
Q:いい食材は、どこで手に入れればいいでしょうか?
野村:いい質問ですね(笑)。どこに住んでいらっしゃるかにもよりますが、なるべく流通を通っていない食材を扱っているお店が近くにあれば、そうしたところで。もしくは専門店ですね。鶏だったら鶏専門店へ行くと、潰したての鶏が手に入ったり、ひき肉も冷凍のものとは味がまったく違います。いいお店が見つかれば楽しいと思います。
酒井:自分の住んでいる地域を知るところからはじめるといいかもしれないですね。
野村:そうですね。あと、港とか市場とかで、なるべくパック詰めではない状態のものを買うのもいいと思います。
酒井:今日は改めて「食べること」や食材について考えるきっかけになるキーワードをたくさんいただきました。本当にありがとうございます。
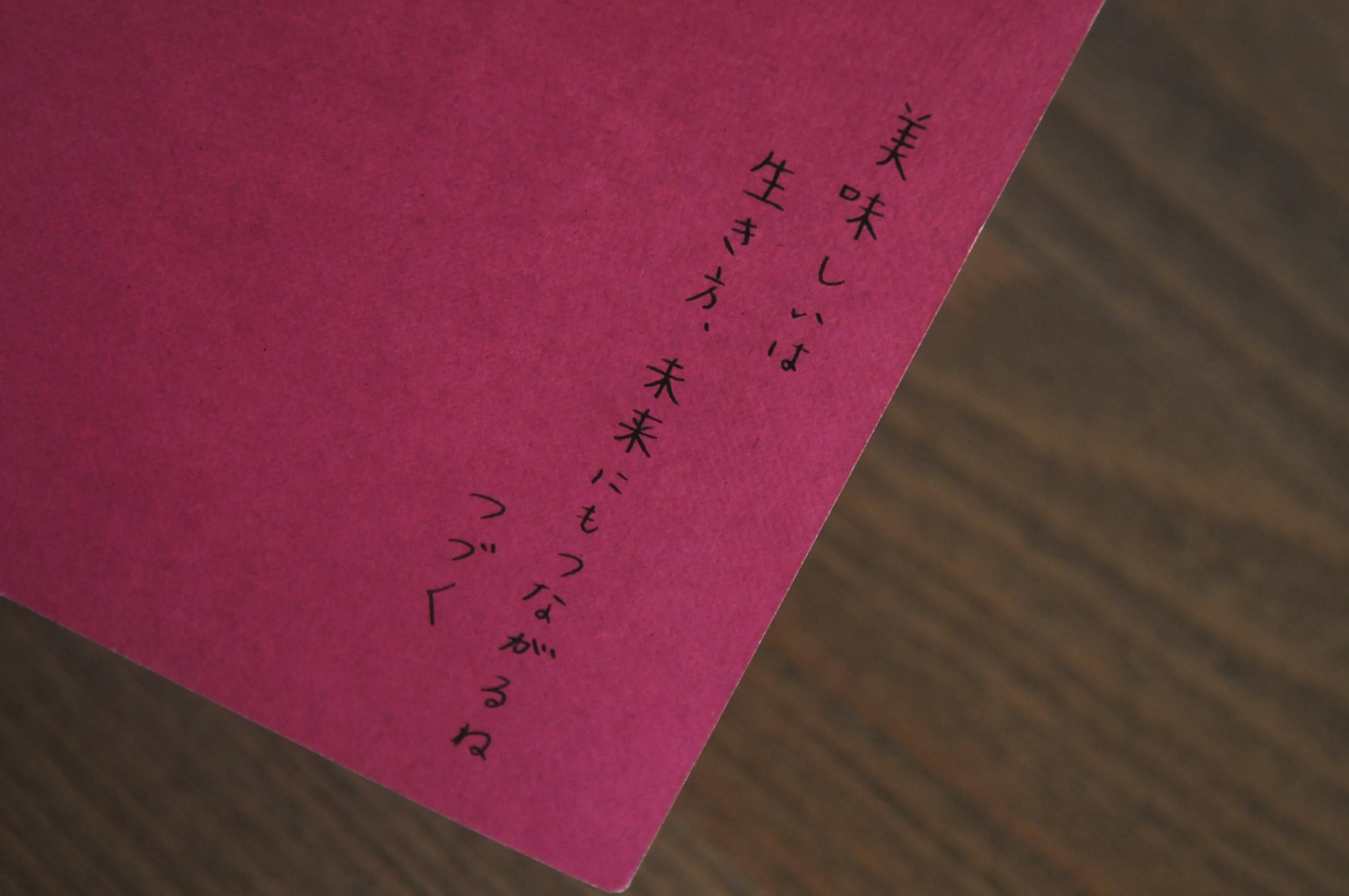
野村友里(のむら・ゆり)さん
フードディレクターとして、ケータリングフードの演出、料理教室、雑誌の連載、ラジオ番組などを担当し、2009年には初の監督作品『eatrip』が公開される。2012年、東京・原宿に一軒家の「restaurant eatrip」をオープン、2019年には表参道にグロッサリーショップ「eatrip soil」をオープンする。著書に『eatlip gift』『春夏秋冬 おいしい手帖』(マガジンハウス)、『Tokyo Eatrip』(講談社)など。「人生は食べる旅」という想いに共鳴する仲間たちと、食の活動 “eatrip” を続けている。