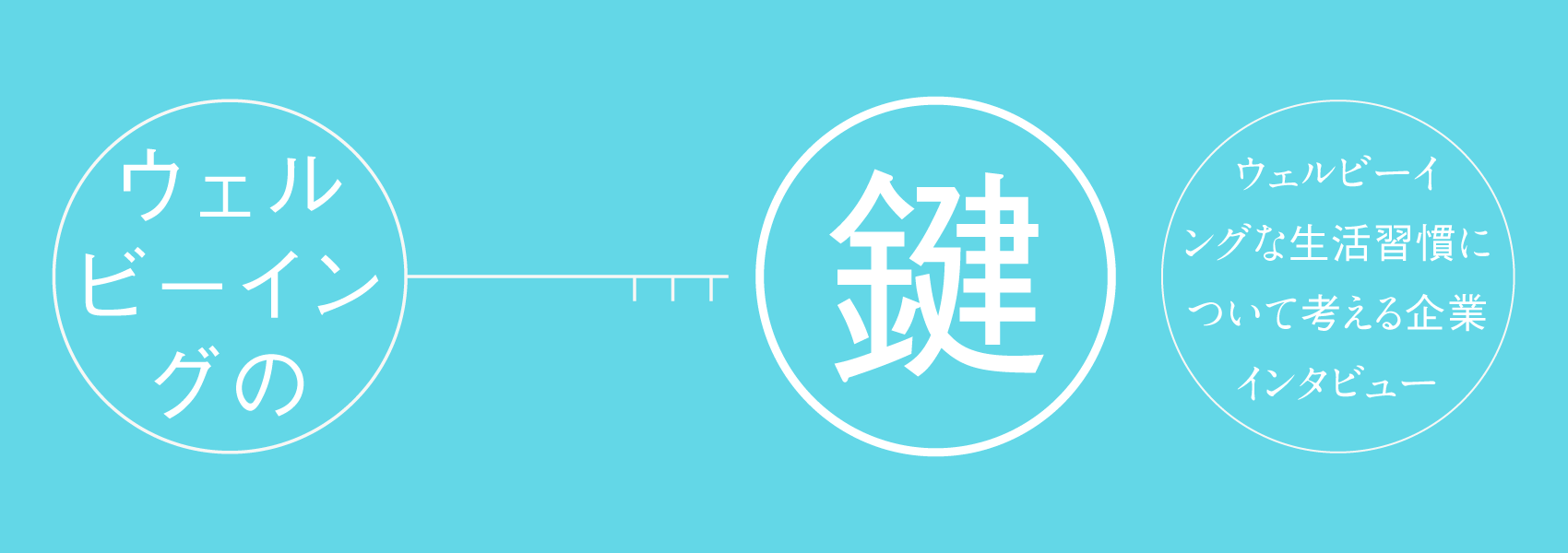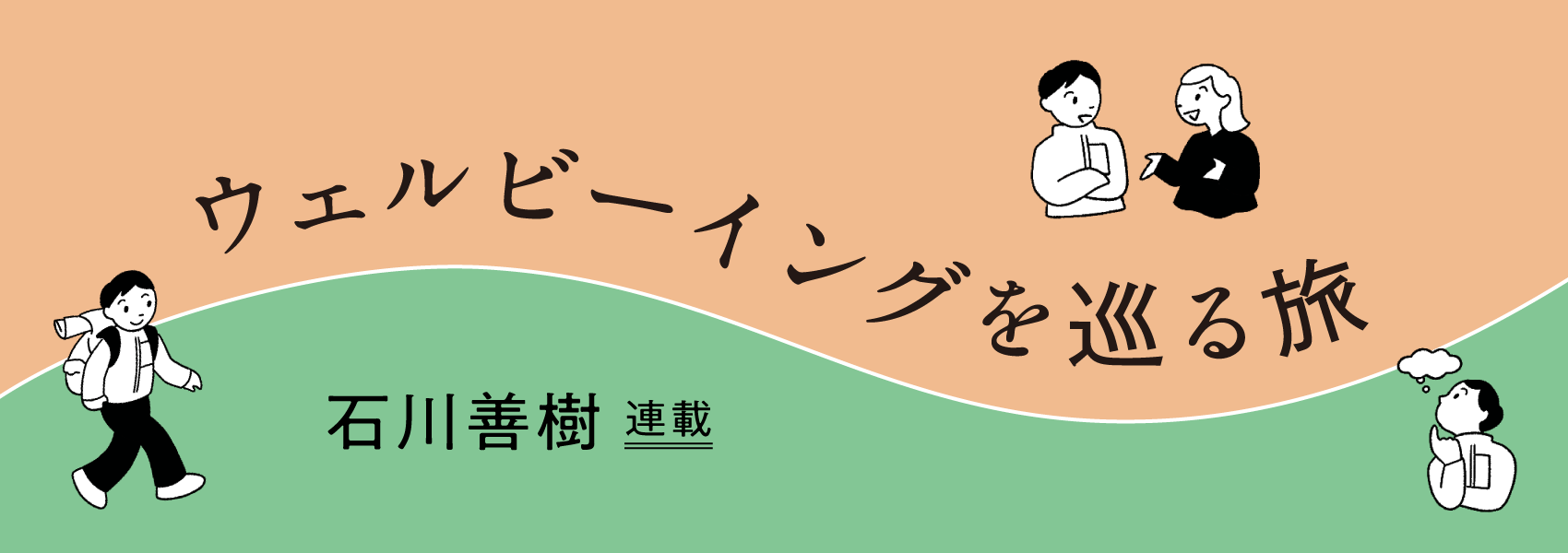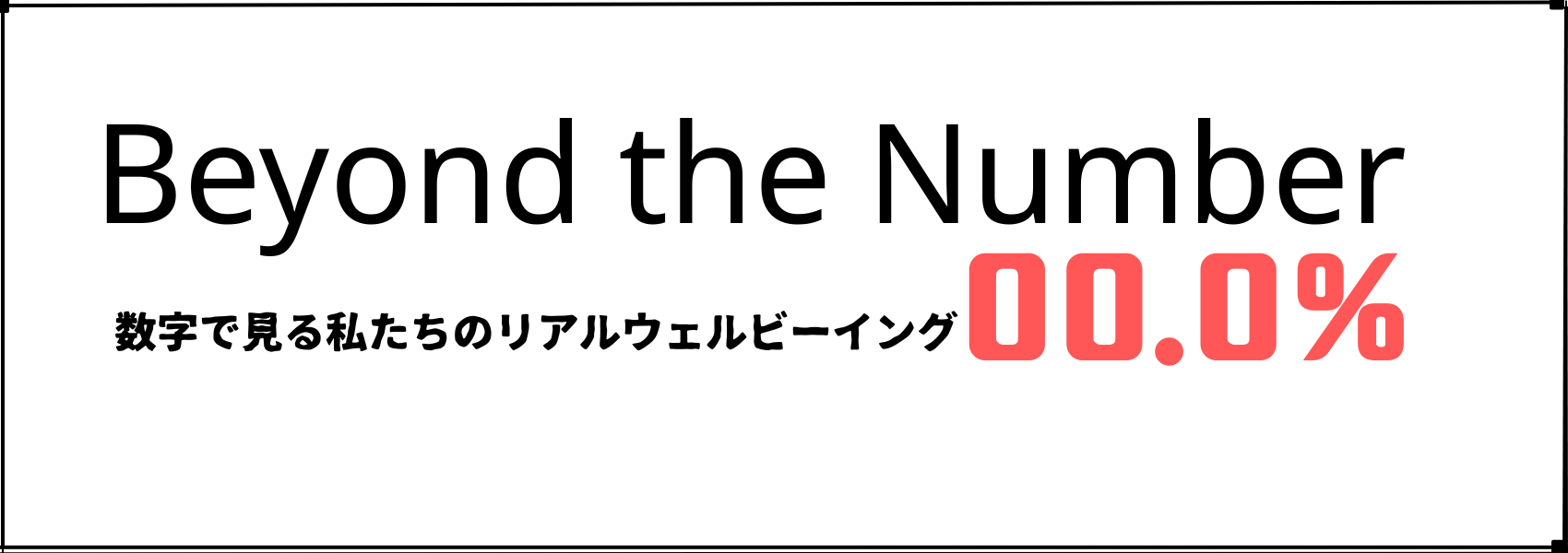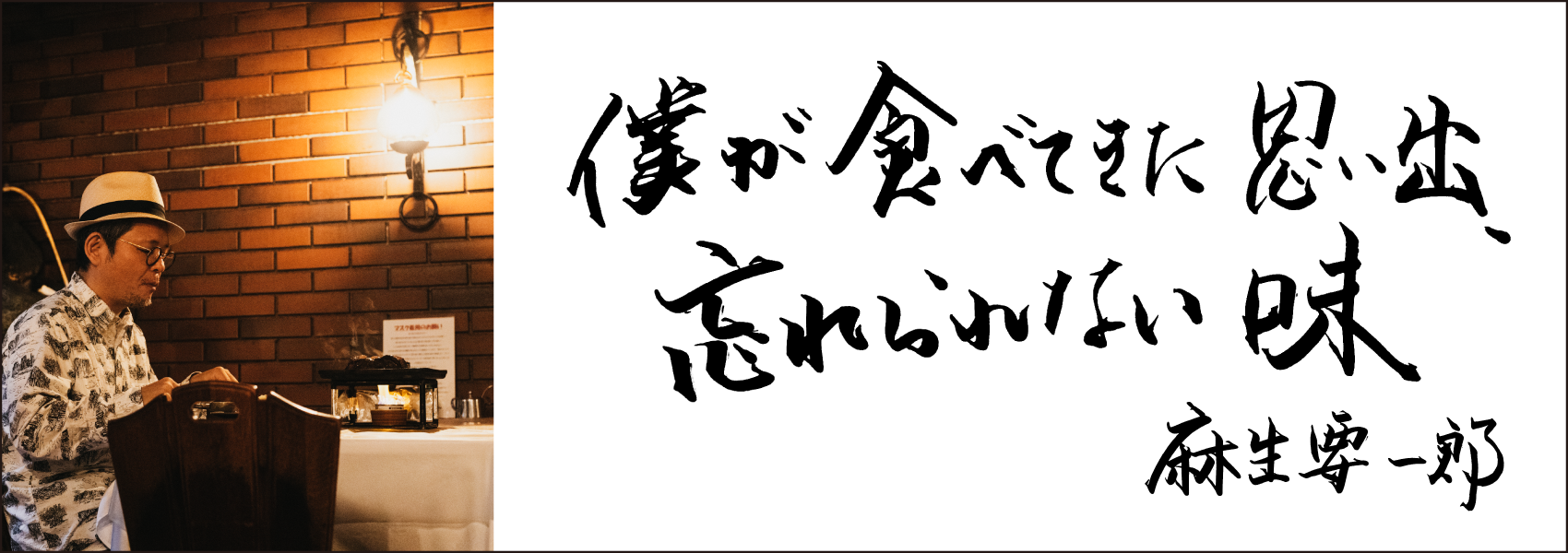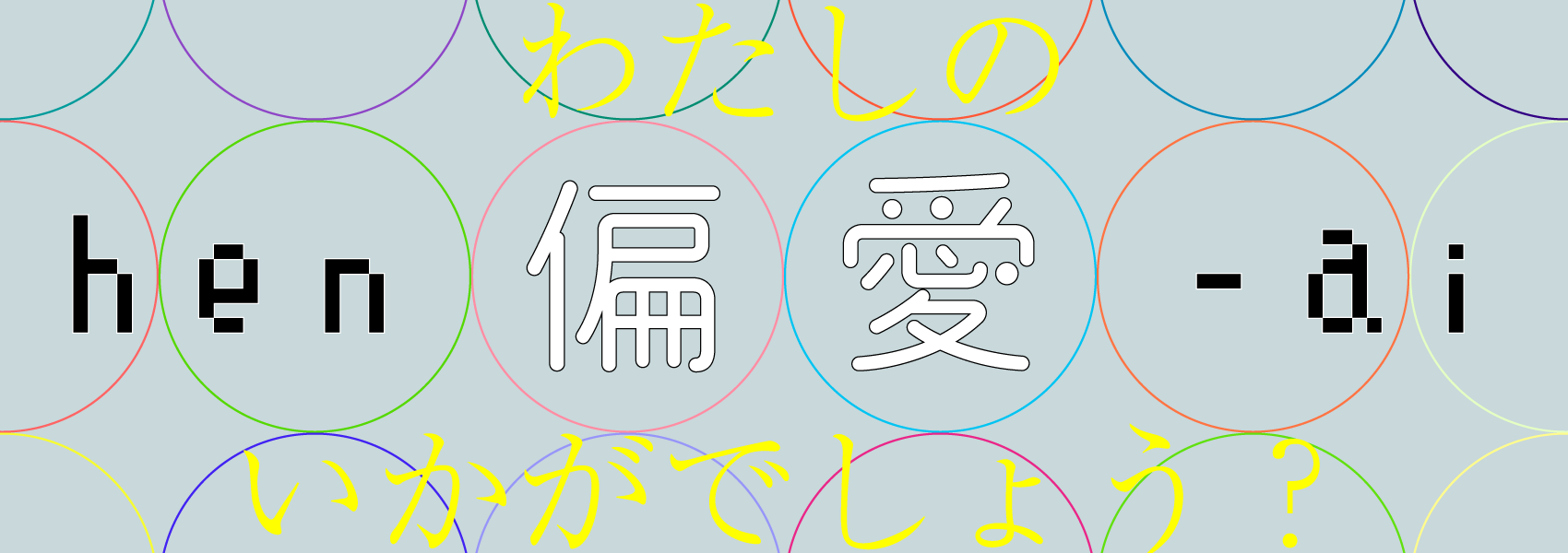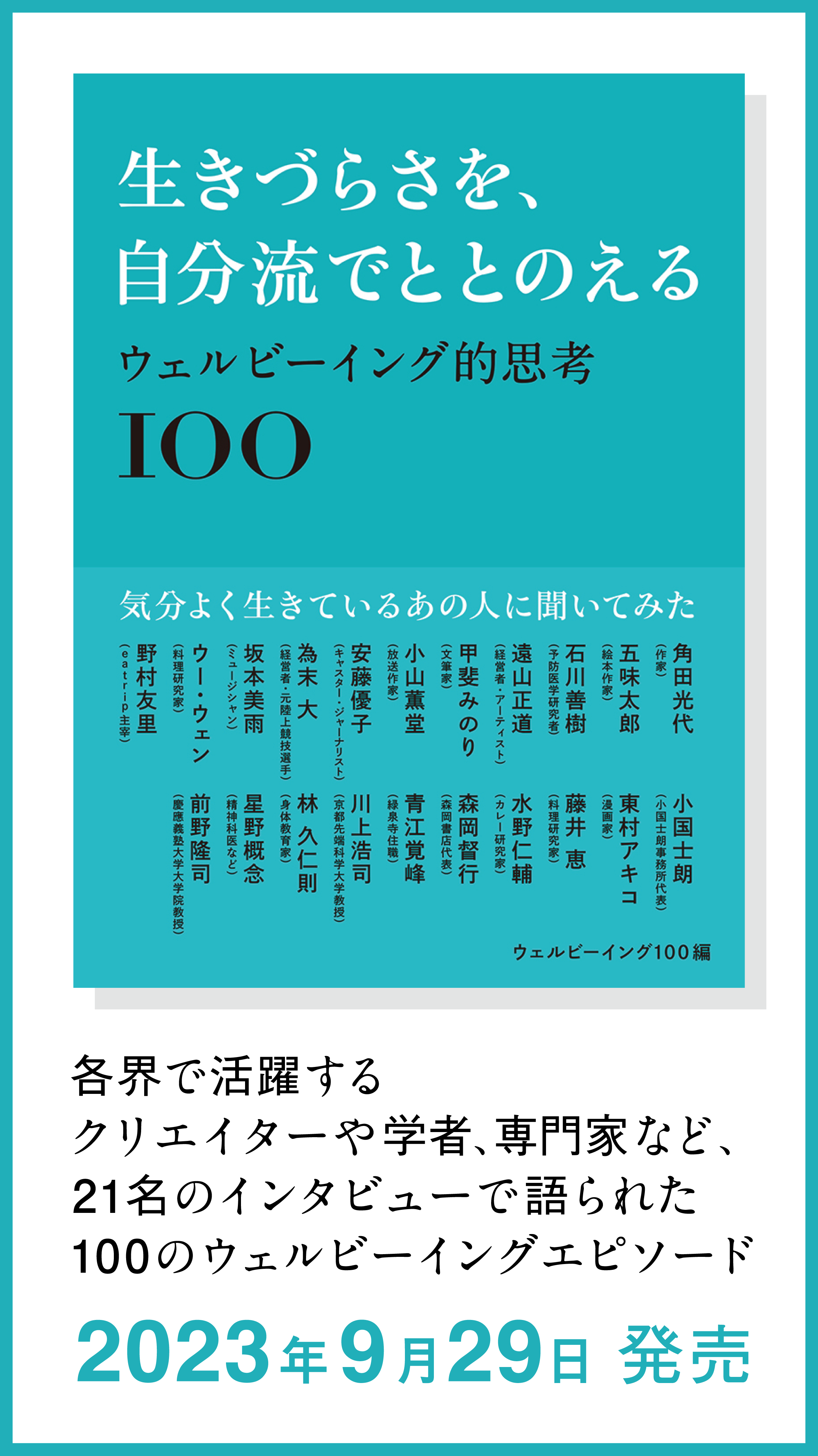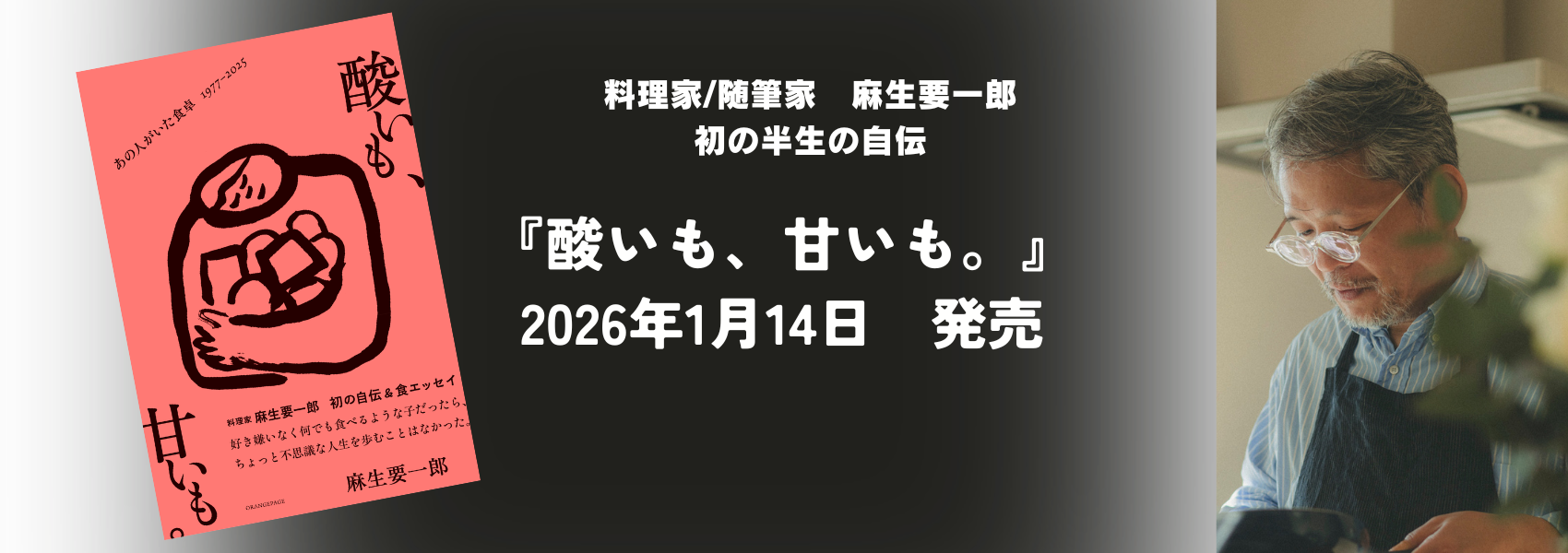食生活はこころとからだを満たして、気分よく歳を重ねるための重要なカギ。
「料理をつくること」は、日々の暮らしの豊かさと深くつながっています。
今回、ご登場いただいたのは、料理とグラフィックデザインのユニット、
オカズデザイン代表の吉岡秀治、吉岡知子夫妻。
映画「食堂かたつむり」やN H K連続テレビ小説「ちむどんどん」等の映像の料理監修・制作や、各種レシピ制作、器の開発などを手がけ、
東京都杉並区で器と料理の店「カモシカ」を営んでいます。
「時間がおいしくしてくれるもの」をテーマに活動されているお二人に、
映像の仕事に至った経緯や、料理との向き合い方について、語っていただきました。
お話をうかがった人/料理ユニット:オカズデザイン 吉岡秀治さん 吉岡知子さん
聞き手/ウェルビーイング100byオレンジページ編集長:前田洋子
撮影/原 幹和
文/岩原和子

「吉岡ズ」から始まる物語
前田 まず、オカズデザインさん、というより吉岡知子さんが料理を始めたきっかけは何だったんでしょうか?
知子「結婚したのが2001年で、当時、秀治は駆け出しのグラフィックデザイナー、私は日本茶の専門店で働いていたんですけど、二人いっぺんにお互いがやりたいことをやるのは難しいなと思って、結婚を機に私はいったん職を辞めたんです。だけど、いずれは戻るつもりでした。食の仕事に就くことを自分の中では疑問に思わず、食に一生関わっていきたいと考えていたので。それはやはり、両親が食を大切にしていて、食いしん坊で。まぁ、一族が皆そうだったんですけど、そういう土壌があったからじゃないかなと思いますね」
前田 じゃあ、知子さんは子どもの頃から、お料理をされていたんですか。
知子「母がすごく料理上手で。ただ具体的に教わった経験は少ないんです。もちろん手伝ってはいましたけど、母は結構完璧主義の人で、ちょっとでも間違えたら鬼のように怒る(笑)。それと同時に、自分で考えてやりなさい、とよく言っていました。手取り足取り教わることはなかったです」
前田 それ、すごいですね。普通のお母さんはそこまで厳しくないと思いますが……。
知子「そうですね。その、考えろって言われたことの意味が、今ならすごくわかりますけど、当時は全然わかんなくて、教えてくれればいいのになって思いながらやっていました」
前田 それで、最初に料理でお金を稼いだのは?
知子「結婚当時コーポラティブハウスに住んでいたんですが、15世帯ほどの中で私達が一番若くて、他はプラス10歳くらい。モノをつくっている方が多くて、インテリアデザイナーだったり造園家だったり。で、コーポラティブハウスは建てる段階から集まって相談するので、ファミリー感が出てくると言いますか、仲よくなって毎週毎週、宴があったんです。その席で、週に1回でもごはんをつくってもらえたら嬉しいなと言われて」
秀治「何か新しいことを始めたり、小さいお子さんの子育てだったりで、ちょっと手が回らない世帯があったんですね。そこに料理を持っていくのが初めての仕事でした」
前田 それは、宴会で知子さんが出した料理がおいしかったからってことですよね。
知子「うーん、どうでしょうか……。料理がすごく楽しそうだったんだと思います。ずっと食べ物の話をしているとか」
秀治「昔からこのひとの親戚は、食べながら食べ物の話しかしないんです(笑)。何を食べたとか、あそこの店には行ったのかとか。うちのほうは食に対してそんなに思い入れがなかったので、最初はすごいカルチャーショックだったんですけど、今ではだいぶなじみました」

前田 なかなかいそうでいないですものね、そういう人って。だから周りの人も、これはいいわって思ったんでしょうね。それで、それを続けて……。
秀治「何回か続けている間に、同じコーポラティブハウスにいらしたインディーズレーベルの社長さんから、今度イベントがあるんだけど料理をやらないかっていう話をいただいて。そのへんからケータリングみたいな形態を試して」
前田 最初はやはり、自分の料理でお金をいただくということに緊張しましたか。
知子「ものすごくプレッシャーがありました。今思うと安いんですけど、それでもお金をもらうのはプロだと思いますし、皆さん、厳しくてですね。メニューをつけてお届けするんですけど、例えば『特製コロッケ』だと、これは何がどう特製なのって」
秀治「デザイナーですからね。人と対峙して仕事をされていた方々なんで、そういうことに厳しいんですよ」
知子「特製って言葉にあんまり意味がないんだったら、単にコロッケのほうがいいよとか、そういう言葉の使い方、カタカナなのかひらがななのか漢字なのか、というのも含めて教わって。もちろん味についても、あれがどうだったとか。とにかくすごい緊張感がありました」
前田 デザイナーは、いろんなところで細かく厳しい判断をしないといけないでしょうから、つい、そういう教育も(笑)。とにかく鍛えられたわけですね。で、オカズデザインっていう名前はどこから?
知子「グラフィックデザインをしていたときからの名前なんですけど、単純に言ってしまうと、吉岡二人で吉岡ズ、そのデザインだから吉岡ズデザインで、それがオカズデザインに」
秀治「ただそれはあとづけなんですよ。コーポラティブハウスで『吉岡ズ』って呼ばれていたんですけど、ちっちゃい子どもがそう言えなくて、『今日オカズ来るの?』って言ったっていうのを聞いて、ちょっとおもしろかったんで、それを採用してしまったという」
知子「ちょうど屋号を考えていた時期だったんで、いいね、オカズデザインって、ってなったんですけど、あとあと考えると、本当に名前がこの仕事を連れてきてくれたような」

原作者小川糸さんとの出会いがもたらした「食堂かたつむり」撮影現場の仕事。
前田 すごいですね! 何か、その子は天使みたいな(笑)。それで、そのコーポラティブハウスで鍛えられて、そこからどういうきっかけで映像のお仕事に?
知子「それはですね、またそのコーポラティブハウスでの話なんですけど、敷地内に皆が使える共有スペースの古民家があって、そこでイベントなんかもしていて、あるとき小説家の小川糸さんが来られたんです。彼女のブログは前から読んでいたんですけど、向こうも私達のブログを何かのきっかけで読んでくれていて、声をかけられて、あっという間に仲良くなって。一緒にごはんを食べたり、そういうお付き合いが今も続いているんですけど。
それで、小川さんの大ベストセラーの『食堂かたつむり』が映画化されるときに、お声がかかったんです。その小説の主人公のつくる料理が、オカズデザインさんの料理のイメージに近いらしいんですって、映画の人が言ってきて。でもそれはレシピを考えるなり、監修をってことだったんだと思いますけど、同じレシピでもつくる人によって味が違ってくる。レシピを提供したとしても、つくる人のカラーが濃くなると私は考えています。なので、もし関わるんだったら料理制作までやらせてほしいってお願いしちゃったんですね」
秀治「映像のこと何も知らないから、言っちゃって(笑)」
知子「そう、言っちゃって。どんなに大変か全然わかってなかったんで、言ってしまったんです。それがきっかけでしたね。映像の仕事はすべてそこから」
前田 映像の現場で、いわゆる“消えモノ”っていう仕事ですよね。で、どうでした、最初は?
知子「いや、もう、本当にしんどかったです。もう二度とやらないって思いました(笑)。初めての業界で勝手がわからない上に、物量も多くて。また、刺身に色を塗るようなことを平気でやるんですよ。料理の話なのに、業界としては食を大切にしていない。そういう慣習があるように感じました
でも、優秀なフードコーディネーターさんがいっぱいいる中で、私達に声がかかったってことは、うまくやるというよりは、実質的においしいものをつくらないと意味がないと思いました。ハンバーグを実際に現場で肉を叩いてつくったり、コーヒーも焙煎家の方にそのシーンのために調合してもらったブレンドをネルで淹れるとか。それは映らないけど、きっとにじみ出るものがあるんじゃないか。じゃないと私達がやる意味がないっていう、そんな想いでやり抜きました。今思えばつたないですし、現場的にはスムーズにいかなかったと思うので反省もあります」
秀治「あの頃の映像の現場って、今と違って労働環境がひどくて。朝8時から始めて、夜、てっぺん(深夜12時)越えになりそうって途中で言われて、2時くらいまで撮影して。それでまた8時からやるんで5時には現場に入ってないといけない。そういうことが2週間くらい続いて、途中で死ぬかなと思いました(笑)。実際、睡眠不足で何度も事故りそうになりました」
前田 映像の消えモノって、無名の人がやる仕事だったじゃないですか。そういうところで自分の『個』というものをちゃんと出して、私はこれでやっていくんだ、これがオカズデザインなんだってがんばって、そうなさったのが本当にすごいと思います。
知子「主人公が天才料理人の話ですから、自分のできることでそこをやり切るしかない。もっとキャリアを積んだスタイリストさんなら、おいしそうに見える術があったでしょうけれど、私達はただただ、おいしいものをつくることしかできない。ならば、そこは徹底させてほしい、と受けた仕事だったので」
前田 原作者の推薦ですからね。作家の方に、自分の小説の主人公の料理があなたの料理なんだ、と言われたのは、やはり嬉しかったですか。
知子「すごく嬉しかったですね。ただ、小説の中で夢のようにおいしく描かれるじゃないですか。それを形にしないといけないのは、本当に胃が痛いなって思いながらやってました」
前田 でも、その仕事ぶりが認めらて、映像の仕事が広がっていったのですものね。そういう映像の仕事との比較で、普通にレシピを考えて料理するのと、文学作品の中の、いわば架空のものをつくるのは仕事としてずいぶん違うと思うんですが、そこはどんな感じなんですか。
知子「違いますね。やっぱり、その主人公だったらどうするかっていうところに軸を置くので。架空ではありますが、私はこうしないけど、この子だったらこうするかなって。手間のかけ方とか食材の選び方とかを膨らませて膨らませて、妄想を具現化していく感じですね」
前田 原作には書いてなくても、その主人公のことをきっとこうだろうなと想像して。
知子「そうですね。たとえばパンをつくるんなら、パンの酵母の起こし方もいろいろあるんですけど、あの子だったらこういう感じで起こすかな、こういう小麦粉を使うかな、とか」
前田 そういうアイデアって、ちっちゃい頃から耳に入ってきた家族の食の話とか、自然に体得してきたものが、こうクラウドみたいになっているところからシューっと降りてくるような(笑)。引き出しが多いのってすごいですね、やっぱり。
知子「自分では多いと思わないんでけど……秀治が私にはない引き出しを持ってくれているのはありがたいです。スパイスやハーブの知識があったり、鶏や豚を解体できたり。あと植物にくわしくて、森を歩いていても食べられるものを知っていたりするので……」
秀治「東京の稲城ってところに住んでいたんですけど、当時は今よりずっと田舎で、山で遊ぶことが多かったんですよ。それで植物や動物のことを覚えていって」
前田 領域も違うし、お二人合わせるとすごい引き出しですね。それで、なるべくしてこうなったというか。

時間をおいておいしくなる料理は、人を静めてくれる料理
知子「来たボールを全部打ち返していったらこうなった、っていうのが正直なところです。それは最初、駆け出しのデザイナーだったこともあると思います。来る仕事は断らないという。それからさっきも話に出た、インディーズレーベルの方の音楽イベントがかなり大きくて、いきなり何千食っていう話で。そこで手間のかけ方とか保存をどうするかとか、そのオペレーションですね、そういうのを全部実践で学びました。他の料理家さんより、体力というか叩き上げ感があるのは、そういった経験があるからかも」
前田 何千食ですか!? どうやってやるのか、ちょっと想像がつかないですね。
知子「二人なのでとても手が回らない。そこから保存する、時間をおいておいしくなるっていうことに注目していったんです。今それが私達のコンセプトの大きな一つですけれども」
秀治「最初の頃のうちの主力商品がレモネードで。日本は柑橘の種類が多くて、それをオレンジから黄色、緑ってグラデーションに10色くらいかな、並べて出すというのをやったんです。冷蔵場所が足りないから、冷暗所で保存して提供できるものって考えたときに思いつきました。ビジュアル的にもいいし、料理とデザインが合体した最初の仕事はそれかもしれないです」
前田 その「時間がおいしくする」ということを、ぜひくわしくおうかがいしたいです。時間と料理の関係について。
知子「そうですね。保存などの事情もありながら、自分達がそういった少し時間をおいた料理が好みだっていうのが大きかったと思います。できたての料理は勢いがあるというか、人を心身共にハイにする感じがあると思うんですけど、熟成させたり寝かせたりした料理は、その気配がだいぶ静まって静かな味わいになる。勢いはなくなるけど余韻が長く残り、味がまろやかになっていく。そういった料理が好きなんです。アッパーにするんではなく、静めてくれる料理。そういったものをつくっていきたいなと思うようになって。デザインにおいても派手ではないけど長く残っていく、普遍性を意識してやっていこうと」
前田 すばらしいです。
知子「いえ、そうありたいという(笑)」
秀治「速いペースで料理をガンガン提供するようなことは習ってもいないし、自分達のペースでベストなものを出すには、そういう料理のほうが自分達の意思を出しやすい。駅前で店をされている方達とは全然違う考え方をしなきゃいけないっていうのは、もう最初からわかっていたことなんで」
料理は作る人が何を大切にして、どんなものに心を動かされるかがわかるもの
前田 家庭の主婦でも、きんぴらのつくりたてと一晩おいたのは味が違うってわかると思うんです。冷たいきんぴらを温かいご飯にのせて食べる喜びってありますよね。そういうことに気づいて、それを自分達の仕事の中で完成させたのはとても“かっこいい!”と思います。話は変わりますけど、今、東京と岡山の二拠点生活なんですよね。なぜ岡山に?

知子「水ですね。料理の上で水は重要で、素材を洗うにしても煮込むにしても、ご飯を炊くにしろ、水がすごく影響するというのがわかっていたので、水のいい場所を探したいなとずっと思っていて。あちこち見に行ったりしたんですけど、二人のどちらかがピンとこなかったり、いいと思っても何年も土地が見つからなかったり。
それで探し始めて10年くらいたったときに、たまたま岡山に呼ばれる機会があって、そこで知った場所の水がすばらしくおいしかったんですね。しかも出汁をとったり煮込んだりしたときにものすごくよさを発揮する。それで2、3年通いながら土地を探して、暮らすようになったっていう感じです。岡山ですけど、私たちの住んでいるところはすぐ鳥取で、海もわりと近いし、山のものも手に入るっていうことも大きかったですね」
前田 いいですね。本当に料理と共にある感じだと思うんですけど、料理がお二人にもたらしたものというのは何なのか。料理をやっていて一番よかったことって何でしょう?
秀治「料理って自分達からするとなくてはならないもので、晩ごはんを何にするかって話だけでも、その人のことがわかるじゃないですか。何でもないことですけど、コミュニケーションの一部。食べない人なんていないので、誰とでも話せるツールではあるなと思っていて。そういう意味では、こちらにはいろいろ食の知識があることで、初対面の人と話がしやすいと感じることがあります」
前田 ああ、確かにそうですね。食べることがどうでもいい人もいるかもしれないけど、それでも、おなか空いた? とかから話し始められますものね。
知子「うちのスタッフの面接のときに、必ず一品何かをつくってきてくださいってお願いしているんですね。それは自分にとって一番の料理。一番うまくつくれるということではなくて、繰り返しつくっていたり、自分の中で大切にしているもの。料理じゃなくてコーヒーを淹れるとかでもいいし、何でもいいよってお題を投げるんです。なぜそれをやっているかというと、その人の育ち方とか大切にしたい考えが透けて見えるというか。とくに一緒に仕事をする上では、こういうことがおいしいよねっていうのを共通して思えないと、なかなかやっていくのが難しいんで、それでずっと続けているんですけども。
そのへんじゃないですか、料理というのは何かというのは。その人の価値観が表れるというか、何を大切にして、どんなものに心が動いてというのを、見せてくれるものだと思います」
オカズデザイン
2000年、吉岡秀治・吉岡知子が結成。
“時間がおいしくしてくれるもの”をテーマに、シンプルで普遍的なもの作りを目指す。
書籍や広告のレシピ制作・器の開発・映画やドラマの料理監修などを手がける。
東京都杉並区にて器と料理の店「カモシカ」を月に一度オープン、様々な作家の器の展示会を中心に、食にまつわる企画を開催。https://okaz-design.jp/
著書に『沖縄食堂ごはん』(オレンジページ)、『二菜弁当』(成美堂出版)、『マリネ』(主婦と生活社刊)など。
映像では映画『食堂かたつむり』、NHK朝の連続テレビ小説『てっぱん』『半分、青い。』『ちむどんどん』などに関わる。
※文中敬称略