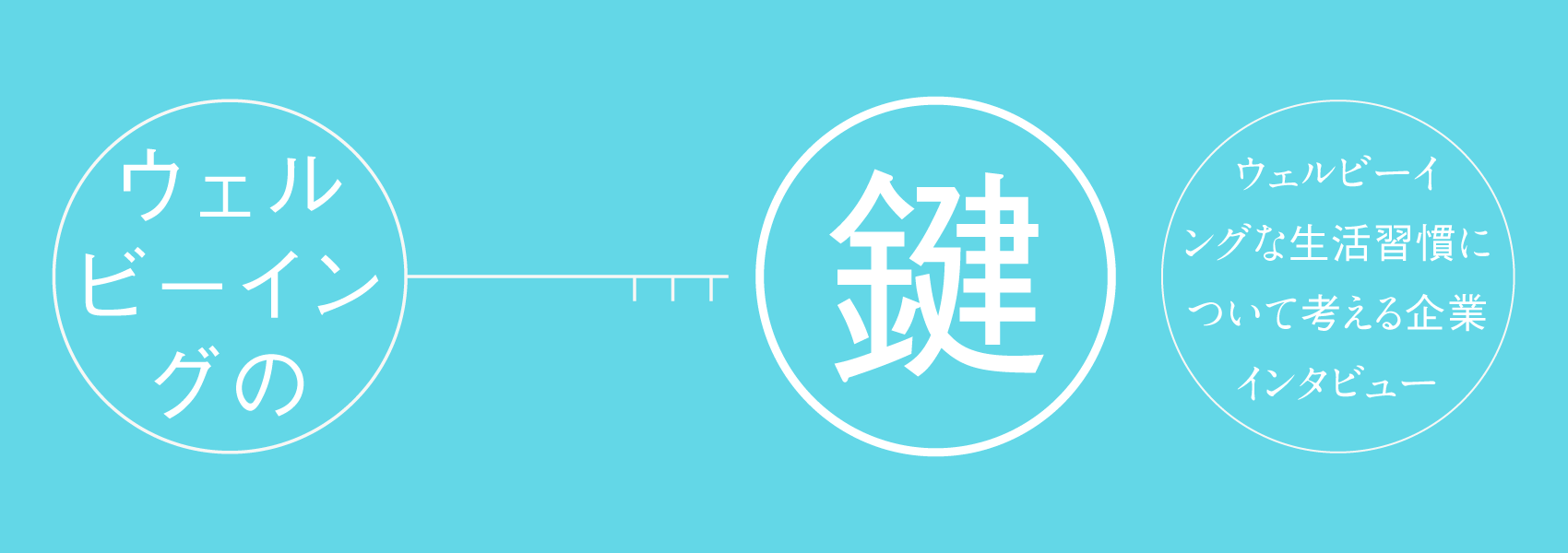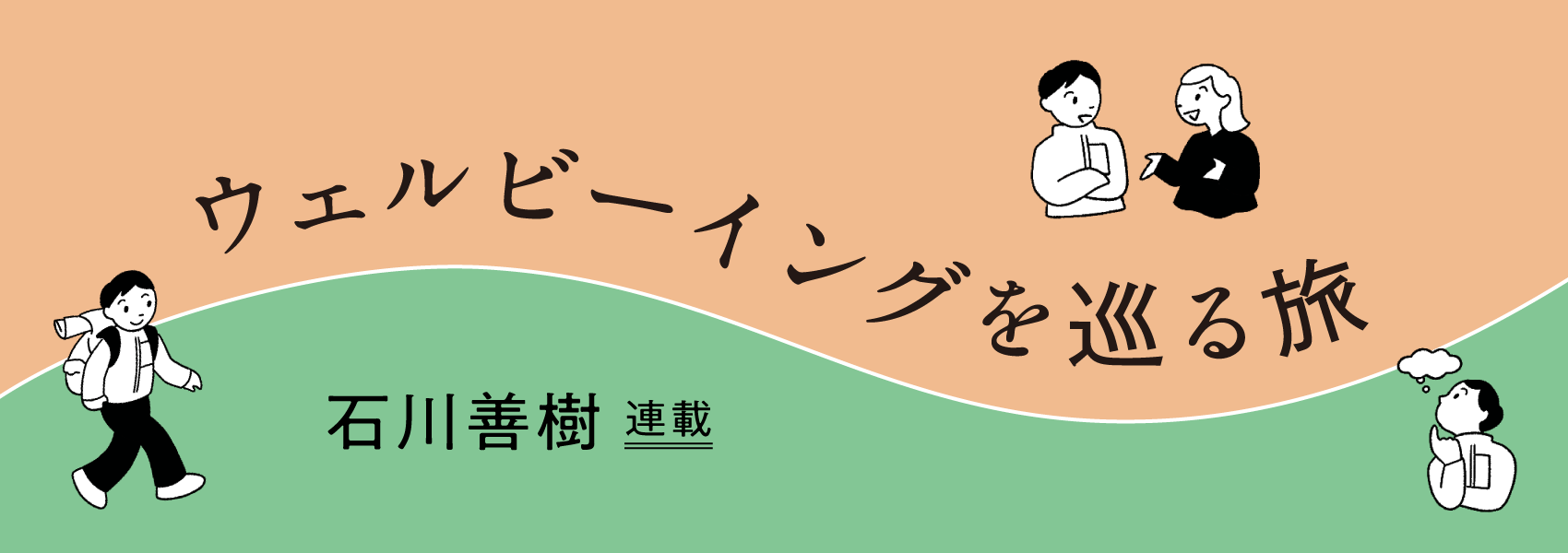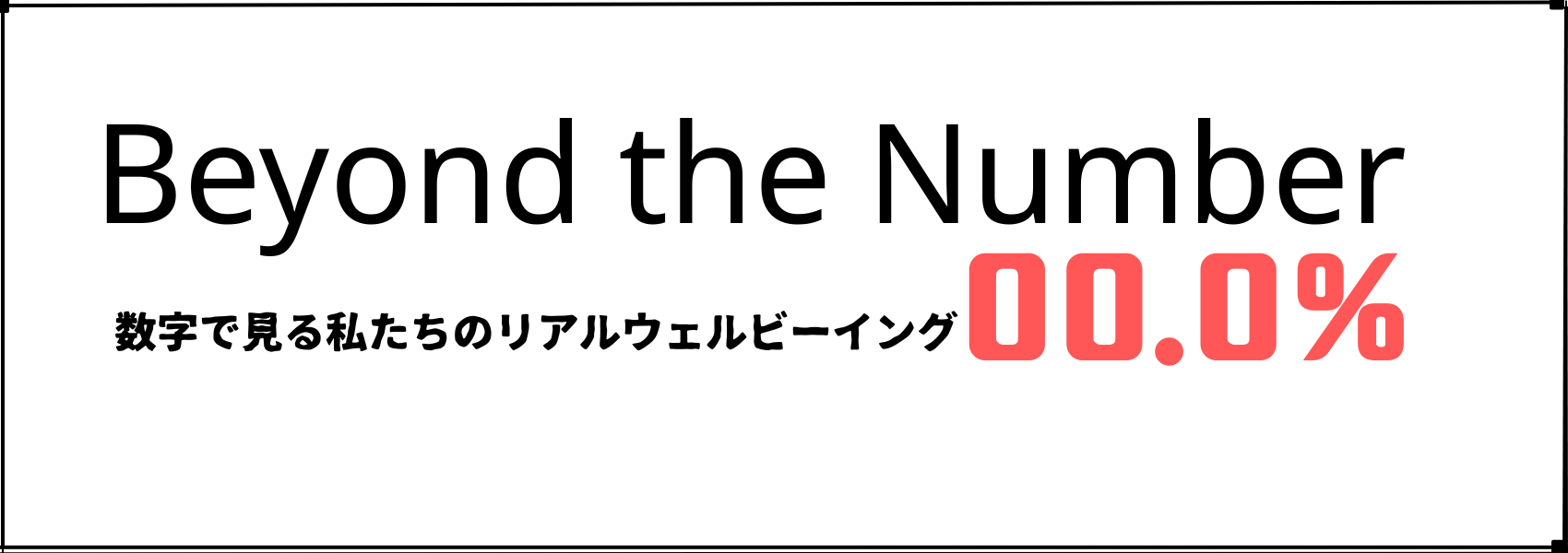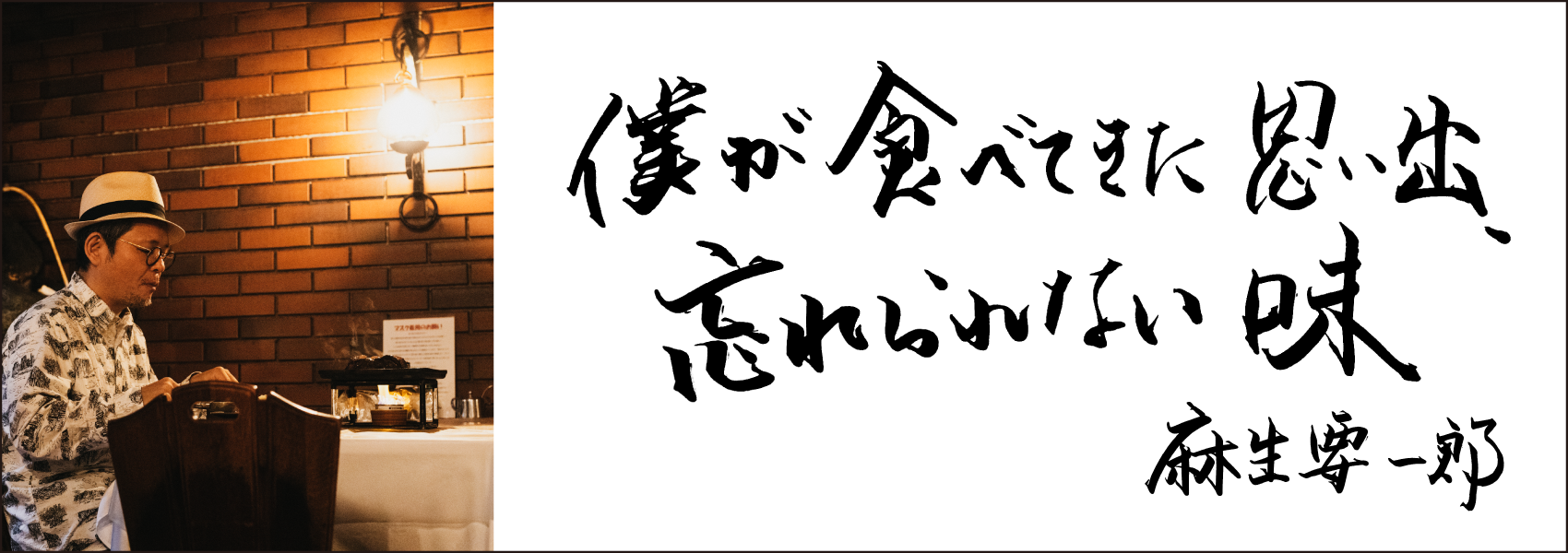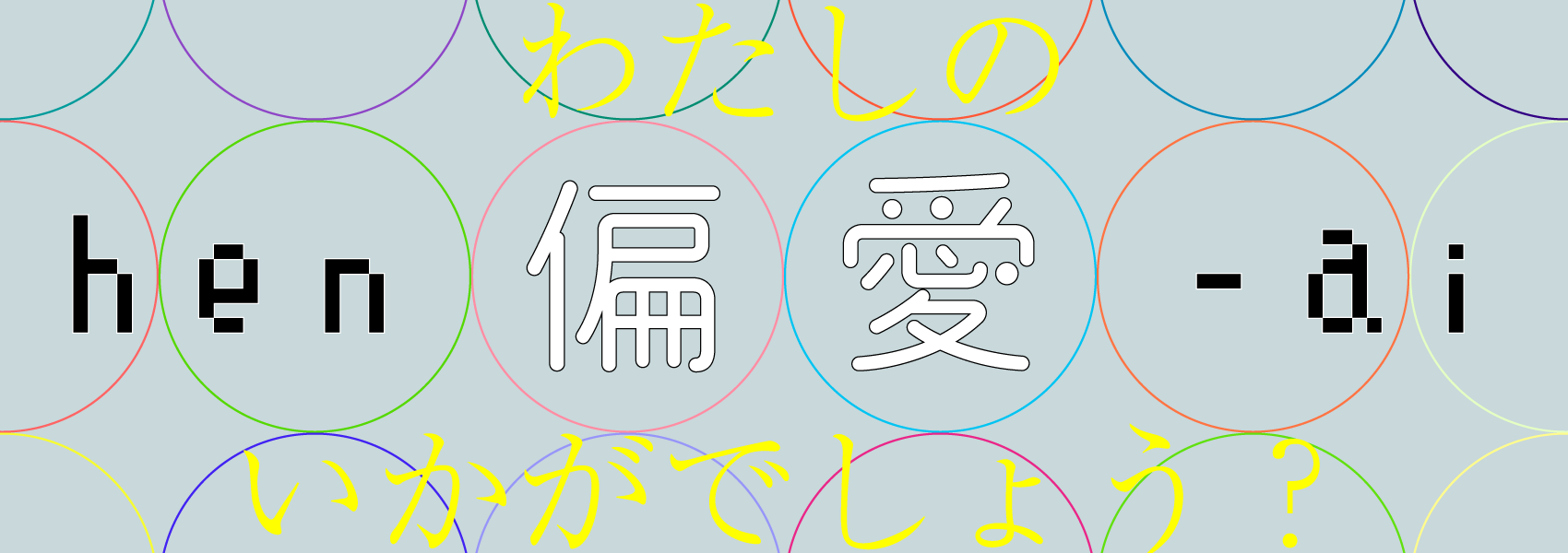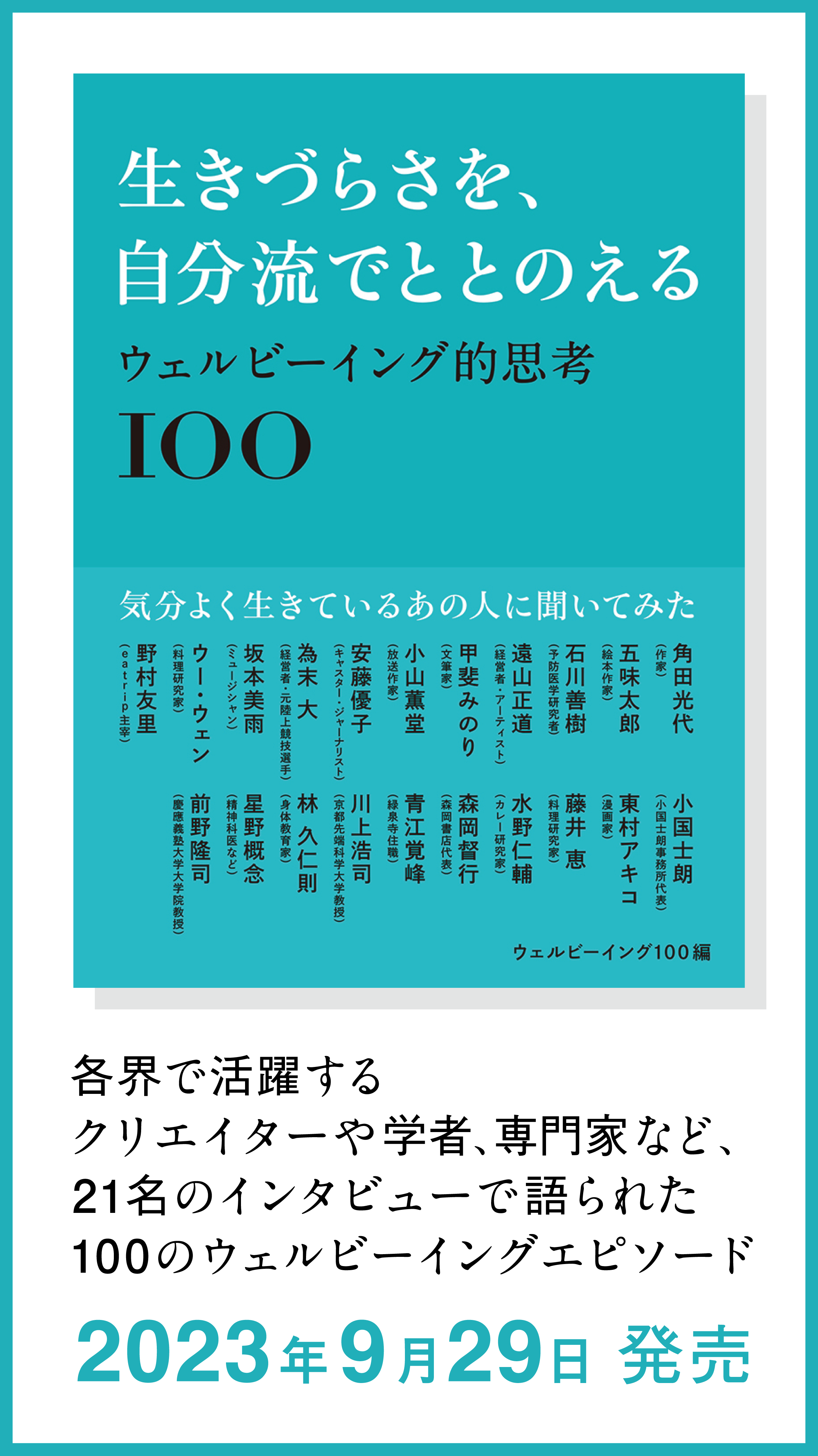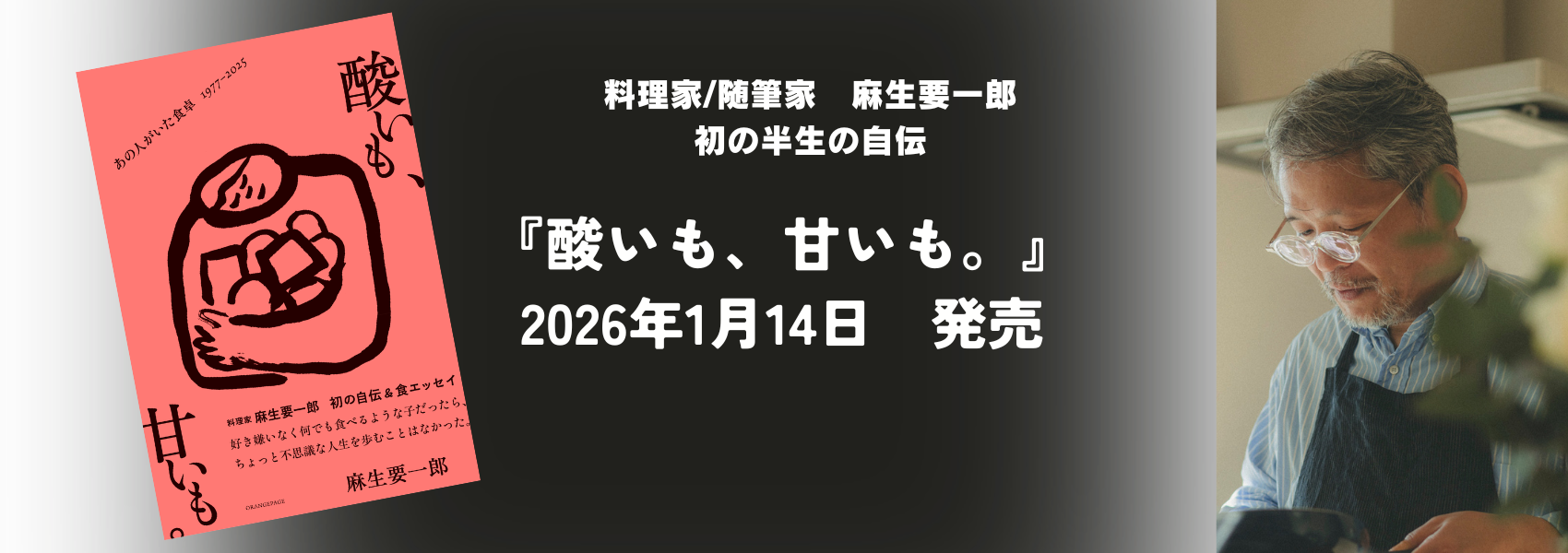障害のある人は、奉仕の精神をもって支援するべき存在。
そんな凝り固まった差別意識を打ち破り、知的障害のある人たちと対等に手を組んで、
軽やかに、おしゃれに、ビジネスとして成功させた会社があります。
人生100年、年齢を重ねれば誰もが心身に不自由を負うであろうこの時代に、
障害の有無とは関係なく、誰もがハッピーに生きられるヒントはないか。
各界から熱い注目を集める『ヘラルボニー』に、創業の背景や考え方をうかがいました。
お話しをうかがった人/(株)ヘラルボニー 代表取締役社長 松田崇弥さん、リテール部門シニアマネージャー小森樹子さん
聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100 byオレンジページ編集長:前田洋子
撮影/原 幹和
文/小林みどり

━━━障害のある作家のアート作品で事業を展開していらっしゃいます。具体的にはどんなことをされているのでしょうか。
松田さん(以下、松田)「日本全国の福祉施設や個人で活動されている作家さんと、アートのライセンス契約を結んでいます。
今(2022年8月現在)、主に知的障害のある153名の作家さん、37の福祉施設法人と契約していて、2000点件以上のアート作品のデータを著作権管理しています。
そのデータを軸に、ジャケットやハンカチなどのアートのプロダクト、成田空港の空間装飾、ホテルのプロデュースなど、さまざまにライセンス事業を展開している会社です。ライセンスのエージェンシーのような形でイメージしていただくと分かりやすいと思います」
━━━ヘラルボニーのようなライセンス契約のビジネスがあることを、障害のある作家さんはどこから知るのでしょう。どんなところに接点が?
小森さん(以下、小森)「ありがたいことに、私たちが紹介されたテレビ番組を見てお問い合わせいただいたり、うちの息子の作品を見てくださいとご応募いただくケースも多いですね。
また、建設現場などの仮囲いにアート作品を展示する際に、その土地ならではの作家さんがいらっしゃらないかなと、アートを基点に運営されているその地域の福祉施設さんを探し、お話しを進めさせていただくこともあります」
━━━地方自治体などともコラボできそうですね。
松田「ありがとうございます。実は今、地域密着型のプロジェクトがすごく多いです。沖縄にある銀行の建物の仮囲いにソーシャルアートミュージアムを設置したり、北海道を拠点とする事業主さんともお話しが進んでいますし、楽天イーグルスと地元・仙台の作家さんが組んで球団の応援グッズを作ったり。地域性は重要なキーワードになっていますね」
━━━地域性と相性がよさそうですね。ヘラルボニーを立ち上げた背景は何だったのでしょうか。
松田「4歳上の兄が重度の知的障害をともなう自閉症で、母も福祉活動に積極的でたくさんの団体に入っていました。だから私が小学生の頃はみんなでキャンプに行ったりして、もう土日はすべてそういった活動に捧げるような暮らし。それがすごく楽しくて、かわいがってくれる大人たちもみんな福祉業界の人たちだったので、私の夢は特別支援学校の先生だと作文に書いていました。
将来はそういった領域にかかわるんだろうなと漠然と思いながら生きていましたが、そのうちにデザインに興味が出てきて、高校時代に小山薫堂さんの本を読み、これはおもしろいと。当時、小山さんが東北芸術工科大学のデザイン工学部に企画構想学科を立ち上げたばかりで、そこに二期生として入学し、そのまま小山さんの会社に就職しました。
一方で、30歳までにはキャリアチェンジして福祉の領域で勝負したいという思いも持っていて、これまでに培ってきたクリエイティブな領域と福祉をかけ合わせて、何かおもしろいことをやれないか、知的障害のイメージを変えるような何かをしたいと考えて、今のビジネスモデルを思いついき、27歳のときに起業しました」
━━━企画構想学科から松田さんのような人が出てくると、大学としては万々歳だったでしょうね(笑)
松田「大学のパンフレットの1ページ目に自分!みたいな(笑)。 本当にありがたいですね。褒められるような学生ではなかったので、教授からも言われますね(笑)
本当に素晴らしい大学でした。産学連携だらけで、すごく実践的。菓子メーカーの商品化企画や音楽祭を立ち上げたり。協賛社集めに自分も名刺を持って企業を回るなど、まるで会社みたいな立ち位置で学生が動くという学科だったので、すごくおもしろかったですね。
実は高校までは本当にダメダメで、部活のキャプテンなどはしていましたが勉強は本当にできなくて、学業で褒められることなんてなかったんです。それが、大学に入ってすごく褒められて。自発性があるし、アイデアも言うし、いいねと。前に出させてもらう機会がすごく増えて、そこからは学ぶことが強烈におもしろくなりました。なので、企画構想学科の授業だけはかなり一生懸命やったという自負はありますね」

━━━松田さんにはとても身近な知的障害者のことが、社会の中では特別な人扱いされるという違和感を、しっかり社会に受け入れてもらえる形のビジネスにしているところが素晴らしいと感じます。
松田「小森もお兄さんのことがあって入社してきていて、うちの会社にはそういう人が多いですね」
小森「私にも4つ上に兄がいて、20歳になるまでいわゆる障害があるなんて家族全員分からなかったんです。それまではずっと、なんだこの変わったお兄ちゃんと思っていました(笑)」
松田「なんでそんなことするんだろうなって(笑)」
小森「そう。なんで? もう! と怒るような関わり方をしていて、気づいたらすごく兄の自己肯定感が下がってしまい、失敗体験をいっぱい積み重ねてしまったことから精神に浮き沈みが出て、いろいろ調べていくうちに発達障がいの診断を受けました」
松田「社員が30人、副業やインターンも含めてスタッフは40名くらいいますが、家族に障害のあるが人がいるのはそのうちの3割くらいじゃないでしょうか。世の中的に見れば非常に多い数値かもしれませんね。
ただ、福祉を専門に学んだ人はほぼいなくて、民間企業でふつうに営業などで働いていた人がほとんど。もともと障害のある人への周囲のイメージに違和感を持ち、イメージを変えることには興味があったけれど、福祉業界で働くのは何か違うと。
ヘラルボニーのライセンスビジネスで社会側の思想を変えるというコンセプトに共感してくれて、ここなら株式会社だし数字も追えるし、おもしろいなっていうので入ってくれる人は多いですね」
━━━ヘラルボニーが目指すところ、ミッションは何でしょう。
松田「会社名のヘラルボニーは、兄が小学生のとき日記帳などいろいろなところに書いていたナゾの言葉なんですが、このヘラルボニーという言葉が将来、概念化していったらいいなと思っています。
たとえば建物にヘラルボニービルと書いてあったら、ああ、ここは障害のある人に配慮された素晴らしいビルなんだなと分かったり、ヘラルボニーカップラーメンと書かれていたら、これは障害のある人も含めみんなが食べやすいとか。
兄は重度の知的障害があるのでスイミングスクールや書道教室に通えませんでした。断られてしまうんですよ、手に負えないからと。でも、ヘラルボニースイミングスクールとかヘラルボニー書道教室と書いてあったら、ここは障害があってもなくても全員が入れる教室なんだなと。
いちいち細かく説明しなくちゃいけないところを、言葉で説明がいらない状態に、数十年先にでもできたらいいですね。それで、辞書にもそう書いてあるとか(笑) そうなったらいいなと思うんですけどね」

━━━ヘラルボニーの商品を拝見しましたが、何の説明がなくてもすごくカッコイイ。その先にストーリーがあるというのも魅力的です。そういうアート作品を扱ってプロダクトや空間に落とし込むときに、大切にされていることはありますか?
小森「この作品はここがメインだろうと私たちが思っても、実際に作家さんに伺うと、いやいや実はこだわりはここじゃなくて端のほうにあるんだ、みたいなケースが多くて(笑)」
松田「あるある(笑) ありますね」
小森「どっちが絵の上と下なんですかと聞くと、ぐるぐる回りながら描いているので上下みたいな概念はないんです、なんて作品もあったり。アート作品を作ろうと思って描いているわけではない作家さんもいらっしゃいます。
なので、私たちの勝手な思い込みで起用せずに、作家さんがどういう過程で描いているのか、その作品ひとつひとつにどんな背景があるのかなどをしっかりと探りつつ、プロダクトに落とし込んだときにどの部分をメインに持ってくるのか、どういう配置がアートとして映えるかを考えます。
そういった事情があるため、プロダクトには全部、アートハンカチーフとかアートトートバッグなど、ネーミングの最初に“アート”を入れています」
━━━なるほど。本流の現代アートは、何か意図を読み取ることを試されているようで、ちょっとしんどく感じることがあります。でも、ヘラルボニーのアート作品は、純粋に見て楽しめますね。先ほど概念化するというお話しがありましたが、何か新しいアートのジャンルが生まれるかもしれませんね。
松田「そうなってくれたらいいなと思います。ヘラルボニーというジャンルになってくれたらいいなと。
私たちの契約している作家さんのほとんどに重度の知的障害があり、これは上下が逆ですとか、どこを使ってもらってもかまわないとか、自分でスラスラと話すことはあまりないんですね。自分がアーティストであると思っていない作家さんも多いと思います。それを私たちがアートと呼ばせていただいて、展示や販売をさせてもらうことによって、数十万で売れるような形になるわけです。
現代アートなら、コンテクストや布石みたいなものも含めて強く作品としてあるわけですが、ヘラルボニーの作家さんは本人が何かを語るわけではないので、私たちはどれだけがんばっても代弁者にすぎず、雰囲気から予想したことしか伝えることができません。
なのでヘラルボニーで扱う作品は、かなり鑑賞者側に委ねられている部分が大きいです。私たちが接客する際に、「この作品はこういう背景があってこれが正解なんです」ではなくて、「私たちはこういうふうに思っていて、こうだと考えているんです」、と。そうやって正解を鑑賞者と一緒に考えていけるというのは、すごくおもしろいなと思いますね」
━━━それを事業としてしっかり成功されている印象です。福祉事業とは向き合い方が違いますね。
小森「私はヘラルボニーに入社する前は、民間の福祉関係の企業で働いていました。そこでは運営する側として使う言葉もふるまいも、こうあらねばいけない、ということがとても多くて。すごく細かく神経を張り巡らせながら事業を運営していた感覚がありました。
でも今、ヘラルボニーに参加して、一緒に楽しんでいる感覚、おもしろがって推進していく感覚が前職とは全然違うなと思います。もっと肩の力を抜いて、え、そっちにこだわりがあるの!とか、上とか下とか関係ないんだとか(笑) そういうのでちょっと拍子抜けと言いますか、一緒に笑いながら進めていくことが多いですね」

━━━ヘラルボニーを立ち上げるときにも、障害者とともに作っていくならこうあるべき、みたいな意見や葛藤がありそうです。
松田「前の会社をやめて、こういうビジネスを考えていると両親に話したとき、ふたりともすごく反対しました。父は銀行員、母は教職でわりと硬い家庭ですが、やめたほうがいい、そんなのでお金を借りられるわけがないと。
でも仕事をやめて、双子の兄である文登と会社を興しました。最初の1年目は本当に鳴かず飛ばずで、前職の先輩から仕事をもらって食いつないで(笑) ライフワークとライスワークを完全に分けて、ほとんどお金にならないヘラルボニーの事業を続けながら、会社の定款とはまったく関係のない仕事で食い扶持を稼ぐという状態。これが1年半くらいですね。
でもヘラルボニーの事業としては今とやっていることは変わらなくて、日本全国の福祉施設に文登と夜行バスで行って、契約させていただいて。
支援じゃなくビジネスでこれをやっていくなんて福祉の畑では絶対にできないから、ぜひ挑戦してほしいと皆さん熱烈に応援してくださいました。お金じゃなく、知的障害のある人のイメージを変えたいんだと兄とふたりで熱心に話していたので、その目的に好感を持ってくださったのだと思います。
でも、いろいろな企業などに営業に行くと、やはりチャリティーのように思われることが多い。チャンスがあったとしても、通されるのはCSR(企業の社会的責任)を扱う部署。CSRもやりたいと思っていたので悪いわけではありませんが、やはりきちんと利益を出すビジネスとは思われないんだなと痛感しました。
この最初の1年で気づいたのは、自分たちでブランドを作り、世界観を打って出ないと伝わらない。ライセンスビジネスをやる会社ですと話を持って行くのではなく、私たちはブランドの会社です、そのブランドのライセンスしませんか、という順番で話を進めようと考えたわけです。
それで3年ほど前、銀行から借り入れて自社ブランドの店舗をつくりました。小売りが厳しいのは分かっていたし、コロナ禍だし、正直なところ在庫は持ちたくなかったんですよね。
でもちゃんとリスクを背負って出店して、うちのブランドの作品はこんなジャケットになったりTシャツになったりするんですよと物販を見せたら、何か変わるんじゃないかと思って。
ブランドのキービジュアルも創り込み、これらのアート作品はこんな世界観を表現できるんだと、モノやビジュアルで具体的に見せるようにしたら、状況がガラッと変わりました。
支援ではなくビジネス、障害のある人をビジネスパートナーと捉えていることなど、言っていることは以前とまったく変わりません。でも、ああ、こういう世界観を念頭に置いた話だったんだねと分かってもらえるようになりました」

━━━ビジネスとしてのヘラルボニーが軌道に乗ったわけですが、知的障害のある方のイメージをどう変えていきたいとお考えですか?
松田「障害と聞いたときに、劣っているとか欠落みたいなものが連想されるのではなく、おもしろさがパッと出てくるようになるといいなと単純に思っているんですよね。
たとえば、私の兄はここに水があったら必ず一気飲みします。で、テーブルの真ん中を探してコップを中心地まで持って行くわけですよ(笑) エレベーターも10秒くらい静止してから乗り込むとか、その人独自のユニークなこだわりっていっぱいあるんですよ。でも学校生活ではこういうのを問題行動と思われたり、地域を歩いていて指を指されたりすることもあるんですよね。
自分にはない思考回路を持っているという事実はあるので、そこをバカにするのではなく、なんでだろう、おもしろいよね、こんなこと私には思いつかない、みたいな価値観に変化させていきたい。
私の中学時代には、自閉症スペクトラムのことを“スぺ”と揶揄して、ちょっと変なことをすればスぺの教室行けよ! という言葉を吐かれたり、歩き方が変だと“身障”と呼んで身体障害者みたいだとからかわれたりしていました。
そういうバカにする風潮みたいなものが、イメージを変えることで消えていくんじゃないかと期待しています」
━━━ウェルビーイングの観点からも、非常に興味深いビジネスですね。
小森「前職で10年ほど障害福祉の分野で働いていて、何でも語り合える親友でさえ、その会社を説明すると伝わっているようで伝わっていないというか、ちょっと硬いこと、自分とは距離のあることのように思われがちでした。
でもヘラルボニーの店舗には、手に取ることで幸福感を得られる商品、ふと思い出したときにハッピーな気持ちになれる商品がある。ただのハンカチではなく、ハンカチを広げたときにいつも思い出されるストーリーや風景があるわけです。そういうバトンを繋げていけることを、私もヘラルボニーで初めて体感しました」
━━━人生100年時代について読者アンケートをすると、ネガティブな人がとても多いんです。64%の人がそんなに長生きしたくないと。見た目にときめく商品で、さらにそこにストーリーがあり、自分もその輪の中にいることを実感できるヘラルボニーの事業は、不安がつのる高齢化社会にも希望をもたらしてくれそうです。
松田「日本も景気が悪いし、ニュースを見ていると暗くなることも多いですよね。ハッピーなニュースしか流さないテレビ局や新聞社があればいいのにと思います。マインドセットってけっこう重要だと思うんですよ。
ヘラルボニーもありがたいことに仕事が忙しく大変なんですけど、うちのすごくいいところは、作家さんがすごく喜んでくれているとか、施設職員から感謝の連絡が届いていますとか、親御さんからお手紙が届いていますなど、本当にシャワーのようにハッピーなニュースが届くことですね。それが社内スラックの全体共有で3日に1度回ってくるわけです。こんなふうに言ってもらえました! 〇〇さんと会えました! と。
あれが、自分が何のために仕事をやっているのかを思い出させてくれるんです。その都度その都度シャワーのように浴びて、ああ、私の仕事が誰かの喜びになっているんだなと実感できる。消費者だけでなく、一緒に仕事をしている福祉施設の人や親御さんや作家さんのリアクションからもそれが分かるというのが、うちの一番の強みだと思っています。毎日シャワーのようにハッピーなニュースを浴び続けられる環境が、うちのウェルビーイングですね」

━━━そういう思いを持って仕事をできるのは、何よりも幸せですね。今後の展望、チャレンジしたいことはありますか。
小森「今はアートが得意な作家さんがメインですが、アートの文脈以外にもいろいろなおもしろさを持っている方がいらっしゃいますし、才能とか光るものがないとダメなのかというと、それは誰かのモノサシで一方的に決めているものです。本当にありのままのその人らしさが見えるような、そういった環境をヘラルボニーが作っていきたいと思っています。
今ひとつ構想としてあるのは、たとえば私たちが運営しているブランドショップで、障害がいのある方ない方関係なくスタッフとして働く環境づくりですね。同じ言葉を繰り返している人が店頭に立っているとか、ゆっくりだけれどめちゃくちゃ丁寧にラッピングしてくれる人がレジにいるとか。それこそ福祉の領域を拡張するような、そういった空間、環境を作っていくことをひとつの展望として掲げています」
松田「福祉施設で箱折りなど軽作業的なことをクローズドな空間の中で行っていて、しかもあまり賃金も高くなくて。どんな仕事をやりがいを持ってやろうか、というよりは、仕事をしてもらうことが目的化しているような状況かと思います。そういうクローズドな場所ではなく、丸の内のカフェで知的障害のある人が普通に働いているような、ハレの場で働く。そこまでいけたらいいですね。
アートはパッと見て分かりやすくて、ああオレには描けないと尊敬を生み出すハードルが低くて、とても有効な手段だと思うんです。
ただ、本当の意味でのイノベーションというのは、特別な才能もない私の兄みたいな、今は空き缶を潰し続ける毎日を送っている人が、誰もが当たり前に行き交う場所で働けるようになることだと思うんです。
その景色を作っていける存在にまで昇華できたら、親御さんたちも伝え方が変わるんだろうなと思うんですよね」
━━━自治体の方がこの話を聞いたら、興味を持たれそうですね。
松田「そうですね。いつか街づくりもやってみたい。たとえば本社のある岩手県の村の一角はヘラルボニーシティになっていて、そこだけ実験特区でいろんなものが実現されるなんていいじゃないですか(笑) まだ計画も何もないですけど、興味はありますね」
小森「いいですよね。でもやはり、知的障害について一般的にはほとんど知られていないことが障壁になっているとすごく感じています。電車に乗ってブツブツ言っている人がいたら、ちょっと車両変えようかなとか関わらないほうがいいかなと思うかもしれませんが、それが日常の中でたびたび見かける風景になっていくと、ああこういう人もいるよねと、当たり前のこととして受け入れられますよね。
認め合わなくちゃ、となるとちょっと重たさもありますが、それもあっていいよね、前にもそういう人いたな、あれは危害を加えようとしているのではなく落ち着くからしているだけなんだな、と。お互いを知って、眼差しがやわらかい社会になっていくといいですね」


【インフォメーション】
「異彩を、放て。」をミッションに2018年に設立。経済産業省が主宰する「日本スタートアップ大賞2022」の審査委員会特別賞をはじめ数々の受賞歴を誇る、注目の福祉実験ユニット。自社のアートライフスタイルブランドをはじめ、建設現場の仮囲いをアートミュージアムに見立てる地域密着型のプロジェクト、各企業とのコラボ商品など、知的障害のある作家のアート作品を多彩に展開。