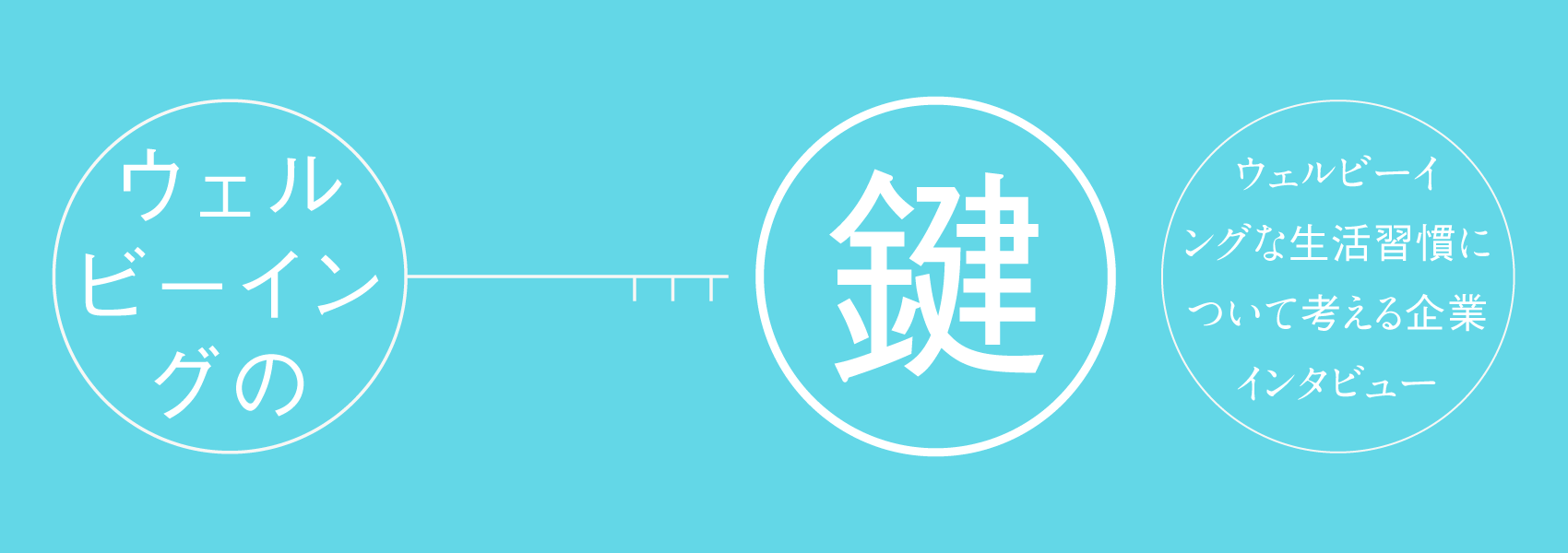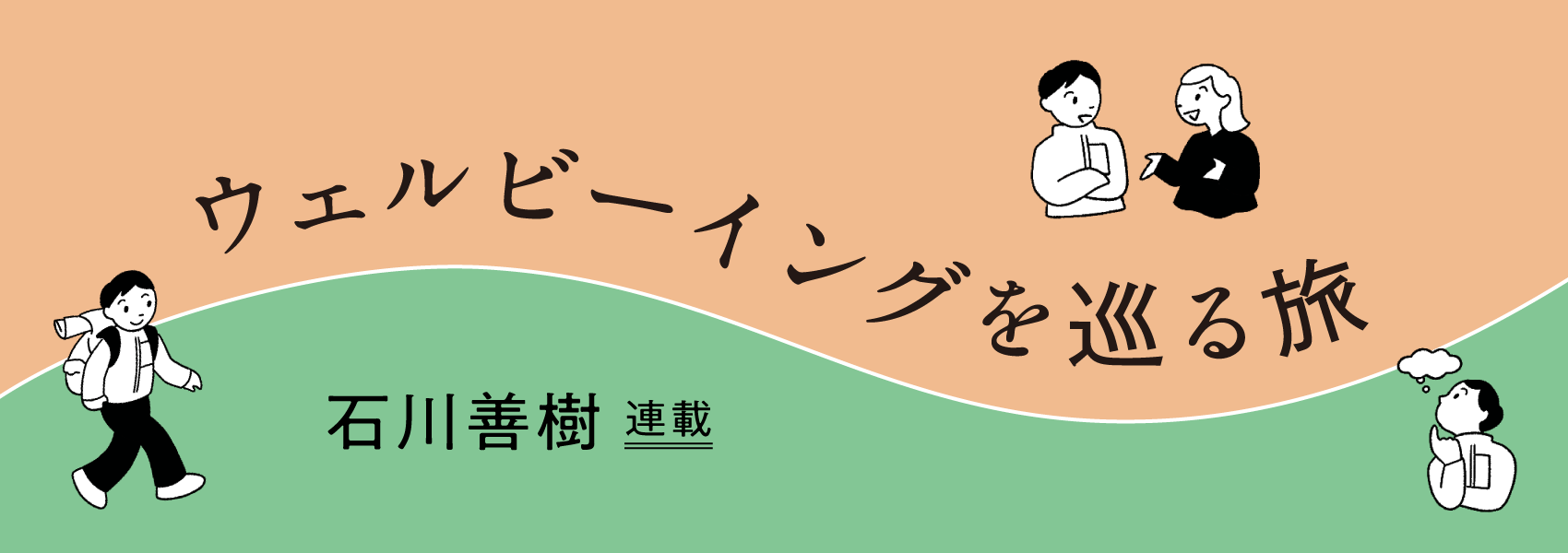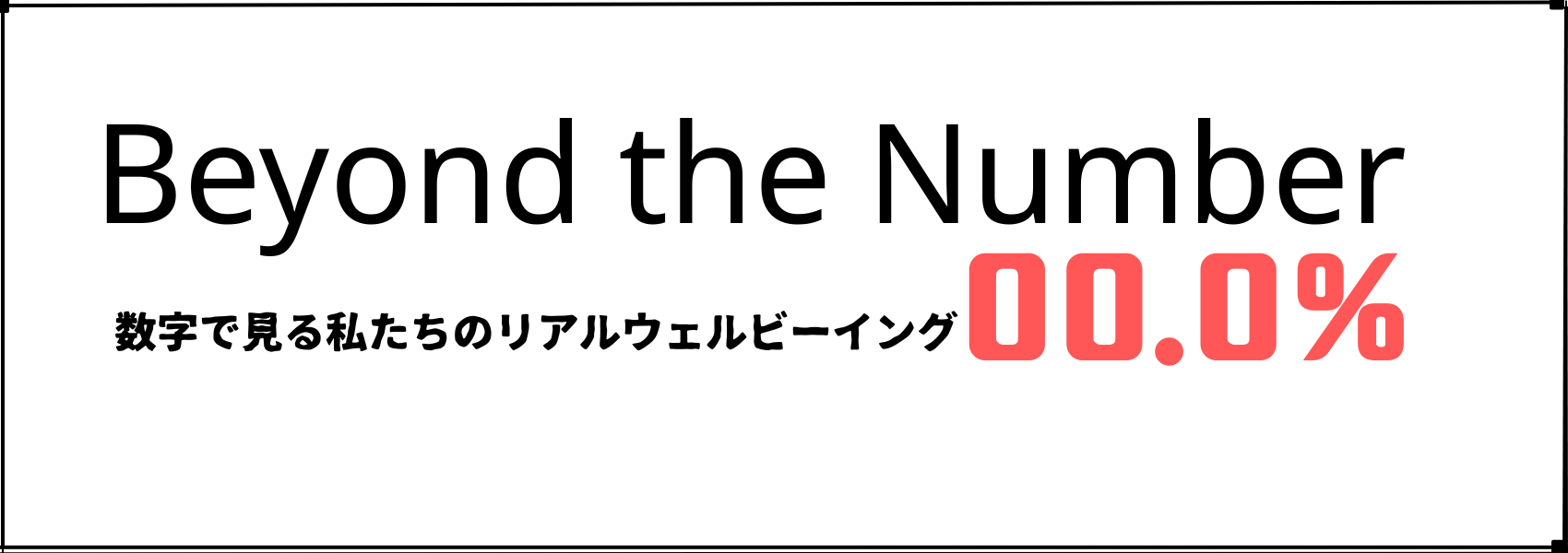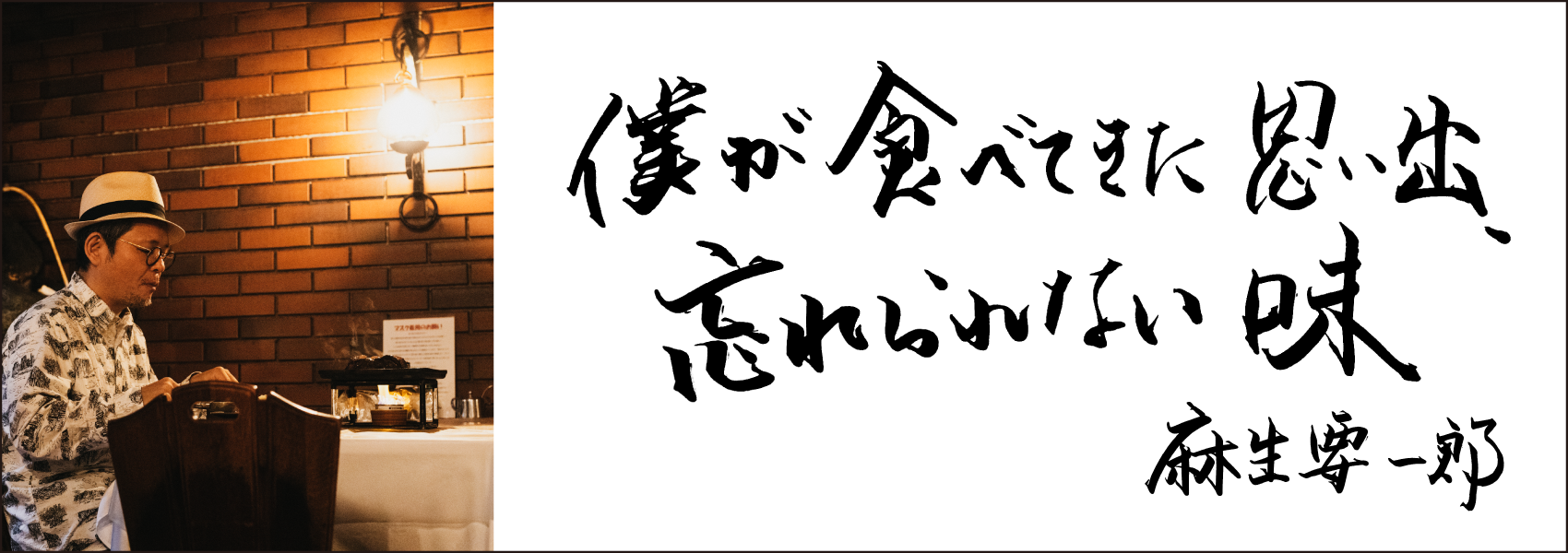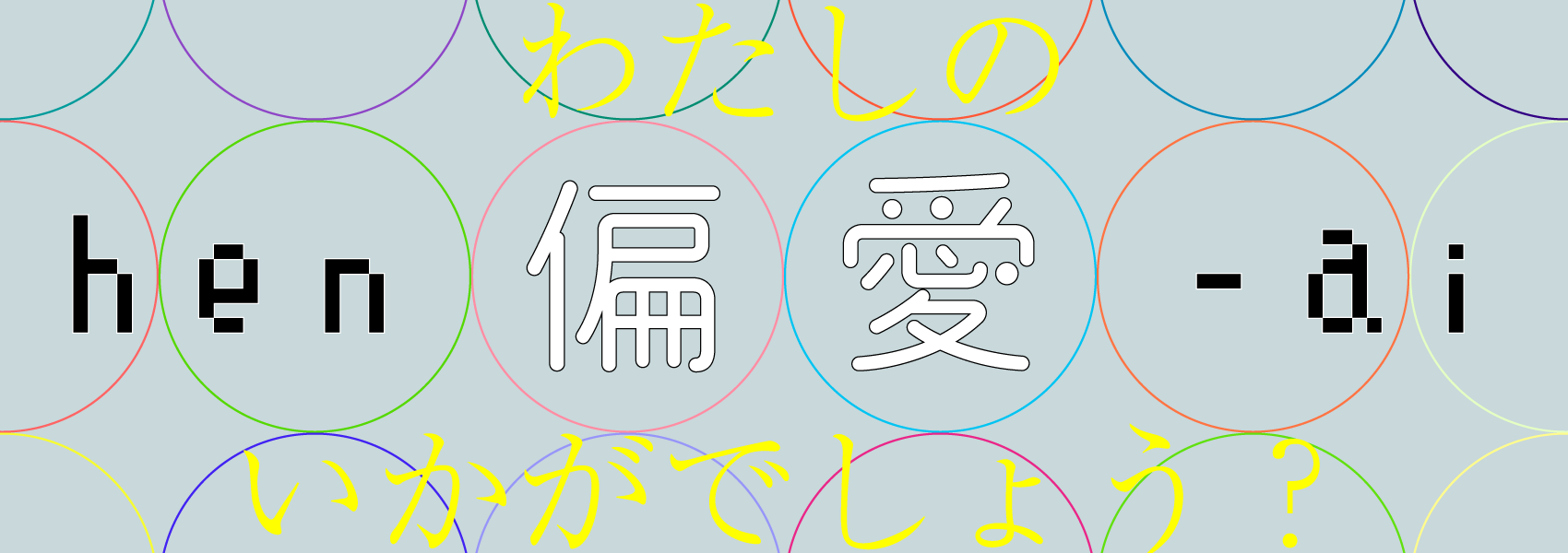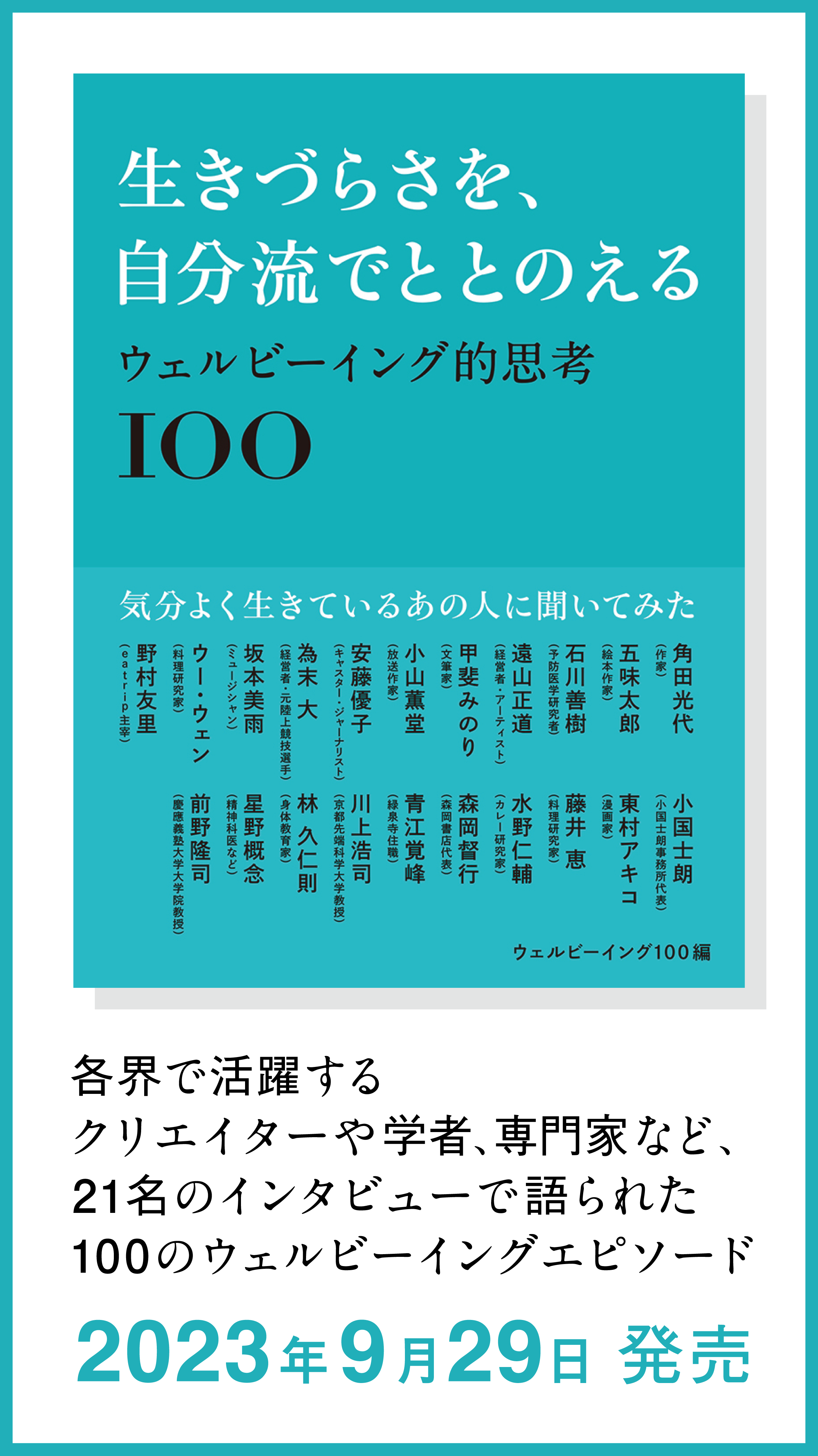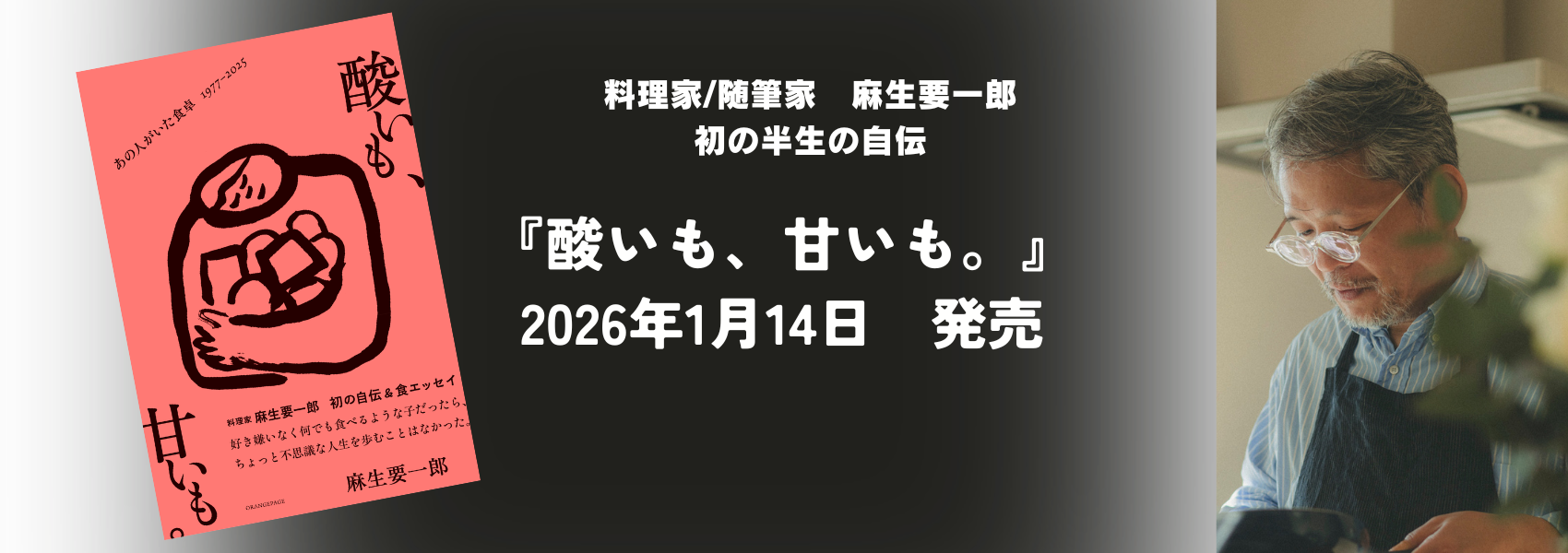食生活はこころとからだを満たして、気分よく歳を重ねるための重要なカギ。
「料理をつくること」は、日々の暮らしの豊かさと深くつながっています。
今回、お話を聞かせてくださったのは、菜園料理家でダンサーの藤田承紀さん。
農業や料理にとどまらず、興味のあることに次々と挑戦し、
新たな可能性を広げる藤田さんに、人と料理とのいい関係とはどういうものなのか、料理との向き合い方について、お伺いしました。
お話をうかがった人/料理家:藤田承紀さん
聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100 byオレンジページ編集長:前田洋子
撮影/原 幹和
文/中村 円

前田 藤田さんは料理家であり、菜園家であり、ダンサーであり。「ウェルビーイング」というのは、人がどんな時に満足感を得られるか、「ああ気分いいな」って思えるかを考えることでもあるんですが、藤田さんは毎日が充実していらして、まさにウェルビーイングな生き方をされているようにお見受けします。現在はお米を作っていらっしゃるとか?
藤田 はい。去年から念願の米仕事が出来るようになりました。妻の実家が宮城県で代々続く米農家で、僕も千葉県で10年くらい自然農法の畑をやっていて、米も作りたいと思っていたのですが、田んぼを手伝わせてもらえることになって。宮城に移ってからは、古い建物を使わせていただいて、それを手仕事の作業場にして、真鍮作品や家具を作ったり、家づくりの準備をしていますもう、ほんと、毎日寝るときに「幸せだなぁ」って思って床に就くんです。
酒井 藤田さんは料理家としてもイタリア料理を本格的に勉強されていらっしゃいますが、料理の道に進もうと思ったきっかけは何だったんですか?
けがで中断を余儀なくされたダンサーの道。
失意の中、心動かされるものを求めてイタリアへ
藤田 大学時代にダンスに出合い、卒業後はavexでプロのダンサーとして活動していました。ところがひざの半月板を割ってしまい、ダンスができなくなってしまったのです。もう、気分が底に落ちて、このままではダメだ「心動かされることがしたい」と思いました。それでイタリアに行ってみようかと思い立ったんです。その頃、飲料メーカーに勤めていた父が、イタリア食材商社を任されるようになって、日々「イタリアはいいぞ」と聞かされていたんです。父はそれまで、すごく厳しい人だったんですが、イタリアに関わるようになってから、すごく明るく、丸くなって。それと、ひざのリハビリの先生に「体を治すには、安静にするよりも、歩いて食生活を整えなさい」といわれたこともあって、イタリアに行ってみたいと思いました。いざイタリアに行ったらもう、食べるもの、食べるものすべてがすごくおいしくて。現地の食とその文化に魅了されて、料理の道に進もうと決めて帰ってきました。
前田 イタリアに行くのと、料理を仕事にするまでにも段階がありそうですが。料理が好きだったのですか? それとも文化が好き? イタリア料理を食べるだけでいい、という単純なことではなかったのですね。
藤田 イタリアで「食」そのものへの興味が強くなり、好きになったというか。ダンスを教えていた生徒さんたちにも、食生活が乱れている子が少なくなくて、漠然と「食事が大事」という気持ちはあったんですが、イタリアで本当にそうだと思いました。実際、けがした足は手術が必要だといわれていたのですが、毎日しっかり歩いて、食べ物に気をつけていたら、3か月くらいで治ってしまいました。
酒井 イタリアという場所で、けがと食、体の関係についての気づきがあって、重なった感じですか?
藤田 そうです、そうです! それで、旅行から帰ってから、料理研究家のかたのアシスタントをしながら料理学校に留学する準備を始めましたが、偶然、イタリアには親戚も住んでいることがわかって、しかもご主人がダンサーで、「来年また、踊りにおいで」といわれたりして、ダンスの縁でもつながって、まるでイタリアに呼ばれている感じでした。

嫌がらせもあったイタリア修行時代。
逆境下では勝とうとせず、折れない、めげない、へこたれない
酒井 イタリアでの暮らしはどうでしたか?
藤田 まず料理学校に入って、その後は料理店での研修がありました。留学したのが27歳だったんですけど、30歳までに一人前になりたくて、「一番厳しい店に行きたい」と希望を出して、日本人が全然いない地方のリゾートレストランに入りました。でも、最初はボディブローです。
酒井 ボディブロー?
藤田 「日本人はまねをする」って嫌われて、意地悪をされるんです。イタリア語もあまりわかっていないから、「こいつなんなんだ」って感じで、とにかく相手はすごい怒っていました。意地悪されて殴られて、「いてぇ」っていうと、その言葉がおもしろいとまた殴られる。
酒井 英語も通じなかったんですか?
藤田 英語は通じました。でも、母国語のほうが本当のことを言ってくれると思ったし、それで語り合えるほうが、教えてもらったことが身になるし、時間が限られていたから、何がなんでもイタリア語で吸収したかった。それで、馬鹿にされ続けていましたけど、辞書を持ち歩いて過ごしていたら、少しずつ仲よくなれて。あるときパーティがあって、「踊ってみろ」といわれて踊ったら、「面白いやつがいる!」「すごい日本人がいる!」「ヨシキ、お前は家族だ!」って一気に受け入れてもらえたんです。芸は身を助く! ですね(笑)。イタリア人は一度「家族」になるとすごく親切で、いっぱいよくしてもらいました。
前田 逆境下で、いじめにあって、真正面から立ち向かっていくのって大変ですよね。
藤田 僕は生まれつき左耳が聞こえないんですけど、母や周囲が、ポジティブにとらえてくれていました。大学の卒論のテーマは障害者スポーツだったんですけど、その中で「何ができないか」ではなく、「何があって、何ができるのかを考える」っていう考え方を知りました。「左耳が聞こえない」ではなくて、「右耳が聞こえる」って。それで、「殴られているっていうことは、コミュニケーションが取れているということ」って受け止めるようにして。けんかのときも、相手を打ちまかそうとはしません。勝とうとは思わないけれど、折れない。めげない。へこたれない。だれかと競うのではなくて、いつも自分が主体。自分が上がるか、下がるか。そんな風に考えているところがあります。

食材を深く知るために始めた畑仕事から、
料理の新たな世界が開いた
酒井 まさにウェルビーイングにつながる考え方ですね。日本に帰国後は?
藤田 イタリアではキッチンの旬しか知らなかったので、野菜のことを知りたくて畑を始めました。その縁で、アメリカ大使館のオーガニックガーデンの管理を頼まれたり、畑を教えてくれた人が「日本の綿、和綿も作りなさい」というので綿を栽培したり。綿から糸を作るようになって、織りも覚えたいと思って、地元の織り機を持っているかたのところを突撃してみたら、「近くに糸つむぎができる人がいるって聞いてたのよ」って。お互い相手を探してたんです。しかもそこは、障がい者福祉サービス事業所を運営している法人なんですが、「施設の利用者さんが食事をしたり、働けるレストランを作りたいと思っていたのよ」って。
酒井 すごい引き寄せですね!
藤田 それで、利用者さんとの交流が始まって、月に一度、「森のレストラン」という食事会を始めました。障がいを持っていると、レストランにはすごく行きにくくて、遠慮をして、一生レストランというところには行かないままの子もいるんです。そんな子たちに料理を出すと、食べて泣く子がいるんですよ。いつも暴れる子が、レストランの日は正座をして待っていてくれる。料理を出したらすぐに食べて、おかわりをしてくれる。今って料理を出しても写真を撮ったり、料理から一歩引いているお客さまが多いんですけど、彼らは前のめりで料理が一番おいしい瞬間に食べてくれる。料理人として、とってもうれしいことで、得難い経験をしました。そして、彼らと歩く道を、危なくないようにと毎日掃除をしていたら、それを陰から見ていた地主さんが土地を譲ってくれたり、市の補助金が下りたり、ありがたいことが重なって、「らんどね空と海」という障がい者が食事を楽しめて、さらに働けるお店をオープンすることができたんです。
酒井 ダンスと料理と畑、みんなつながっていく感じですね。
キャリアは1本道ではなく、
大きくゆるやかに円を描くらせん階段

藤田 僕の道は一直線に駆け上がっていくのではなくて、らせん階段みたいな感じです。料理と畑、畑とダンス、みんな円でつながって、少しずつ上がっていく感じ。レオナルドダヴィンチにはなれないけれど、彼みたいにいろいろなことをしていたいと思っているんです。それに、どんなことをやっていても、<下がる時期>がありますけど、速度が落ちているとき、沈んでいるときはやらない。その時にやっていることの中から成長できるものをやる。複数の仕事を持っていれば、上がっていくものを選べますから。
酒井 まさに現代版のお百姓さん、ですね。
藤田 そのためには好きでやっていることが趣味で終わらないように、プロになれるようにと思っています。僕の中でプロか、そうでないかの線引きははっきりしていて、お金をいただける技術、レベルであるかどうか。プロに対価を支払うことを、自分でできればそれは何かを買ったのと同義だと思っていて、たとえば今、子どものために座面にコードを張った椅子を作っているんですけど、コードの張り替えをプロにお願いすると2万円かかる。それが身近にあるものを使って自分でできれば、2万円で買った、2万円稼いだのと同じかな、と。
酒井 自分で使うものを自分で作る。サーキュラーエコノミーっていうのかな、現代では資源の投入量や消費を抑えたり、有効活用したりしながら経済を回すことが求められていますけど、藤田さんはまさにそれを実践していますね。何もないところから何かを生み出すのは、ダンスに似ている気がしますが、キャリアのスタートがダンスだったことは、その後にも関係していますか?
藤田 関係しています。ダンスは体ひとつでできるし、アートであり、スポーツであり、自分の中のさまざまなことを表現できる。僕にとっての料理がダンスに近づいてきたのかもしれません。
家庭料理の底上げが、食の世界そのものの
底上げにつながる
酒井 なるほど。藤田さんにとって、料理って何ですか?
藤田 呼吸するみたいに、自然なことです。実は僕が一番やりたいことは、料理を教えたり、料理家として活動することで、日本の家庭料理を底上げしたいんです! 「食べること」にもっと興味と関心を持ってもらいたいんです! イタリアではマンマだけでなく、若い人も料理をするし、みんなすごく知識があって、若い人でも「今日はこれを食べるから、ワインはあれね」なんて言う会話が普通にできるんです。たとえばサンドイッチ、パニーニのお店では具材を自由に選べるんですけど、2種類でも4種類でも値段は同じで。僕が「モッツァレラにアンチョビに…」って欲張っていろいろ選んじゃうと、「ヨシキ、モッツァレラに合わせるのは、トマトだけがいいんだよ」って。老若男女、みんな食べることを楽しんでいるし、そのとき何を食べるべきかわかっているんですよ。だからこそプロの料理人には大きな敬意を払うんです。
酒井 自分が食べるものを選ぶ、という行為も料理なんですね。
藤田 家庭の食が充実すれば、外食でも「安かろう」がよしではなくて、プロの仕事にきちんとお金を払おうという気持ちになります。食の世界の全体的なブラッシュアップは、家庭の食からだと思っていて。そのとき自分が求めている、いちばんおいしいと思える料理を作れるのは自分自身ですしね。イタリアから帰ってきて、レストランのシェフになるという選択肢もありましたが、家庭の食にアプローチしたくて料理家になりました。都内のデパートで8年くらい、デモンストレーション型の料理教室をやらせてもらっていて、今は、オンラインレッスンも始めています。
酒井 料理家ではあるけれど、それだけでない。藤田さんは料理を取り巻く世界を組織する「料理組織人」なのかもしれませんね。今後も楽しみですね。

藤田承紀(ふじたよしき)
料理家、菜園家、ダンサー、真鍮作家。イタリアでの料理修行後、菜園料理家として活動を開始。アメリカ大使館内大使夫人の菜園管理人、サルヴァトーレフェラガモ氏とのコラボレーションディナー、服部栄養専門学校特別講師、書籍出版、テレビ・ラジオ・雑誌出演等。
2016年より、環境省「つなげよう支えよう森里川海」プロジェクトのアンバサダーや、食書籍著者で構成される「日本食文化会議」の運営委員を務める。
2021年仙台市泉ヶ岳の麓に移住し、農と手仕事のある暮らしをしている。
instagram:https://www.instagram.com/yoshiki_yasai/
HP:http://fujitayoshiki.com/