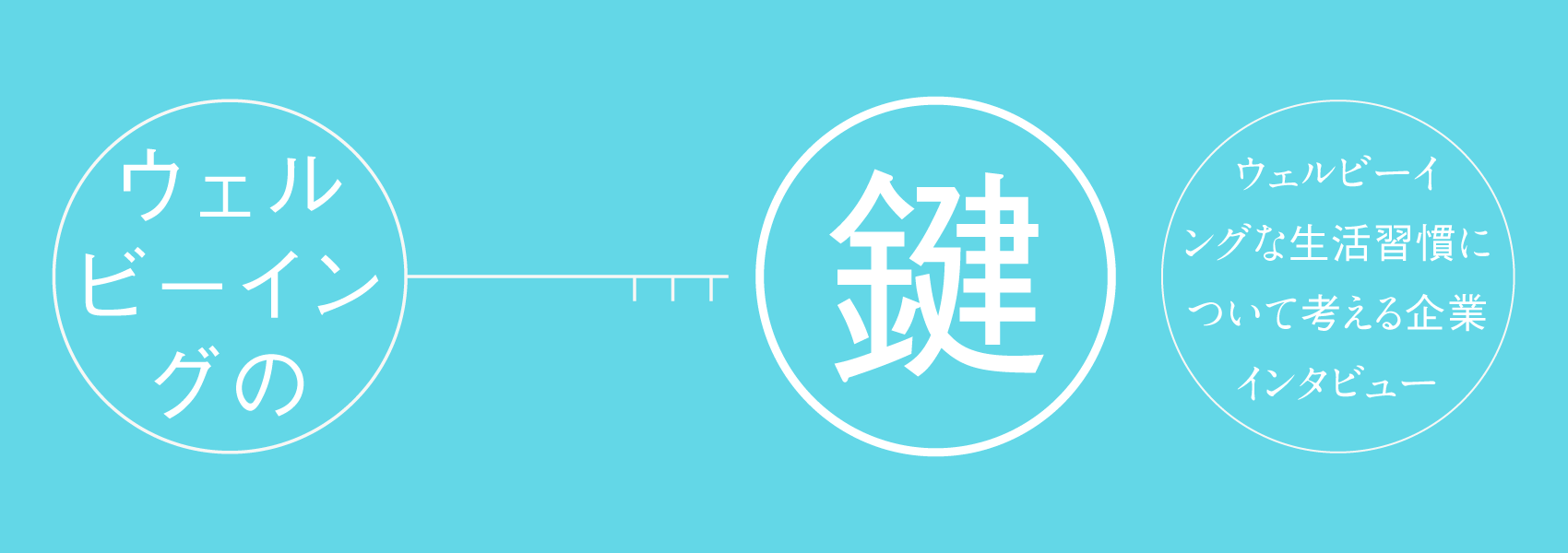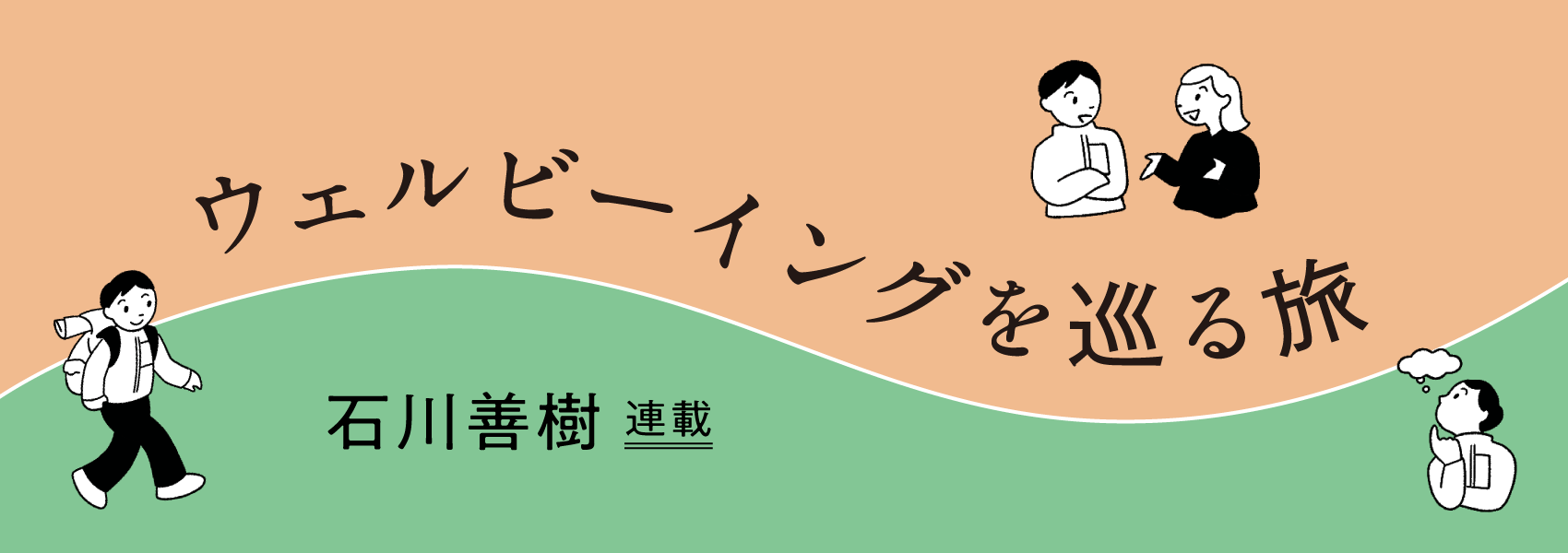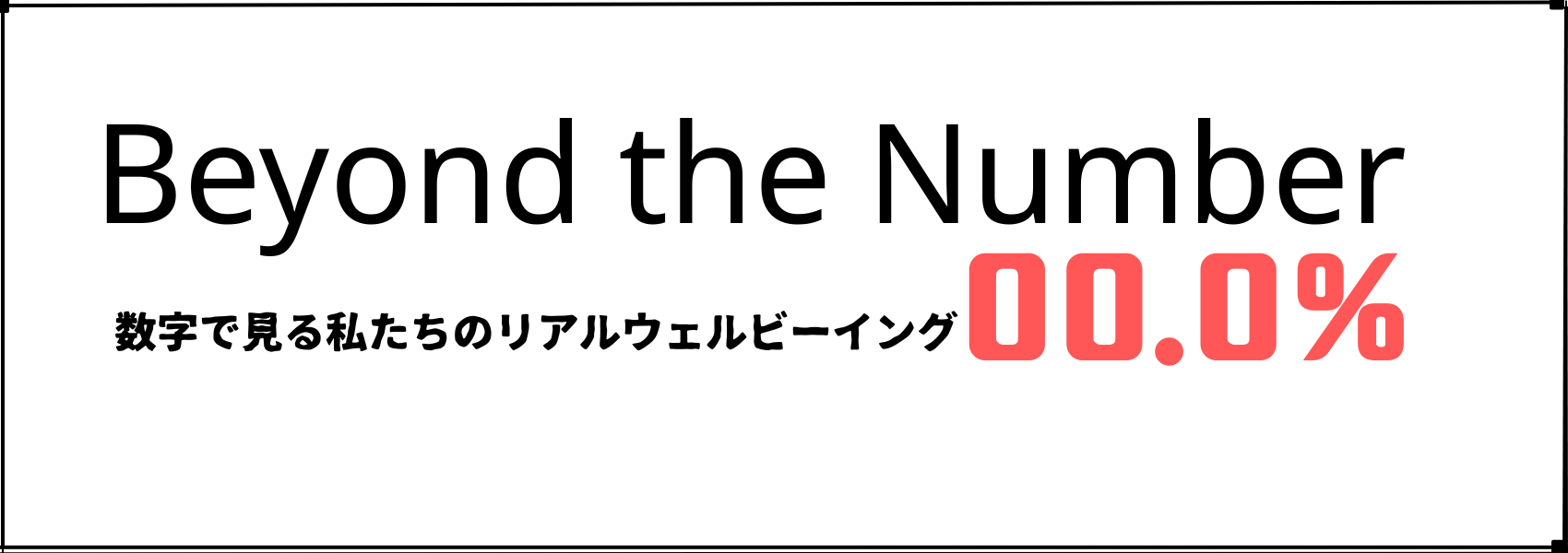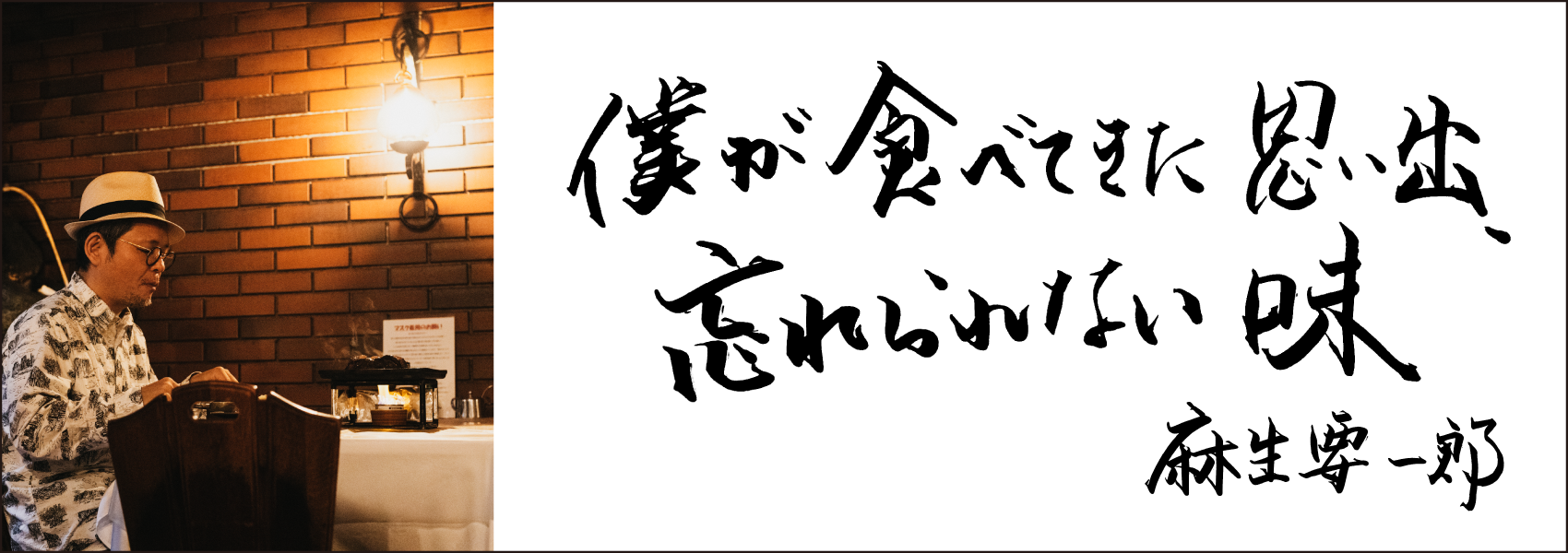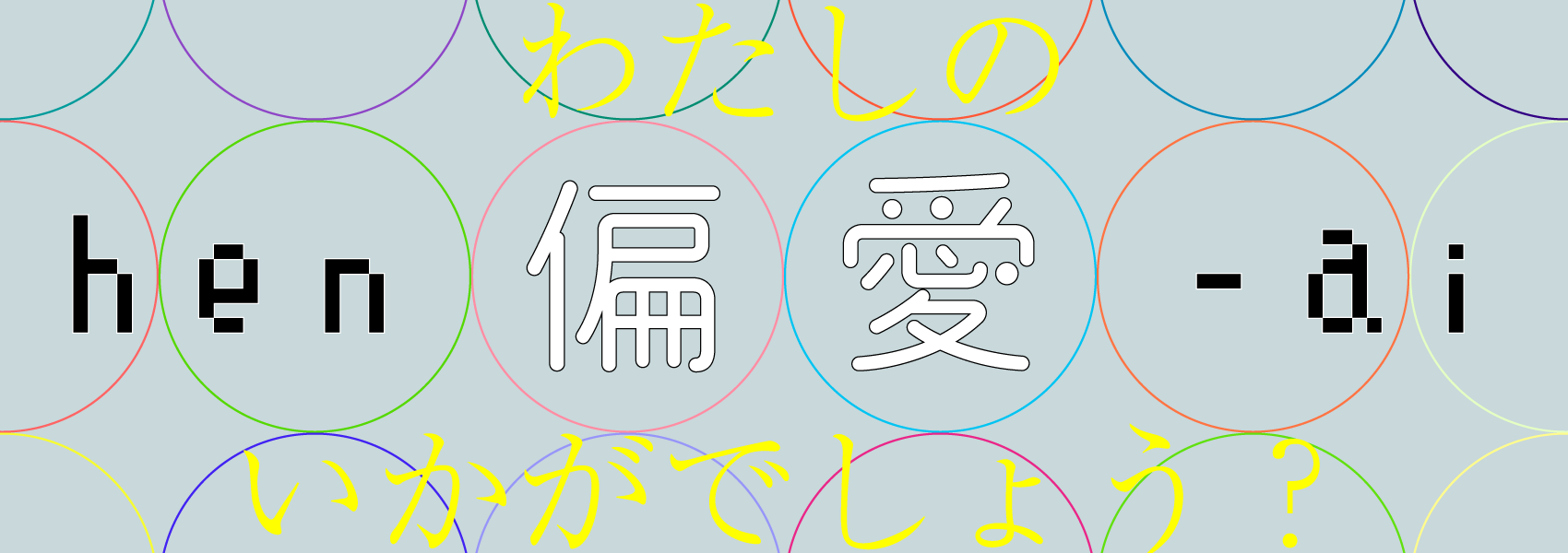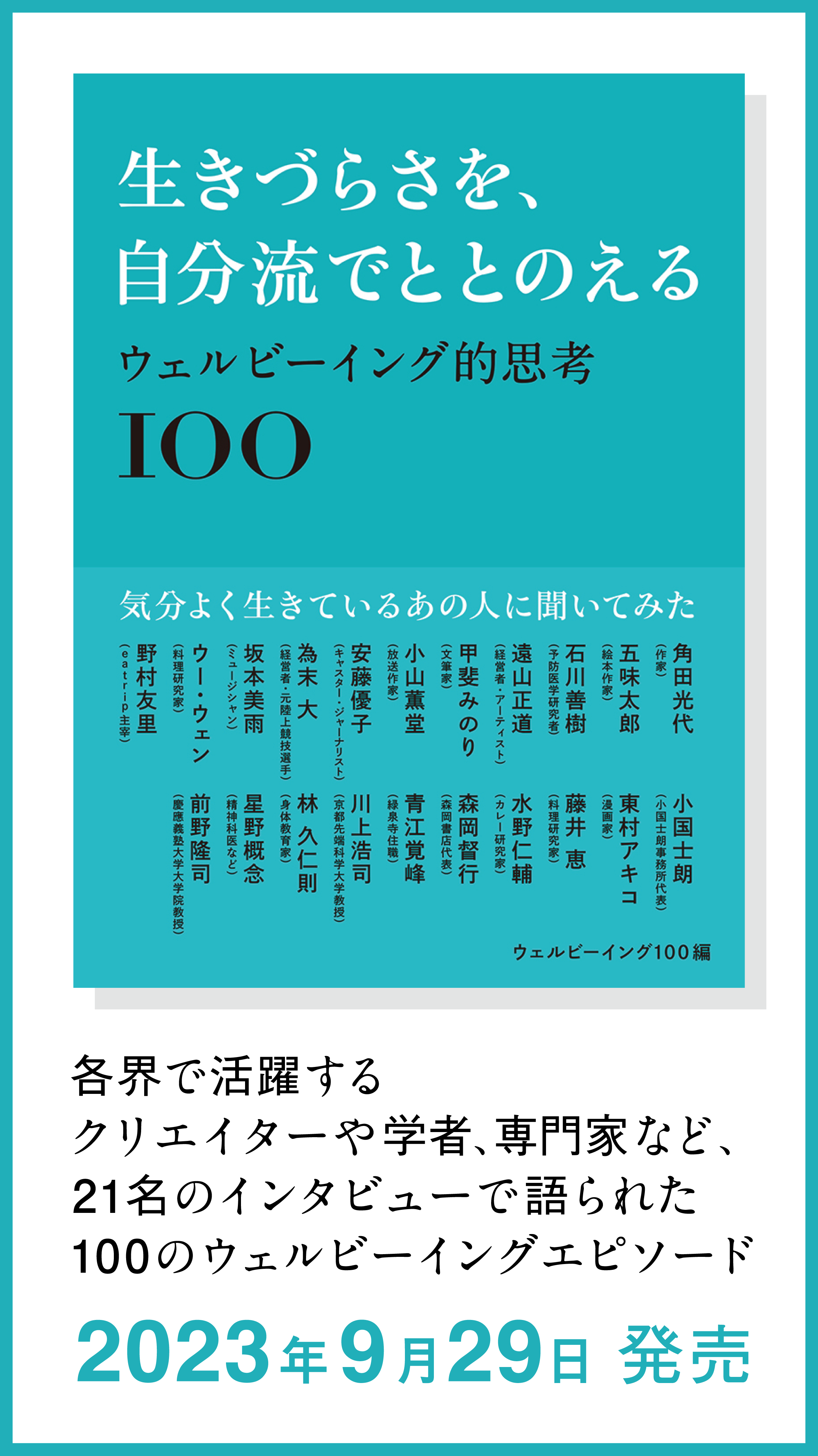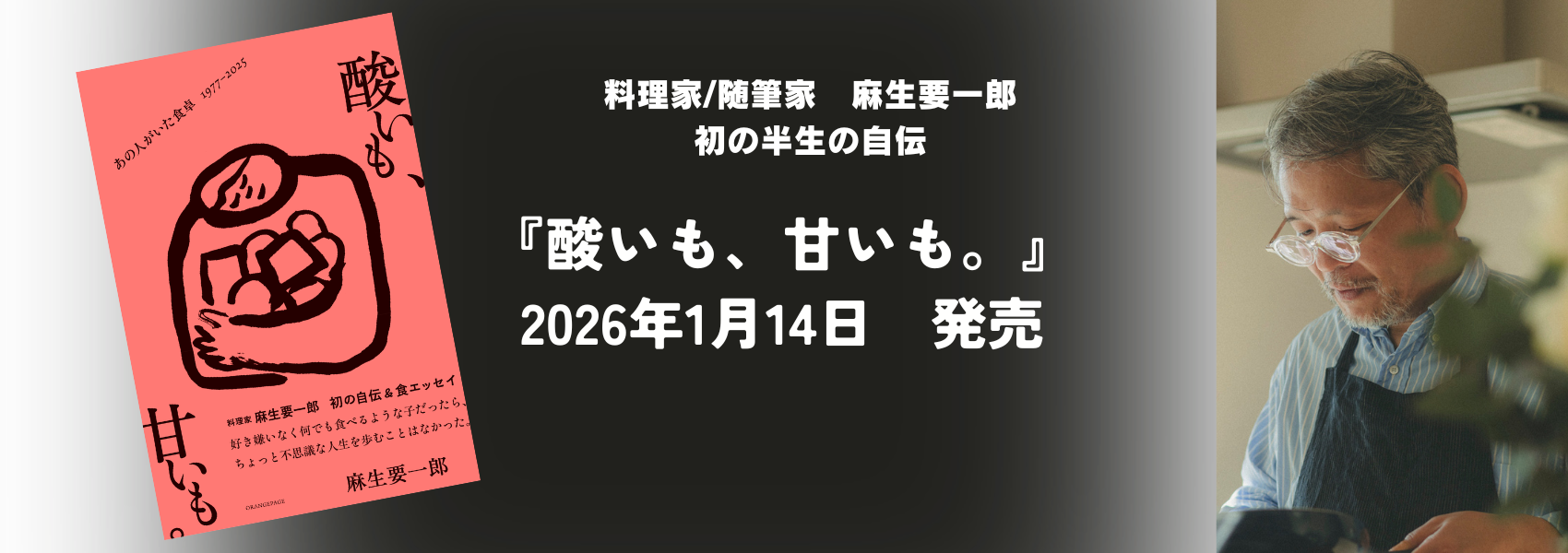さて、お待たせいたしました!
ウェルビーイング研究の第一人者・石川善樹さんの各界の俊英とのリレー方式の対談、そしてその「振り返り対談」、またある時はリアル旅! もあるかもしれない、いままでにない「ウェルビーイングを旅する」新連載です。第1回は古典エッセイストで『源氏物語』の全訳も手がけた大塚ひかりさんです。大塚さんの著書『昔話はなぜ、お爺さんとお婆さんが主役なのか』を読んで「この方と話したい!」と思ったという石川さん。時間をさかのぼり、古典の世界の男女の距離感や、人とモノとの“間の取り方”など、古典ファンも古典を知らない人にも、興味が尽きない話が続きます。
さあ、人が生きる、って何だろう? を考え、巡る旅の始まりです。
文/中川和子
撮影/JOHN LEE(書籍)

石川善樹(いしかわよしき)
予防医学研究者、博士(医学)
1981年、広島県生まれ。東京大学医学部健康科学科卒業、ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で博士(医学)取得。公益財団法人Wellbeing for Planet Earth代表理事。「人がよく生きる(Good Life)とは何か」をテーマとして、企業や大学と学際的研究を行う。専門分野は、予防医学、行動科学、計算創造学、概念進化論など。近著は、『フルライフ』(NewsPicks Publishing)、『考え続ける力』(ちくま新書)など。
https://twitter.com/ishikun3
https://yoshikiishikawa.com/

大塚ひかり(おおつかひかり)
古典エッセイスト
1961年生まれ。早稲田大学第一文学部で日本史学専攻卒業。『源氏物語』全訳6巻のほか、『本当はエロかった昔の日本』『毒親の日本史』『くそじじいとくそばばあの日本史』『くそじじいとくそばばあの日本史 長生きは成功のもと』など著書多数
石川「“人がよく生きるって何だろう?”っていう疑問が尽きないのです」
石川:本日はありがとうございます。よろしくお願いします。昔から「人がよく生きるって何なんだろう?」という疑問が尽きなくて、最近は“ウェルビーイング”という角度から追及しています。とはいえ、自分でも「ウェルビーイングっていったい何だろうか?」とは思っています(笑)。
大塚:外国なんかだと「ウェルビーイング月間」みたいなのがあって「今日は会社で焼物をしてみよう、とかサークル活動的なものがある」と海外に住んでいる人に聞いたりしたんですけれど。石川さんは「日本的ウェルビーイング」を追究していらっしゃるということですが、石川さんと吉田尚紀さんとの共著『むかしむかしあるところにウェルビーイングがありました」を読むと、「幸せに生きるには」とか書かれていて、「自己啓発とどう違うんだろう?」と思って、最初、あやしい感じがしたんですよ(笑)
石川:「幸せ」って、世界共通の価値観じゃないというか。イスラム圏だと幸せってあんまり好まれないみたいです。どちらかというと「辛く苦しいのに耐えたほうが結果としてよい」みたいな感じで。ハッピーとか幸せって感じてると、それは神様に対して悪いことをしているという感覚にすらなる。幸せに対する恐怖ってよく言われるんですけれど「フィア・オブ・ハピネス(fear of happiness)」っていう。
大塚:日本もそういうのがないでしょうか?
石川:近いのがありますね。「幸せすぎて怖い」という言葉があったり。
大塚:私は古典をエンタメとして読んできているので、そこに何かを見出そうというのは、あんまり意識して読んでなかったんですね。日本史学専攻なので、歴史的背景とかは資料としておもしろく読んでいたんです。それが石川さんの著書のオビには「日本文化は幸せになる秘訣の宝庫だった」とあったりして。そこに幸せを発見するのはどうなのかなと疑問を覚えたりもしました。
石川:「幸せ」という言葉は僕もあんまり使っていなくて、個人的にはウェルビーイングを「よい間」と訳しています。他者との関係性とか自然との関係性とか、「間の取り方」っていうことを追求すればそれがウェルビーイングなのかなって。
大塚:もともと日本の古典文学を読んでいても、男女の境も親子の境も他人との境も割とあいまいな感じがするんですよ。だからこそ塀を高くしているというようなきらいもあって、男女の境っていうことでいうと、簡単に男が女になって、女が男になるというか……。たとえば『土佐日記』では「男もやっているという日記なるものを女の自分が真似してやってみるよ」と男の紀貫之が言っているわけですから。
※『土佐日記』……紀貫之作。土佐国守の任期が終わり、京の旧宅に入るまでの旅を記した日記。日本で初めて仮名文で、女性に仮託して書かれている。935年頃成立したと思われる。


大塚「平安時代の上流階級では同じ女性に三回通ったら結婚成立、みたいなところも。だからやたらと三回は通わない(笑)」
石川:そもそも昔は、「恋愛」ってどういう感覚だったんでしょうか。
大塚:「恋」という言葉は万葉集の昔からあって、太古の昔から人は恋をしていました。ただ、平安時代などは、これは身分にもよりますが、恋と結婚の境もやや薄いところがあったかもしれません。相手の女性のところに3日通ったら結婚成立、みたいなところもあったので。
石川:それは奥さんなりダンナなりがいたとしても、新しい人のところに3日通ったら、あるいは通われたら、そっちに移るということですか?
大塚:移るっていうことではないんですけれども、3日通うと結婚成立する。上流社会の場合には、一夫多妻だったりしますので、そういう相手が2,3人いたということですね。
石川:聞いた話なんですがアマゾンのある原住民は、たとえ結婚していても気になる相手ができたら一緒に森の中に消えていくらしいんですね。で、1日で帰ってきたら奥さんは「あんた、何やってんのよ」って怒るんです。が、ダンナは謝ってまた元に戻るんですけど、3日経って帰ってくると、それはダンナが別の人に乗り換えたってことになるらしいです。
大塚:それは日本の古代とちょっと似てる気がする(笑)。
石川:そうでしたか(笑)
大塚:でも、やたらと3日通うわけじゃないんですよ。1日で逃げるっていうのもあって。それだとただのセックスフレンドとかやり逃げになっちゃって。3日通って女の家で披露宴みたいなことをすると結婚が成立するから、そうそう3日は通わないんですよ。そもそも上流社会の結婚ですと、その前に手紙のやりとりをして、男はやっと本人(女)から返事をもらって、女の屋敷を訪ねてもすぐには会えない。まずは外に近い「簀の子」と呼ばれる場所に通されて、それが通うにつれ、だんだん奥の方に通してもらって、初めて会えるという……。第一回目のセックスに至るには段階を踏まなきゃいけない。そんなわけで同じセックスでも「見る」と「語らう」の2種類あって、「見る」というのは結婚前提のセックスなんですよ。
石川:目で見るの「見る」ですか?
大塚:どうしてかと言うと、当時、特に上流階級の女の人っていうのは、顔を見せる男っていうのは親兄弟か夫しかいなかったから、男が女の顔を見たっていう時点で、もう結婚なんですよ。
石川:ああ、なるほど。
大塚:「あの女を見たい」と言ったら、結婚したいということになって。一方、そのセフレ的な、ただやりたいっていうのは「語らう」って言うんですよ。語らうっていうのはどちらかというとただの恋愛というか、そんなに本気ではない。その違いがあったんですよ。さっき説明したのは「見る」までにとても時間がかかる、結婚前提の恋とセックスですね。
石川:そういえば、これも聞いた話なんですが、ある方が「3回同じ人とセックスしたら、もめる」という謎の持論を展開してまして。さらに「できたら1回、2回、セックスしたほうが、そのあと男女の関係というよりも、人と人の関係として、すごく長いあいだうまくいくんだ」と。
大塚:でも、その3回セックスしたらもめるっていうのは、そこで結婚しないからもめるわけですよね?
石川:きっとそういうことだと思います。
大塚:3という数字に何かあるんですかね(笑)
石川:ぜひ追及して考えてみます(笑)
石川「日本は幸福度が低いけれど、北陸は比較的高いといわれます」
大塚:調査によると、日本人の幸福度って世界の中でも低いじゃないですか。そんな日本でも幸福度が高い地域ってどんなところなんですか?
石川:北陸(福井県、富山県、石川県)なんかは、よく幸福度が高いといわれますね。
大塚:それはどういうことと関係してるんですかね?
石川:一つの理由として、浄土真宗が根づいているからじゃないかといわれてます。
※浄土真宗……浄土教の一派で開祖は親鸞。一向宗ともいう。肉食妻帯で在家主義。
大塚:浄土真宗って妻帯を許していたりして、性的にゆるいってところがあるんですかね?
石川:あると思います。親鸞自身が「それでも自分には煩悩がある」と言って高野山を降りてるくらいですからね(笑)
大塚:もうひとつ、日本ってセックス専用のラブホテルがあったり、すごくスケベな国民なのかと思いきや、世界のセックス調査ではいつも最下位みたいな感じじゃないですか。あれもいつもおもしろいなと思ってるんですけど。
石川:そうなんですよね。僕が健康づくりの研究をやっている中で、日本人の問題のひとつは睡眠が足りてない、ってことなんです。国際比較でみても日本人は睡眠時間が少なくて「なぜだろう??」って考えてみると、極端な仮説かもしれませんが、「セックスの少なさ」ってのはありそうだなと思ってます。
大塚:日本では結婚するとしなくなるのが当たり前というような妙な風潮がありますよね。それは私は昔からそんな感じだったと思っていますが、ただ、通い婚の時代にはひょっとして少しは違ったかもしれませんね。平安時代の場合、男が妻の実家に通って、それで子どもが生まれると独立して同居するようなところがあったから。あと、貴族などは一夫多妻というのもあるから、女性のところに通っていると何かしないといけないみたいなところがあったかもしれませんね。
石川:江戸時代の俳人の小林一茶はすごいですよね(笑)
大塚:あの人は『七番日記』という句日記に回数を書いていますものね。1日何交とかいって、1日に5交とかもある。小林一茶は結婚したのが50過ぎですから、ほんとに早く子どもをつくりたいということで、頑張ってたというのもあったと思うんですけれど、すごいですよね。今と昔を比べてどうなんですかね。そのへんの統計がないからわからないですけれど。
※『七番日記』……小林一茶の1810年から1818年に至る9年間の句日記。48歳から56歳までの句とともに、その日の出来事が簡潔に記される。
大塚「平安時代、女性が男性から和歌をもらっても即レスしたらなめられちゃうから、わざと時間をおいたり、既読スルーしたり」
石川:平安時代って、和歌のやりとり以外、心のやりとりって何かあったんですか?
大塚:和歌のやりとり以外だと、やっぱり贈り物というんですか。歌に花を添えたりとか。和歌のやりとりがメインなんですけれど、ただ和歌だけじゃなくて、そこで見られるのが紙の色、どんな紙に書いたとか、そういうことで趣味をものすごく見られるんですよ。添える花がちょっと季節にそぐわない、おかしな色だとか。でも、それは一周まわって意図があったってこともあるんですけど。歌の文字面だけじゃなくて、墨色とか、あと、使いの者に持って行かせるわけじゃないですか。それがどういう人かとか、趣味から何から全部で総合判断される。歌が素晴らしいだけではダメだったりするのです。歌のやりとりのタイミングも重要ですし。
石川:「この人ダサい」とか思われたら、もうダメなんですね。
大塚:そうですね。そこで趣味を測られちゃうという。あとやっぱり、和歌も即レスとかだとなめられちゃうんですよ。女性が和歌の返事をする場合、すぐさま返事をすると「俺に気があるんだ」ということでなめられたりするから、時に返事をしないとか。ものすごく時間をおいてするとか。あと、最初の返事は自分では書かないで、代筆、代返させるとか。そういうことから距離をつめていくというのはあります。
石川:今でも同じようなことをやってるような気がしますね(笑)
大塚:即レスとか既読スルーとかね(笑)
石川:恋愛の指南本みたいなのもあったりするんでしょうか?
大塚:指南本というのは、『源氏物語』がとくに後世そういう本として読まれていた節もあるし、紫式部もそれを意図していたところもあったんじゃないかと。私はそういう気がします。江戸時代の大名家や公家(くげ)は、『源氏物語』を美麗に装丁して嫁入り道具に持たせたりしているんですよ。女性のための性教育の書というんですかね。そういう側面もあったんじゃないかと……。
※『源氏物語』……平安中期の長編物語で紫式部の作。光源氏を中心に宮廷生活とその愛憎を描き、その子孫を描いた『宇治十帖』を合わせた全54帖から成る。
石川:なるほど。
大塚:いろんな恋愛のパターンがあるじゃないですか。六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)みたいに身分も高くて才能もあるのに、なめられちゃうとか。あとものすごく愛される理由とかパターンとかで、そこがすごく書き分けられているんですよ。さっき言った“即レス”なんかは六条御息所ですね。六条御息所って、関係したはいいけれど、正式な結婚もしてもらえないまま、恨みをつのらせてもののけになっちゃう人じゃないですか。だけどよく読んでみると、それこそ「間がダメ」っていうか、自分から歌を出したりもしているんです。
※六条御息所……『源氏物語』の登場人物。光源氏の年上の愛人となるが、嫉妬のあまり生霊となって光源氏の正妻をとり殺す。
石川:ああ、そうですね。
大塚:源氏と相手の女と、どちらが先に歌を贈って、どちらがそれに答えたか。それを見ていくと、六条御息所の場合、源氏からの歌への返事が二首なのに、自分が先に贈った歌は七首もある。しかも、返事をするのも即レスだったりする。だけど、源氏に生涯愛された藤壺の中宮は同じ年上の女性でも、自分からは二首で、源氏への返歌が八首。ほんとに自分からは出してない。しかも、返歌もしないこともあるんですよ。源氏物語ですごく男性に愛されてる女性というのは、その手の人が多いです。あと玉鬘(たまかずら)なんて、養父である源氏に迫られて、かなり際どいところまでいくんですが、なんとか身をかわして、無事自分を護るんですけれど。そういうのをいかに賢く対処したかということもちゃんと書かれている。そういう指南書的なところはありますよね。玉鬘というのは、源氏とセックス中に19歳で変死しちゃった夕顔の娘で、母の夕顔のほうは男を拒めなくて、来たらもう言いなりみたいな感じで、それで死んじゃった人なんですけれども。そういう対処のしかたみたいなのが、すごくちゃんと書き分けられているんです。
石川:大塚さんご自身は古典にふれる中で、影響を受けて実践しているようなことはありますか?
大塚:あまりありません。が、強いて言うなら、たとえば、恋愛相談を受けたときなんかは、やっぱり古典文学を基準にして答えているところがありますね。「嫉妬してしまうけど、どうしたらいいか」とか相談されたら「いやもう、それは嫉妬、OKじゃないですか」みたいな。嫉妬に気づいただけでいいんじゃないかという例として、『蜻蛉日記(かげろうにっき)』の道綱の母を出します。彼女はものすごい嫉妬を日記に書いていて、ライバルみたいな女がいるんですけど、その女にめちゃくちゃ嫉妬して、夫がどこへ行くのか、そのあとまでつけさせて家をつきとめる。その女は、藤原兼家(道綱の母の夫でもある)の子を産んだあと、兼家との関係が悪くなり、挙句の果てにその女が産んだ子まで死んでしまうんです。そうしたら“いまぞ胸はあきたる”と書いてるんですよ。「今こそ胸がスッとした」と。けれど、夫との関係はやっぱり変わらない。不幸な日常だ、みたいな感じなんですけれども。嫉妬する自分に気づいて、そんな自分を直視しただけでもえらいというか。六条御息所みたいに、気づかないで、人を悪しかれという気持ちはないけれども、ライバルを乱暴に扱ったりする夢を何度も見ちゃうみたいな記述が『源氏物語』にあるんですけど「そこで嫉妬とか、人を悪しかれという気持ちに気づいただけでいいじゃん」みたいな感じで、古典を例にしてアドバイスしたり、考えるということはありますよ。
※『蜻蛉日記』……藤原道綱の母の自伝的な日記。954年から足かけ21年間にわたる夫との結婚生活を細かく描いた。
石川:なるほどね。古典はいろんな喜怒哀楽というか、感情がすごいですね。いろんな感情が描かれているというか。
大塚:そうですね。でも、昔、『感情を出せない源氏の人びと』っていう本を書いて。古典文学の感情表現というのを古事記からずっと調べたことがあるんですよ。源氏物語に関しては、感情を爆発させていないんですよね。
石川:そうなんですか!
大塚:『古事記』とか『蜻蛉日記』とか、すごく感情を爆発させる話はある一方で、『源氏物語』で感情を爆発させるのは悪役や傍流の人が多くて、源氏や紫の上といったメインの人たちはすごく感情を抑えているんです。でも、少なくとも『源氏物語』以前の古典に関しては、感情を爆発させる話が多いですよね。
石川:『古事記』とかすごいことになってますよね。神様が大泣きしたりとか(笑)。
石川「日本人は神様との“間”のとり方も、かなり独特なんでしょうね」
大塚:あと、芸能人の不倫とかよくスキャンダルになってるけど『源氏物語』の時代なんかじゃ、リアルな歴史をみても、他人を呪詛(じゅそ)したとかいって、それが政治スキャンダルになって失脚はしても、不倫とかそんな恋愛で失脚とかあんまりないですからね。
石川:それじゃあ、呪いをかけたっていうほうがよくなかったんですね。
大塚:呪いはよくないです。失脚するというのは、当時の人たちが何を悪いと思っているかというのを反映してたと思うんです。呪いはやっぱり、口から出た言葉っていうのは現実になったりするパワーがあるから。だけどそれって、最近もそうじゃないですか。どこかの企業の人が変なことを言って、その言葉のせいで株価が下がったり、不買運動が起きたりするから、言葉が呪いに通じるというのは今も同じかなと思ったりしています。
石川:芸能人のスキャンダルって、いつぐらいからスキャンダルになったんですかね?
大塚:恋愛スキャンダルって、実は平安時代にもあるにはあるんですけど、それは神に仕える斎宮とか斎院とかいるじゃないですか。そういうのをやっていた内親王などが恋愛しちゃったみたいなのはスキャンダルで騒がれるというのはありました。だから恋愛スキャンダル自体はあるけど、そのハードルは低いです。今の不倫みたいなのはスキャンダルのうちには入らない。タブーがちょっと違うから。
※斎宮……天皇の名代として伊勢神宮に奉仕した皇女。天皇の代替わりごとに選ばれて、都から派遣された。
※斎院……平安時代から鎌倉時代にかけて賀茂神社(下鴨神社と上賀茂神社)に奉仕した皇女。斎宮と斎院をあわせて斎王という。
石川:そうか、タブーが違うんですね。
大塚:そうそう、さっきの前斎宮とのスキャンダルにしたって、『栄花物語』によればお父さんが大騒ぎして大変なことになるんだけれども、乳母が手引きしたんじゃないかと、乳母もクビにしたりしているんですけれど、世間では「斎宮もやめたんだし、ちょっとお父さん、怒りすぎじゃないか」的なトーンで書かれています。
※『栄花物語』……宇多天皇から堀河天皇までのおよそ200年を編年体で書いた平安後期の歴史物語。藤原道長の栄華を中心に、宮廷貴族の生活を描いている。30巻と続編の10巻があり、作者は諸説ある。
石川:なるほどね。
大塚:だから、性のタブーになる基準というのが低いというか、薄いですよね。
石川:むかしから不思議に思っているのが、「性、政治、宗教」の3つはタブーというか、あんまり人に話さないですよね。あと、あんまり試さない。たとえば「いろんな宗教に入ってみてイスラム教にしました」って人、僕、聞いたことがない。「いろんな政党に入ってみて公明党にしました」とかも。性も「男も女もいろいろ試したけど、こうしました」って人は……。
大塚:それは確かにそうですよね。宗教はなんとなく怖いものだというイメージがついてしまっているし。
石川:日本人は神様との間のとり方も、かなり独特なんでしょうね。
大塚:日本人は無宗教だともいわれているけれど、私はちょっと違う想いで。意外と無宗教ではないんじゃないかと。寺や神社があると、どこでも手を合わせたりするじゃないですか。お財布とか落ちていてもくすねたりとかしないで返すというのは、日本が豊かだからとよく言わるけれど、幕末や明治初期に来日した西洋人の紀行などを見ると、そのころ貧しい日本の庶民でもそうだったみたいで。だから必ずしも豊かだからとかじゃなくて、何かに見られているというんですか。お天道様みたいなのに。それこそ八百万(やおよろず)の神的な何かが見てるみたいな。そういうのが今もあるのかしらと思ったり。
石川:そうですね。
大塚:それは世間の目かもしれないんですけど、たとえ人が見ていないとしても、何かが見てるんじゃないかと。それって、もしかしたら、動物とかお天道様とか、そういうのと境が薄いというのか。日本人に関する限り、古典を読んでも今の人を見ても、何だかいろんなものの境が薄いという気がしてならないんですけどね。
石川:それはおもしろいですね!
大塚:動物なんかもすごく擬人化して扱ったり、人間ときっぱり分けないというんですかね。西洋の人なんかは、動物が寝たきりになったりすると、あんまり延命措置などせずに安楽死させたりするとか聞くんですけれど、日本人はそういう感じはないですもんね。動物の命と人間の命の境も薄いような。
石川:境が薄いというか、間が絶妙というか、これに関する本って書かれたことはありますか?
大塚:ないです。
石川:書かれてたら読んでみたいなあと思って(笑)
大塚:ジェンダーの本を頼まれて書いていて、ジェンダーから見ても、前近代の日本は意外と境が薄いところがあったなというのは感じています。それが、ことジェンダーに限らないなということは思っています。
大塚「光源氏は何もかも得て“欲しいものは手に入らなかった”と嘆き、最後のヒロイン浮舟は親子男女のしがらみから離れて気持ちが晴れやかになっているんです」
石川:今、世の中はダイバーシティ(多様性)っていわれるじゃないですか。ダイバーシティって、前提の思想が「人って違うよね」っていう、違いから入っているというか。違うからそれを認め合おうよということなんですけれど。だから、ダイバーシティをやればやるほど、違いに着目しやすくなる。そういう無意識の大きな流れが、つくられちゃうと思っているんですね。
ウェルビーイングって「ヒューマンビーイング」っていうことで、「人って何か似たところがあるよね」っていう。昔の日本人も今の日本人も何か似たところがあるよねとか、共通項から入っていこうという活動なので。さっきの即レスはダメだよとか、間のとり方みたいなところで、昔も今も似てるなと思うようなことはあったりしますか? 「境がないよね」みたいなことが。たぶん、今もそうなんじゃないですか?
大塚:境があまりないというのは、親子関係とかもそうですね。今は減ってるかもしれないけど、親子心中とかあるじゃないですか。それはやっぱり子どもと自分を同一視していることだと思うんです。源氏物語でも、子と自分の同一視というのが終わりにいくほど激しくて、最後の『宇治十帖』で、中将の君っていう八の宮のお手つき、女房だった人が出てくるんですけど、その人の、八の宮、皇族の種の浮舟という娘への期待感というのがものすごい。「この子にだけは幸せな道を」ということで、最初は「自分の二の舞にならないように」と、大貴族の薫から人づてにオファーが来ても本気にしないでいたんですが、実際に薫とか匂(におうみや)といった上流社会の人たちを目の当たりにすると「この子だけは、上流で生きてほしい」みたいになる。でも、「この子だけは」と思いつつ、実はすごく重ねているんですよ、自分と。自分ができなかったこと全部子に託して。それで浮舟を薫に任せることにするんですが、浮舟は薫というパトロンがいながら、匂宮ともセックスしてしまう。それで挙句の果てには自殺を図るのですが、その理由は二人の男の板挟みになって、とよく言われるんですけど、よく読んでみるとそうじゃなくて、きっかけはお母さんです。「お母さんにこんなことが知れたら」ってところなんですよ。パトロンの薫がとうとう妻のひとりにしてくれるということで、ほんとうにいい結婚ができるとお母さんが来るわけなんですよ。それで元同僚と話していて、「もし、この子がよからぬことをしでかしたら、ほんとにどんなにかわいい娘であっても私は娘と二度と会わない」と言う。この辺、すごく複雑な関係もあって……匂宮は浮舟の異母姉の中の君の夫でもあって、色好みで有名で、元同僚は匂宮と浮舟の関係を疑ってカマをかけた。母はそれに答えたのですが、それを娘の浮舟は聞いて「自分が匂宮とも関係していることが母親にバレたら、もう自分は生きていけない」と思い詰めて自殺未遂しちゃう。
※薫……源氏物語の『宇治十帖』に登場する中心人物のひとり。生まれつき体から芳香を帯びていたことからこの名で呼ばれる。光源氏の次男だが、実は母・女三宮と柏木の子である可能性が高い。
※匂宮……光源氏の外孫。浮舟が薫の恋人と知りながら薫を装って浮舟を犯し、浮舟の苦悩の原因をつくる。
石川:宇治川に入水して。
大塚:で、最後、それこそウェルビーイングなんですけど、源氏物語って、ずっとその幸せの追求というか、源氏みたいに身分も顔も良くて、女もいてという人が、満ち足りない人生だったって言ってるんですよ。お金もあり、地位も得たけど、振り返ってみると、満ち足りない人生だったっていう、そんな人が多いんだけど、浮舟はお母さんの身分も低く田舎育ちですが、自殺未遂したところをお坊さんに救われて、誰も知らないところで擬似家族のような中で生きて、出家しちゃうんです。その時、これで世間並の生活をしなければと思わなくてすむようになった、それが本当にすばらしい、”胸のあきたる心地“がしたって、それこそ蜻蛉日記と同じ表現なんですけど、胸がスッとして嬉しい。そんなふうに歴代のヒロインの中で初めて感じている。だから、お母さん、家族関係を離れ、男女関係を離れ、すべてのしがらみから抜けたところで、すごく自他の境の薄いところからバーンと抜けたところで一つの幸せを感じていますね。
石川:いろんなものを手に入れてきた源氏は満ち足りなくて、いろんなものを手放した浮舟のほうがスッとしたという。
大塚:そうなんです。それがほんとうに『源氏物語』っておもしろい。楽しいんですよね。しかも、さっきウェルビーイングはダイバーシティとは違うよというお話があったじゃないですか。源氏物語を読んでいると、違いっていうのは、つまり、自分はかけがえのない人間とかそういうことですよね。他とは違う。だけど『源氏物語』を読んでいると、とくに女ですけれど、誰かの身代わりになっていて、他人にとっては……という条件付きで見ると、かけがえのない人間なんていないんだってことが、これでもかこれでもかって出てくるんですよ。源氏の父親の桐壺帝は桐壺更衣っていう最愛の人を亡くして、藤壺っていうそっくりな女性を得て、悲しみがまぎれるわけじゃないんだけど、なんとなく心がなぐさめられる。源氏は、この藤壺という、お母さんに似た人を愛したけれども、父帝の中宮だから手に入れられなくて、そっくりの紫の上っていう藤壺の姪を手に入れて、プチ満足みたいな。なんかこう身代わりが次々に出てくるんですよ。
石川:確かにそうですね。
大塚:で、最後のヒロインの浮舟も、実は大君というもっと高貴な母親を持つ姉の身代わりなんですよ、パトロンの薫にとっては。身代わりにしたほうはそこそこ満足で、そこそこの満足なんだけど、最終的にものすごく幸せになってるかというと、何か満ち足りなさが残る。で、身代わりにされた女というのはもっと満ち足りなくて。紫の上なんかもそうなのですが。最後に身代わりにされた浮舟のてん末を見ると「なんだ、身代わりなんだから、代わりはいるんだ」と思えば、そこを飛び出せるってことかな、と。他人の期待になんか応えないですむっていうか、親の期待にも異性の期待にも、世間の期待にも。自分の身代わりがいくらでもいるなら、期待に応えなくてもいいんじゃないかみたいな(笑)。そういうのをひしひし感じるというか。
石川:『源氏物語』って、古典の中ではかなり特殊なんですかね?
大塚:私はすごく特殊な感じがするんですよね。特殊だし革命的な、当時の人はすごく驚いたんじゃないかなというぐらい、斬新な物語だったと思います。
石川:後年、大名家が嫁入り道具に持たせるぐらいですからね。
大塚:源氏物語以前の物語というのは、顔がいい人っていうのがいい役で、不細工な人は悪役っていうんで、ブスが出てきたら大金持ちの意地悪な人とか、そういう感じなんだけど、源氏物語のブスというのは悪役じゃないですからね。そういう意味でもすごく画期的だし、すべてにおいて文学的実験というか、いろんなものに逆らっている。当時の価値観とか覆そうとしているような。
石川:そうですね。
大塚:でも、それが逆に、ものすごい人の共感を得たという。
石川:僕、本居宣長がすごく好きで。「大和心はもののあはれなんだ」っていう、その“益荒男振り(ますらおぶり)”じゃないんだと述べたのがすごくおもしろいなあと思っていまして。源氏物語はすごく特殊なんだろうなと思います。「かけがえのない」なんてないんだと。代わりはいるんだとかって、なんかもののあはれな感じがします(笑)
※本居宣長……江戸中期の国学者。30年あまりを費やして古事記の注釈書『古事記伝』を完成させた。源氏物語にみられる「もののあはれ」を日本固有の情緒で文学の本質であると唱え、外来的な儒教の教えを批判した。
※益荒男振り(ますらおぶり)……男性的で大らかな歌風。加茂真淵らの歌人が和歌の理想とし、万葉集にこの歌風があるとした。反語は手弱女振り(たをためぶり)。
大塚:身代わりの人がいっぱい出てきますからね。
石川:手に入れても入れても満ち足りないから、手放しなさいとか。
大塚:光源氏なんかいろんなものに恵まれて、最後、太上天皇(上皇)に准じる地位まで手に入れたのに、「自分の人生は欲しいものだけが得られない人生だった」みたいな感じの考えを得て。
石川:そうですね。だから「もののあはれ」はほんとうにいろんな人との関係性から生まれてくる、間から生まれてくるしみじみとした情緒みたいなことで。
大塚:大和心という話が出ましたが、文献上の大和魂の初出は『源氏物語』なんですよ、実は。のちのイメージと全然違う意味で“実用的な実務能力”の意味なんです。それは中国由来の学識と対になる言葉で、そのような学問をもととしてこそ大和魂がいかされると言っているんです。大和魂は実務的な才能っていう意味だから、本居宣長とか、江戸中期以降の人のところから、現代人がちょっと誤解しているところはあるような気がするんですね。
石川:なるほどね。
大塚:源氏物語って完全なエンタメだから、ちょっと書けるとすぐに持って行って、宮廷でみんなが読む。連載小説みたいな、連ドラみたいな感じで楽しんでいたと思うし。
石川:NHKの朝ドラみたいな感じ(笑)
大塚:当時の人はそういう感じで楽しみにしていた。後世の人はもののあはれとか、いろんな意味づけをしたけれど、当時の人にとってはエンタメだし、実際、読んでみるとほんとにエンタメです。数百年とか千年残っているものはおもしろいし、それこそウェルビーイング的にいっても、実はお金じゃないということを書いています。ほんとに当たり外れが少ないから私、子どもの頃から古典とマンガばかりで(笑)。
石川:お気に入りのマンガは?
大塚:『ハッピーマニア』とか。
石川:あ、あれおもしろいですよね! 安野モヨコさんですか。いまその続きである、「後ハッピーマニア」やってますもんね。このままマンガ談議に行きたいところですが、なんと時間ですか。はい、それにしても、今日は楽しかったです。どうもありがとうございました。ぜひまたお願いします!
大塚:とても楽しかったです。ありがとうございます。
次回予告:大塚ひかりさんとの対談を聞いた編集部、スタッフが「話を聞いてどう思ったか、何かが変わったか」を石川善樹さんと話し合う振り返り対談です。どうぞお楽しみに!