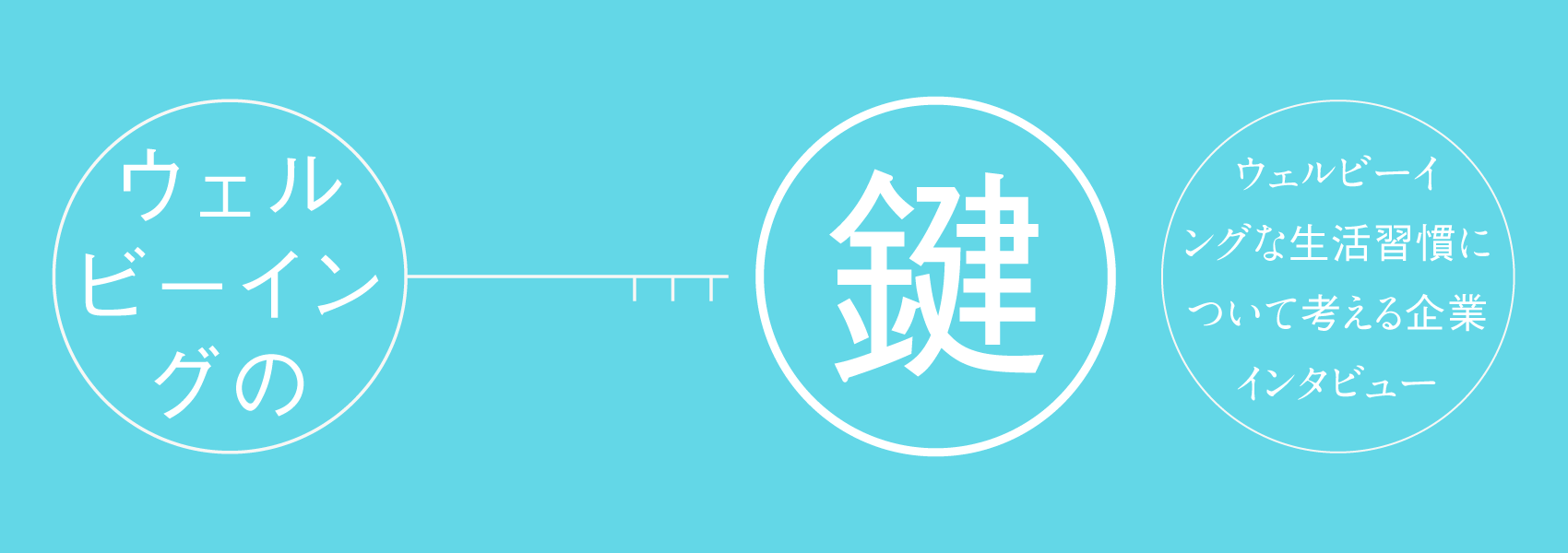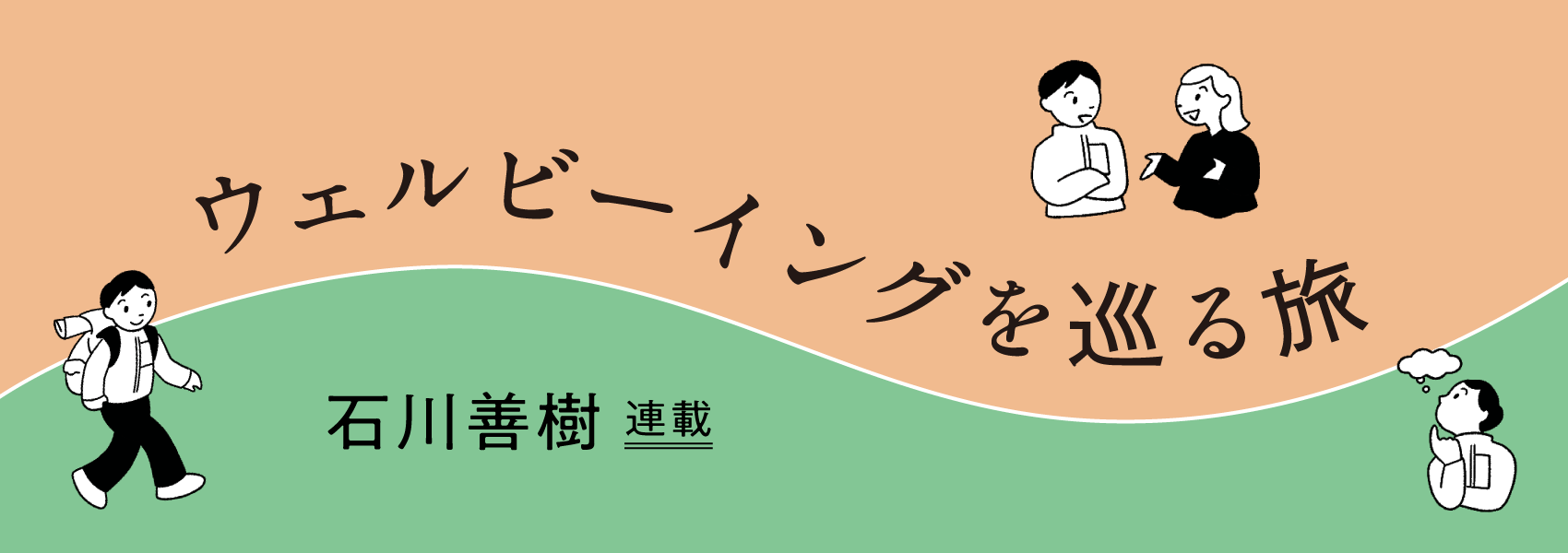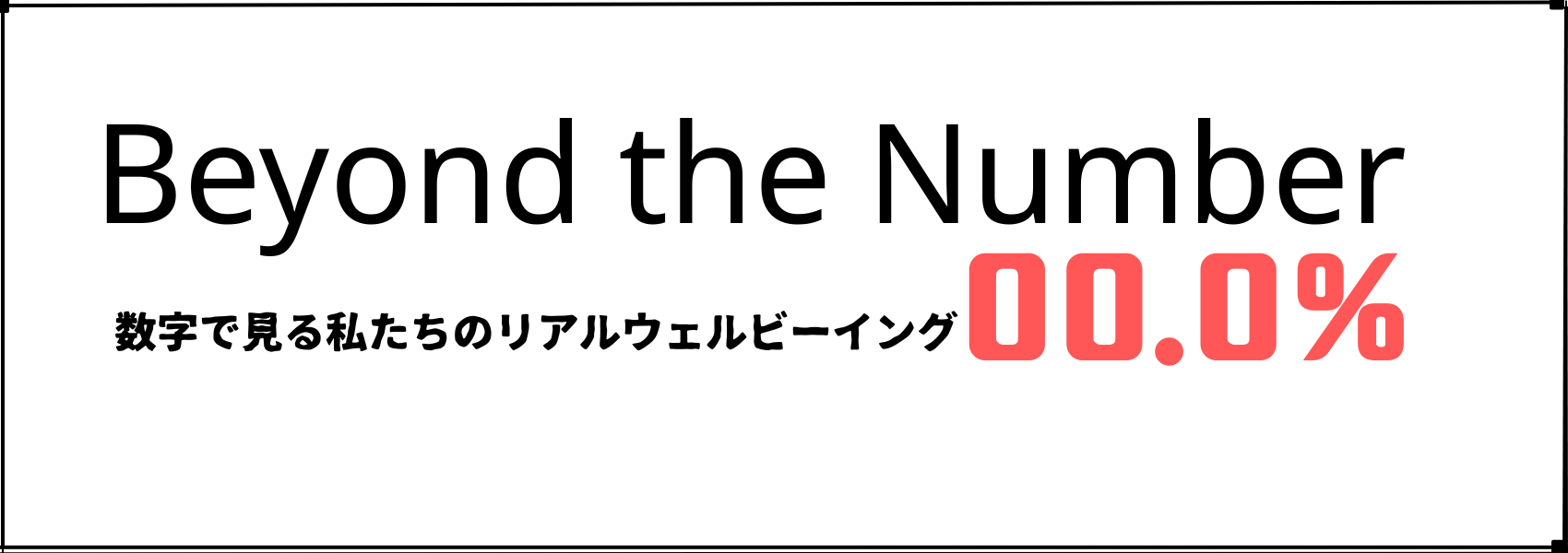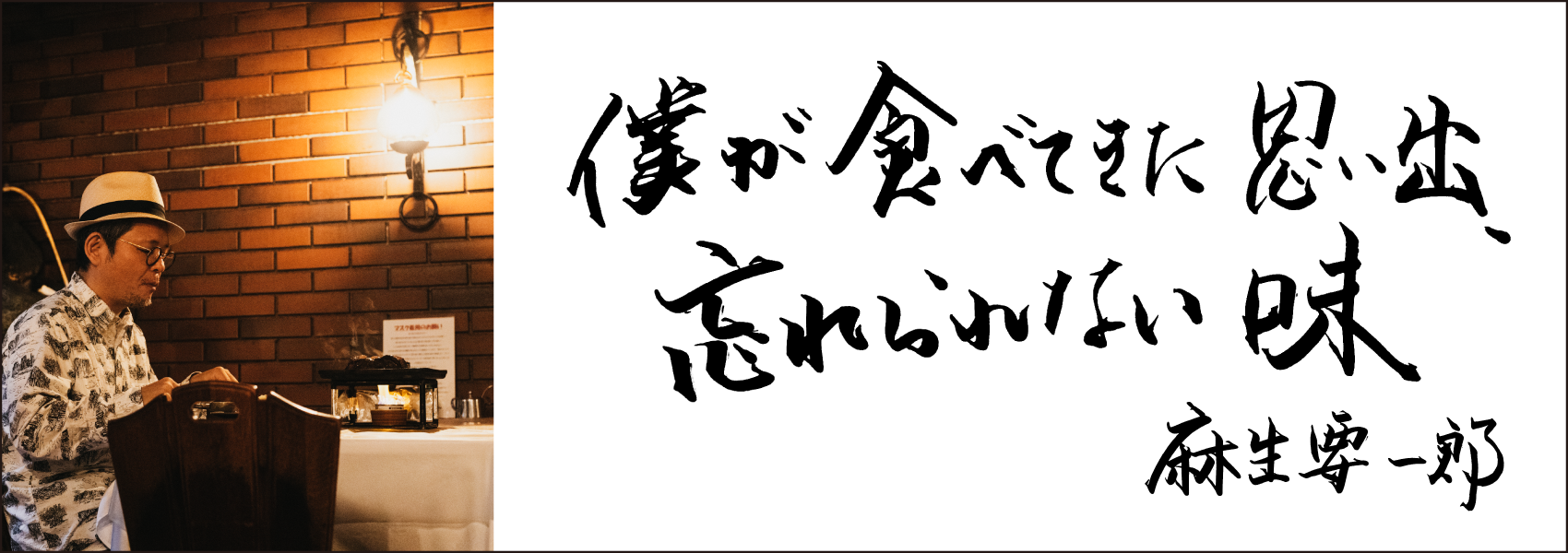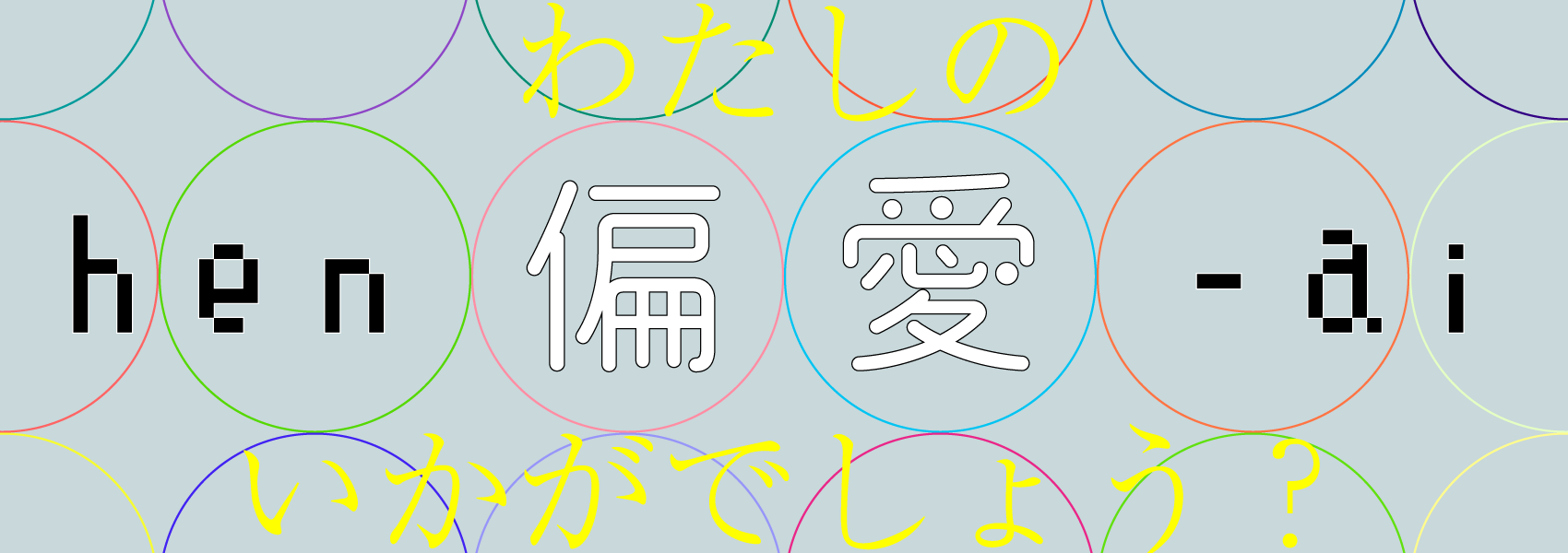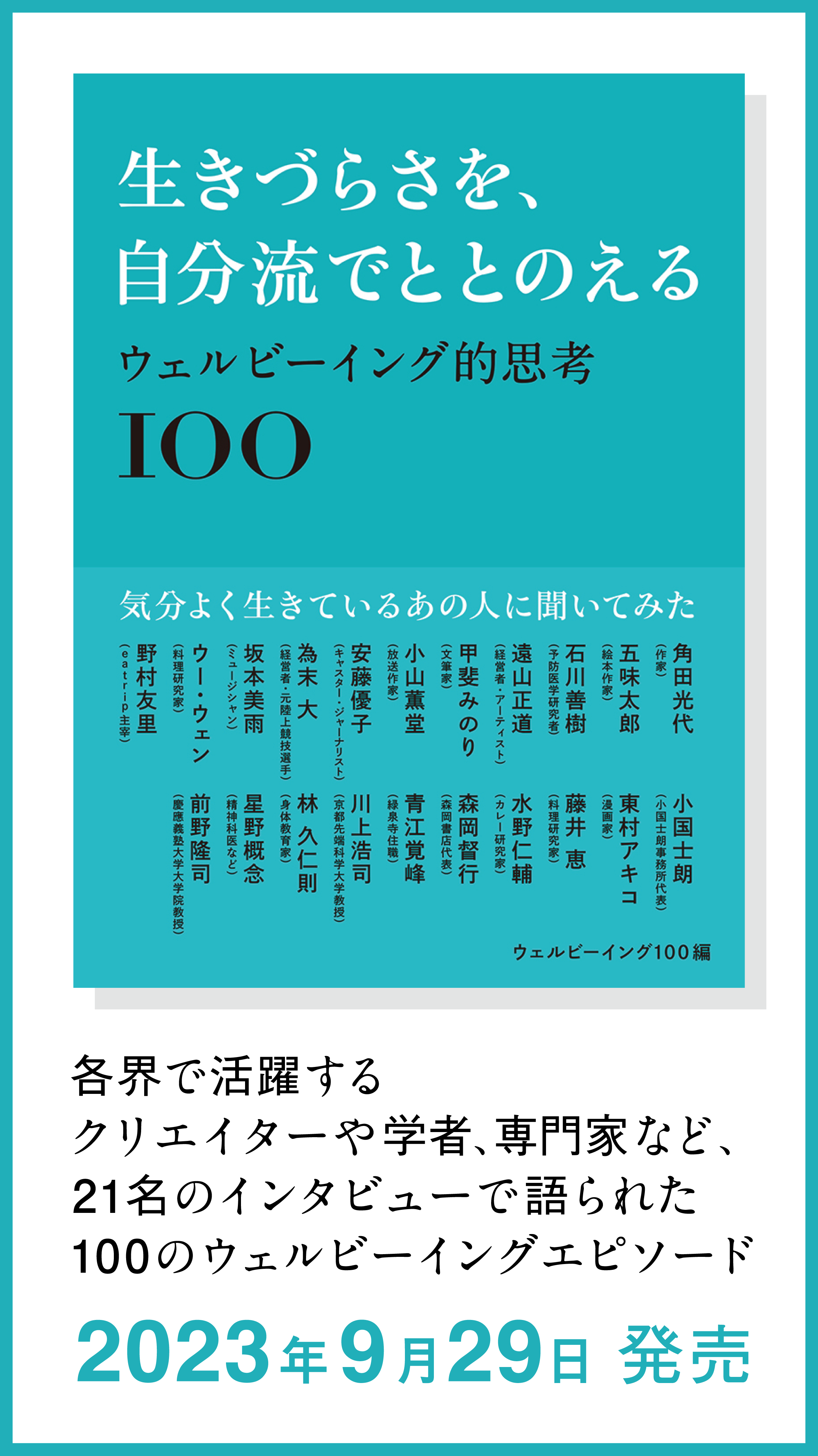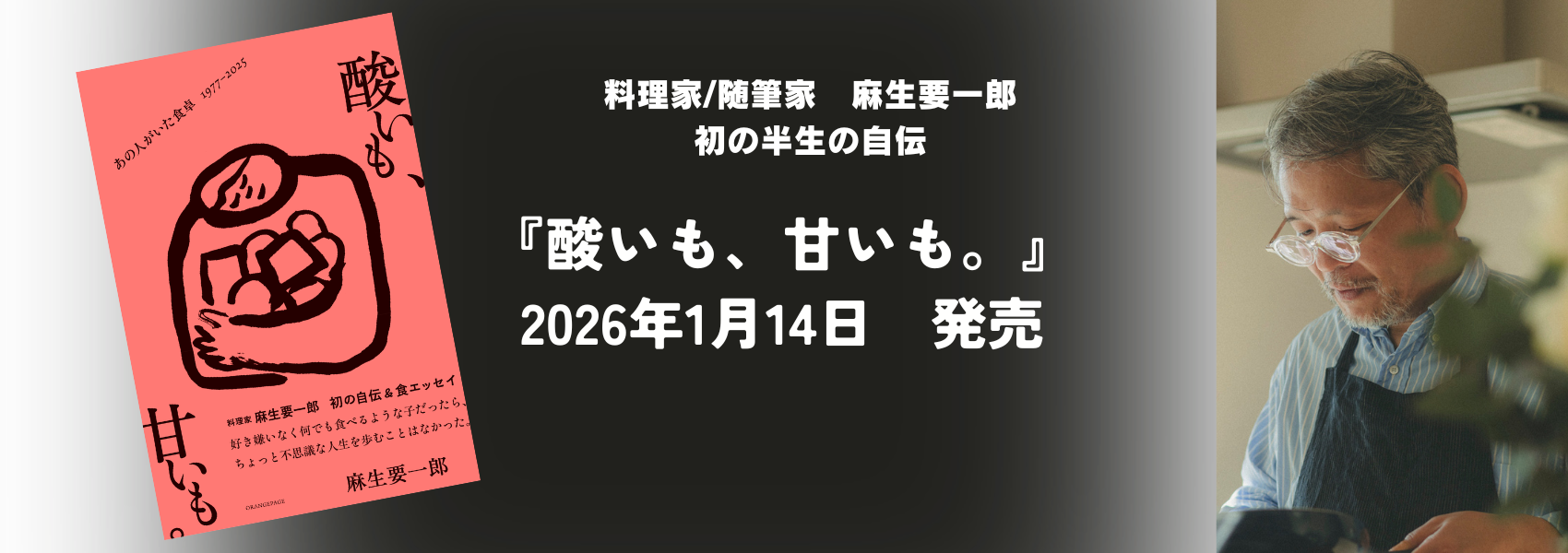これまでになかった視点や気づきを学ぶ『ウェルビーイング100大学 公開インタビュー』。第8回は、ジャーナリスト・キャスターの安藤優子さんです。認知症のお母様を介護された経験から語られた言葉は、すでに介護を終えた人、いつかは介護と向き合うかもしれないと考えている人の両方に深く響くものでした。
聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100 byオレンジページ編集長:前田洋子
撮影/原 幹和
文/中川和子

社交的だった母親が引きこもるようになった“異変”
酒井:安藤さんは16年にわたって認知症のお母様の介護をご経験されたということなんですが、最初にお母様の異変に気づかれたきっかけは?
安藤:今、16年というお話をしていただきましたが、正確に言うと、母がホームに入ってからの7年と、その前の3年の10年間ぐらいなんですが、母の異変に気づいたのは、それよりもけっこう前だったんです。
前田:すぐに気づかれたのですか?
安藤:母が亡くなったのが89歳だったので、73か74ぐらい、70代の前半にすごく落ち込むことが多くなったんです。当時、母は父とふたりでマンションの8階に住んでいたのですが、ベランダに飛び出して「死んでやる! 飛び降りてやる!」みたいなことを言ったんだそうです。実際には柵を乗り越えられなかったのですが、父はそれを見ていて「ほんとうにゾッとした」と言っていて。その頃から徐々に徐々に変化がありました。
酒井:それで何かおかしいと思われたわけですか?
安藤:思い返してみると、あれは母が年齢を重ねていくうえでの、老人性うつの始まりだったと今では理解しているんですけれど。そのとき、家族としてすぐに心療内科に連れて行って「うちの母、ちょっとおかしいんですけれど」というふうにはいたらなかったわけですよね。何が母をそういうふうにさせているのかについて、理解もできなければ納得もできないので、何をすべきかというのはたった1回の「飛び降りてやる!」の発言だけでは対処のしようがないですね。どこに連れて行っていいか、今みたいにもの忘れ外来とか、認知症のための外来が整備されている時代とはちょっとまた違いますので、母をどこに連れていくべきなのか、また、どういう予兆として捉えるべきなのかについては、私の知識が足りなさすぎたと思いますね。ただ、そのあたりから「あれ? あれ?」ということがいくつか重なっていきました。
酒井:お母様はどんな方だったのですか?
安藤:それまではアクティブにやれヨガだとか、ジムだとか、水泳だとか、とにかく他人がやっていておもしろそうなことは、何にでも首を突っ込むような、ものすごく社交的で活動的な人で、好奇心まる出しというか、全開の人でした。その母が水着に着替えるのも億劫、人に会って何かお話しするのも億劫みたいになってきて、どんどん家に引きこもるようになると体重も増えるし、膝も痛くなるということで。あるとき玄関でころんで、父が助け起こせなかったんですよ。で、そのまま玄関に一晩放置してしまって。次の日の朝に、うちの姉のところに電話があって。姉はびっくりして「すぐに救急車を呼んで」ということで、呼んだんですけれど、ストレッチャーが上げられなくて、そうしたらハシゴ車まで来てしまって。病院に運ばれて、幸いケガはなかったんですが、それが大正生まれの母にしてみれば、自分はただころんだだけなのに、ハシゴ車が来て救急車が来て、世間体が悪いわけです。そこで自分が恥ずかしくて恥ずかしくて、ご近所に合わせる顔がないというので、その日から、自分のベッドのある部屋に引きこもりが始まったんです。私たち娘にも口をきいてくれないし、ひとことも喋らないんです。
酒井:おケガがなくてよかったですけれど、心のほうにダメージが。
安藤:とにかく引きこもり状態になって。それを見たときに「これはおかしい」ということで、知り合いの高齢者施設と病院を経営している理事長先生に電話をしてうかがったら「もしかしたら甲状腺の問題かもしれない」と言われたんです。でも、病院に連れて行こうにも、頑として動かない。自分はどこもおかしくないと思っているわけですから。「こんなふうに大騒ぎをしたあんたたちが悪い。そんなあんたたちの言うことなんか聞くもんか!」というふうになって。そこから認知症の傾向は続きましたね。

変わっていく母、父のがん、仕事、そして「自分が気持ちいい」時間を作ることの効果
酒井:それまでのお母様と安藤さんの関係性は?
安藤:母は旅行も大好きですし、一緒にハワイに行ったり、イタリアに行ったり。犬がいるので父は留守番で、母と姉と一緒に毎年、旅行したり。私は3人きょうだいの末っ子ということもあって、割合、小さいときから母にくっついて育ちました。すごくベタベタしていたわけじゃないですけど、極めて仲はよかったと思います。
酒井:お母様にそういう症状がみられるようになって「まさか自分の母親が」という安藤さん自身のショックは?
安藤:どなたでもそうだと思うんですが、親ってずっと自分を育ててくれる存在じゃないですか。つまり、どちらかと言うと、自分を包み込んでくれて、どんなときでも頼れるのが親っていう、子どもにしてみれば甘ったれた部分があるわけですよね。その母がだんだん自分の知らない母親のような、簡単に言うと幼児退行していくわけです。そうすると「今まで私を育ててくれた母は、どうしてこんなふうになってしまったんだろう?」っていう、やっぱり最初は受け入れることが難しかったというか、できれば受け入れたくない。そんな母を見たこともなかったし、とてもじゃないけれど、今までの母とのギャップがありすぎて、受け入れられないという気持ちのほうが強かったですね。
酒井:逆にお母様のほうも受け入れられない?
安藤:母にしてみれば、自分はこれまでと同じなんですよ。なのに「あんたたちはどうして私に対してそういう態度を取るの?」というのが、たぶん母の言い分だったと思うんです。「変わったのは自分じゃなくてまわり」というのが母に見えている風景、景色だったと思うんです。だから母にとってみれば、それは受け入れ難い。「こんなに一生懸命育ててきた娘や息子がなんでこんな偉そうにしてるの?」っていう感じを受けたんじゃないかと思います。
酒井:その頃、安藤さん、お仕事もかなり大変な時期だったそうで。
安藤:そうですね。年間170日とか海外出張していたときと重なっていましたので。ただでさえ東京にいる時間が短いのに、私の時間なんてないのねという生活でした。月曜から金曜までは生放送がありますから、金曜の夜から実家に泊まりに行って、できれば日曜の昼間は自分のところに戻ってきて、仕事に備えるという感じだったんですが、土日でもテレビ局に呼ばれることはしょっちゅうだったので、それをやりくりするというのは、今だから言いますけれど、物理的にも精神的にもけっこうしんどかったですね。
前田:それはしんどかったでしょうね。
酒井:そういうとき、安藤さん、セルフケアはどうされていましたか?
安藤:母がそういうふうに「おかしいなあ」ということになった矢先に、父のがんが見つかったんです。それで入退院を繰り返す。そのあたりから母も当然、おかしくなりますよね。父の闘病は半年で終わったんですが、毎日、夕方のニュースが終わると、父の病院に1時間半くらいかけて行って、父が寝る頃までいて、家に戻って11時12時だったんです。それを毎日やってたんですよ。それで土日は母のところで、もうボロボロになっちゃって。そのときに何をしたかというと、私っぽいんですけれど、すごくトレーニングをしたんです。朝の6時半くらいから。わざとやったんです。そこで「私、もうダメだ」みたいになっちゃうと、ほんとにダメになっちゃいそうで。トレーナーについて早朝から朝の時間帯を有効に使うようにして、トレーニングをやったあとにエステに行ったり。とにかく朝の時間は自分のためだけに使うっていうふうにして、テレビのオンエアが終わったら父のところに行く。で、帰って寝る。早朝起きる、みたいな。
酒井:フィジカルに働きかける方向だったんですね。
安藤:どうしてそんなふうにしたかと言うと、運動するとほんとうに自分の中に、心に風が吹くように、すごく気持ちよかったんです。単純にそれだけなんです。「はあー、気持ちいい」っていう時間を自分で持ちたかったので。それで私は積極的にトレーニングをするようにしました。もちろん、運動嫌いの方もいらっしゃるし、他のことでセルフケアをされるのもいいと思うんですが、私の場合に限って言うと、運動したときの気持ちのよさって理屈じゃないんですよ。
前田:そうです、そうです。私も経験があります。
安藤:その気持ちのよさを知ってしまうと、もうそこに頼るところを見つけるというか。体に余分な脂肪がつかなくなってくると、自分の心も余計なものが削ぎ落とされる感じがして。とにかく運動しているときは、あんまりいろいろなことを考えないですむので。父が秋から闘病して、2月に亡くなるんですが、その年の年明け、元日から3日間、ずっとトレーニングしてました。
前田:わかります。
安藤:なんだかわからないんですけれど、つらすぎて。父が闘病でいちばん大変なときは、私、お風呂にも入れないんです、父に悪くて。「あんなにつらい想いをしている父がいるのに、私がお風呂に入って気持ちよくなっていいんだろうか」ぐらいになって。どんどんそういう思考回路になっていっちゃう。だからこそ、運動して自分を解放するってことを心がけました。

心を鬼にして嫌がる母親をホームへ
酒井:お母様もなかなか病院に行ってくれないという状況で。
安藤:結局、ホームに入るまでは病院に行かなかったです。
酒井:でも、それでよくホームに入ることを受け入れられましたね。
安藤:いや、全然ですよ。父が入退院を繰り返しているあいだは、私たちも父の面倒を見たりするので、母にかかりっきりにはなれないので、ヘルパーさんに来てもらったりしたんです。ところが、とにかく他人に自分の牙城を荒らされるというのが我慢ならないんですよ。自分がキッチンに立って料理ができるわけじゃないのに、勝手にさわられるのはイヤで、そういう人は敵。だから、勝手にヘルパーさんをやめさせちゃう。父が亡くなって、犬と自分が取り残されて、そこらへんからそういうのがエスカレートしていくわけですね。被害妄想があって、他者に対して攻撃的になったり、お金をとられたとか、靴がなくなったとか。まったくそんなことはないんですよ。誰かを犯人に仕立てて、母の中にストーリーができちゃうわけです。
酒井:そういうことがあるんですね。
安藤:それを聞かされるこっちもつらいですし。それこそ家に遊びにきた人たちはみんなウェルカムで、ごはん食べていきなさいって一生懸命ごはんを作ってもてなすのが大好きだった母が、人を疑ったり、人を否定したりする人間になってしまったと思うと、悲しくて悲しくて。「私の母親はこんな人間ではなかったはずだ」っていうのがいちばんつらいときでしたね。病気のせいだっていうことが、私たちもまだはっきりわかっていなくて。ただ、たとえあのとき「これは病気が言わせている」と言われても、そんな簡単に受け入れられるようなものではなかったと思いますが、それにしても、認知症であるということがきちんと診断がつくのは、母がホームに入って、併設されたクリニックで診ていただいてからです。
酒井:お母様はすぐにホームでの生活になじまれましたか?
安藤:いえいえ、脱走したりして大変でした。激昂して、私たちに「こんな仕打ちをして!」と言って帰りたがる母を見ると「マンションの水道が壊れたから」という嘘をついてまでホームに連れてきたことはそもそも間違っていたんじゃないかと思い始めました。で、姉と話をして「だったら、もう私が母と一緒に暮らすよ」と言いました。姉はそのときはもう、ご主人のお姑さんも一緒に住んでいましたから、姉は無理ということもあって「じゃあ、私が一緒に暮らす」って言ったら、うちのお手伝いさん(看護師だった方)にすごく怒られたんです。「優子さん、一時的な感情でそういうことを言うけれども、真夜中はどうするんですか? 優子さんが海外に行っているとき、誰が来てくれるんですか? 昼間は私が来ますけど、夜中は優子さんひとりですよ。トイレの世話とか、いちいち話しかけられて眠れないですよ。どうするんですか? どうやって仕事をするんですか?」って。「一時的な感情でそういうことを言うことが、お母さんを結局苦しめて、優子さんも苦しむことになるから、そういうことを言うのはよくない!」と。そこで、少し冷静になって。「母と暮らす」と言ってはみたものの、現実としての計画もなければ、戦略もないわけですよ。ただ、一時的な感情にまかせて言っちゃったってところで、よく考えてみれば、お手伝いさんの言ったことのほうが正しいわけですよ。そこから、とにかく心を鬼にして「母にホームに慣れてもらおう」というふうになりました。

酒井:そこはなかなか論理的になれないというか、感情的になってしまいますよね。
安藤:なりますね。特に泣かれたりすると。あと「電話をかけろ」ってホームの方にすごくしつこいわけですよ。ホームの方が、電話線がつながっていない電話を渡したりするんですけれど「バカにしてんのか!」みたいになっちゃうわけです。「今、優子さんに電話したけど、優子さんお留守みたい」って言うと、携帯に電話しろって言うし、私がいなければ姉に電話する。姉がいなければまた私に電話しろって言う、繰り返しなわけじゃないですか。だから、そういうこともあって、慣れるまではそれなりの年月というか時間を要しましたね。
酒井:そこをどうやって乗り越えられたんでしょう?
安藤:たぶん日薬だと思うんですよ。母はホームの方たちに、自分が気にそぐわない介護をされるっていうこと、介護されるってこと事体が気に食わないわけです。自分はそんなんじゃないと思っているわけですから。もう介護される側だということ事体が許せない。母は入居した当時は太っていたので、入浴時は力のある男性の介護士さんに介助されてたんです。男性に入浴の介助をされるなんて、母にしてみれば屈辱以外の何ものでもなくて、屈辱地獄みたいなものなんです。だからその介護士さんを手で払ったりつねったり「訴えてやる」と言ったりとか、日々その繰り返し。それでも介護士さんたちが、母に「みどりさん」って話しかけてくれて。母の硬直した心を少しでも解きほぐすように、母の若いときの話を聞いてくださったりして、とにかく日々の信頼関係を築いていただいたことがすごく大きかったと思います。
酒井:介護士さんたちはすごいですね。
安藤:私は、あのときの介護士さんたちの奮闘ぶりというか、それを見せていただいて、あの方たちの、ある意味善意にすがりついているところがいっぱいあるわけじゃないですか。私はあれはほんとうに、日本の介護の限界だと思いますね。いちばん大変な仕事で、しかも、保育士さんの待遇の話もすごく問題になりますけど、介護士さんというのは、終末期を見取るっていう、精神的にもすごくつらいものをお持ちなわけですね。「これから成長していく」ではなくて「これから人生を閉じていく」っていう、イヤでも死と直面しなくてはいけないお仕事でいらっしゃるわけですよね。そういうしぼんでいく、閉じていく人生に立ち合うっていうことを、日々自分たちの仕事の宿命として、自分たちを鼓舞しながら頑張っていらっしゃるわけですよね。でも、なかにはうちの母みたいなのもいるわけじゃないですか。あの方たちの善意に、もうすがりついて日本の介護って成り立っている現状を目の当たりにして、そういう介護士さんたちが、3Kみたいな仕事だっていうふうな認識が社会の中にあるってことは、極端に間違っていますよね。私は、終末期を見取ることを余儀なくされる介護士さんたちこそいちばん尊敬を集めるべきだし、私たちが感謝すべき存在だと思うんです。でなければ、やってられないって思いますよね。ちょっと話が脱線しましたけど。

「否定」が「肯定」に変わると介護する側、される側の関係が変わる
酒井:お母様とのあいだに変化が生まれた“臨床美術”のお話を伺いたいのですが。
安藤:臨床美術、日本発の回想療法のひとつなんです。簡単に言うと“臨床美術士”という資格を持った方。臨床美術協会というところがあって、日本でつくられた回想療法で、セラピーなんですね。これは何かというと、たとえば、母が指導していただいたのは、題材があるんですね。何でもいいんです。お正月だったらクワイ。お節料理によく入っているクワイ。臨床美術士さんがクワイをお持ちになって、母と、そのクワイにまつわる母の記憶を聞き出すようなお話をされるんです。クワイといえばお正月料理だから、たとえばお正月にまつわる、♪もういくつ寝るとお正月♪みたいな歌を聴いたりとかして、ちょっと窓を開けて「ずいぶん寒くなってきましたね。もうすぐお正月ですね」っていう話をして「じゃあみどりさんのお正月、クワイはどんなふうにして食べたんですか」とか。そんなにたくさん話はできないんですけれども、特にそのクワイそのものを描くのではなくて、母にとってのクワイの周辺の思い出を最後の10分間ぐらいで絵にするんですよ。ごめんなさい、説明がうまくなくて。
酒井:いえ、わかります。
安藤:たとえば、ハワイっていう題材があるとすると、アンスリウムの花を1輪、美術士さんが持ってきてくださるんですね。母はハワイが大好きなので、そういう話も臨床美術士さんは先に知っていらっしゃって。母のお部屋にたくさんハワイアンキルトのクッションとかあるので、ハワイの思い出をそのキルトで引き出そうとしたり、あとハワイアンの音楽を流してくださったりして、なんとなくハワイにいるような気持ちにさせながら、最後の10分間で、母はその目の前にあるアンスリウムに、ハワイへの想いを託して描くんですよ。
一同:なるほど。
安藤:でも、不思議なぐらい、ものすごくアンスリウムをちゃんと描くんです。そのアンスリウムが素晴らしい絵で。私が言うのもなんなんですが。それを見たときに母が「よ・く・で・き・た」っていうふうに声を絞り出して、自分を自己評価したんです。自己肯定っていうんですか。その自己肯定をしたアンスリウムの作品があまりにもステキだったので、私はその絵を集めて「よく、デ・キ・タ!」っていう個展を代官山のギャラリーで開いたんですが。なんでそんなことをしたかっていうと、その「よ・く・で・き・た」って母が自己肯定をした絵には、ものすごく明るい、真っ赤なアンスリウムに黄色とかグリーンとかでキレイな、すごく骨太でおおらかで、明るい母そのものの色使いがあって。まさに「母はどこに行っちゃったんだろう?」と思っていた私に「ここにいるじゃない。私はここにいるのよ」って言っているかのような絵だったんです。ですから、私は「なんだ、母って実はなんら変わっていないんだ」っていうことをそこで確認することができた。なおかつ母も「よ・く・で・き・た」って言ったときに自己肯定をすることができた。なにしろそれまで自己否定の嵐だったわけです。

前田:そうですよね。自分の思うようにならないことばかりで。
安藤:旅行も行けない、買い物も行けない、人とも話せない、電話もできない、自分で好きなものを食べられないっていう。そういう自己否定の嵐の中で、その自己否定が彼女にとっては怒りだったわけです。それが私たちに向けられ、ヘルパーさんに向けられ、介護士さんに向けられてきたわけですよね。でも、自己肯定をしたことによって、もうびっくりするぐらい母が穏やかになったんです。ほんとうに。最初はやる気のない、いたずら書きみたいな絵だったんですが、臨床美術士さんが母の気持ちを聞いてくださって回想療法をしていくうちに、母なりの想いみたいなのがあふれて出てきたんじゃないですかね。あれで、自分で「よくできた」って自己肯定をしたところから、母はほんとうに変わりました。
酒井:社交的で好奇心旺盛だった頃のお母様がそこにいるということを確認されて、安藤さんの心も変わりましたか?
安藤:私はものすごく楽になりました。それまで母は自己否定をしてたと思うんですよ。だけど、同時に私も母を否定していたわけじゃないですか。
前田:ああ、そうですね。
安藤:だから、お互いに否定的だった。それがその絵を見たときに、お互いに肯定することができて、私も母をもう一度受け入れるというか「なんだ、そこにいるじゃないか、変わらない! 母は」っていう。たとえ認知症になっても、母の本質って何ら変わらないのですよ。つまり認知症になるっていうことは、自分を表現できなくなることがいっぱい出てくるということなんです。
酒井:ああ、なるほど。
安藤:今日は何月何日で、あなたは誰で、私はこうしたいっていう、意志を伝えることもだんだんできなくなる。私は何が食べたいです、って食べたいものも食べられなくなる。あそこに行きたいですって言って、歩くこともままならない。だけれども、そういう表現とか行動容態は変わっても、その人の本質にあるものまでは認知症は奪わないんです。それを私は、その母の絵を見て気づいたっていうか。ちょっと遅かったですけど、気づいて、母の中心にあるおおらかさとか、明るさとか、温かさって変わっていないんだっていうことを知ったことによって、私はすごく解放されたというか、許されたというか。
酒井:認知症に対する認識が、今、変わりました。
安藤:絶対いますよ、そのまんまの親が。それはこっちの見る目も違っているし、お母さん自体もそう見られていることに対して「私は、ただ表現できないだけなのに」っていう、もどかしさ。「私は変わってないのよ」って母は思っているってさっき申し上げましたけど、ほんとに変わってなかったんです。変わったって思ったのは私たちで、たぶんそれは鏡のようにお互いに映し合っていたんですね。
前田:合わせ鏡だったと。
安藤:「あの母はどこにいっちゃったんだろう?」と思う私たちと「そんなふうに見えるの、私が?」っていう母が、お互いに鏡どうしで映し合っていたというか。そんな気がしますね。

「どう生きてほしいか」目的を決めて情報を取捨選択する
酒井:情報を発信する側にいらっしゃる安藤さんだから伺いたいんですが、自分が受け手側に立ったとき、どういうふうに情報を取捨選択していかれたんでしょうか?
安藤:母の認知症、進行をおさえることはできないので、対処療法として、いくつかお薬を服用していたわけですよね。それで、攻撃性を抑える薬で、常にウトウトして嚥下がしにくい状態になる薬があったんです。薬の効能や副作用には個人差があるので、一概には言えないのですが、クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)という点で、ただ生きていてほしいのか、それとも母らしくいてほしいのかというところをすごく考えたんです。
ウトウト状態で咀しゃくもままならない状態でただ座っていてほしいのか、それとも喜怒哀楽があって、好きなものを最後まで食べられる母でいてほしいのかということをすごく考えて、薬について徹底的に調べました。もちろん、薬をやめる選択は主治医にも相談をしたうえで、決断したんですが「この薬をやめると、もう一度暴力的になるかもしれません」と言われ、そのときはホームを退所させられるかもしれないというリスクもあったんです。でも、私はやっぱり母らしく生きる時間をまっとうしてほしいという気持ちのほうがまさってしまって、姉とも相談して、その薬はちょっとやめていただいて。「もし、母が攻撃的になってしまったあかつきには、わかりました。こちらで責任を取ります」という覚悟で薬をやめました。そういうことについてはすごく調べましたけれども、でもこれもほんとうに「どうありたいか」という「どういうふうに母にいてほしいか」ということの、その先にある情報の取捨選択なので。玉石混交って言うんですか。ほんとうにいろいろな情報が入り乱れていて、なかなか難しいと思うんですが、その先にあるゴールを見据えれば、自ずと拾わなくちゃいけない情報というのは飛び込んでくるのかなあという気はします。
前田:その先にある目的を見据えて取捨選択されたと。
安藤:うつらうつらの母ではなく、たまには「焼き芋食べたい!」みたいなことを言ってくれるぐらいの母がいいなっていう。最後の最後まで母は、朝ご飯を食べて、最後のひと口で心臓が止まったので。ほんとうにそういう意味では“ピンピンコロリ”の人でした。彼女なりの生き方を全うすることができたので、そこは彼女も納得してくれているんじゃないかと思いますし、私たちもすごく「母らしいよね」「うらやましいよね」と。痛いとか苦しいとかいうことをひとつも経験しないで老衰で逝ったので。そういう意味ではとても幸せだったと思います。
“忘れること”にもっと寛容になれば、みんなが楽になる
安藤:たぶん、母と私って似てるんですよ。姉よりも私のほうが似てるんじゃないかと思うんですが、だからこそ、母が認知症になったときに、ある種、壊れていく様を私は母に近い分、許せなかったんだと思うんですよ。自分の行く末を見るようで。でも、母が臨床美術で「自分はまだここにいるよ」ってことを示してくれたときに、世の中ってもうちょっと忘れることに対して寛容になるべきだってすごく思ったんです。よく話しかけるでしょ? 「みどりさん、おはようございます」「みどりさん、今日は何月何日ですか?」とか必要ないと思うんですよ。ほんとにみなさん頑張ってお声がけしてくださるんですが、私は母が大正から、昭和、平成と生きてきて、そこで戦争も経験して、うら若いおしゃれもしたかった時代にモンペ姿で動員されたりして、そういう少女から女性の時代を生きてきて、父と結婚して、父に仕えて私たち3人を育て、まあ言うに言われないお姑さんの苦労をしてという、頑張ってきて今があるわけじゃないですか。認知症になって、そういう浮世のことを忘れるのが何が悪いんだと思うわけですよ。もうこれは母に神様がくださったギフトですよね。もういいよって。今日が何月何日だろうが、娘が誰だっていいよって、そういう浮世のことをすべて放っておいて、お花畑のようなところでふんわりふんわり、自分のことだけ考えていいんだよっていうギフトの時間なんじゃないかって、私はすごく思ったんですね。
前田:ほんとにそうですね。
安藤:だから私は母に「今日は何月何日」とか、「私、だあれ?」って聞いたことないんですよ。忘れたっていいと思ってるんですね。忘れることに対して、ちょっと不寛容すぎる気がするんですよ。忘れたっていいじゃないですか。まあもちろん、母の場合は、それなりに年をとっていたということもありますし、若年性アルツハイマーになられる方とは、まったくケースは別ですけれども、少なくとも、私が母に対して何を学ばせてもらったかというと、よく生きて、人生の最後をよく生きるためにも、私は世の中が、認知症に対するネガティブな感じというか、ネガティブな感覚、意識を変えていかないとダメなんじゃないか。忘れたっていいじゃない。私が優子でも誰でも。みなさん、寂しいっておっしゃいますよね。自分のことを、子どものことを認識しないなんて。いや、わかってますって。ただ単に名前が出てこないだけなんです。わかってますよ。絶対わかってますよ、って私は思っているんです。だから、そういうことに対して社会全体も家族も、もうちょっと寛容になったほうがお互いに楽じゃないかなっていう気がすごくしましたね。
前田:その通りだと思います。
安藤:89にもなろう人間が、今日、何月何日か知ってたって、あんまり意味ない気がするんですよ。だから、いいんじゃないかって。もちろん、90過ぎてもかくしゃくとされている方、それはそれでまた人生、違う人生がおありだと思いますし。ただ、母の場合は、そうなったときに死ぬ前の3年間ぐらいはほんとうにお花畑にいるような感じがしていたってある方に言われたんです。それだったらすごくよかったなあっていう気がしますね。

以下、安藤さんがみなさんのご質問にお答えします。
Q:仕事との両立はどうでしたか?
安藤:私は仕事してるときは、ものすごく気が楽でした。いや、どこかにあるんですよ。「あ、今頃どうしてるだろう?」とかすごくあるんですけれど、でも、そこで放棄していくわけにいかないじゃないですか。実は母が亡くなった日も、普通に私、ニュースをやったんですね。
前田:ああ、そうだったんですか。
安藤:はい。母は、ニュースの会議の何時間か前に亡くなったので。母も私のスケジュールは頭に入っていたんじゃないかっていうぐらい、そのまま会議に行って、そのままニュース、生放送をやりました。父が亡くなったときも、そのまま病院からテレビ局に行って、生放送。それがいいか悪いかということではなくて、私にとってはそれが当たり前というか、やっぱりデイリーのニュースをやっている責任もありますし、見ていてくださる視聴者のみなさんもいらっしゃるので。
酒井:仕事との両立は悩ましいですね。
安藤:仕事は助けでもありましたね。だから、介護離職される方が今、潜在的にどれくらいいらっしゃるのかなあ? 20万人とかいう数字もありますけど、実際にはもっと多いんじゃないかという気もして。やっぱり介護離職っていうのは経済的な部分も含めて、決していいことじゃないんですよ。だから、それしか介護する手がないかもしれませんが、でも、やっぱり公的なサービスをお使いになるべきだし、だから国民皆保険があるわけですし、私たち保険料も納めてきて、そうやってきてるわけじゃないですか、介護保険の部分も。誰にはばかることなく、大手を振って使っていただきたいし、第三者に頼ることにちょっと罪悪感を感じる部分、そんな必要はまったくないので、大いばりで公的サービスを使ってほしいと思います。
Q:私の両親は70代でまだ元気ですが、先々のことを考えて、家族で早めに相談しておいたほうがいいことはあるでしょうか?
安藤:まだご両親がお元気でいらっしゃるならば、ご両親の体が弱ってきたときにどうしたいかという意志の確認というか。今のご両親はもう子どもには頼らないという方がいらっしゃるので、先々、体が弱ったときにどうしたいか、たとえば、ホームに行って子どもの世話になりたくないということであれば、家はどうするんだとか、ほんとうはあんまり言いたくない話、現実になって待ったなしになると、人間ってアワアワ状態になるので、そういうことも心の想定ができるのであれば、ご両親が今後どうされたいのか、ずっとご自宅にいらして在宅で介護されたいのか、それともホームに入って子どもたちの世話にはならずに第三者の世話で快適に暮らしていきたいのかっていう、そのあたりの意志確認みたいなことをきちっとされたほうがいいんじゃないでしょうか。
Q:同じような環境にある介護仲間はいらっしゃいましたか? 第三者と気持ちを分かち合うと楽になるような気もしますが、逆につらくなってしまうこともありそう。家族や友人以外の人に介護の相談をすることについてはどう思われますか?
安藤:母の介護をしているときには、同じような介護をしている人と定期的に会って話をするっていうのはなかったですけれども、何人か同じ年代の友達には同じような親の状況の友達もいましたけれど、みんなそれぞれに状況は違うわけですよね。似たような状況だけど個別の状況は違う。だから、会って話はするけれども、うちはこうだけどおたくはどうなのっていう比較になるじゃないですか。それは私はあえてしなかったですね。ただ、介護士さんや母を診てくれている主治医の先生や兄姉とかは、ほんとうに密接に情報共有したりとか、話をしました。それとホームの入所者のご家族とすごく懇意になって、そこの一つの輪みたいなのが大きかったです。みなさん、会いにいらっしゃいますよね。そうすると顔見知りになって「うちはこうでこうで」とか「うちはこうでご迷惑をおかけしますが」みたいな話になるじゃないですか。そういう連携はすごくありました。ひとつのコミュニティみたいな。
酒井:まだご両親が元気な方というのは、今後、あるかもしれない介護のことを考えるとほんとうに不安なんですが。
安藤:介護ってすごくネガティブなイメージがあるじゃないですか。私も、自分がその最中にいるときには、そんなにポジティブにばかりは考えられなかったんですけれど、よくよく考えてみると、介護する時間というのは、もちろん介護への関わり方の濃淡はありますし、ご自宅で介護されている方のご苦労に比べたら、私なんてほんのささいなことですが、それでも、ここまで母のことを理解しようとした時間ってなかったと思うんです。小さいときは育ててもらってたわけじゃないですか。だから母を理解するとかじゃなくて、いっときでも早く飛び立とうとしていた自分がいるわけですよね。そうじゃなくて、今度はいっときでも長く母と一緒にいたいと思った自分がそこにいて、そのときに母をよくよく理解しようとした自分がそこにいるわけです。そこは介護のものすごく不思議な時間、という気がしました。たとえば、母の口にものを運ぶとか、そんなことは小さい頃は考えられないじゃないですか。そのときに、母はこれを食べたいのか食べたくないのか。これは好きだったのか嫌いだったのか。「私、母のこんなこと、知らなかったっけ?」っていうようなこともあったりして、最後に母と過ごした何年間というのは、母をよくよく母として理解しようとした時間というか。「ああそうか、母親ってこういう人だったんだ」って発見とか、母を知る時間でした。

安藤優子(あんどう・ゆうこ)さん
1958年、千葉県生まれ。上智大学外国語学部比較文化学科卒。2019年上智大学グローバルスタディーズ・グローバル社会学博士号取得。学生時代から報道に携わり、1987年からはフジテレビの報道番組で長くメインキャスターを務める。語学力を活かした世界の要人へのインタビュー、現場に足を運んだ取材・レポートなどでも知られ、日本を代表するジャーナリスト・キャスターとして活躍。民放連賞、ギャラクシー個人奨励賞など数々の賞を受賞している。
Instagram: https://www.instagram.com/yukoando0203/